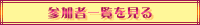ヴァイシャリーの街、賑やかな通り。
「……何か素敵な物は見つかりまして?」
イングリット・ネルソンは隣で店頭のワゴンに溢れる小物を眺めているグィネヴィア・フェリシカに訊ねました。
「……いいえ。あの、何が皆様に一番喜ばれるのか分かりませんわ。イングリット様、何か良い案はありませんでしょうか?」
グィネヴィアはふるりと頭を振り、悩み顔をイングリットに向けました。
「……お世話になった方達に贈り物をしたいんですのよね。心を込めるには手作りが一番でしょうけど、大勢の方への贈り物となれば」
とイングリット。グィネヴィアから今までに世話を掛けた人に感謝を形にしたいという相談を受けてグィネヴィアを連れて贈り物を探しに忙しくしているのです。
「……食べ物が良いかもしれませんわね。時間は掛かりますけど大量に作れますし、生ものでなければ保存も何とかなりますわ」
「イングリット様、素敵ですわ!」
イングリットは自分の提案に喜ぶグィネヴィアを連れ、贈り物作戦に必要な材料集めを開始しようとしました。
その時、
「……あの、良かったらこれを使って下さい。とても美味しいですよ」
二人の会話を聞いていたと思われる15歳の少年が声をかけて来ました。手には大量の林檎が入ったバスケットがあります。
「まぁ、真っ赤な林檎ですわ」
「全部あげます。その代わり名前をお願いします」
嬉しそうに林檎を見ているグィネヴィアに少年が一枚の紙を差し出しました。
「はい」
すっかり林檎に心を奪われているグィネヴィアはためらう事無く署名をしようとします。
「グィネヴィアさん、待って下さいませ。貰えるのは助かりますけどなぜ署名ですの?」
何か嫌なものを感じたイングリットが待ったをかけました。
「……えと、そ、それは……そうです。あの、甘味を増加させる魔法がかけられた林檎を作った人があげた人の名前が必要だと言っていて。ほ、ほらここにも書いてますよ。そ、それと是非、一口食べてみて下さい。作った人に感想も教えてあげたいので」
イングリットのいぶかしむ目から逃れるかのように目を泳がせながら少年はしどろもどろに理由を話します。
「……確かにそう書いていますわね。でも」
疑心消えないイングリット。
「これでよろしいでしょうか……とても美味しいですわ」
イングリットが自分を避難させる考えに至るよりも速くグィネヴィアは署名して林檎を食べてしまいました。
「……大丈夫ですわね」
嬉しそうに林檎を一かじりするグィネヴィアの様子にイングリットは警戒が徒労に終わったと少しだけ安心していました。
「……あ、ありがとうございます」
少年は礼を言うなりどこかに行ってしまいました。
静かな通り。
「ねぇ、グィネヴィア様に悪い事は起きないよね。この薬を手に入れる代わりにあのおばあさんの言う通りにしたけど」
少年は心配そうにグィネヴィアの署名が入った紙に目を落としました。紙は激しい光を発すると共に散り散りに破れたかと思ったら白い小鳥達に姿を変えてどこかに飛んで行ってしまいました。光と共に書かれた内容がグィネヴィアの声と精気を老婆に全て渡すという契約書に変わった事に少年は気付きませんでした。
『問題無い。早くティル・ナ・ノーグに戻るぞ』
ペンダントから聞こえる男性の声に急かされ、少年は故郷に戻るため急ぎました。
賑やかな通り。少年が去った後。
「……イングリット様、これで素敵な物が……」
嬉しそうなグィネヴィアの声が突然、途切れてしまいました。驚いてパクパクと口を動かしますが、全く声が生まれません。
「グィネヴィアさん、声が出ないんですのね。すぐに何とか……」
イングリットが何か方法を思考していた時、状況はさらに悪化してしまいました。
「グィネヴィアさん!!」
声を失ったグィネヴィアのまぶたが眠たげに閉じられふらりと傾いたのです。
イングリットは素早い動作でグィネヴィアが地面に倒れる前に受け止めました。
「……もしかして林檎に毒が? とにかく、グィネヴィアさんを」
精気を吸い取られているかのような土気色のグィネヴィアに嫌な気配を感じつつ古流武術で鍛えているイングリットは軽々とグィネヴィアを背負ってから林檎を全て拾い上げて近くのベンチに移動しました。
近くのベンチ。
「……誰か人を呼ぶ必要がありますわね。それからわたくしは真犯人捜しですわ」
イングリットはベンチに寝かせたグィネヴィアを見た後、速やかに救援要請をしました。武人としての勘なのか少年が犯人とは考えていません。
「……あれは……火事……妙な感じですわ。ただの火ではなそうですわね。確かめたいですけど」
ふとイングリットは前方に見える煙に険しい顔をしました。早く要請した救援が駆けつけてくれる事を願いながら。
薄暗い通り。古ぼけた家。
「可愛らしい声を上げて助けを呼べば誰かが来る。愛らしいその姿は人にちやほやされる。わしは醜く老いているというのにこれほど世の中不幸な事があるか。何もかも奪ってやりたい。自分と同じ不幸にしてやりたい……その時が今来た。ティル・ナ・ノーグを離れ、ここに移って良かった」
暗い室内でフードを深く被った老婆が気味の悪い声を上げながら倒れたグィネヴィアの姿を映す魔法の鏡を見ています。全ては彼女の仕組んだ事。
「ふふふ、あの子供も何も知らずにわしの指示通りにしたようだし。何もかも上々。運が向いてきた……来た来た」
老婆は薬を求めて故郷からやって来た少年の事を思い出していました。薬と引き替えに今回の計画を騙して手伝わせたのです。
その計画の報酬が今、老婆に支払われます。
「おぉ、顔にある火傷の跡もすっかり消えておるし弱った力も戻っておる。ふふふ、今頃あの愚かな小娘は目覚めぬ夢の中。これでティル・ナ・ノーグの住民達は絶望するだろうな。仕上げをしたいところだが、あの少年に譲ってわしは愉しもうか。せっかくのこの姿」
枯れ切った姿は瑞々しい乙女となり、地の底から響くかのような声は可愛らしい声に変わり、老化により衰えた力もみなぎっています。老婆が望み、グィネヴィアから奪い取ったものです。
若返った老婆は邪悪な笑みを浮かべながら家を出て行きました。
薄暗い通り。
「……力の使い方を忘れていないか確かめようか。それが終われば忌々しいティル・ナ・ノーグに戻るのも良いな」
老婆は瓶を取り出し、中に入っている赤紫色の粉を手のひらにこんもりと載せました。
「……炎、水でも消えぬ炎で覆い尽くそうか。肌を焼き、息を奪い、心臓を止める」
老婆は魔法を込めた息を粉に吹きかけました。力を得た粉は鈍く輝きながら街中のあちこちに飛び炎に姿を変え、煙と共に街中を走ります。火傷を負わされた過去を持つためか火に対して執着を持っているようです。
「ふふふ、愉しいな。ついでに今後のお楽しみに必要な物でも揃えようか」
老婆はフードを取り、偽りの美しさを振りまきながら賑やかな通りに出て行き交う人々に舐めるような目を向けながらゆっくりと歩き始めました。異変を察する者がいるとも知らずに。