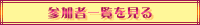コンロンの郊外にある大きな屋敷。
その中にある、長く薄暗い廊下。
「どんな群れにも必ず二つのものが存在する。……何か分かるかね?」
男は後ろを振り返り、両手を拘束されて兵士たちに連行されている楊霞にそんな質問を投げかける。
男は絹のような髪に端正な顔立ち、少し痩せ気味の体躯といった典型的な優男のような姿をしていたが、涼しげな瞳では野心の炎が渦巻いてるのを楊霞は目を見ずとも感じ取っていた。
「……ふむ、答えてはくれないか……なら教えよう。どんな群れにも必ず『主』がいてそれに『従う者』がいる。特に人という群れはその関係で出来ているね? 君の父、楊将軍がコンロン帝に従うようにだ……でも、コンロン帝が本当に群れの『主』であることが正しいと言えるかい?」
「……コンロン名家の一家である劉玄白が、よくコンロン領でそんな発言が出来ますね?」
玄白と呼ばれた男は口角を静かに吊り上げた。
「いいんだよ、私はコンロン帝は群れの『主』に相応しくないと思ってるからね」
言いながら玄白は立ち上がり楊霞に近づいていくが、その最中も彼は口を動かすのを止めない。
「群れを治めるのに必要なのは圧倒的な力。お金も権力も軍隊も国家も思想も愛も正義も、単純で圧倒的な力の前には屈せざるを得ない。……そういう存在が人という群れの『主』になるべきだと私は考える」
「それは自分だとでも言うつもりですか?」
「いやいや……そんな事は言わないよ。……人を統率する群れの主は、」
玄白は一度言葉を句切り、楊霞の前で膝を折ると、
「楊霞……君こそが相応しい」
愛おしそうに玄白は楊霞の頬を撫でる。
「僕はてっきり自分の手で世界を手中に収めたいとか言い出す人だと思っていましたよ」
「言っただろう? 圧倒的な力を持つ者が人の群れの『主』であるべきだと。……君が主となれば、僕は喜んで君の踏み台になろう、死ねと言われれば喜んで首でも腹でも切ろう。『従う者』は主の手足となって何も考えずに動く、それが俺の考える究極の主従だ」
長い演説が終わり、楊霞は深いため息をついた。
「イカレてますね世界征服をしたいのに、それを人の手に委ねるなんて」
「私は私の正しいと思っていることをやるだけさ、その点では周りの人間も同じことをしている。……それに僕の目標は世界征服じゃなくて人の群れの絶対的な『主』を決めようと言ってるだけなんだよ?」
「……どのみち、僕は貴方の思想に協力する気はありません」
ハッキリと断られて玄白は苦笑を浮かべる。
「そうか……でも、その答えを出すのはこれを見てからでも遅くないんじゃないかな?」
「先程から……僕はどこに連れて行かれてるんですか?」
「地下だよ。俺が見せたいものは、まだ地上に出せないんだ──なにせ、巨大だからね」
そう言いながら玄白は廊下の終わり、重たいドアを開けた。
ドアの先には何十人という女性が作業服を着こみ働いていた。
全員が機械の油を作業服にこびりつかせ、疲労困憊と言った表情で蒸し暑い地下の中をあくせくと巨大な工事足場を使って右往左往していた。
「ここで働いている人たちって……」
「そうだよ……君たちがこの間潰してくれた人攫いが攫ってきた子たちだよ。女性は器用だし働き者だから男よりよっぽど役に立つんだよ」
「ここで一体なにを……」
「うん、それじゃあ少しだけ見せてあげようか」
玄白は嬉しそうに楊霞の背後に回るとバイザーを外して見せ、
「これは……!」
楊霞は改めて目の前の状況に絶句する。
工事足場の中心には──ロボットが立っていたのだ。
「機晶石で動く巨大ロボットだよ大きさは40メートルってところかな……いくら君でも機械に乗った相手を石化することは出来ないから、補助役にと思ってね」
そう言いながら玄白は再びバイザーを楊霞の目に戻した。
「それで……まだ君の気持ちは変わらないかい?」
「ええ、どうあっても賛同できません」
「そうか……紅玉」
「ここに」
名前を呼ぶと一人の女が現れた。女は、楊霞をここに連れてきたあの女だった。
「始めろ」
「仰せのままに」
紅玉と呼ばれた女は、錠剤を一つ取り出すとそれを無理やり楊霞に飲み込ませた。
「ぐ……! 何を……」
「ちょっとした催眠薬です。しばらくは紅玉に再教育してもらってください……それが終わったら──コンロン帝とそれに従う楊将軍の首を取りに行ってもらいます」
「……!」
楊霞は心臓が大きく脈打つのと同時に、意識が遠のいていくのを感じた。
「残念ですが……コントラクター達がいる限り……貴方の計画は失敗に終わります
よ……」
不敵な笑みを浮かべて楊霞は気を失う。
「うん、君のことだ既にこの居場所に君がいることは誰かに知らせているのだろう? ならば、来る相手をここで迎え撃って葬ろう……君を使ってね……ああ、楽しくなってきた」
玄白は弧を描くように笑みを浮かべた。
メイド喫茶『バーボンハウス』
「あっはっは……いや、笑えないな……」
店長は笑うのをやめて、真剣な眼差しで自分の手元にあるレーダーを見つめる。
店長が手に持っているのは発信器の居場所を特定するという代物だ。アルバイトのメイドたちを助けると言って出て行った楊霞が立ち去り際に渡したものだ。
一日で戻る。
楊霞は確かにそう告げ、もし帰ってこなかったらレーダーの映る場所に人を送って欲しいと頼まれていたのだ。
そして、そのレーダーの反応が今無くなってしまったのだ。
「場所は……コンロンの外れかな? とりあえず、百合園女学院にでも助けを求めようか……無事でいてくれ楊霞くん、でないと笑えないにも程があるからね」
店長は楊霞の無事を強く祈りながら店を飛びだした。