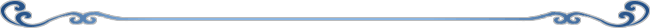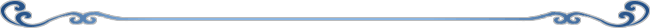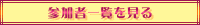パラミタ最大の国家、エリュシオン帝国。
樹高12000メートルの世界樹ユグドラシルの恵みと高度な魔法技術、
そして、勇猛な神によって構成された龍騎士団の守護によって栄えていた国ですが、
帝国を統べるアスコルド大帝が床に伏せてからは、その威光にも陰りが見えていました。
しかし、
その帝国にも新たな時代の波が訪れようとしていたのです――――
= = =
シャンバラ大荒野。
「ふむ、シャンバラの契約者たちの力を借りたいと?」
「ええ」
波羅蜜多実業高等学校 校長石原肥満(いしはら こえみつ)の問いかけに、
エリュシオン帝国第三龍騎士団副団長キリアナ・マクシモーヴァは、うなずきました。
他の龍騎士たちの姿は無く、キリアナは一人でキマクにやってきていました。
今、ある罪人を追う特命を受けているのだと言います。
「ウチが追ってるのは、セルウスいう樹隷のお人よって……」
樹隷――
世界樹ユグドラシルの整備に従事する特別な者たち。
彼らはエリュシオンの国土そのものであり、ユグドラシルの一部であり、神ですら不可侵とされます。
神聖視されており、帝国の人々にもその実態は良く知られていません。
「通常、樹隷は帝国臣民と接触することはなく、
もし出会ってしまったとしても、互いに“見なかったこと”にするのが習慣なのは知ってはりますやろ?
つまり――」
「帝国臣民である龍騎士や従龍騎士は、その罪人と接触することは出来ず、捕まえることも出来ない。
だが、シャンバラの契約者なら、その者を直接捕らえる事が出来る。そういうことじゃな」
「そうです。
ウチはちょっと特別やさかい、そこのとこは問題無くて、だから、この任務を命じられているのやけど」
「なるほどのぉ。
さて、それで、彼は一体どのような罪を犯したのかな?」
「樹隷がその義務を放棄して逃亡――
しただけならば、ウチら龍騎士団が動く事も無い。
ただ、従龍騎士の試験会場を荒らしてったゆうのんが、なぁ」
「ほっほ、元気の良いことじゃな。
しかし、帝国さんにもプライドがあるしのぉ」
「その後、セルウスはシボラの方へ逃げたらしいんです。
あそこを一人で探すのは、少し難儀やなぁと」
「あい分かった。
皆に協力してもらえるよう声をかけておこう」
「ありがたいわぁ。
もちろん、帝国から謝礼やらは出ますよって。
それに、ウチからも……まあ、ちょっとした接吻くらいなら」
キリアナは冗談めかすように付け加えてから、ぽんっと手を打ちました。
「ああ、せや。協力してもらえるなら、ウチの龍エニセイの分龍をお貸しします」
言って、キリアナは剣を抜き、
自身が乗ってきた龍「エニセイ」を神速で切り分け、分裂させました。
「ほっほ、珍しい龍じゃのぉ。
そして、細胞を見極めて斬り分け、分裂させるキリアナ君の才能も面白い」
「いややわぁ、こんなん大した事あらへん。
シャンバラにも凄いお人がぎょうさん居てると聞いてますえ。
ウチの剣なんて、それに比べたら。ねぇ?」
そう、キリアナは得意げに微笑んだのでした。
= = =
数日後――シボラの奥地。
樹隷の少年セルウスは、腰に携えた頭蓋骨クトニオスと、
逃亡の途中で出会った帝国の少年ドミトリエと共に暗闇の中を進んでいました。
彼らは密林を進む内に、
化石化したシボラの世界樹アウタナの中へと迷い込んでいたのです。
そして――
彼らは、半ば樹と一体化したような姿の老人の元へと辿りついたのでした。
「この人、世界樹と同化してる?」
セルウスの零した言葉に、ドミトリエが「ン」と小さく置いて。
「聞いたことがあるな。国家神であるシボラの長老はアウタナと同化している、と」
『では、この御仁がシボラの長老であるというのカ……?
だとしたら――』
クトニオスが少し興奮気味に言葉を続けようとした、その時。
(ここに客人が来たのは2000年振りだな)
彼らの頭の中に声が響きました。
「これは……この老人の意識?」
そう少し身構えたドミトリエとは対照的に、
セルウスは樹と同化している長老のそばへと近寄って、固いその表面を、ペシペシしました。
『うぉいっ、国家神をペシペシするナ!!!』
クトニオスに怒られたセルウスは手を引っ込めてから、
改めて、長老を見やりました。
「こんにちわ」
(ユグドラシルの良きしもべたる者よ。
お前は何故ここにいる?)
「師匠に言われたんだ。
俺はコンロンに行かなきゃならないって」
セルウスは腰の頭蓋骨クトニオスを指さしながら言いました。
(…………。
古き盟約の良きしもべたる者よ。
お前は、この少年に宿命を感じたというのか)
『いかにも。
そして……今、こうして導かれ、シボラの国家神と出会えたということは、
ワシの目に間違いはなかったのジャと思うておる!』
クトニオスはカチカチと骨を鳴らして答えました。
「大げさだな」
ドミトリエが冷ややかに言いました。
(――急げ。お前たちを追う者が迫っている。
ドワーフの坑道を使うのだ)
「やはり、坑道の入り口がこの近くにもあったか」
『やはり?』
「知ってたの?」
クトニオスとセルウスの言葉にドミトリエは頷きました。
「俺はドワーフに育てられたんだ。
だが、坑道は余りに広大だから、全てを把握してるわけじゃない」
(幾人かのシャンバラの契約者へ、お前たちの力となってくれるよう伝えておこう。
彼らの力を借り、まずはシャンバラへと逃れろ)
長老から、坑道の入口までの道を頭に直接送り込まれたドミトリエは問いました。
「なぜ俺たちに協力する?
あなたも、セルウスが特別な使命を背負っている、と?」
(アスコルドは気に入らん。……それだけのことだ)