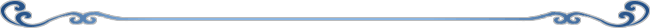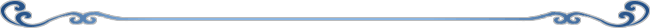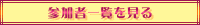「私も薔薇の学舎に入りたいんです、お願いします!」
男色の吸血鬼が一人、薔薇の学舎の校門に貼り付いています。
彼の名前はヴラド。血のような赤色をした瞳を見開き、手入れのいき届いていない亜麻色の長髪を風になびかせ、必死の形相で職員に縋り付き入学を請うていますが、如何せんここはエリート学校薔薇の学舎。校長のスカウトに引っ掛からなければ、入学は叶いません。
彼のパートナーであるシェディは、毎日のように薔薇の学舎に通っては門前払いをくらう彼の姿を少し離れた木陰から困ったように眺めていました。薔薇の学舎に興味を示して以来、ヴラドはシェディとの会話もおざなりになっていました。シェディが服装を提案したところで、聞き入れる様子もありません。
「……どうしたものか……」
ぽつりと呟くその言葉も、ヴラドの耳には入りません。とぼとぼと歩いて行く背中を、シェディはこっそり追いかけます。
病的に白い肌を太陽から隠す為に麦わら帽子を深く被ったヴラドは、木陰で深々と溜息を吐き出しました。三日間悩んだ末に着用を決めた白衣は所々赤黒く汚れていて、がっくりと落ちた肩の部分がほつれています。
薄汚れた鏡をポケットから取り出してまじまじと眺めますが、美しさとはほど遠く思える自分自身の姿に、ヴラドは改めて肩を落としました。ここのところは寝ても覚めても薔薇の学舎の事が頭から離れず、あまりパラミタを訪れなくなったパートナーを気にする余裕すらありませんでした。
男色の彼にとって、薔薇の学舎は憧れでした。美しい男子生徒たちが連れ立って歩いて行く姿はヴラドの目には鮮やかに輝いているように映りました。その中に混ざりたいと思ったヴラドは、長年篭り続けたさびれた屋敷に別れを告げる決心をつけたのでした。しかし、現実は甘くはありませんでした。
「こうなったら……」
長い爪の生えた指をぎゅっと握り締め、ヴラドは決意を表情に浮かべます。どう見ても胡散臭い笑顔にしか見えませんが、それがヴラドの精一杯の真剣な表情でした。
「助けを求めるしかありませんね」
ヴラドは一度屋敷に引き返し、何やら大きな紙に書き始めます。長年ずっとペットとして飼っていた、一匹のドラゴンパピーの頭をそっと撫でて、言いました。
「あなたにも手伝ってもらいますよ、たま」
大きく欠伸をしたドラゴンパピーのたまに首輪を嵌め、ヴラドは一枚のポスターを作りました。
『・あなたの美しさを教えて下さい・
薔薇の学舎の皆さま。美しさに自信のある諸君。
その美しさ、私の目に見せ付けて頂きましょう。
美しい歌声。美しい容姿。美しい筋肉。
美しい友愛。美しい戦闘。そして美しい、愛。
あなたの美しさを、教えて下さい。
美しい方には、見合うだけのお礼を致します。
明日、屋敷でお待ちしています。
追伸:魔物を一匹ご用意しました。こちらをパフォーマンスにご利用頂いても構いません。……が、命までは奪わないであげて下さいね』
繊細な文字で書かれた文章の下に大きく地図の描かれたポスターをこっそり貼り付け、上機嫌な笑みを浮かべてヴラドは帰って行きました。
そんなヴラドの後を密かに付けていたシェディは、彼の書いた文章の下に何やら書き加えると、明日に備えヴラドの屋敷に忍び込むため、森への道を歩いて行きました。
『……頼む。あいつの目を覚まさせてやってほしい。
本当に美しいものを見ればきっと、あいつも諦める……だろう』