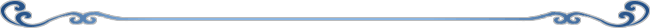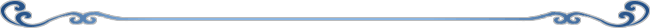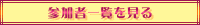それはある日のこと……。
「え……また行方不明者が出たの?」
「そう……これでここ一週間だけでも5人だよ? やっぱり何かあるんだよ、あそこ」
蒼空学園校舎の隅にある物置のような教室で、二人の少女が対面する椅子に座りながら、怖れるような顔で話していました。
彼女たちは、この学園にあって密かに活動している『歴史研究会』の部員たちです。
部員数からも活動の地味さからも、あまり学園自体にも知られているとは言いがたいマイナーサークルの数少ない部員たちは、ここ最近噂になっている、ツァンダの南東にある遺跡で新たな被害者が出たことを話していました。
「森の中に住んでる獣人たちすらも近寄らない、未踏の遺跡……そこに足を踏み入れた者は、二度と帰ってこられないという……」
「昔はとある神様を祭る美しい神聖な場所だったらしいけど、それも今となっては被害者のゾンビたちが徘徊していて、侵入者に襲い掛かるという話……しかも、最近では謎の魔道書の噂もちらほら……」
二人は、まるで怪談でも話しているかのような神妙な顔で言葉を切ります。
もちろん、その後は笑い話で済ませるか、あるいは誤魔化すような苦笑いでその場を収めるつもりだったのでしょう。
しかし――予想外のことが起きたのはそのときです。
「ふむ、なるほど。それは興味深いな」
「……え」
背後から聞こえてきた声に、一人の少女は振り返り、一人は顔をあげました。
そこには、小学生かと見間違えるほどに小柄ながらも、威風堂々とした立ち振る舞いの少女が立っています。
「シェ、シェミーさんっ!?」
「おい、お化けでも見たように言うのはやめろ」
「い、いつ帰ってこられたんですかっ?」
それまで怪談話をしていたせいでしょうか、ひくつったように驚く二人に、シェミーと呼ばれた少女は憮然とした顔で答えました。
「ついさっきだ。色々と思うところもあってだな、顔を見せに寄ったんだが……どうやらあいつもいないようだし、あたしが心配するようなことはないかと思って、こっちにも挨拶をしにな」
そう言うシェミーは、背中に背負っていた巨大な布袋をどさっと床に落としました。
使い古されたそれは、少女の荷物が大量に入ってある、言わば旅袋です。
「――が、まあ、それはさておきだ。なにやら面白いことを話していたじゃないか?」
シェミーは悪戯でも思いついたかのような、不敵な顔を浮かべました。
小学生のような童顔がにやりと笑う様は、まるで一生懸命背伸びをしているかのような愛らしさも持っていますが、どうやら二人の部員は彼女の恐ろしさ……もとい、厄介さを知っているようです。
苦笑しつつ、話を誤魔化そうとします。
「あ、あれは〜、その〜、え、えっとお化け屋敷でもつくろうかな〜という話で」
「お化け屋敷ねえ。では、その魔道書とやらも出てくるお化け屋敷について詳しく聞かせてもらおうか。……嘘でも言おうものなら、明日の学園生活をないと思え」
「…………はい」
二人は諦めた顔で答えました。
「ふむ、人の姿を見るという話か」
シェミーはくしゃくしゃになっていた乳白色の髪を綺麗にツインテールに纏めて、改めて二人の話を聞いていました。
何でも、遺跡の近くで女の子の姿を見ることが多くなったという話です。
最初は獣人か何かのことかと思われたそうですが、どうやらそうでもないらしく……。
「……それで、その女の子が、不思議な装丁をした本を持っていたって話なんです」
「そもそも、その遺跡自体がほとんど誰も近寄らないような場所ですし、そこに女の子がいるのが目撃されたことや、本のことも関係して、魔道書の化身なんじゃないかって話が……」
「……なるほどな」
シェミーは考えるよう顎を押さえて、頷きました。
自分たちよりも一回りも小さい少女に、明らかな下手から言葉を進言する二人の学生は奇妙な図でもありましたが、どうやらこの『歴史研究会』においては当たり前のようです。
この――自称天才歴史学者のシェミー・バズアリーには、サークルの誰もが逆らうことを許されていないのでしょう。
いや、というより、その自由奔放さと頭脳明晰さには、恐らく誰もが逆らうことすら出来ずに振り回されているのです。
「と、なれば……」
シェミーは再びにやりと笑いました。
二人の部員には嫌な予感が走ります。
シェミーがこうして面白そうな顔をするときは、何かしらトラブルを持ち込むことを思いついたときなのですから。
「その遺跡を、探索しに行くしかないなっ!」
無論――自分たちさえも巻き込まれそうな勢いに、その提案を『歴史研究会』の二人が必死で拒んだのは言うまでもないのでした。
シェミーはこうして、一人では埒があかないと、協力者を募るために各地に依頼を発布しました。
自称天才歴史学者の興味本位で始まった遺跡探索……ぜひ、彼女の探究心にご協力ください!