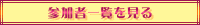ヒラニプラ東北部、ヴァイシャリーとの領境に程近い山岳地帯の一角に、豊富な産出量で知られる機晶鉱山モルベディが、幾つもの鉱山町を裾野に従える形で鎮座しています。
モルベディの地下鉱脈はヒラニプラ内でも屈指の広がりを見せており、一部は鉱山町の地下にまで及んでいることが判明しています。
豊かな採掘量で潤うモルベディ周辺の鉱山町ですが、そのうちのひとつソレムは伝統的に、山賊団や魔物の群れによる襲撃を多く受けてきており、その対策として古くから頑健な城壁や砦を常備する堅牢な城塞都市として知られていました。
近年ではシャンバラ教導団による一掃作戦や、コントラクター達の個々の活躍によってそれらの脅威は激減しており、ソレムの城塞は今や無用の長物に成り下がろうとしていましたが、一部は観光スポットとして、旅行者の目を楽しませる施設へと変貌を遂げつつありました。
* * *
2022年の、年の暮。
エリュシオンの上流貴族アレディード家の令嬢フェンデス・アレディードは、休日を利用してソレムを訪れ、歴史ある鉱山町と趣のある城塞の数々を見学するツアーに参加していました。
親類から多くの竜騎士を輩出していることもあり、アレディード家の家格はエリュシオン国内でも決して低くはありません。
仮にフェンデスの身に何かあれば、即座にシャンバラとエリュシオン間の国際問題にまで発展する可能性があった為、警護に当たる教導団の護衛部隊は、常に神経を張り詰めて配置に就かなくてはなりませんでした。
ところが、そんな警護部隊の努力をまるで嘲笑うかのように、その事件は絶望的な危難を伴って発生し、フェンデス一行に容赦無く襲いかかってきました。
爆音、黒煙、舞い上がる炎の渦。
その日、ソレムはほんの小一時間という日常の中の空隙を突くようにして、ほとんど一瞬にして戦場と化しました。
町の住民はことごとく最新鋭の銃火器を装備して街路に飛び出し、フェンデスを護衛する教導団員を次々と殺害していきます。
辛うじて生き残った教導団員達は必死の防戦を展開しながら、何とかフェンデス一行を町のほぼ中心に位置する石造りの大講堂へと避難させました。
が、四方八方を敵と化した町の住民に包囲されてしまい、籠城戦を余儀なくされています。
一体どうして、こんなことになってしまったのか――明確な答えを持てる者は、誰ひとりとしていませんでした。
状況は極めて困難であり、予断を許さないどころか、ほとんど絶望的といっても過言ではありませんでした。ソレムの住民の大半が、いきなり最新鋭の銃火器を装備する情け容赦の無いのテロ集団と化してしまったのですから。
「くそっ……完全に包囲されてしまったか」
警護部隊の隊長を務めていたレオン・ダンドリオン(れおん・たんどりおん)中尉は、全身の至る所に、爆発と銃撃による無数の細かい傷を作りながら、それでもダメージを受けた素振りは一切見せずに、二階の窓から、そこかしこに火の手が上がっている凄惨な街並みを、じっと凝視していました。
彼らが籠城しているこの堅牢な大講堂は、もともとが城塞として設計されていた為、防御力は通常の建物の比ではありませんでした。
しかしながら、水や食料などは堂内にはほとんど備蓄されておらず、警護部隊の面々が辛うじて所持していた簡易レーションだけで、何とか持ち堪えなければならないという状況です。
自分達が如何に苦しい立場に置かれているのか、誰もが明瞭に悟っていました。
「ダンドリオン中尉……助けは、来るのでしょうか?」
数名の侍女を従えたフェンデスがレオンの居る二階の出窓前に姿を現し、青みを帯びた銀髪を煤で黒っぽく汚したまま、細面の美貌を引き締めて小さく問いかけました。
レオンは無用のパニックを避ける為、努めて明るい表情をフェンデス達に返します。
「教導団の救出能力の素晴らしさを、皆様にお見せすることになるでしょう。それまでしばらくご辛抱頂くことになりますが、とにかく今は、どうぞお心安らかに」
「……ありがとう。そのように励まして頂けると、私どもも、少しは落ち着くことが出来ます」
それだけいい残してフェンデス達は引き下がっていきましたが、レオンは内心で、自分の言葉が全くの嘘であることが、フェンデスにもばれているだろうと苦笑せざるを得ません。
この極限の中で、お互いに気を遣っているというのは、まだそれだけ精神的にゆとりがある証拠ではありましたが、それも果たして、いつまで持つかどうか。
* * *
しかし、レオンの言葉とは裏腹に、教導団はソレムへの救出部隊の編成に随分と苦労していました。
そもそもソレムは、モルベディの鉱脈が町の下にまで続いている、ある種の巨大な火薬庫のような性質を持っており、大規模な爆撃や強力な火力による救出支援はご法度でした。
もし町の下に広がる機晶石鉱脈に破壊の波動が影響すれば、モルベディを中心とする山岳地帯が一瞬にして消し飛んでしまう連鎖爆発が起きてしまう可能性があったのです。
そうなれば、同じくモルベディを生活の糧とする他の鉱山町の罪も無いひとびとが、数千人、いや数万人規模で一気に死に絶えることになる訳です。
如何に国際問題を孕むフェンデス一行の救出作戦とはいえ、そこまで大規模な数の住民の命と引き換えに、という訳にはいきませんでした。
更にいえば、突如テロリストと化したソレムの住民達を、教導団はおいそれと攻撃することが出来なかったのです。
何故なら――。
ソレムの北の端に位置する街門上の楼閣で、鏖殺寺院の残党集団のひとつ『パニッシュ・コープス』の幹部であるモハメド・ザレスマンの姿がありました。
彼は町の中心へと続く大通りで、最新鋭の銃火器を揃えて教導団の駐屯部隊と交戦する住民達の、極めて勇猛果敢な戦いぶりを満足げに見下ろしていました。
そして同じ楼閣内には応接テーブルが据えられており、そこに、コーラをがぶがぶと飲んでいる端正な面の巨漢の姿が。
その人物は、同じくパニッシュ・コープスに所属するバイオメカニクス技術者若崎 源次郎(わかざき げんじろう)という名で知られていました。
ザレスマンは大通りから屋内に視線を写し、漫画雑誌を開いている源次郎に向き直りました。
「若崎さん、見事なものですな。S3は即効性だけでなく、操作性と戦闘力向上の点に於いても、S2とは比較になりません」
「あぁ、そら結構な話ですわ。開発費にちょっと予算取られましたけど、これならすぐペイ出来そうでんな」
称賛の声を受けて、しかし源次郎は相変わらず漫画雑誌を読みふけったまま、適当な調子でザレスマンに応じます。
五十代半ばの壮年男性であるザレスマンは、源次郎のそんな態度にも腹を立てた様子は無く、ただにこにこと満足げに、何度も頷くばかりです。
「それにしても若崎さんは、肉体年齢ばかりではなく、趣味嗜好もお若いですな。確かもう、今年で還暦を迎えられるお年でしたな?」
「そうですねん。っちゅうても、孫のひとりも居らんのは寂しい話ですわ」
全くそんな素振りはなく、ただ口だけでそういっているだけの源次郎。
ザレスマンは、小声で笑いました。
「矢張り、ヘッドマッシャーの完成体ともなると、我々のような通常の肉体に縛られ、通常の時の中で生きる者とは思考そのものが違うのかも知れませんな」
「んなこたぁおまへんがな。わしなんて、ただのコーラ好きでんがな」
その言葉を実証するかのように、源次郎はペットボトルに半分ぐらい残っていたコーラを一気飲みします。
それからひとつ大きなげっぷを放った後、2メートルを超える巨躯をのっそりと立ち上がらせました。
「向こうさんも、どうしたもんやと考えとるでしょうな。わしがワクチンの存在を公開したから、教導団としても、ソレムの住民を救う手立て無しとして殺す訳にはいかんようになった」
「……かといって、アレディード家の令嬢を見殺しには出来ない上に、この町の下には機晶鉱脈がほぼ全領域に亘って広がっているから、火力を極めて援護する訳にもいかない。戦術上、これ程の困難に置かれたのは、ここ最近では中々無かったのではないですかな?」
嬉しそうに笑うザレスマンの双眸の奥に、残忍な光が宿っていました。
その一方で源次郎は、二本目のコーラの栓を開けようとしながら、ふと何かに気づいたのか、遥か東北東――ザンスカールの森が位置する方角に、ちらりと視線を転じました。
「何か、気になることでも?」
「んぁー、いや、何でもおまへん」
源次郎は小さくかぶりを振ると、ペットボトルの蓋をこじ開け、しゅわしゅわと泡立つコーラを美味そうにあおり始めました。