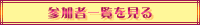イルミンスールの東、パラミタ内海沿岸に、要塞ともいうべき巨大な軍港が、その礎を構えています。
シャンバラ政府の要請を受けて建設された軍港ケーランスは、内海洋上の防衛戦略拠点のひとつとして、教導団によって運用されています。
このケーランスから先日、一隻の潜水艦が進水式を迎え、試験航行へと出航しました。
新型の機晶エンジンを搭載するこのロサンゼルス級攻撃型潜水艦は、バッキンガムと命名されました。
バッキンガムは最高水準の新式装備を搭載しており、SLCMをはじめとする各種の強力なミサイル兵装を整えた戦略兵器です。
ケーランスを発ったバッキンガムは、一週間後には試験航行を終えて帰港することになっていました。
ところが二週間が経過しても尚、バッキンガムはケーランスに引き返してくる気配がありません。それどころか、十日前からケーランスへの定時連絡が途絶えているという状況が続いていました。
バッキンガムに、何かがあった――ケーランス総督デルコ・ウィシャワー中将はそう判断し、バッキンガム捜索に向けてオハイオ級巡洋型機晶式潜水艦ヴェルサイユに対して、捜索航海への出航を命じました。
* * *
ヴェルサイユ艦長ロベルト・ギーラス中佐は、ケーランス第二桟橋にて、目の前に居並ぶ数十名の乗員達をぐるりと見渡し、うむ、と小さく頷きました。
「どの顔も、良い緊張感を保っている。陸に上がっている間も、訓練を絶やさなかった証拠だな」
「しかし艦長、今回は少しばかり、様子が異なります」
女性ながらヴェルサイユの航海長を務めるドリュー・バスケス少佐が、端正な面に幾分不機嫌そうな色を浮かべて、ギーラス中佐の横からそっと耳打ちしてきました。
「各校のコントラクターが、捜索協力要員として本艦に乗り込んでくるらしいな」
「自分も同じくコントラクター故、彼らをあまり悪くいいたくはありませんが……正直、素人に潜水航行を引っ掻き回されるのではないかと、少なからず危惧しております」
バスケス少佐の言葉に、ギーラス中佐は一切の不安を払拭するかのように、微かな笑みを濃い髭の下に形作ります。
「ヴェルサイユはオハイオ級ながらSLBMを一切排して、わざわざ巡洋型として設計されたのだ。他校のコントラクター達を押し込めておけるだけの空間は、十分に確保出来るだろう。それに今回は僚艦として巡洋艦ノイシュヴァンシュタインが同行する。こちらにもコントラクターは分乗するから、我々ばかりに負担がかかるという訳でもない」
ギーラス中佐の応えに、バスケス少佐は曖昧に頷くしかありませんでした。
ヴェルサイユの乗員はいずれも潜水艦乗りのプロばかりであり、潜水航行の何たるかを熟知しています。しかしその一方で、今回、捜索協力要員として乗り込んでくるコントラクターの大半は、洋上訓練すらも受けていないような素人が多くを占めていました。
そんな連中が潜航中にどんな問題を引き起こすのか、分かったものではない――それが、バスケス少佐の偽らざる不安でした。
しかし軍上層部からの命令である以上、バスケス少佐とてこの決定に異論を挟むことは出来ません。
果たしてギーラス中佐は、彼らコントラクター達をどのように扱うつもりなのか。
バスケス少佐は内心で、酷く気が重くなるのをどうにも抑え切れそうにはありませんでした。
* * *
一方、捜索対象となっているバッキンガムの艦内では――。
「く……くそッ! 何なんだ、あれは!?」
艦内通路を必死の形相で駆け抜けるひとりの若い乗組員が、天をも呪う程の勢いで獰猛に吐き捨てました。
バッキンガムは既に十日以上、パラミタ内海のどこかに着底したまま、まるで動き出す気配がありませんでした。
のみならず、艦内には不穏な影が出現しはじめ、乗組員がひとり、またひとりと行方不明になってゆくという有様です。
密閉された狭い空間内で、こんなことが起きるものなのか――若い乗組員は、混乱する頭の中で、その点だけは随分と冷静に疑問視していました。
しかし事実、何者かが艦内を徘徊しており、警戒に警戒を重ねる乗組員達の必死な思いを嘲笑うかの如く、次々と神隠しに近しい状況へと引きずり込んでいくのです。
「何とか……何とか、友軍に連絡を取らないと……!」
憔悴し切った表情の若い乗組員は拳銃を構えたまま、艦橋内の長距離通信装置前へと歩を進めてきました。
ですが、結局彼は海上との通信を開くことは出来ませんでした。
若い乗組員が通信用マイクを握った直後、彼の背後に迫っていた巨大な影がぬっと太い腕を伸ばし、彼の姿を艦内から消し去ってしまったのです。
バッキンガム艦内では確かに、何かが起こっていました。