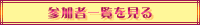「ん……、あれ、ここは………?」
正岡 すずなが目覚めた場所は、暗い場所だった。
どうやら自分が壁際に座り込んでいるらしい、動こうとして腕が天井から吊るされた鎖に繋がれている事に気づいた。少し動かすと、随分と長い間こんな無理な格好をしていたからか体の節々が痛む。
「あー、そっかヘマしちゃったんだっけ」
暗闇に慣れてきた目で最初に確認したのは、自分の正面にある鉄格子だ。どうやら、ここは牢獄か何からしい。
壁は石を積まれたもので、床も石で作られている。あまり手入れをされていないようで、あちこちボロボロだ。少しカビ臭くあるようにも思う。
鉄格子の向こうは暗くてよく見えないが、人の居る気配はない。見張りはいないようだ。
鎖に繋がった手枷は、簡単に開いてはくれなさそうだ。最も、道具になりそうなものは全部取り上げられているらしい。
「みんな大丈夫かなぁ………、ここには居ないみたいだから、きっとうまく逃げたんだろうけど、心配だなぁ」
彼女が心配しているのは、モンスターに襲われていたカナン流民達だ。襲われている彼らを偶然目撃し、一緒に居た仲間と共に助けようとしたのだが………。
ここに姿が無いのならば、うまく逃げてくれているのだろう。
そう思っても、不安が拭えるわけではなく、最悪の想像が頭をよぎっては首を振ってそれを追い出すのを繰り返していた。
そんな彼女の耳に、音が聞こえてきた。足音だ。その足音は、真っ直ぐに彼女の方へと向かってきていた。
やがて人影で見え、その人影は牢を開けて中に入ってくる。どうやら、牢には鍵をかけていなかったらしい。
「ごきげんよう、気分はどうだ? ま、聞くまでもないだろうけどな。でも、他の奴のように石になるよりはずっとマシだ。そうだろう?」
やってきたのは、赤髪の目つきの悪い男だった。その風貌には似つかわしくない、やたら豪華な鎧を着込んでいる。
「………まさかっ!」
「なんだ、別に睨まなくてもいいじゃんか。別に取って食いやしないさ。それに、あんたのお友達? も別に殺しちゃいないしな。」
着込んでいる鎧とは裏腹に、その口調はやたら軽薄だ。薄笑みを浮かべながら喋る姿には、なぜか苛立ちを覚える。
「私をどうするつもり?」
「んー、別に。せっかく捕まえたんだから、一人ぐらいもらってみようかと思ったんだけど、別に俺石像を並べる趣味ないんだよねぇ。だから、あー、保留かなぁ」
どうやら、この男はあまり物事を深く考えずに気分で動くようだ。
すずながここに居るのも、彼の気まぐれなのだろう。
「みんなをどうしたのよ! それに、石にするってどういう意味なのさ!」
「んー、外の奴に言ってもいいのかなぁ。まぁ、いっか。ここで捕まえた奴はみんな別の場所に連れてくんどさ、そのままにしとくとうるさいし、変な事されても困るだろ? だから、とりあえず石にして運び出すんだよ」
その口調は、本当に興味が無さそうだ。人を捕まえるのが彼の任務かなにかなのだろうが、あまり一生懸命仕事に精を出しているようではないらしい。
ここに他の人が居ないのは、運び出されているからなのだろう。そうなると、あの流民も仲間も無事かどうかはわからない。
他のみんながどこに連れていかれたか聞いてみようか、目の前の男なら簡単に喋ってくれるかもしれない。
「みっ!!」
みんなは、と問いかけようとした言葉が突然の轟音と振動で詰まってしまう。
それほど離れていない場所で、爆発でも起きたらしい。
「あんたの為かは知らないけどさ、どうやらこの砦を落とそうと人が集まってるんだ。いいね、やっと戦争ができる。今日まで頑張ってきた甲斐があったよ………おっと」
つり上がった口角を、赤髪の男は手で押さえた。
「ま、そういう事。ああ、でも君の………ああ、君の名前はなんて言うんだい?」
「………」
「名乗る時は自分からだろうって事? 仕方ないなぁ、俺の名前はウーダイオス。一応軍人をやっている。さぁ、君の番だ」
「………私は、正岡すずな」
「そうか、変わった名前だな。今は色んなところから人が来てるんだっけか、まぁよろしく正岡すずな。それでだ、君の持ってた銃という玩具、あれは面白い。初めてみたけど、武器としても上々だ。悪いけど、あれは俺のものにした。それだけ。んじゃ、早くお友達が助けに来るといいね」
そう言うと、ウーダイオスはすずなに背を向けて行ってしまった。
先ほどの爆発以外は、何も聞こえてこない。ここは、随分と外から離れた場所のようだ。
外の様子がわからない以上、自分でなんとかするしかないだろう。ここにやってきた人たちが、彼女の味方になってくれるかもわからないのだから。
φ
すずなが目を覚ます一日前―――。
「我々は、今日まで苦しい戦いを繰り返してきた。誇りに背いて、敵に背を向けてきた。しかし、それも間もなく終わる」
アイアル・ヘシュウァンは粗末な台の上に立って声を響かせていた。
彼の前には、僅かな兵が集まっている。兵達の装備は統一されておらず、見ただけで壊れているのがわかる鎧を身に着けている者も少なくない。
「我々の手から奪われた砦を取り戻す時が来たのだ。四方を城壁に囲まれたあの砦は、かつてより難攻不落とされてきた。だが、見取り図にもない地下通路を我々は見つける事ができた。この地下通路を使い、内側からモンスターを指揮している者を仕留めさえすれば、あの砦に蓄えられた力のほとんどは無意味と化すだろう」
ドン・マルドゥークから兵を借り受け、今日までアイアルは熾烈なゲリラ戦を続けていた。そのため、こうして見渡す兵達の顔に疲労が浮かんでいない者は一人としていない。しかし、まだ諦めの色が浮かんでいる者も一人もいないでいた。
「あの砦にあるであろう兵力は、恐らく我々の数倍か数十倍はあるだろう。だが、あの砦には多くの民が連れ去られているとの報告もある。もし、この戦に負けてしまえば、もう我々に何かをする力もなくなり、そしてさらわれた民達の命運も尽きるだろう。故に、この戦は決して敗北するわけにはいかなのだ。それに、我々にも全く希望がないわけではない!」
アイアルは、地続きの遠くの大地を指差して続ける。
「この地の向こう、シャンバラの子らに応援の要請がなされている。約束通りであるならば、今夜か明日の開戦までにはやってきてくれるとのことだ。これはひとえに、我らがマルドゥーク様のご尽力の賜物である。マルドゥーク様の意思に応えるためにも、そしてなによりこの新たな友の信頼を勝ち取るためにも、この戦は勝利が何よりも求められている。例え剣折れ、鎧を貫かれようとも、この戦だけは決して奴らに譲るわけにはいかないのだ! ………以上だ。援軍が合流するまで、好きに休んでいてくれたまえ」
台を降りたアイアルの表情は、決して希望に満ち溢れたものではなかった。
例え指揮官を倒せても、部隊への損害は深刻なものになるだろう。頼みの綱は、約束された援軍だが本当に来てくれるかどうかはわからない。
それでも、不安を兵に見せずにアイアルは振舞うしかない。今夜、援軍が来てくれると信じて待つしかないのだ。
こうして、彼らの最後になるかもしれない戦いが始まろうとしていた。