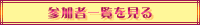「だからさァ、『産学連携』っての? それでやってみようと思ってるワケよ!」
某長寿時代劇シリーズの終了からはや十年。
未だ、時代劇は冬の時代を脱せずにいた。
ここは地上・東京にある某テレビ局。
「やはり『王道の美学』と言いますか、『変わらないこと』が時代劇の長所の一つなのではないでしょうか」
「……ったってよォ、『変わらないこと』で勝負したら、『すでにでき上がっているもの』に勝てるわけねェだろ?」
部下の意見を、田名部常春(たなべ・つねはる)はバッサリと一言で切って捨てた。
確かに、時代劇にはある程度決まったパターンがあり、それを大きく外れることがないからこそ、視聴者が安心して見られる、という部分はある。
しかしながら、それは裏を返せば「できることが少ない」という意味でもある。
その上、十年もすれば確実に「どこか古くさい雰囲気」が漂ってしまう現代劇と違って、時代劇の舞台は今も昔も変わることはなく、従って「過去の時代劇」の全てが「現役のライバル」となってしまうのだから、実に時代劇は難しいのだ。
「だから言ってンだよ、時代劇にも新しい要素を取り入れないと、ってな」
得意そうに言う常春だが、そういった試み自体はすでにかなり以前から行われており……まあ、よくて小当たり程度で、大半はコケている。
そもそも、そこで大当たりするようなアイディアが出ていれば、少なくともこんな厳しい状況にはなっていないはずだ。
そう考えると、彼のやろうとしていることは無謀な挑戦でしかない、のだが。
この常春、実はこのテレビ局のトップの孫なのである。
それ故に周りも変に気を使って、強く止めることができないのだ。
「だとすれば、開拓すべき新天地は一つ……パラミタ以外にねェだろ」
その言葉に、周りのスタッフはさらに頭を抱える。
「困ったときのパラミタ頼り」で率が稼げたのも昔の話であり、すでにパラミタがあることが当たり前となってきている現在では、パラミタというだけではそこまで視聴者の興味は惹けないのである。
とはいえ、「パラミタ+時代劇」という組み合わせ自体は、少なくともこれまでにはあまり試みられたことはない。
意外とそれにふさわしいかもしれない人材がそこそこいるにも関わらず、だ。
はたしてこの企画、吉か、凶か。
悩むスタッフたちに、常春はにやりと笑ってこう続けた。
「実はすでに一度下見に行っててな。意外な収穫もあったんだぜ?」
その言葉とともに、彼の隣のドアが開き、長髪の青年が姿を現した。
「将軍様の英霊だ。今回の企画の監修をしてもらう」
……将軍様?
そういう真っ当な人間がいれば、ひょっとしたら、ひょっとするだろうか?
その期待のまなざしを一身に受けて、青年は堂々とした態度でこう名乗った。
「うむ。俺が鎌倉幕府第二代将軍、源頼家(みなもとの・よりいえ)である」
――ああ、もう、どうしてそっち行っちゃうかなぁ!
スタッフが揃ってため息をついたことは言うまでもない。