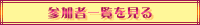シャンバラの某所、古代遺跡にて。
大きな嵐の後、遺跡の調査をしていた調査団たちは、崩れた遺跡の中から奇妙な入り口を発見しました。
岩盤にカモフラージュされていた何かの施設と思しき、大きく口を開いたその入り口をくぐり、調査団たちは奥を目指していました。
「軍事施設か、実験施設……のように見えるな」
調査団のリーダー、クローディスが呟きました。
機晶エネルギーが届いていないのか薄暗いですが、天井はかなり高く、壁面は金属的な素材で出来ており、装飾も無く整然とした様子は、何かの工場か要塞といった雰囲気があります。
「これなんか照明ぽいですしね」
「照明って言うよりはセンサーに見えるな」
調査員の一人が指差したのは、等間隔に壁面に並ぶ、丸いレンズのようなものでした。
動く様子もありませんが、確かにセンサーのようにも照明のようにも見えます。
そんなレンズが並んだ、他に横道の無い真っ直ぐな通路を進むこと十数分ほど。
調査団は、唐突に開けた場所に辿り着きました。
ライトを正面へ向けても、その先が見通せないほどの広さをしたその場所は、何本かの大きな柱があり、その中央に当たる位置に、黒い半月型のオブジェが鎮座しています。
「何だ、こりゃ」
クローディスが首を捻りましたが、結局、それが何かわからないまま、更に奥へと足を進めた調査団は、最奥地へと辿り着きました。
「かなり大掛かりな装置だな……」
こじ開けたドアの先、遺跡の中央制御室と思われるその部屋には、物々しい装置が所狭しと並んでいました。
施設内のあらゆる設備の制御を司るその装置には、簡単な注釈がいくつかあり、防御システム、自動攻撃システム、などといった単語から、見たところ、どうやら軍事施設のようですが、手入れがされていないため、計器も埃を被っていました。
「随分使われていないもののようですね……例の5000年前頃のものとすれば、当たり前ですけど」
調査員のサブリーダーツライッツが装置を調べながら言います。
「動かせそうか?」
「どうなんでしょうね……あ、これが、主電源かな」
クローディスの言葉に唸りながら、手探りで見つけた一つのスイッチを入れた、その時でした。
『エネル、ギー供給確認。シス、テムノ起動ヲ開、始シマス――……エラー、施設、内ニ異常ヲ、感知シマシタ』
制御中枢のコンピュータから流れた自動音声がそう告げるのと同時、施設内の照明が一気にその光を溢れさせたかと思うと、けたたましい警告音が、施設内に響き渡ったのです。
『自動防御シ、ステム、起動シマス――……中、央ロビー、守護者起動』
微妙に音程の狂ったアナウンスが、途切れ途切れに流れ、ガシャンと金属的な音が、先ほどの広間の方から聞こえてきます。それに不吉なものを感じる暇もなく、アナウンスは続けます。
『機晶ワーム、ノ、半重力場発生カク、ニン。機晶ワーム、攻勢防御、開始、シマス』
ヴウン、と制御装置のいくつかが点灯したかと思うと、どこかで大きな機械音が響き渡りました。
『”フレイム・オブ・ゴモラ”起動シマス。動力装置トノマッチング作業開始。充填率0.001%』
「フレイム・オブ・ゴモラ?」
神話を思い起こさせる、その不吉な単語に、クローディスが眉を潜めました。
「まさか……兵器か!?」
「大変だ!」
叫ぶクローディスに、青ざめた調査団の何人かが、動転たのか、中央制御室から走り出しました――が。
「ぎゃあ……っ!」
ドリルが地面を抉っている時のような、ガガガッという音と共に叫び声が響き、慌ててその方向を見たクローディスは、息を呑みました。
先ほど通ってきた広い空間の中央にあった、モニュメントのように蹲っていた、巨大な機晶兵器が、鳴り響く警告音によって目を覚まし、尚悪いことに、調査団たちを敵として認識したようです。
咄嗟に中央制御室のドアを塞いだことで、見失ったのかそれ以上攻撃することはありませんでしたが、最悪の事態は、まだ終わりではありませんでした。
『リーダー、何事ですか!? こっちに変な機械が……わああッ!』
入り口付近の調査に残っていたメンバーからの通信に、悲鳴が混ざりこみました。
その場所から見ることはかないませんでしたが、そのとき、入り口からの続く通路に並んでいたレンズ――それら、壁に格納されていた機晶ワーム達が、危険信号を受けて壁からずるりとその姿を現していたのです。
そして――……
「まずいですよ、リーダー……」
ツライッツが緊迫した声で言いました。
ガラス張りの中央制御室から見えた地下にある巨大な砲台が、”フレイム・オブ・ゴモラ”であるのは明らかでした。
「点灯、してます。起動――しようとしてる」
最後は独り言のように呟くツライッツに、クローディスは肩を揺さぶるように強く掴みました。
「ツライッツ、制御装置は!」
その言葉にはっとなり、ツライッツを含めた調査団員たちは、急いで装置を調査し始めましたが、状況は絶望的でした。 長い間使われないでいたためか、それとも天災が何かの影響を与えたのか、システムは上手く起動せず、施設のシステムはコントロールが効かなくなっていたのです。
「照準は、空京を指しています。このままじゃ……!」
システムの表示を信じるなら、この兵器は町を一つ焼き尽くすぐらいはわけの無い程の威力を持っているのです。そんなものが、人口の密集地域へ攻撃を加えればどうなるか。悲痛な声に、クローディスは滲む脂汗を拭いながら「落ち着け」と皆に声をかけました。
「幸いにも、あれは起動したばかりで、エネルギーも十二分に無いようだ。発射されるまで、まだ時間がある」
冷静にそう告げると、クローディスは現在の位置や状況、調べられた限りの情報と共に、各方面へ一斉にSOSを送りました。
勿論、ただ助けをまつわけにもいきません。調査団は、中央制御室の調査を急ぎはじめました。制御装置さえ直れば、止めることは出来るはずです。
「とにかく、情報を集めろ。ツライッツ、君は動力室へ向かってくれ。動力の方をカットできるかもしれん」
「はい」
ですが、間に合うかどうかは五分五分、といったところなのも、良くわかっていました。
「最悪の場合、ここを兵器ごと吹き飛ばしてしまうしかない――」
リーダーの言葉に、生き残った調査団のメンバーたちは、顔を真っ青にしながらも、強く頷きました。