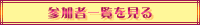――前回までのあらすじ――
人喰い勇者ハイ・シェンの生誕三百周年を祝うカーニバル。
しかし、華やかな表舞台とは一転。この街の暗部では、犯罪結社コルッテロの恐ろしい計画が進められていました。
結社の構成員であったリュカは計画の鍵であるペンダントをどうにか持ち去り、命からがら逃げ延びました。
そんな彼女とカーニバルの一日目に出会った観光客の彦星明人は、彼女に一目惚れし、協力することを決めました。
それが全ての始まりだとは露知らず。
結社の追っ手を振り切り、五日目まで生き残った二人は数名の契約者と合流しました。
しかし、六日目にリュカが倒れたことにより、これ以上の逃亡を断念。特別警備部隊による保護を廃墟にて待つことを選びます。
同時期、部隊の詰所に赤い手紙が届きました。
手紙は強奪戦という殺し合いへの招待状。六人の子供を人質にとられた彼らはそれに参加するしかありませんでした。
アルマ・ウェルバやストゥルトゥスを初めとした多くの死者を出し、カーニバルの六日目は終わりを迎えます。
部隊は明人とリュカの保護に成功、また強奪戦にて子供達を逃がすことにも成功しました。
だが、結社の首領であるアウィス・オルトゥスの卑劣な罠にかかってしまいます。
強奪戦に参加した面々は疲弊したところを狙われ、圧倒的な物量により、倉庫だった廃墟への篭城を余儀なくされました。
彼らの命と引き換えに、アウィスはペンダントを求め、部隊に交渉を持ち掛けます。
残りの者達はそれをとりあえず受けることにし、他の面々を助けるために強奪戦の会場へ向かっていました。
その裏。
ルベル・エクスハティオ改め、ハイ・シェンが第三の勢力を立ち上げます。
目的は復讐。
自分の家族を失うきっかけとなったこの街、そして関連する者を全て壊しつくすことが、彼女の望みです。
この一連の事件を終始操っていたヴィータ・インケルタは、少々道筋は違えども自分の思い通りに事が運び、小さく笑みを零しました。
そして、カーニバルは最終日を迎えます。
三つの勢力全てが最南端の区画へと集結し、長い祭りを締めくくる戦いが始まろうとしていました。
――――――――――
特別警備部隊
自由都市プレッシオ、最南端の区画。
強奪戦に参加した部隊の者達は倉庫だった廃墟に集まり、篭城しています。
「すぐに他の皆が来てくれる。それまで生きるんだ。まだ、まだ……希望を失うなっ!」
煤原大介の声が、広い室内に反響しました。
周りには重度の負傷者たちが寝かせられていて、戦えない軽度の負傷者たちが彼らの治療に当たっています。
大介もその中の一人であり、手際こそ良くはないがフランに教えてもらった知識を思い出しながら懸命に当たっていました。
「だから死ぬな。戻ってこい、頼む、戻ってきてくれッ!」
しかし、彼らの努力は報われません。
医療器具も満足にない、衛生状態も最悪なこの場所で、失いかけている命を救うことなど到底出来るはずがないからです。
「死にたくない、嫌だ嫌だ、たすけて」
脊髄を砕かれたある男は、吐血に噎びながらすすり泣きました。
彼の赤黒い手は助けを求めるように大介の顔に触れ、やがて、温度と力を失い床に落ちます。
「……くそっ、ちくしょう」
大介は付着した血液を拭うことなく、肩を震わせました。
仲間が死んだ、助けることが出来なかったと。自分の無力さを嘆き、怒り、叫びます。
「チクショウ、チクショウッ!」
悲痛な声を耳にした李 梅琳(り・めいりん)は痛む心を我慢しつつ、気丈に振舞っていました。
それはリーダーである彼女が一度崩れれば、ぎりぎりのところで持っているこの部隊が壊滅してしまうからです。
梅琳は廃墟の内部を見回しました。
大きな嵐に晒された小屋のように建物全体がガタガタと震動しています。
この建物を包囲する構成員達が内部に侵入してくるのも、時間の問題のように思えました。
(不味いわね。これ以上建物を攻撃されるのは。時間を稼ぐには……)
そう判断した梅琳は、白銀の刀を抜き、まだ戦える者達に号令をかけました。
「行くわよ。私に続けぇぇっ!」
梅琳は危険を承知で走り出し、倉庫の大きな扉を一気に開けて、外へと飛び出しました。
圧倒的な数に立ち向かいます。
彼女に続いて、他の者たちも向かっていきます。
その猛々しさに一瞬だけ、マシンガンを構える構成員たちの目が恐怖で揺れました。
「抗うわよ、最後まで――!」
最南端の区画に、梅琳の咆哮が響きわたりました。
◆
強奪戦に参加しなかった部隊の者たちは、やっと最南端の区画にたどり着きました。
その中の一人――彦星明人は首にかけた計画の鍵であるペンダントを片手で握り締めます。
それはリュカが守った物であり、親友達の思いが込められた遺品でもあり、そしてアルマ・ウェルバが死ぬことになった原因の一つでもあります。
(……助けるべき仲間がいる。終わらせるべき戦いがある)
明人は一瞬だけ目を伏せ、開き、鋭い目つきで区画を睨みました。
激しく打ち鳴る戦音。音だけで、戦闘の激しさが手にとるように分かります。
(僕はもう迷わない。誓ったんだ。
リュカの前では、本物のヒーローになるって誓ったんだ)
明人は決戦を前にして震えだす手を握り、無理やり押し込めました。
(その言葉を嘘にはしたくない。だから、僕は前に進む。進んでやる)
進むべき道は決まっています。
ならば、とるべき行動は一つだけ。
「行きましょう。これが、最後の戦いだ……!」
そして高級マンションのように趣味の悪い建物――アジトに向かい、駆け出しました。
その心に精一杯の勇気と決意を。
覚悟を決めた一人前の戦士は、今日よりも幸せな明日に繋がる道を進んでいきました。
――――――――――
犯罪結社コルッテロ
「ひひひ……あっひゃっひゃっひゃっひゃ!」
コルッテロのアジトの最上階には、アウィス・オルトゥスの哄笑が響いていました。
「っひは、頑張るねぇ。
つくづく滑稽だぁ……滑稽、滑稽、滑稽、滑稽ッ!」
色とりどりの宝石に彩られた五指を口元に引き寄せました。
金色の両目は喜悦に満ちています。
モニターには、圧倒的な数を相手にしても心の折れない部隊の者達が映っていました。
「一人たりとも逃がすんじゃねぇぞ。
ゆっくり、じわじわと追い込んでいくんだ。
そいつらに許された運命は、隷属か絶望の死か、それだけなんだからよ」
包囲する構成員たちに殺せ、と命令すればいともたやすく蹂躙できます。
多くの命が自分の掌の上にあるという愉悦に浸り、唇がことさらに吊り上がりました。
「それがコルッテロに弓引いた奴の末路なんだからよぉ!」
アウィスは邪悪に満ちた笑みを浮かべながら、振り返りました。
壊れたガラスの外には、プレッシオの街並みが広がっています。
望めば何でも与えられてきた彼が、いくら欲しくても欲しくても決して手に入ることのなかった御伽の町が、美しい情景が、広がっています。
「もうすぐだ。もうすぐ、やっと、この街が俺様のもんになるんだ」
アウィスは我慢出来なくなった子供のような口ぶりで言いました。
これから起こる出来事を想像し、計画が成功に近づいている事を実感して、どこまでもどこまでも胸を躍らせながら。
◆
廃墟前の戦闘を一望出来るどこかの屋上。
そこで、ひとりの狂人が恍惚な表情で眼下の光景を眺めていました。
「ああ、ああああ、ああ――素晴らしい、素晴らしいよ。本当に素敵だね」
髪も肌も恐ろしいほど白い青年――ルクス・ラルウァは動悸を押さえつけるように胸を掴みます。
決して諦めることない部隊の面々。
その姿はどこまでも気高く、美しく……彼女らの一挙手一投足が、ルクスの胸を強くつよく高鳴らせていました。
「こんなに僕を恋焦がらさせるなんて……ああっ、なんて罪作りな人達なんだ、彼女らは!」
両目を一杯に広げた青年は、細い二本の手を横合いにゆっくりと伸ばしました。
バターが溶けるように顔に広がる無邪気な悪意は、中性的な容姿にだんだん浮かび上がっていきます。
「さぁ愛し合おうじゃないか! 僕たちの劇場で愛を堪能しようよ恋人たち!!」
兵器のような破壊力を持つ両手。
人を殺すには十分すぎる威力を有した両手を水平に広げ、青年は笑っていました。
白のイメージから遠く離れた、歪(いびつ)に歪(ひず)み歪(ゆが)んだ笑みを。
◆
廃墟前のすぐ近く、メインストリート。
ニゲル・ラルウァは鉢合わせになったアルブム・ラルウァを見て、目を丸めました。
「あーららっ、そんな傷だらけで一体どうしたんだよ?」
「……少しみすっただけ」
「要するに、負けたってことか?」
「……びーくわいえっと。次は勝つ」
そっぽを向くアルブムに、ニゲルは頭を掻きながら言い放ちました。
「幾分かマシになったと思ってたのによぉ……やっぱ、相変わらず弱ーんだな、てめーは」
「ッ、黙れ!」
アルブムは血相を変え、鋼糸をニゲルの首元へと張り巡らしました。
「……あたいは強い。あたいはラルウァ家の一員なんだッ」
食い込んだ鋼糸はぷちゅと水っぽい音をたて、皮膚を僅かに切り裂きました。
アルブムが少しでも指を動かせば首が断ち切られるというのに、ニゲルはさして気にした様子もなく、呆れたようにため息を吐きます。
「強い奴は次は勝つなんて言わねーよ。
負けちまったらそこでお終いだ。俺たちみてーな職業は特にな。
だから、腕を飛ばされようが足がもがれようが、立ち向かう事は決して止めねーよ」
アルブムは目を開き、悔しそうに唇を噛み締めました。
「そんな中途半端な覚悟なら、殺しの仕事なんて止めとけよ。邪魔なだけだ。
ったく、だから俺は当主様にあれだけ進言したんだ。ニゲルは殺しの仕事に関わらせるんじゃなく、家を守らせておいたほうがいいってな」
「あたいは、あたいは――ッ!」
「あたいはなんだよ? ちょっと殺しを経験したぐらいで図に乗りやがって。
技術は確かに成長したかもしんねーが、てめーの精神はやっぱまだまだラルウァ家の一員には程遠いぜ?」
「……っっ!」
アルブムは打ちのめされたような表情で、涙を堪えながら絡めた鋼糸を解きます。
ニゲルは滲んだ血を掌で拭い、首を何度か左右に振ってから、すれ違い様に囁きました。
「んな風に言われたくねー、認めてほしい。
そう思うんなら、もっと死ぬ気で事に当たれよ。んで、生ある限り最善を尽くせ。そういうこった」
アルブムは顔を隠すように俯き、まるで迷子の少女のように震えた声で呟きます。
「……あたいは、弱くない。出来損ないなんかじゃない。あたいも、立派なラルウァ家の一員なんだ」
ニゲルは面倒くさそうに頭をボリボリと掻きます。
そして口の中で独りごちた言葉は呆れたようでもあり、手間のかかる妹を持つ兄の愚痴のようでもありました。
「ったく、まだ引きずってやがんのかよ……んな昔の事忘れろってーの」
――――――――――
第三の勢力
「てめーらはコルッテロが雇った傭兵だろ!?」
光が届かない路地裏で、一人の構成員が縛られていました。
彼を険しい目で見つめるのは、腰に武器を差した幾人もの男と女。その大半がコルッテロに雇われていた傭兵達です。
「俺はコルッテロの一員だ! てめーらの雇い主の部下だぞ!!」
構成員は必死に身を捩るが、幾重にも巻きついた鎖は解けません。
彼が叫ぶも、周りの傭兵達は動きませんでした。直立不動のまま立っています。
「アタシ達は、コルッテロとの契約を切らせてもらう」
冷たい女性の声が響きます。
構成員が視線を動かすと、路地裏の奥の闇に人影が立っていました。
「コルッテロも特別警備部隊もこの街も、アタシは全てを壊しつくす」
その人影であるルベル・エクスハティオ――いや、ハイ・シェンは歩み出し、構成員に顔を近づけました。
互いに息がかかるほどの接近。
構成員が恐怖で硬直しました。それは彼女の瞳に潜む底知れぬ悪意と憎悪を本能的に感じたからです。
「だから、命をもらうわ」
赤毛の女は真紅の刀身を構成員の口内へとねじ込み、悲鳴を抑えます。
業火のように紅い目で彼を見下ろしながら、ハイ・シェンは言いました。
「最初の犠牲者はアンタよ」
ハイ・シェンが真紅の槍を押しました。
皮を突き抜け、骨を粉砕し、肉を破壊しながら、刀身が頭の中に入っていきます。
殺意の炎が刃に点り、構成員の頭が爆発しました。
顔面は細かい肉片がボロボロの炭となって飛び散ります。両側頭部からは、バラバラに砕けた頭蓋骨の破片と、脳漿や体液の混ぜ合わせが吹き出しました。
構成員の顎より上は何もなくなり、下顎と焦げた舌が、さらけ出されます。
肉が焼ける異臭が、路地裏に香り立ちました。
「……賽は、投げられたわ」
ハイ・シェンは刃に付着した血液と体液を蒸発させ、振り返りました。
紅の双眸に晒された傭兵達は、無言で肯定し、彼女の次の言葉を待ちます。
「ならば、アタシらがすべきことはただ一つ。
正義を掲げる契約者を殲滅し、それに乗じて刃を向ける構成員の牙を折れ。
血を恐れるな。赤き血潮こそが力の源。アタシらの血で奴らの血を洗い落とせ」
紅い目はすべてを凍らせるように鋭く、冷たくなります。
一瞬の間を置いて、肺から空気を搾り出したような声をあげました。
「今より復讐を開始する。鉄槌は夜明けの光とともに――!」
世界を呪うように。
叫んだ女の声は、開戦の狼煙となりて街に響きわたりました。
◆
傭兵たちが散った後、ハイ・シェンはある人物を探していました。
やがて、自分を生まれ変えさせた禁忌の術式の前に立つ目当ての人影を見つけ、非難するような視線を向けます。
「……そんなとこで何ぼけーっとしてんのよ」
声に気づいた人影は背中に広がる上質なマントのような金髪を翻し、振り返りました。
ハイ・シェンが思わず息を呑みました。
ヴィータ・インケルタ(う゛ぃーた・いんけるた)がその美しい顔に、薄ら笑いを浮かべていなかったからです。
「おんやぁ? こりゃまた、びっくらこんこんなリアクションしてどうしたの?」
先ほどまでの表情が白昼夢だったように、ヴィータはニヤニヤと笑みを作っていました。
見間違いかと思い、ハイ・シェンは一つ咳払いをした後、用件を話し出します。
「アンタに聞きたいことがあるの」
「場合によってはノーコメントで。スリーサイズとか、男性経験とか」
「……アタシが知りたいのはただ一つ。この得体の知れない感覚のことよ」
ハイ・シェンは自分の手をまじまじと見つめ、拳を握り、また開きます。それは、何かを確かめるような仕草でした。
「自分が強くなったことはありありと感じられる。
けど、それ以外に変な感覚がアタシを包んでる……アンタならこの正体を知ってるでしょ?」
その問いに、ヴィータは口の端を僅かに持ち上げました。
そして両手を頭上に挙げると、パチパチとやる気のない拍手を送りました。
「いやぁ、すごいすごい。もうそれに気づいちゃったんだ。
教えてあげようか? それはね、人喰い勇者の術式のもう一つの効果だーよ」
ヴィータは地面に描かれた血の式を指差しました。
「この術式には二つの効果があるの。
一つは、あなたがその身で体験した壮絶なまでの強化。
愛する人の肉を喰らうことで憎悪と悪意をとことん拡大させて、その生命を人ならざる高みへと昇華させる事」
薄紅色の唇に人指し指を当てて、ヴィータはにぃっと口元に笑みを作りました。
「そしてもう一つは、取り込んだ魂を異なるモノへと変貌させる事よ」
「……それが、この不思議な感覚の正体だって言うの?」
「そ、いえーす。パンパカパーン」
くす玉が割れる擬音を口にして、ヴィータはにっこり微笑みました。
「変貌させるものは何でもござれ。あなたの意思で選びなさい。
戦うための武器にしたり、身を守る防具にしたり――または、フラワシなんかに生まれ変わらせたりね」
ハイ・シェンはごく僅かに表情を和らげました。
姿かたちは違えども、ベリタス・ディメントと共に復讐する事が出来るのです。
生前の彼に思いを馳せながら頭の中で少しずつイメージを固めていると、ヴィータが最後に言いました。
「って、少ししゃべりすぎたかな。
そんじゃ、そろそろわたしは行くけど……あとで後悔しないよう慎重に選びなさいよ」
ヴィータはくるりと踵を返します。
その華奢な背中を見つめ、ハイ・シェンは思考を中断し声をかけました。
「……それは、アタシに同情してのアドバイスなの?」
「ノーコメントで」
「答えてよ。三百年前この街を救った――人喰い勇者ハイ・シェン」
ぴたりと足が止まります。
ヴィータは振り返りこそしなかったが、意識をハイ・シェンに向けながら静かな声で答えました。
「ただの経験談よ。敗者である惨めなわたしのね」
「――敗者?」
「自分の愛する人を救えなかった。それ以上の敗北なんてこの世にないでしょ?」
ハイ・シェンが口を結びます。
ヴィータは再び歩き出し、路地裏の闇に溶け込むように消えていきました。
◆
カツン、カツン、と路地裏に靴音が反響します。
暗闇を掻き分けるように進むヴィータの顔には笑みなど一切存在せず、余裕のない表情でした。
「あーあ、また失敗か。
これだけお膳立てしてるのに、なんであの人は現れないのよ」
ヴィータは足を止め、建物に切り取られた空を見上げました。
夜明けの光が差す空は薄暗く、うっすらと星の影を確認することが出来ます。
最愛の彼――モルスと初めて出会ったは、この空に少しだけ似ている星影さやかな夜でした。
(少しだけ昔を思い出しちゃうなぁ……)
町の状況なんて最悪で、びっくりするぐらい貧乏で、それでも満ち足りた日々。
彼がいるだけで楽しくて、嬉しくて……不満は少なからずあったけれど、それを上回る幸せがそこにはありました。
そんな幸福を。
失ったあの日の出来事は三百年経っても薄れることなく、鮮明にありありと思い出すことが出来ます。
「ほんっと、嫌になっちゃう」
仲間の治療によってくっ付いた左腕を伸ばし、星を透かすように見ながら自嘲する風に言いました。
「小さなこの手は、そんなちっぽけなものも掴めないんだから」
ヴィータは悲しそうに目を伏せ、左手を胸の前に引き戻します。
(……悪いのは自分。そんなことぐらい分かってるんだけどね)
実行した正義を否定こそしないが――復讐という甘美な誘惑に負け、愛する彼を永遠に閉じ込めてしまったのは事実。
他ならぬ自分の力、最強の武器として。
あれほどまで身も心も美しかった彼がこんな化け物に成り果てるとはついも想像しなかったが……それでも、これが彼が変貌したモノだと思えば、それはそれはとても愛しい存在に違いはありませんでした。
だが、それだけの話。
今のモルスはフラワシであって、自分を愛してくれた彼ではないのだから。
(だから、取り戻さなくっちゃ)
愛しい彼を。
どうしようもないぐらい大好きなモルスを。
(わたしがナラカでもう一度生を受けたとき、決めたでしょ)
三百年前に禁忌の知識を与えてくれたあの人から、魂を解放する手立てを聞きだすと。
そのために自分は身も心も悪となり、ゲームと称して何度も何度も色んな物を壊してきたのだから。
自分と同じように絶望的な状況を再現できればあの人が現れる――そんなあるかどうかもわからない希望を信じているのだから。
「しかも自分が救ったこの街さえ、壊そうとしているんだから……ね」
ヴィータは小さく笑いました。
生前にやった事を無駄にしちゃったなと。
愚かな自分を嘲笑うように笑い声を洩らし――もう一度、心の奥底で決意しました。
嘆きはいらない。
怒りはいらない。
憎みはいらない。
どれもいらない。彼を取り戻すには、どれもいらない。
必要なのにはただ――この理不尽な定めに、残酷な世界に、邪魔する正義に、立ち向かう覚悟だけだ。
笑い声が止まります。
俯いた顔を上げます。
「きゃは♪ さあて――」
ヴィータは、いつも通り嗤っていました。
「運命を叩き潰すゲームを始めましょう」