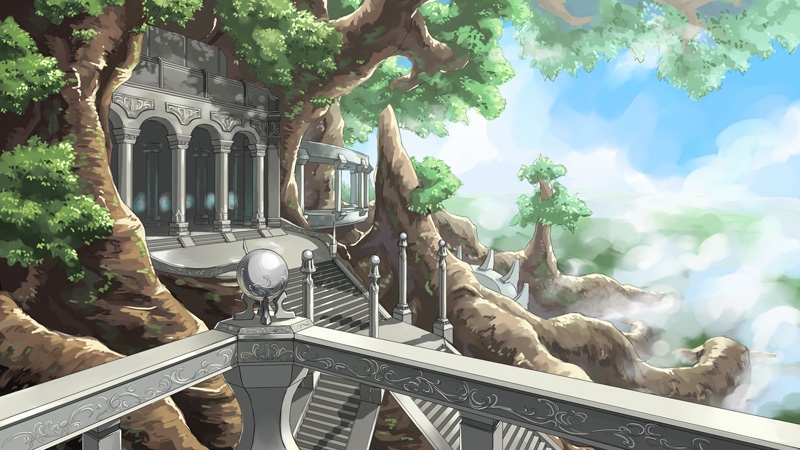リアクション
キマクにて 「俺はここで、シオン・グラード(しおん・ぐらーど)と会う予定になっている」 ナン・アルグラード(なん・あるぐらーど)が、キマク荒野の一本道で、目の前にいるレティシア・トワイニング(れてぃしあ・とわいにんぐ)に言った。 「我も、ここでフレンディス・ティラ(ふれんでぃす・てぃら)と会うことになっておる」 少しも動じず、レティシア・トワイニングが答えた。 「邪魔だ、どけ」 「ゆえに、退け!」 おたがいに一歩も引かずに両者が言い放った。さすがは、梟雄同士、引くことを知らない。ちなみに、道の左右は見渡す限りのシャンバラ大荒野で、すれ違えない方がどうかしているわけだが。 「なら仕方ない。排除するだけだ」 「その通り」 変なところで意気投合する二人であった。 「お待ちください、ナン様」 ナン・アルグラードのお供をしていたニャンルー山田が、スッと前に進み出た。 「このような者、私で充分ですにゃ」 「えっ……」 山田を見たとたん、初めてレティシア・トワイニングが動揺をみせた。実は、レティシア・トワイニングもお供ニャンルーとして、ニャンルー・モミジとニャンルー・サクラの姉妹を連れている。実は、極度のニャンルーマニアだったのだ。 「見てくだにゃい。敵は、私を恐れて尻込みしています。殺れます」 レティシア・トワイニングの様子を見て、山田がすでに勝ちを確信した。 「レティシア様ー。ボクたちが戦いましょうかあ」 レティシア・トワイニングを守るように、モミジとサクラが彼女の前に出る。 「二匹か。一匹では力不足と見える。なあ、山田よ」 「はっ、そのようでございますな」 カラカラと笑うナン・アルグラードに、チラチラとサクラの方を見ながら山田が答えた。 「くっ……。山田が可愛いのは認めよう。だが我のモミジとサクラは優秀で愛らしいのだぞ?」 負けじと、レティシア・トワイニングが言い返した。なんだか、話の焦点がおかしい。 「まあいい。二対一でも遅れはとらないだろう。なあ、山田よ」 ナン・アルグラードの言葉に、山田がうなずく。 「その心意気やよし。ならば、これを授けよう」 そう言うと、ナン・アルグラードが山田にロケットランチャーを見せた。 「はは」 うやうやしくそれを受け取ろうとする山田だったが、なんだかでっかすぎて扱いにくい気がする。はて、ペット用のロケットランチャーのはずなのであるが……。 「これは、どうやって扱ったら?」 「これはな、こうやって使うのだあ!!」 山田に聞かれて、ナン・アルグラードがロケットランチャーを自ら構えた。そのロケットランチャーに装填されたのは、なんと山田である。 「ゆっけー、やあまあだあぁぁぁぁ! 敵を粉砕するのだあ!」 「にゃあぁぁぁぁぁ!!」 ロケットランチャーから発射された山田が、一直線にレティシア・トワイニングにむかって飛んでいった。 「にゃああ!!」 あわてて受けとめようとするレティシア・トワイニングよりも先に、サクラとモミジが山田を受けとめた。そのまま猫団子となって、ゴロゴロと転がっていく。 「くっ、山田を投げるとはかわいそ……もとい卑怯な真似を。粗末にするならば我が貰い受けるぞ」 「ふっ、山田が俺を裏切るものか。お前のところとは信頼が違うんだ」 「投げた時点で捨てたも同然。もう貰った!」 言い合う二人が振り返ると、三匹のニャンルーたちはのんびりと名刺交換をしていた。 「おたがい、大変だにゃー」 「まあ、いつものことだーにゃ」 「これを期に、お友達になりたいにゃー」 なんだか、ニャンルー同士でいつの間にか和んでしまったらしい。 「こら、何をしている」 「きゃー、和んでる♪」 あわてて駆け寄ると、二人が自分たちのニャンルーをだきかかえた。放っておくと、相手に連れ去られてしまいそうだったからだ。 「覚えておけ、お前が勝ったのではない、そのニャンルーのおかげだということを!」 たがいに捨て台詞を吐くと、ニャンルーをかかえて元来た道を戻っていく。 そしてしばらくして、シャンバラ荒野のど真ん中で、ポツンと待ちぼうけするシオン・グラードとフレンディス・ティラの姿があった。 |
||