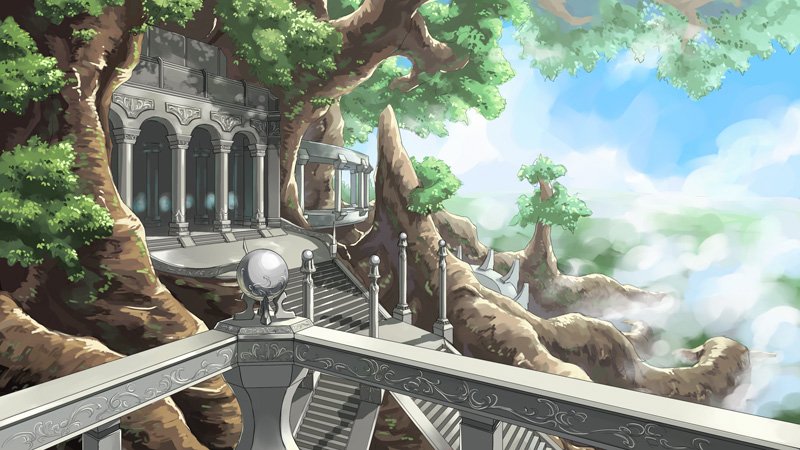リアクション
◇ ――森の中。 「……いつまで付いてくるつもりだ?」 木々の合間を縫って散策をしていた七夜 織(ななや・しき)が、振り返りながら半眼で問う。視線の先では、斎藤 ハツネ(さいとう・はつね)が、薄笑いを浮かべて首を傾けていた。 「あ……あの、ご迷惑、ですよ、ね」 ハツネの横では、天神山 葛葉(てんじんやま・くずは)がオロオロと目を泳がせるだけで、明確な回答は帰ってこない。 「迷惑というよりも……どういうつもりだ?」 「えっと、すみません」 「…………」 視線が合わないハツネは元より、葛葉はひたすら申し訳なさそうに頭を下げるのみで話が進まない。 織としては、この物語に登場する『狼』を誰よりも早く見つけ出して、手柄を上げようと考えている為、誰かが付いてくるこの状況は好ましくない。当然、この物語が狼を倒したところでハッピーエンドになり、それが手柄となるかは別の話だが。 織が深い溜息を吐ききった時、生い茂る草の向こう側から、低い唸り声が聞こえた。 ハツネ達を気にする事を止め、織は走り出した。距離はそう遠くない。 携えた竹箒に仕込んでいる刀を引き抜いて、視界を邪魔する草を切り払うと、その先では師王 アスカ(しおう・あすか)と、一匹の狼が対峙していた。 牙を剥き出しにして唸り声を上げる狼に、アスカは武器を構える事もせずに、ゆっくりと語りかける。 「貴方はオオカミですか? これからどこにいきますか?」 低い姿勢で威嚇を続ける狼に、アスカは問い続ける。言葉が通じるかはわからないが、ここは本の中。もしかしたら、対話が可能かもしれない、と。 「……貴方は赤ずきんに食べられますか?」 変わらず威嚇を続けていた狼が、ピクリ、と反応を見せた。そして突然、大きく口を開いてアスカに襲い掛かる! しかし、鋭い牙はアスカに届く前に、織の手にした竹箒によって防がれていた。 「危……ねぇな! あんた、さっさと逃げろよ」 狼の牙を、織が身体ごと押し戻す。 (そのまま倒してくれねぇかなぁ) やや離れた位置から、その様子を見ていたアキラ・セイルーン(あきら・せいるーん)が胸中で呟く。 この物語の真意はわからないが、とにかく赤ずきんと狼を会わせずにいれば、全て穏便に終わるのではないか。そう思って捜索をしていたところ、狼と戦っている織を見つけたのだ。 「危なくなったら助けるけど、な。とりあえずは頑張ってく……あ?」 傍観を決め込もうとした瞬間、僅かに地面の振動を感じたような気がして、アキラは振り向いた。 樹々の向こうで土埃が舞っている。よく見えないが、何かが接近しているようだ。 次第に大きくなる振動と、音。 それは、地面を埋め尽くさんばかりの、集団の狼だった。 「はは……何の冗談だよ、こりゃ」 アキラは、雪崩の様に押し寄せてくる狼の集団を見て、その場から逃げ出した。 ◇ 「ねぇ、寄り道って何をするの?」 「お花を見たり、お話したりするの」 「おつかいはよくやるの?」 「ときどきだよ」 芦原 郁乃(あはら・いくの)の質問を、小さなバスケットを抱えながら赤ずきんが答える。 『真実で誠実で確実』な赤ずきんの言葉を引き出して、郁乃はこの物語の情報を出来るだけ理解しようとしていた。 だが、赤ずきんは思いの外、自分から口を開かなかった。特に地図を見るわけでもなく、ひたすら淡々と歩いていく。 やがて、歩いていた道の先が開けて、湖畔にたどり着いた。 「娘。お前のずきんは白いままか?」 笑顔を浮かべながら、座り込んで湖の側に咲く花を見ていた赤ずきんに、高柳 陣(たかやなぎ・じん)が聞く。 この物語から出るのに一番早いのは、やはり主人公の赤ずきんについてくるのがいいだろう、と近くには居るが、完全に信用はしておらず、警戒の色は濃い。 赤ずきんは、しばらく首をかしげていたが、やがて何かを思いついたように自らの頭巾に手を伸ばした。 「白いときもあれば、赤いときもあるよ」 「……?」 警戒を解かずに陣が見ていると、赤ずきんは被っている頭巾の裏地を見せてきた。捲る頭巾の裏地は、鮮やかな赤。 「……リバーシブル?」 陣の後ろから顔をのぞかせて、ティエン・シア(てぃえん・しあ)がそう言うと、赤ずきんは嬉しそうに頷いた。 はにかむ赤ずきんに、ティエンが近づいて隣に座る。 「おばあちゃんは元気なの?」 「おばあちゃんは、いつも元気だよ」 ティエンの質問に答えながら、赤ずきんは花を摘み始める。白い小さな花弁の付いた花を丁寧に集めていく。 「僕たちより前に来たヒトは、みんな自分のお家に帰れたのかな?」 「お家には帰れたよ」 淀みなく答える赤ずきんに、ティエンは陣に視線を送る。陣はその回答を聞きながら、眉間に皺を刻んでいく。 (その答えはおかしい……この本の中に入った人間は誰一人帰っていないはず) 軽く首を縦に振る陣を見て、ティエンは再び赤ずきんに向かって質問を続けた。 「狼さんは君と同じお肉を食べるの?」 その言葉に、花を摘んでいた赤ずきんの手が止まる。 ゆっくりと顔をティエンに向けた赤ずきんは、小さくかぶりを振るだけで、結局何も答えなかった。 ◇ 「えっと、ねぇ北斗……ここはどこ?」 「知らねー」 同じ景色が広がる森を歩く天海 護(あまみ・まもる)の疑問に、パートナーの天海 北斗(あまみ・ほくと)が、キッパリと答える。 「ちょっと! それって迷子じゃん!」 「知らねー」 「あ、誰か人がいるみたいだよ? ちょっと行ってみよう?」 「知ら ……ぉ、おぅ」 半ば機械的に返事をしていた北斗が、どもりながら護の方へ向き直る。 「あれ? 護お兄さんと北斗、二人もここに居たのか」 護達に気が付いて振り返ったのは、セルマ・アリス(せるま・ありす)だった。周囲を警戒しながら、セルマは護に手を上げる。 「ここが『赤ずきん』の中ですか、凄いですねー」 隣では、辺りを見回しながら、オルフェリア・クインレイナー(おるふぇりあ・くいんれいなー)が嬉しそうに声を上げている。しかし、その傍らでは、オルフェリアのパートナー不束 奏戯(ふつつか・かなぎ)が、膝を付いて涙に暮れていた。 「俺様、家で『マザーとトゥギャザー』見てたはずなのに……リアルタイムで見れると思って録画してないんだぜ!?」 膝を付いた姿勢のまま怒声を上げる奏戯に、オルフェリアは下唇を噛み締めながら瞳に涙を溜めていく。 「奏戯と一緒に……本の中に入れたら……楽しいか、と、お、思って」 「あ、うそ、嘘嘘すいません。オルフェちゃん泣くの我慢しないで、良心がとがめるから」 今にも零れそうなほどに溜まった涙を見て、奏戯が慌てて立ち上がる。 「もういいから!! 諦めるから!! うんそれでいい。うん……うん」 奏戯のその言葉に、オルフェリアの顔に笑顔が浮かぶ。 「じゃあ、記念にサインを貰いに行くのです♪」 「ややまる……ぴっこる……ほーろり」 溜息混じりに奇妙な音程で謎の言葉を吐き出しながら、奏戯は肩を落とした。 すっかり元気を取り戻したオルフェリアが、ふと護の顔を見る。 視線が合った護は、顔を引き攣らせて、やや後ずさった。元々褐色だった顔の色は青ざめ、青黒くなっている。 「大丈夫ですかー? 具合悪そうです!!」 「……ってオルフェ! 兄貴ってば女の子苦手だからそんなに近づいちゃ……あぁ」 制止する北斗の言葉を聴かずに、オルフェリアが震える護の手を取って顔を近づけると、短い悲鳴と共に護の動きが停止した。 その様子を見ていた北斗が、眉根を寄せながら手で顔を覆う。 「あ、せるるーのお友達ー? おうおう! もう俺様と出会ったら秒の単位で親友になれるんだぜ」 そう言って、深い溜息を吐く北斗の肩に手を置きながら、奏戯が『マブダチマブダチ♪』と笑顔で語りかけた。 「別に、友達少ないとかそんなんじゃ……あ、はい、すいません……」 見る見るうちにテンションを下げて頬に涙を流す奏戯の背中に、北斗はそっと手を置いた。何か境遇的に通ずるものがあるらしい。 「……そろそろ、移動しましょうか。サイン、貰いに行くんですよね?」 それぞれに談笑(?)を楽しんでいた一行は、セルマのその言葉に視線を向ける。 「行きましょうー♪」 「助……け、て」 笑顔で歩き出したオルフェリアに半ば引き摺られるように歩く護の声は、誰にも届く事はなかった。 ――セルマを先頭に、しばらく歩いていた一行の前に、湖畔が広がる。 「赤ずきんちゃんですー♪」 手に溢れんばかりの花を持った赤ずきんを見つけたオルフェリアが、駆け寄って手帳を取り出した。 「サインを、下さいっ」 「さいん?」 目の前に差し出された手帳とペンを前に、赤ずきんはきょとんとした表情で聞き返す。しばらく困った表情を浮かべていた赤ずきんだったが、やがてペンを手に取り、手帳を受け取る。 「何を書いたらいいの?」 「あなたの名前と、あと下に『オルフェリアへ』って下さい♪」 ご機嫌な表情を浮かべるオルフェリアに、赤ずきんは名前を書き始める。子供らしい文字で『あかずきん』と書いた下に、小さく『オルフェリアへ』と書いた手帳を、赤ずきんがオルフェリアに返した。 「ありがとうございますー♪」 「どういたしまして」 満足そうな表情で手帳を受け取るオルフェリアを見て、赤ずきんが笑いかける。 「ん……特に反応は無いなぁ……」 黒髪の合間から生えた犬耳をピコピコと動かしながら、清泉 北都(いずみ・ほくと)が笑顔で会話を続ける赤ずきんを見つめている。 この物語の結末は気になるが、自分の身に危険が迫るのは避けたい、と張った保護結界も、今は何も反応が無かった。 「何も起こらないなら、それはそれでいいんだけどねぇ」 そう呟いて、赤ずきんの視界に入る前に、自分の犬耳を引っ込める。 「狼の耳と間違われて突然襲われでもしたら……笑えないよねぇ」 「案外仲良くなれるかもしれないぜ? この本の中なら」 北都の発言に、ソーマ・アルジェント(そーま・あるじぇんと)が苦笑する。 「狼を倒して肉ゲット、でパーティタイムでめでたしめでたし……だと思うんだけどなぁ」 「俺達が肉になる可能性だってあるさ……確かめてみるか?」 「ソーマ」 指を鳴らして赤ずきんに近づこうとするソーマを、久途 侘助(くず・わびすけ)が引き止めた。 「話を聞いてみてからでも遅くないと思うぜ。色々考えてみたがよくわからねぇ事ばっかりだ」 出来るだけ周囲――特に、赤ずきんに聞こえないように耳打ちをする。 耳に触れるか触れないかの距離で会話を続ける侘助の声を聞きながら、ソーマが視線を流すと、香住 火藍(かすみ・からん)が小さく頷いた。 「何かあったら……すぐに行く。無理はするなよ」 ソーマのその言葉に、侘助は笑顔で応えた。 「すみません、少し宜しいでしょうか」 「……? こんにちは」 火藍が、湖面を見つめる赤ずきんに語りかける。丁寧な物言いに赤ずきんが挨拶を返すと、火藍は軽く頭を下げた。 「あなたの行動がとても気になるんです。お邪魔はしません、同行しても構わないでしょうか?」 「うん。いいよ」 火藍の申し出を、赤ずきんは二つ返事で快諾した。次いで、侘助が口を開く。 「お前の母は護衛を頼んだ、その護衛はどこに行っちまったんだ?」 「どこにも行ってないよ。みんな、一緒だよ。変なこと言うんだね」 侘助の質問に、赤ずきんがクスクスと笑う。 「どうして護衛はいらない、だなんて言ったんだ?」 「だって、みんな一緒のほうが楽しいもの」 要領を得ない答えを返しながら、赤ずきんがスッと立ち上がる。そして、手にしていた花弁を風に乗せて飛ばした。 湖面を、白い花弁が点々と埋めていく。 「綺麗……です」 「アリエル? 駄目だよ。見た目が綺麗な物ほど、警戒しなくちゃ」 ここは童話の中なんだよ、と言いながらリオルグ・クレセント(りおるぐ・くれせんと)が、白手袋に包まれた指先で、シルクハットのつばを撫でた。 「わかっています、ただ……本当に、綺麗で」 アリエル・シュネーデル(ありえる・しゅねーでる)が、リオルグの制止に小声で答える。 二人は、赤ずきん達がいる場所から見て、湖を挟んだ反対側で身を潜めていた。 リオルグは、この本の存在を聞いた時『おそらく登場人物の『赤ずきん』は本を書いた本人であり、そして同時に捕食者――狼の性質を持っている者』だと、仮説を立てた。 それ故に、単純に『童話の中に入れる』事を喜び、この世界に入り込んだアリエルに対して警告を示したのだ。 『赤ずきん』に触れてはいけない、と。 「それでも……せめて、結末だけは」 悲しそうに目を伏せるアリエルを見て、リオルグは笑顔のまま、モノクルに手を伸ばした。 「……どうして狼は出ると思うんですか? 一体どうやって狼は登場するんですか?」 手の中にあった花弁を全て落とした赤ずきんに、火藍が静かに問いかけた。 「出るんじゃなくて、会うんだよ。登場するんじゃなくて、来るんだよ」 まるで童歌でも歌うように、赤ずきんが答える。そして、笑顔を浮かべたまま、赤ずきんがステップを踏んで踊りだした。 スカートを翻しながら、鼻歌を口ずさんでクルクルと回る。 やがて、小石に躓いて転びそうになった赤ずきんを、葉月 可憐(はづき・かれん)が支えた。 「大丈夫ですか?」 「うん、ありがとう」 体重を任せたままになっている赤ずきんの身体を、可憐が持ち上げて立たせる。体勢を立て直した赤ずきんは、改めて「ありがとう」と言いながら、頭を下げた。 「えと……貴女のお名前は?」 「わたし? 『赤ずきん』よ。今日は、よく名前を聞かれる日ね」 微笑む赤ずきんの顔を見ながら、アリス・テスタイン(ありす・てすたいん)が可憐のメイド服の裾を引っ張った。 奇妙な事に、開いた口の動きと聞こえた声が見事にズレている。 少女が『赤ずきん』と名乗った瞬間、彼女の顔を見ていた者達が、互いに顔を見合わせた。 ――明らかに、彼女の名前は『何か』によって捻じ曲げられている。 何の為なのか、誰によるものなのか。それは誰もわからなかったが、目の前にいる少女が、ただの少女ではないことを誰もが確信していた。 (実は被害者、って可能性もありますけど……) 可憐が、赤ずきんの背後にまわりディテクトエビルを発動させようとした瞬間、森の奥から轟音が鳴り響いた。 |
||