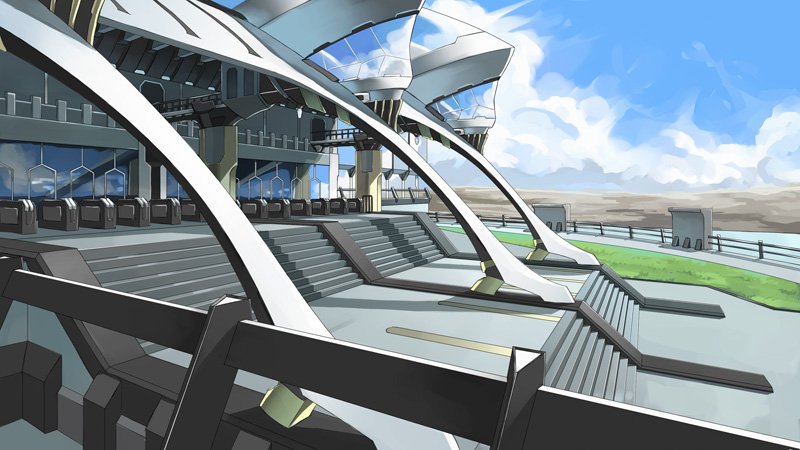リアクション
空を見上げて。 * * * ツァンダの通りを歩きながら。 「ふふっ。うれしいですわ、お父さまとこうしてお出かけできて」 笑顔で横から見上げてくる朱桜 雨泉(すおう・めい)に風羽 斐(かざはね・あやる)は 「そうかね?」 と応じた。 「ええ。本当にひさしぶりなんですもの。 あの……腕を組んでもよろしいでしょうか?」 ためらいがちな、どこか恥じらったような声だった。 強化人間になって以来変化の止まった外見はともかく、内面的には立派に大人の女性だ。大人の女性が父親と腕を組んで歩きたいと思うのは、少しおかしいのかもしれない…。 だが斐はそんな雨泉の内心に気付いた様子はなく、あっさりと答える。 「ああ、かまわないよ」 とたん、笑顔になって腕を組んで歩く、本当にうれしそうな雨泉を見て、斐は少し自嘲気味に思った。こんなに喜んでくれるのなら、もっと頻繁に連れ出してあげればよかったか、と。 しかし斐には仕事があった。研究に熱中するあまり、寝食を忘れることもしばしばだ。雨泉が気をつけてあれこれ世話を焼いてくれなかったら1日研究室で、それこそ朝か夜かも分からない生活を送っているだろう。 本当はこの出かける約束も、大分前にしたものだった。 髪結いのリボンをプレゼントしてくれたお礼と、誕生日の祝いとして、どこか食べに連れて行ってあげようと約束したのだ。 ちなみに雨泉の誕生日は5月である。 すぎたからといって雨泉はなんら文句や不満をつのらせることはない。父親のことは、いいところも悪いところも理解している。 次の休日には、次の休日こそ、そんな感じで日ばかりすぎていくことにしびれを切らしたのは翠門 静玖(みかな・しずひさ)の方だった。 「おいオッサン。明日は引きずってでも連れて行くぞ」 「え? しかし明日は研究が――」 「いいから!」 そうして3人は連れ立って、ツァンダの街へ出かけて来たのだった。 (まったく、あのオッサン。世事にうといのもいいかげんにしろってんだ) 並んで歩く2人の少し後ろを歩きながら、静玖はつくづく思う。 だから妻にも去られるのだ。 もちろん結婚し、子を成した男女の間で起きた諸々の出来事、苦悩や葛藤、離婚に至るまでの心理など、静玖は本当には分からない。しかしあれもそのうちの1つだったのではないかというのは容易に想像がついた。 両親が別れたとき静玖はまだ5歳の子どもだったが、あれから十数年が経って大人になった今、なんとなくだが経緯という背景にまで意識が及ぶようになっている。 (……っていうか……あれ? ちょっと待てよ? 俺、もうじきオッサンが離婚したのと同じ歳になるんじゃ…?) 衝撃の事実発覚。(というか自覚) つまり今の自分の歳のときに、斐には2人の子どもと妻がいたわけで。 「えっ……ええ?」 人知れずプチパニ起こしている静玖の耳に、そのときとまどった雨泉の声が届いた。 「前世でも過去でも、それこそ何でもござれなのですよー」 どこから現れたのかフードマントの者が、熱心に雨泉を勧誘している。 「ええ。ですが、私は特に何も思い出したいと思うことがないんです。申し訳ありませんが――」 「どうした? メイ」 そこへ静玖が走って近付く。 「ああ、お兄さま。こちらの方が「忘れていることを思い出させてあげましょう」と言われまして」 「なんだそりゃ。うさんくせーな」 眇めた目でじっとフードマントの者を見る。かなり小さくて静玖は見下ろす格好になり、影になったフードの下は口元しか見えない。 「うさんくさくなどないのです! 占い師にはできて当然のことなのですから!」 実力を疑われた自称占い師は、ぷんぷんと怒ったように両こぶしを振り上げる。 「いや、過去はともかく前世は無理だろ」 それが事実か調べる方法だってないし。十分うさんくさすぎる。 「俺たち急いでるんで」 そう言おうとしたときだった。 「前世か…」 斐が考え込む素振りでぽつっともらした。 瞬間、静玖のなかでいたずら心がむくむくと起きる。 「あれ? オッサン興味あるのか? じゃあひとつやってもらえよ。出し物としては面白そうだし」 「そうしてみるか」 占い師は自分の術を出し物呼ばわりされたことに少しムッとしたようだったが、乗り気になった斐を見てニコニコ上機嫌になった。 「ではお客さま、前世ですねー」 「特に思い出したい過去というのもないからね」 「ではいきます。きおくー、よみがえれ〜、きおくー」 占い師が糸のついた五円玉を取り出して斐の前でブラブラさせ始めたとき。 「ちょっと待て!!」 突然大きな声が横手の路地から飛んできた。 「なんだ?」 いつからいたのか、そこには両手にデパートの紙袋をぶら下げた、肩で息する少年が立っている。 歳のころは10歳前後といったところか。だが怒りに燃えた茶色の目は、歳に見合わぬ殺気を放っていた。 「おまえ…」 「やっと見つけたぞ、きさまが彼女をあんなふうにした元凶か…」 「あんなふう?」 少年の目が静玖の方を向く。 「そこのあなた。とっととやめさせた方がいいですよ。あんなふうになりたくなかったら、ですが」 くい、と少年が背後を指差す。 路地の出口。つまり静玖たちのいる通りとは道をはさんだとなりの通りだが、そこを、悲鳴を上げながら男が通りすぎていった。一拍置いて、今度は剣を両手に持った女が…。 「要、コロス!」 「いやーーっ! この若さでまだ輪っか頭に浮かべたくなーーーーいっ!!」 「あれは…」 「街がおかしなことになってるのに気付いてなかったんですか? すべてその占い師のせいですよ!」 そのとき、タイムリーにも同じ通りをぱぴゅんっ! と1組の男女が駆け抜けて行った。 というか、女が男を飛ぶ勢いで引っ張りながら走って行った。 「逃げるのよ、ロミオ! ここには長くいすぎたわ! きっとヴェローナの追手に見つかってしまう!!」 「……僕、ロミオじゃないよ、美羽…」 言っても無駄だろうけど。 せっかくのデートが……しくしく、しくしく。 そしてあとを追って、やはり走り抜けて行くベアトリーチェ。 「待ってください、美羽さん! コハクくん!」 そしてなぜかその後ろを走ってついて行くダンボール箱(大)。 後ろの一辺が地面についていて、そこから砂煙が上がっている。 「……い、一体何が――はっ! オッサン!!」 あわてて振り返った先、斐は苦悩しているかのように顔をおおい、背を丸めていた。 「オッサン! おい、大丈夫か!? オッサン!!」 「……ああ、大丈夫だ、問題ない」 「オッサン…」 ほっとしたのもつかの間。顔を上げた斐には、今まで一度たりと見たことのない軽薄な笑みが…。 「やっと自分が何者か思い出せたよ。実にすがすがしい気分だ。うん、サイコーだね!」 「えっ?」 サイコー……だね…? 手をポケットに突っ込み、斜にかまえている立ち姿も、全然斐らしくない。 術は完了していた。 「お父さま…」 となりにいて一部始終を見ていた雨泉も、とまどいを隠せないでいた。身を退いて少し距離をとろうとする。 「おや? きみ、エヴァじゃないか。驚いたねぇ、こんな所で何をしているんだい? 私だよ、アルベルトだ」 「アルベルト、さん…?」 「なんだよ? そんな、きょとんとして。「さん」なんて他人行儀な。アルでいいよ。そう呼んでくれてたろ?」 ずい、と一気に距離を縮められた。 「うーん……かわいいきみに、そんなふうに見つめられたら私はドキドキしてしまうよ」 「いや、見つめてるのはオッサンの方…」 ぽん、と斐が手を打つ。 「そうだ! ここで逢ったのも何かの縁だ、これから私と一緒にお茶でもどう? すぐそこにいい茶葉を仕入れる店があるんだ。あそこで飲むアフタヌーンティーは最高なんだよ。ああそれから、きみの大好きなザッハトルテも置いてあるよ」 ウインク飛ばしてみたりして。 なんだ? このナンパ野郎は。 「こんなのオッサンじゃねえ…」 「ん? なんだい? きみ」 そこで初めて斐は静玖の存在に気付いたように振り返った。 「エヴァの知り合いなの? やだなぁ、それならそうと言ってくれればいいのに。僕はアルベルト、よろしくっ!」 ちゃっ! とか額にあてた2本指を振って軽薄なあいさつをしてくる斐を見て、瞬間的に静玖はぞぞぞと鳥肌立てた。 「おいオッサン! なんだそりゃ!? 冗談でもしていい冗談と悪い冗談があってだな――」 「はい。こちらは私の兄で静玖と言います」 「なんと! エヴァには兄がいたんだ!」 「ってメイ! おまえもノってるんじゃない!! ――くそ。これがあの催眠術みたいな術のせいなら、殴れば正気に返るか?」 強い衝撃は、往々にして正気を失った者の目を覚ます方策になる。 こぶしを固めた静玖を止めたのは、雨泉だった。 「だめです、お兄さま。たとえどんなふうに変わっても、お父さまはお父さまです。家族である私たちが支えてあげなくては」 ――え? そういう問題?? 「エヴァ? どうしたの?」 「いいえ。何もありませんわ」 くるっと向き直り、雨泉はほほ笑んだ。 「ぜひそのお店にご案内してください。私、誘っていただけてとってもうれしいです。残念ながらザッハトルテは食べられませんけど、ぜひお茶にしましょうね」 「わあ。それは僕もうれしいなー」 「…………」 喜々として連れ立って歩いて行く2人に、もはや静玖は二の句を継げない。ただふらふらになりながらあとをついて行くだけだ。 「ふふっ。あんなに喜ばれて。またひとつ善行をしてしまいました〜」 笑顔の斐と雨泉を見て、占い師は、よし、とうなずく。 「私の術がこんなにもひとを幸せにするものだったなんて知りませんでしたねー。これは、もっともっと皆さんを幸せにしてさしあげなくてはいけませんねー。そうすることで私の腕にも磨きがかかるし! いいことずくめなのですよ〜」 うきうき気分で立ち去ろうとした占い師だったが。 「逃がさない」 少年――音無 終(おとなし・しゅう)が前方をふさぐように立ちふさがった。 「なんですかー? あなたもよみがえらせてほしい記憶があるのですかー?」 「願い下げだ!」 「えー?」 終の即答に、残念そうに占い師は指をくわえて終を見る。 「じゃあ何の用ですー?」 「決まっている! 俺のつれにかけた術を解け!! 解かないなら腕ずくでもさせるぞ!」 魔銃カルネイジが威嚇のように抜かれる。 「えー? 喜ばれてないんですかぁ?」 「喜んではいる! 本人は! だが俺が被害をこうむって――」 突然のどに回った手でガシッと強く後ろへ引っ張られ、終はそれ以上言葉にすることはできなかった。 「し、静…っ」 引っ張り寄せた銀 静(しろがね・しずか)が、終を腕に抱き込んで、いやいやと悲しそうに首を振っている。 「……え? 余命半年の体で無茶をするなって? だからそれはおまえの思い込みで――」 静の目じりに涙がにじんだ。 そんな悲しい言葉、終の口から聞きたくないとばかりにさらに抱き込む腕の力が強まる。終は豊満な静の胸に埋もれて、窒息しそうだった。 「――ぷはっ! す……少しはひとの話を聞け! 俺は死にかけてないと何度――だから嘘じゃない! 医者がだましてるわけでもなくて!」 終は懸命に静からのテレパシーを否定し、訴えるが、静にそれを聞き入れている様子はなかった。 術にかかった人間というのは、あるいはこういうものなのか。 うるんだ目でじーーーーっと見つめる静は、まるで無垢な子犬のようだ。 何が言いたいのか、テレパシーを受けとらなくても終には分かった。 「残り少ない時間を、私とともに過ごして」 だ。 あのくだらない恋愛ドラマのお嬢さまヒロインは余命いくばくもない恋人の男性にそう訴えていた。 だが終とあの男性では置かれている状況が全く違うし、そもそも自分たちは恋人同士ですらない。 「ああもうっ! 100歩譲って俺の命があと半年だとして――」 その肯定を聞いた瞬間、ぶわっと一気に静の涙が倍増した。 「だから仮定だ! 仮定の話! 余命半年だったとして、どうしてデパートでおまえの買い物に付き合うことになるんだ!? し……しかも、したっ、下着の!」 口にした瞬間顔が赤らむのを止められなかった。 見てくれはたしかに小学生だが、中身は違う。健全な男として当然ながら、ああいう場所は居心地が悪い。周囲の女性たちはみんな彼を男と意識していないと分かっていても、それでも所在なさを感じてしまうのだ。 「第一、俺とおまえの関係はそういうものじゃないだろ!」 じゃあどういうものかと突っ込まれると困るが……少なくとも下着を買ってプレゼントしてやったり、一緒にデパートへ出かけて荷物持ちをしてやる間柄ではない。はずだ。さっきまで従っていたのはそれで隙を伺って、逃げて占い師を捜そうと思っていたからだ。――失敗したが。 とにかく困る。どうしても見てほしいというのなら、あとで部屋で2人きりになったときに見てやってもいい。だがああいう場で意見を求められるのはとても困る。 しかしその微妙で繊細な(?)男の心理を静に理解しろというのは無理な話だった。そもそも分かっていたら最初から連れて行ったりしないだろう。 でも自分がしたことで終がすごく機嫌を損ねているというのは理解できて。 混乱のあまりぷるぷる全身が震えだす。ますます静の涙は増量した。 ぽろぽろこぼれ始めた涙に、終はぎょっとなる。 「待て! それはやめろ! 怒ってるわけじゃない! ……ああもう! 泣くな! 命令だ!」 命令。それなら分かる。 とたん泣くのをやめた静の、全く分かっている様子のない無邪気さにイラつきながらも、ふうとあきらめのため息をつく終。そんな彼を見て静は少し考え込む素振りをしたあと、何か思いついた様子でにこっと笑った。 「……え? いや、だからって本屋でロマンス小説大人買いするのに付き合うとはひと言も――って、1度でいいから俺の話をまともに聞けーっ!!」 なんでこいつ、今回に限ってこんなめげないんだ!? 終は絶叫したが、どうなるものでもない。 がしっと腕を組まれ、そのままずるずる引きずられて行った。せめてもの抵抗か、かかとから土煙が上がっている。 そんな2人を見て、占い師はほうっと息を吐く。 「ああ、すっかり見せつけられちゃいましたねえ。なんだかんだ言っても恋人同士。お幸せそうじゃないですかー」 ――訂正。占い師が見ていたのは静だけでした。 「幸せなのはいいことですねー。お客さんが笑顔だと、した私の方もうれしくなりますー」 これはやはりもっともっと皆さんを幸せにしてあげなくては! 占い師は意気込んで、さっそく目についた、通りの向こう側を歩く男性に声をかけたのだった。 ちなみに斐たち3人の行方について。 あの後、喫茶店でもナンパぶりを遺憾なく発揮した斐は、ついに耐え切れなくなった静玖に 「くそおおおおっ!!! 本気で正気に戻りやがれ、この馬鹿親父ー!!!」 とカタクリズムを用いたブレーンバスターで店内の床にたたきつけられあえなく気絶することになったのだが、雨泉はそれをにこにこ笑って見ているだけだったという…。 |
||