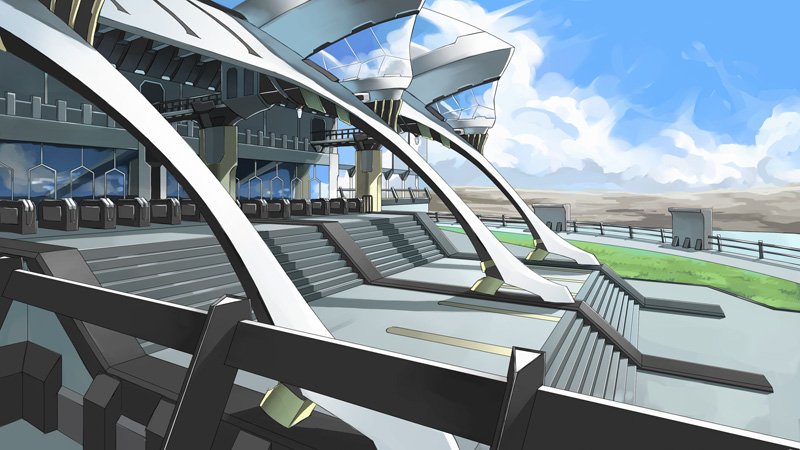リアクション
● ドルパンを倒して、リーズ一行は次なる関門へと向かおうとしていた。 そこに、 「ちょっとそこの獣人娘!」 横柄な口調で突然現れたのは、膝まで届く銀の長髪を靡かせた一人の少女だった。 「わたし?」 リーズは自分を指さして首をかしげる。 少女は力強く頷いた。 「そうよ。そこの狼耳を生やしてる女。ちょっと聞きたいことがあるんだけど」 「な、なに?」 「……帰り道はどこ?」 「…………」 どうやらこの少女は道に迷ってしまったらしい。 それで『狼の試練』のダンジョンに迷い込んでしまうという方向感覚は理解できなかったが、それが『迷子スキル』というものか。 「ありがとっ。助かったわ! このお礼はまた今度ね!」 「え、ええ、さよなら」 道を教えると、少女は元気よくその場を立ち去る 呆気にとられたまま、リーズ一行はその後ろ姿を見送った。 ● 「って、帰り道を教えてもらったのに、ここは何処よおぉっ!」 ダンジョンのとある一室で。 銀髪の少女――ヴェルリア・アルカトル(う゛ぇるりあ・あるかとる)は、再び迷っていた。 「ははははっ、ヴェルリアさん。そんなに嘆いても仕方ありませんよ」 そんなヴェルリアの横で、豪快に笑うのは一人の巨漢だった。 つるつるりんの禿頭。引き締まった筋肉隆々の肉体。快活な笑顔と笑い声。 ヴェルリアと同じく迷子になってしまい、一緒に出口を探しているルイ・フリード(るい・ふりーど)だ。 彼は杯を片手に、見知らぬ獣人たちと笑いあっていた。 どうやらこの部屋は、この『狼の試練』の休憩所らしい。 獣人たちはすでに死した戦士の魂だが、そんな幽霊じみたものなどおかまいなしに、ルイは彼らと一緒に酒盛りを楽しんでいた。 「果報は寝て待てと言うじゃないですか。どうですか? 一緒に一杯」 「だあぁっ、ルイっ! あんたねっ、少しは危機感持ちなさいってのっ!」 「ははははははっ!」 ヴェルリアの言うことはもっともだが、それすらも酔っ払いには笑えてしまう。 というか、この獣人たちはいったい何なのか。それすらもヴェルリアにはわからないわけで、彼女ははぁっとため息をついた。そして、なんとはなしにその辺をふらつくように歩く。 カチッ。 「へっ?」 ひゅひゅひゅんっ! 「だっ、どわっ、どぅぉぇっ!」 足下のスイッチを押したせいで飛び出してきた槍を、巧みに避けるヴェルリア。 まるで変な踊りでも踊っているような格好になって、彼女はわなわなと震えた。 「……なんなのよ、ここはあぁ――――っ!」 「ん……?」 「どうしたの? 真司」 かすかに首を傾げる青年に、どこかから聞こえる声がたずねた。 青年の姿は、黒髪に金の瞳。少し幼さを残した端整な顔立ちが、その冷静な性格を物語る。 そんな彼の近くには誰もいない。にも関わらず、声はどこかから聞こえてきたのだ。それは、青年――柊 真司(ひいらぎ・しんじ)に声をかけたのが、彼の身につける鎧だからだった。 「なにか面白いものでも見つけたの〜?」 くすくすと笑う、鎧の声。 それは魔鎧という契約者に纏われる鎧の種族、リーラ・タイルヒュン(りーら・たいるひゅん)の声だった。 「別に、そんなんじゃないが……」 真司はそう答える。 「いまヴェルリアの悲鳴が聞こえたような気が……」 彼はしばらく、振り向いた横道を見続けた。 しかし、 (気のせいか……) そう判断すると、再び前に向き直った。 二人はただいま、迷子の迷子のヴェルリア・アルカトルを捜索中だった。 理由はもちろん、彼女が勝手に迷子になったからである。はぐれてしまったヴェルリアが、クオルヴェルの集落から出ていったという話を聞いて、こうしてわざわざ『狼の試練』なるダンジョンにまで足を運んだのだった。 「それにしても、リーズに会えて良かったわね。そうじゃなきゃ、なんの手がかりもないのにこの広いダンジョンを探さなきゃいけないところだったわ」 「そうだな。しかし……」 「しかし?」 「あいつが、素直にリーズの言うルートをたどってると思うか?」 「……あははは〜」 リーラの乾いた笑い。 二人はこのダンジョンで旧友のリーズ・クオルヴェルに出遭い、迷子のヴェルリアが向かった先を教えてもらったのだった。 いや、というよりは、リーズがすでにヴェルリアと出会って、彼女に帰り道を教えていたということなのだが。ヴェルリアが素直にそのルートをたどっているとも思えず、二人は迷ったすえに、分かれ道でとりあえず足を止めた。 「さて、どうしたものか……」 真司は困ったようにつぶやく。 「こんなときはお仲間に聞くのが一番よっ。ねーねー、セラさんたちー、どっちに行ったらいいかなー?」 そう言って、リーラは後ろにいる二つの影に聞く。 「どーちぃらにひってもー、いっしょらーのー」 「…………」 そこにいたのは、一人の酔っぱらいだった。 しかも、単なる酔っ払いではない。幼女だ。せいぜい一〇歳程度にしか見えない、鬼の面を被った娘が、酒の入ったひょうたん片手にふらふらとおぼつかない足取りで歩いていた。 「ああもう、桜華! まだお酒は早いですよっ!」 それを止めるのは、真司とそう変わらぬ歳に見えるもう一人の少女。 緑色の長髪を腰ぐらいの場所で先端だけ束ねている娘。まるで娘か妹の世話でもするように、彼女はふらついている幼女を支えていた。 「むぅー、ルイのやつめぇ……わしの頼んだ超有名銘柄の日本酒が届かぬうちに遭難するとはけしからんっ! ひっく! せめてっ……ひっくっ……遭難するなら、わしへ酒を届けてからにせい!」 酔っ払いながらもそんなことをのたまう。 彼女たちは深澄 桜華(みすみ・おうか)にシュリュズベリィ著 セラエノ断章(しゅりゅずべりぃちょ・せらえのだんしょう)。二人も真司たちと同じで、迷子になった仲間を探している最中なのだった。 「こうなったら…………セラっ!」 「は、はい?」 セラはいやな予感を覚えつつ、返事をした。 「おぬしもわしといっしょに酒をのむのだーっ!」 「ちょっ、ちょっと桜華っ、やめっ……」 抵抗はむなしく、馬乗りになった桜華がセラの口にひょうたんを突っ込んだ。 ごくっ、ごくっ、と、セラは勢いよく飲んでしまう。すると、ぴたりと彼女の動きは止まり、しばらくの間の無言の時間が続いた。 と、思いきや――彼女はなにかのスイッチが入ったように、突然ゆらりと起き上がった。その背後には不穏なオーラがゆらめいている。ついでに言えば、桜華もふらつきながら、キシシシと含んだ笑みをもらしていた。 「ふ……ふふ……ふふふっ……」 次にいやな予感を覚えたのは真司だった。 「おい、セラ、桜華……お前ら……」 「突撃ぃ――――っ!」 「ひんむけ、ひんむけーっ! あははははっ!」 「いやあああぁぁっーっ」 顔を真っ赤にして襲いかかってきたセラと桜華が、真司の服をひっぺがす。セラは終始、笑い続けていた。 そして、ひんむかれ、ガランッ、と床に転がされた魔鎧姿のリーラは、 「あっははははっ、真司、真司がはだかにぃ……っ!」 腹を抱えるように笑っていた。 ● |
||