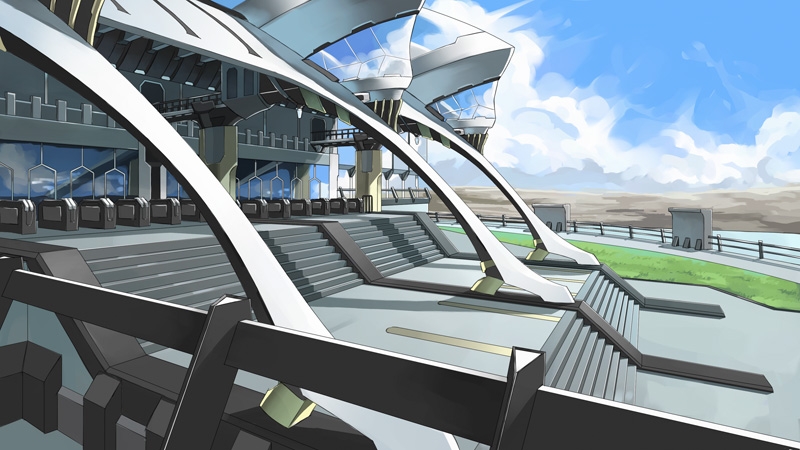リアクション
* * * 「な、ななな……なにしてくださってんのよっ!?」 八雲とその弟に当たる契約者の佐々木 弥十郎(ささき・やじゅうろう)から事情を聞いたフレッドは、驚く以外にしようがなかった なんとこの二人は、ニブルナ家へ宝を盗みに入る旨の予告状を出したというのだ。呆然とするフレッドに対し、二人はなぜかのほほんとしたものだった。 「いやなに、予告状も出さずに捕まったとあっては、クライシアスの名にも恥だろう? ここは正々堂々と、正面から戦いを挑もうじゃないか」 「あのなぁ…………」 笑っている八雲に、フレッドは呆れてものが言えなかった。 「まあまあ、聞いてよ、フレッド君」 そこにフォローしたのは弥十郎だ。彼は特有の柔和な笑みでフレッドの怒りをほぐした。 「出しちゃったものは仕方ないしねぇ。ここは、それを囮にしようじゃないか」 「囮?」 「うん、つまり兄さんは予告状を出した張本人だし、正面から行ってもらうとして……こちらはその隙に警備網の薄い場所から攻めるんだ」 「…………なるほど」 やってしまったことを嘆いても仕方ない。確かに弥十郎の言う通り、それを有効活用するほうが道は見えていた。 「弟よっ!? それは兄に対してあまりにも不憫じゃないか!?」 八雲は、自分がいつの間にか餌役になってしまっていることに不満を漏らした。 が、弥十郎はにこにこした顔を崩さない。むしろ輝く笑みで、兄の肩にぽんと手を置いた。 「頑張って、兄さん。ワタシたちはここでちゃんと見守ってるからね」 「ひどいっ!」 かくして、彼らの作戦は始まった――。 * * * 一方、屋敷にいるニブルナ家のご令嬢アメーリエ・ニブルナは、私室での待機を命じられていた。 「なにかしら? お外が賑やかですが……」 「気にしなくていいのよ、お嬢さま」 アメーリエにそう言って聞かせたのは、綾原 さゆみ(あやはら・さゆみ)だった。 傍にはアデリーヌ・シャントルイユ(あでりーぬ・しゃんとるいゆ)やリリア・オーランソート(りりあ・おーらんそーと)たちの姿も見られる。彼女たちは当主エルンストに頼まれて、アメーリエの護衛と話し相手を兼任していた。 特にさゆみとアデリーヌは、アイドルデュオ「シニフィアン・メイデン」だ。密かに当主エルンストもファンだということで、サインをねだられたついでに、護衛任務も言いつかったのだった。 (それにしても……) ぽわぽわした雰囲気のアメーリエを見て、さゆみは思う。 今どき珍しいぐらい無垢な子だ。 下着ドロという言葉自体聞いたことないのか、さっぱりのようであるし、赤ん坊は殿方と結婚したらこうのとりが運んできてくれるとさえ信じているらしい。 (んなバカな……) そうは思うが、ある意味じゃあ羨ましくも感じる。 さゆみはなるべく彼女の夢を壊さないでいようと思った。 「それにしても下着を盗もうなんて、本当にけしからんですわね! これだから男は!」 アデリーヌは今回の騒動に怒りを覚えているらしい。むかーっと今にもテーブルを叩きそうだった。 「まあまあ」 リリアがそれをなんとかなだめた。 「エースが言ってたけど、男の子っていろいろあるらしいわ。ここは海のように広い心で見守ってあげましょうよ」 大人の女性をアピールするリリア。けれどアデリーヌは納得がいかなかった。 「…………じゃあ、リリアは自分の下着が盗まれそうになったらどうしますの?」 「殺す」 「…………」 即答である。 いっそ笑みが怖かった。 理不尽言うなかれ。女性の下着にはそれだけの重みがあるのだった。 「…………?」 リリアたちの会話の意味がよくわかっていないアメーリエは、首をかしげてる。 その腕に、もこもこした花妖精の珍獣リイム・クローバー(りいむ・くろーばー)を抱きかかえていた。 「むー……僕はこれでも勇敢な賞金稼ぎなのにぃ」 すこし不満を口にするリイム。さゆみがそれにフォローを入れた。 「まあ、いいじゃない。お嬢さまのお気に入りみたいだし」 「ええ、ふかふかです。お日さまの匂いなんですの」 「助けてぇ!」 ぎゅっと顔をうずめてくるアメーリエに、逃げようとするリイム。 けれどもどこにそんな力があるのか。アメーリエの手はぎゅっとリイムを掴み、決して離そうとはしなかった。 ――その時である。 「みんな、準備が出来ましたよー」 扉伝いにあるもう一方のアメーリエの私室から、ローデリヒ・エーヴェルブルグ(ろーでりひ・えーう゛ぇるぶるぐ)の声が聞こえてきた。 彼は食器やら茶器やらを乗せたキャスターを、カラカラと運んできた。 「わー、いい匂い!」 リリアが立ち上がって、さっそく並べられたお茶菓子に近づく。 「匂いって……せめて香りって言ってよ」 苦笑しながら、さゆみもその後に続いていった。 アデリーヌ、リイムを抱くアメーリエと、次々にお茶菓子に近づく。 と、いつの間にかメイドたちがテーブルと椅子をセッティングし終えていて、そこにローデリヒは食器やお茶菓子を並べた。 それだけで優雅なお茶会の様相の完成である。ローデリヒは皆に席につくように促した。 「こほん……。では、今宵は皆様方とこうしてお茶を囲むことが出来たことを、大変喜ばしく――」 「いっただきまーす!」 「話は最後まで聞いてぇっ!」 ローデリヒが言い終わる前に手を伸ばしたさゆみやリリアは、さっそくビスケットやスコーンにぱくつく。 アデリーヌはやれやれといったように呆れた顔になって、リイムはにこにこ笑顔のアメーリエからスコーンの欠片をあーんと食べさせられていた。 「はい、あーん」 「子どもあつかいは嫌でふー……」 「あら……? スコーンはお嫌いだったかしら?」 「お嬢さま。お待ちください。いまこの獣めに口を開かせてやりますので」 「いだいっ! いだいいだいいだいいだいっ! いだいでふ〜〜〜っ!」 メイドに無理やり口を開けさせられたリイムは、そこに大量のスコーンを押し込まれる。 「あらあら………………美味しそう」 それを見ながら、アメーリエはまったく邪気のない顔でにこにこ笑った。 十分後――。 「うぅ……でふ……」 パンパンに膨れあがったお腹で倒れているリイムの姿がそこにあった。 * * * 「あの、マスター……。これって本当に効果があるんでしょうか?」 「ある! あるに決まっている! こんなに愛らしい金髪忍者っ娘がドレスを纏っているのだ! 男ならこれに食いつかないはずはない!」 フレンディス・ティラ(ふれんでぃす・てぃら)の疑問に、ベルク・ウェルナート(べるく・うぇるなーと)は力説した。 ただいま彼らは、アメーリエの部屋でお着替えを終えたばかりである。 フレンディスが着ているのは純白のドレスで、同じ金髪だけに後ろ姿だけではアメーリエとそっくりだ。 これならばきっと侵入者たちを騙せるだろうと、ベルクは思った。 「むー?」 まあ……フレンディス自身はいまいち納得いっていないようだが。 首をかしげている彼女。その不安を除くように、着替えを手伝ったメイドが言った。 「フレンディス様、素敵ですわ。きっとこれなら、殿方もイチコロです」 「ふえ……? そ、そうかな……」 ナイス、メイドさん! 顔を赤くしたフレンディスが鏡を見ながら、ひらっ、ひらっ、とスカートを動かす。 その愛おしさに興奮したベルクは、 (ぬぉっ、やばい、………………抱きしめたい!) 心の中でそう叫んだ。 しかし、葛藤。 (うおおぉぉ…………だ、だめだ、ベルク! フレイのためを思えば!) 必死に自分に言い聞かせた。 で、勝手に身もだえしている彼の後ろで―― 「フレンディス様。わたくしとお揃いですわー」 「あ! アメーリエさん! …………ほんとですー」 同じ純白のドレスを着たアメーリエとフレンディスが、お互いの服を見てにこにこと笑った。 フレンディスが着ているドレスは、アメーリエ自身も普段から着ることの多い服である。 衣装部屋から持ってきた数点の中では特にお気に入りで、彼女はそれがフレンディスにも似合っていることに喜びを感じていた。 「いかがですか? きっと見事に相手を騙しきっていただけると思いますが」 メイドがフレンディスに進言する。 「うー…………」 恥ずかしさはあるが、アメーリエも褒めてくれるとなると断りきれない。 「――わかりました!」 フレンディスは決意を露わに拳を握った。 「不肖、このフレンディス・ティラ! アメーリエさんのためにも、頑張ります!」 「おおー」 ぱちぱちぱちと、メイドやベルクたちから拍手が聞こえる。 「あの、ところで……」 フレンディスはふと冷静になって言った。 「どうして泥棒さんたちは下着なんて狙ってくるのですか……?」 「ん……まあ、それは……男の…………ごにょごにょというか……な……」 顔を赤くしたベルクが言葉をすぼませる。 「…………?」 フレンディスとアメーリエはよくわからず、お互いの顔を見て首をかしげるだけだった。 |
||