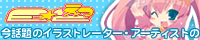今すぐゲームを確認する

参加者
「広い空っ! 輝く太陽っ! そして……青い海っ!」
「まさに――!」
「これこそ夏ッ! って感じだよねっ!」
真更町の浜辺に、三人の若者が立っていた。
その手には浮き輪やビーチバレー用のボールを持っていて、いかにも遊びに来ましたという出で立ちをしている。
Tシャツや短パンを着ているが、下には水着を着ているようで、いつでもその身を太陽の下に晒す準備が出来ているようだった。
太陽に向かって眩しそうに片手をかざす青年は四谷 大助。穏やかな微笑で海を見つめる青年は氷室カイ。そして最後に、沸き立つ興奮を抑え切れないように仁王立ちするのが、駆け出しのグラビアアイドルでもある美少女、久世 沙幸だった。
すると、そんな三人の背後から不吉な声が聞こえてきた。
「夏ねぇ……気温と直射日光に当てられた人間たちが、色恋ざたや一時の快楽に身を任せる季節やろ? 太陽さんもそんなオレらをあざわらっとるんやろうなぁ」
皮肉げな笑みを浮かべながら、背後でパラソルを肩に担いでいる瀬山 裕輝である。
「そこっ! ムードぶち壊すようなこと言わない!」
沙幸はバッと後ろに振り返って、ビシィッと指を突きつけた。
まったく、夏というのになんと空気の読めない奴だ――と言わんばかりの目が、裕輝をむぅっと睨みつける。
そんな視線を軽く受け止めて、
「せやかてなぁ。あれ、見てみい」
裕輝は海の向こうを示した。
「ん……あれは……?」
カイが眉をひそめてその姿を認める。
「あっ、フリッカだっ」
と、同時に、沙幸もそれを確認したようで、赤毛のお嬢様の名を口にした。
「向こうは地球の名門お貴族様。対してこっちは、平々凡々な小市民のちっぽけな慰安旅行や。世の中、格差はあるのが現実。見てるとつらいでぇ」
「ぬぐぐぐぐぅ……」
裕輝のささやくような声に歯を食いしばる沙幸。
が、彼女はふんっとそれを一蹴した。
「笑止! 夏の楽しみはカネで決まるものではないのよ!」
「でも……ここまで連れてきてもらったのって、フレデリカさんのおかげなんだよな」
横から投げ込まれた大助の一言に、
「ぐっ……」
沙幸は声を詰まらせる。
「なんでも近くにプライベートビーチがあるらしいな。さすがに……そこまで世話になるわけにはいかなかったが……」
カイはそう言いながら、今日のこの日が実現した経緯を思い出していた。
赤毛のお嬢様が伊豆半島に行くと聞いたのはつい先日のこと。ちょうど話に居合わせた四人は、彼女の好意もあって、こうして夏の海を満喫しに訪れることが出来ていたのだった。
とはいえ――
「向こうは執事とメイドを連れて豪華客船並みの高級クルーザーでクルージングを満喫。はたやこっちは、浜辺で地道にパラソル立て。まあ、確かに雲泥の差だよね」
海の中央に悠然と浮かぶ高級クルーザーのバカでかさを見ると、さすがに大助も苦笑を隠せなかった。
「だああぁぁ! あんたたちまで気が暗くなること言うなぁ!」
沙幸、怒る。
「ま、言っても……」
それに気を取り直したわけではないが、
「庶民には庶民なりの楽しみ方があるってこと! 今日はグリムたちもいないし! ふふふふっ……久しぶりに腕がなる!」
脇に抱えたサーフボードを手に、大助は不敵な笑みを浮かべた。
「おおぉっ、その調子よ大助! なら……私も水着に着替えよっかな!」
沙幸も気分を良くして、水着の上に来ていたシャツを脱ぐ。
さすがにグラビアアイドル。出るところは出ているし、引っ込むところは引っ込んでいる。身長は少し小さめだが、そのプロポーションは抜群だ。いや、むしろ身長の低さと相まって、幼さと大人の色気を融合させた不思議な色気を醸し出している。
彼女は自信満々に男たちに振り返った。
(いつもはお姉さまに弄られる役ばっかりだけど、今日の主役は私! これで浜辺の視線は独り占め――)
「さーて、パラソルパラソル」
「庶民なりの楽しみ方ねぇ……そういうのって悪あがきとか、無駄な努力とも言うんやけどな……」
「おーい、スイカ冷やしとくぞー」
パラソルを立てる大助に、シートの準備をする裕輝。スイカをクーラーボックスに入れるカイ。
「…………」
彼らが沙幸にぶん殴られたのは、それからすぐのことだった。
豪華客船並みのクルーザーに乗ったフレデリカ・レヴィは、友人たちとその甲板で優雅な食事を取っていた。
そもそも、彼女が今回この伊豆半島に来たのは、久しぶりに地球の友人たちと語らいたかったからである。
地球を離れてパラミタに来てから早幾月。
多くのことが変わって、多くのことを経験した。それはもちろん、フレデリカだけではなく、彼女の地球の友人たちも。
クルーザーの上で、専属の料理人が用意してくれた海の幸をふんだんに使った料理を食べながら、そんな日常の変化や、時には恋の話を話し合う。
好きな人がいるのにお見合い話を持ってこられて――など、その話の内容はいかにも上流階級のお嬢様らしいものだったが、フレデリカは懐かしの邂逅を楽しんでいた。
そんなとき、
「あら……あれって……?」
いかにもお嬢様らしい友人の一人が、食事の手を休めて海を見た。
するとそこでは、巨大な波に乗ってサーフィンを楽しむ大助の姿があった。
「いくぞっ、大ジャンプエアリアル! 続けてスリーシックスティー……ってあれ?」
……あった、のだが。
「うわわわっ!?」
彼は契約者の並外れた身体能力を生かして大技を繰り出そうとしたところ失敗し、サーフボードごと海に墜落した。
「もう……何やってるのよ……」
むろん、フレデリカは呆れ顔である。
貸しボードに乗った沙幸が、大助を引き上げるのを見る。
そして浜辺にいる他の仲間たちも彼女の視界に入った。
裕輝はなにやら馬鹿でかい砂の芸術品を作っているし、カイはどのスイカが一番良いかと、どうでもいいことに真剣に悩んでいて首を傾げている様子である。
友人たちに恥ずかしい連れの人たちを見られたと、そんな気分にもなった。
しかし、
「ふふっ、フリッカが羨ましいわ」
そんな友人の一言。
「羨ましい?」
「あんな賑やかな人たちといつも過ごしてるなんて」
穏やかに笑う友人。
まあ、確かに賑やかである。しかし、賑やか過ぎると言えなくもない。正直言って、地球に居た頃の上流階級の暮らしとは、まったく別物の世界に足を踏み入れたという気もするだろう。
この友人たちはそれでもまだ俗っぽいところがある貴族たちだが、貴族は貴族。フレデリカも最初に地球に来たとき、戸惑っていたことを思い出した。
だけど、今は違う。
そんな気がする。
「パラミタのことを話すあなた、とっても活き活きしてたわよ」
含むような友人の言葉。
他の友人たちも頷いてくすくすと笑う。
「な、なによ、もう……」
フレデリカは急に恥ずかしくなって、顔を真っ赤にして言う。
誰かにからかわれるほどには大切なものになったんだと――そんな気がした。
夕日が海へと、少しずつだが沈もうとしている。
懐かしき友人たちは自分たちの泊まっているそれぞれのホテルや別荘に戻り、フレデリカもまた、パラミタの仲間たちのもとに戻ってきていた。
別れの時、夕日をバックにしてフレデリカは友人たちと再会を約束した。
彼女にとって地球は故郷だ。もちろん、そこには友人たちとのかけがえのない思い出もある。しかし同時に、今の彼女にとってはこの一時も、あの冒険の日々も、かけがえのないものになっていた。
「再会は、楽しめたか?」
彼女の横にいて、同じように夕日を見ていたカイが聞く。
「ええ、とっても……」
フレデリカは、目を眩しそうに細めた。
「さて、じゃあ…………そろそろ俺たちも最後のイベントといくか」
「最後のイベント?」
大助とビーチバレーをしていた沙幸が、首をかしげる。
「これだ」
カイはそう言うと、カメラスタンドと愛用のデジカメを手にした。
そして、後ろで砂の芸術品の完成度を極限まで高めようとしていた裕輝も呼んで、四人が並ぶ。その後ろには、フレデリカが友人たちとの再会を約束したのと同じ夕日があった。
「それじゃあ、撮るぞー!」
カイがデジカメのボタンを押す。
セルフタイマーがスタートした。10秒後にはシャッターが降りるだろう。
「あっ!? ちょっ……まっ……あわわわっ!」
慌てて駆け寄ってきた沙幸の水着の紐が、ほつれかかる。
だが、いまさらそれを結び直すような時間もなくて。
「わわわわわわっ!?」
――パシャッ
五人は夕日をバックに写真を撮った。
それは夏の日の思い出。夏の日の、夕日が見下ろす一時のことだった。