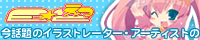今すぐゲームを確認する
- ホーム
- スペシャルコンテンツ
- バレンタインミニノベル2010
- ランツェレット・ハンマーシュミット様
花束とチョコレート / ランツェレット・ハンマーシュミット様
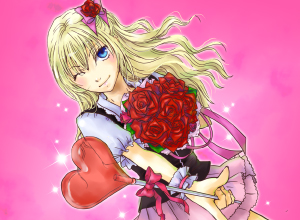
日本式のヴァレンタインは好きだ。
腕によりをかけて作ったつやつやのチョコレートケーキを眺めながら、ランツェレット・ハンマーシュミットはそんなことを思った。
「シャロットは驚くでしょうか。驚くでしょうね。普段はただの弟扱いですもの」
ドイツ式のヴァレンタインでは、男性から女性へ、花束を贈るのが普通だ。
けれど、ドイツ式のヴァレンタインに「義理」や「親愛」のための花束はない。ドイツで、ヴァレンタインに花を贈る相手は、恋人や、人生のパートナーにだけ。つまり「愛情」によるものだけだ。
それは、安心できる反面、すこしつまらない。
「ランツの手作りケーキが、シャロットのためだなんて、なんかもったいないな」
ティーレ・セイラギエンが、からかう様に「ふん」と鼻を鳴らした。
「いいじゃないですか、せっかくのヴァレンタインくらいオトコノコさせてあげたって。ティーレもなにかあげればいいのに。普段舎弟みたいに扱ってるんですから」
「あたしたちはその距離感がちょうどいいからいーの。チョコなんかあげたら、逆にギクシャクしちゃうわ」
「うふふ。そうですか」
ランツェレットが微笑んでみせると、ティーレはきつく見られがちの瞳を、つんとそらした。
日本式のヴァレンタインは好きだ。
あげるのも自由。あげないのも自由。贈りものに込める気持も自由。
だから、チョコレート一つでこんなにわくわくできる。
シャロットは、喜んでくれるだろうか。
手作りのチョコなんてあげたら、変な誤解をするかもしれない。
それとも、「もしかしたらランツからチョコがもらえるかも知れない……」なんて、今この瞬間にもヤキモキしているかも知れない。
「たっだいまー。パーティの主役がやってきたよー」
ミーレス・カッツェンが、巨大なネコそのもののモフモフした両手に、まんまるく膨れたビニール袋を提げて、キッチンに入ってきた。
調理台の上、ランツェレットの手作りケーキの隣にどすんと置かれた袋からは、つやつやした大玉のリンゴや、透明のパック一杯に詰まった、真っ赤に濡れ光るイチゴなどがこぼれおちる。
「こっちも、もういいみたいよ」
ティーレが、コンロで弱火にかけられていた鍋の蓋を取った。濃い湯気が、とろけるような甘い香りと一緒にあふれ出て、つややかにとけたチョコレートが顔をのぞかせる。
「チョコフォンデュー・パーティの主役は、これで揃いましたね。あとは」
――役者。
そうランツェレットが言いかけた時、玄関の扉が遠慮がちに開く音がした。
「みんな、もう来てるの?」
シャロット・マリスが、リビングにひょこりと顔だけ覗かせて、首をかしげた。
外の寒さのせいか、薄く赤みの差した白い頬に、金細工のような髪がさらりとこぼれる。
どきり、とランツェレットの胸が高鳴った。まるで、シャロットに恋でもしてしまったみたいでおかしい。チョコレートの魔法が、作り手までドキドキさせているみたいだ。
「みんな揃ってますよ。シャロットもおいで」
ケーキを背中に隠すようにして、可愛い弟分に手招きする。
シャロットは頷いて、リビングに入ってきた。
チョコレートを渡す瞬間が迫る。自然に、ランツェレットの頬がほころんで……、
「ランツ、これ」
シャロットが差し出してきた真っ赤な花束に、ランツェレットの頬がひきつった。
「えっと……シャロット、これは?」
否応なしにぎこちなくなってしまう声でランツェレットが問うと、シャロットはきょとんと首をかしげて見せた。
「なにって、今日はヴァレンタインでしょ? だから、ランツにプレゼント」
「あっ、なによシャロット。ランツにだけ!」
ティーレが、横からランツェレットを押しのけて、花束に顔を近づけた。
「え? だって、ヴァレンタインのプレゼントはパートナーにするんだよ? 僕のパートナーはランツなんだから、ランツにプレゼントするのが当たり前でしょ?」
「それはドイツの話でしょ? ランツはねえ、別に何とも思っちゃいないあんたのために……」
ランツェレットは、あわててティーレの口をふさいだ。
「う、うふふ、えっと、じゃあみんな集まったから、パーティの準備をしましょうか! ほらほら、ティーレもシャロットも早くお鍋運んで! 果物盛って!」
ランツェレットは、まだ何か言いたそうなティーレとシャロットを、ミーレスもろともリビングに押し戻した。
小ぢんまりとしたキッチンで一人になって、ランツェレットは、甘ったるい匂いのするバラの花束を抱えたまま振り返った。
テラテラ光るチョコケーキが、まだ食べてもいないのに、胃もたれしそうな重さと共にそこにある。
「今わたくしが「日本式のヴァレンタインっていいですよね」なんて言ってチョコレートあげたら、シャロットがスベったみたいじゃない……。せっかくこんなに綺麗な花束、買ってきてくれたのに、それじゃかわいそうだわ」
ランツェレットは、花束をぎゅっと握りしめた。プラスチックフィルムが、ぱりぱりと乾いた音を立てる。
「本当に、シャロットは真面目と言うか、空気が読めないと言うか……。お返し、どうしようかしら。チョコケーキはもうだめね、残念だけれど……あら?」
ランツェレットは、チョコレートケーキの隣、ミーレスが袋からこぼしていった、みずみずしい果実のパックや、色鮮やかなお菓子の袋に目をやった。そのなかで、ピンク色の棒付きキャンディーが、ひときわ眩しく宝石のように輝いている。
「ミーレスったら、お菓子にまでチョコつけて食べる気だったのかしら。……でも、ま。今日ばっかりは、ミーレスの食い気に感謝、だわね」
ランツェレットは、その棒付きキャンディーをひょいと持ち上げて、「うふふ」と笑った。
「シャロット」
ランツェレットの声に、チョコレートの鍋をカセットコンロにかけていたシャロットが顔をあげた。淡いブルーの瞳が、まずランツェレットの顔を見て、それから、両手に抱えた花束とキャンディーに移る。
「ランツ、どうしたの? 花束、気に入らなかった?」
「いいえ、素敵なプレゼントよ。ありがとう」
ランツェレットは微笑んで、花束からバラを一本抜きとった。
きょとんとしたシャロットの胸元に、茎を折ったバラを飾り、それから棒付きキャンディーを、鼻先に突きつけるようにして差し出す。
「はい、花束のお返し」
シャロットは、一瞬微かに首を傾げたが、すぐに柔らかく微笑んで、
「ありがとう」
キャンディーを受け取った。
淡いピンク色をした、ハート型の棒付きキャンディー。主に、結婚式のプチギフトとして贈られるそのハートキャンディーを、シャロットは物珍しげに、くるくると回しながら眺めていた。
「あっ。ランツがシャロットにケーキを……あれ?」
やってきたティーレが、シャロットの手でくるくる回るハートキャンディーを見て、切れ長の目をまん丸くした。
「あ、あれ? ランツ、チョコケーキは?」
ランツェレットは、人差し指をぴんと立てて、唇にあててみせる。
「うふふ。これでいいの」
ランツェレットの微笑みに、ティーレは怪訝な顔で首をかしげた。
キャンディーを眺めるシャロットの胸元で、真っ赤なバラが鮮やかに輝いていた。
その意味をランツェレットだけに誇示するみたいに、咲き誇っていた。
「キャンディーに……バラ一輪……? なんか、意味でもあるの?」
首をかしげて見せたティーレに、ランツェレットは微笑んだ。
「うふふ。ブートニアって分かります?」
「ブートニア?」
「わからないなら、別にいーんです。どうせ、シャロットもわかってないでしょうし」
ますます首をひねるティーレの肩をポンと叩いて、ランツェレットはキッチンに入った。
つやつやと輝くチョコレートケーキが、今か今かと、自分の出番を待っている。
「うふふ」
ランツェレットは、チョコレートケーキが乗ったお皿を、ひょいと持ち上げた。
「ねえ、チョコレートケーキを焼いてきたのだけど、よかったら食べません? もちろん、みんなで!」
日本式のヴァレンタインは好きだ。
愛情でチョコレートを渡すのも自由。親愛でチョコレートを渡すのも自由。
『あなただけに』も自由だし、『みんなに』でも自由。
どんな思いを乗せたとて、チョコレートの輝きは変わらないのだ。
「チョコレートケーキ?」
シャロットがキャンディーから顔を上げて、ケーキに負けないつやつやの瞳でランツェレットを見た。
その胸には赤いバラ。つやつや輝く赤いバラ。
結婚式で貰ったブーケのお返しに、新婦が新郎の胸に飾る、それは誓いのブートニア。
「ええっ、あたしたちもいいの!?」
驚いた声を上げたティーレとミーレルに、ランツェレットは微笑んで頷く。
「うふふ。もちろん」
日本式のヴァレンタインは好きだ。
けれど、こんなふうに楽しめるなら、ドイツ式のヴァレンタインも悪くはない。
甘く高貴なバラの香りに満たされたキッチンで、ランツェレットはそんなことを思った。