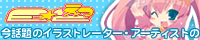今すぐゲームを確認する
- ホーム
- スペシャルコンテンツ
- バレンタインミニノベル2010
- 影野 陽太様
ココアパウダー・コーティング / 影野 陽太様

凍えそうな北風が、音を立てて耳元を掠めていく。
影野陽太は、くすんだこげ茶色のマフラーを、首元にきつく巻きつけた。
今日は二月十四日。セント・ヴァレンタインデー。
ショーウインドーの中では、甘い言葉を添えられた甘いチョコレートが、鮮やかな暖色の光に照らされて、キラキラと輝いている。
けれど、磨かれたガラスの外側、陽太が歩く街道では、薄暗いグレーの空の下、切れかけの街灯がチカチカ点滅するばかり。空気はツンと冷たいだけで、甘い香りはどこにもないし、耳に響くのは風切り音、やわらかな愛の言葉とは聞き違えることさえできない。
「……ん?」
ふと、ガラスの向こうに見えた言葉に、陽太は足を止めた。
鼻の頭を赤くした、半透明のしょげた顔……ガラスに映った自分の向こうに、コロコロした字体のポップが躍っている。『ヴァレンタインの恋の魔法が、ふたりを導いてくれる』
「魔法……かぁ……」
陽太の想うあの人は、この世でいちばん、魔法が効きそうにないひとだ。
御神楽環菜は、どこまでも実利的で、現実的で、尊大で、自信家で……そんなところも陽太は好きだったけれど、今日ばかりは、そんな実利的な性格が、少しさびしい。
「ヴァレンタインのチョコなんて、思いつきもしないだろうな……」
もし万が一、環菜がヴァレンタインの存在を思い出したとしても、わざわざ陽太にチョコレートをくれる可能性などゼロに等しい。
利潤を生まない行為はしない。陽太の好きな環菜は、そういうひとだ。
「いっ……いやいや。マイナスにばかり考えちゃだめだ、俺。もしかしたら、もしかしたら、万が一にでも、環菜会長がチロルチョコの一つくらい、くれる可能性だって……」
――まだ、そのようなありもしない期待をしているんですの!?
寮を出る前に聞いたエリシア・ボックの言葉が、陽太の脳裏に響き渡った。
――そう簡単にチョコがもらえるなら、『自己採点作戦』なんていらないはずでしょう!? チョコがほしいなら、御神楽環菜に認められる努力をして、来年再来年に期待なさい! いつまでも夢みたいな期待ばかりしていると、来年再来年どころか、来世再来世に期待することになりますわよ!
「わかってるよ、わかってるよ、どうせ夢みたいな期待だよ……」
ポップの踊るショーウインドーから目を離して、陽太は歩き出した。
目の端に流れていくチョコレートたちは、厚いガラスの向こうに並んで、甘い匂いさえ、陽太のところにはやってこない。
そうさ、ヴァレンタインなんて、遠い世界の出来事なんだ。
「俺の周りには、ヴァレンタインなんてはじめからなかったんだよ。きっとそう。うん」
そんな、情けない宣言と共に頷いた瞬間、
陽太の鼻を、甘い匂いがくすぐった。
目の前で、チョコレートショップの自動ドアが開いたのだ。夢のような甘い匂いと一緒に、小さな紙袋を小脇に抱えた女性が歩み出てくる。
女性の、すべてを見通すレンズのように冷ややかな瞳が、灰色の街道を見渡した。
陽太の足が、びくりと凍った。足だけではない、全身が凍りついたように動かなくなって、息をするのすら難しくなった。
チョコレートを小脇に抱えて歩み出てきた、御神楽環菜を目の前にして。
「えっ……? 会長……、えっ……!?」
環菜は、陽太のことには気がついていないようだった。ただ、無駄のないしぐさで携帯電話を取り出して、耳にあてる。
どうして、環菜会長がこんなところに? そのチョコレートは、もしかして俺に……?
お花の咲き始めた陽太の頭の中に、
――いつまでも夢みたいな期待ばっかりしてると……!
エリシアの鋭い声が、再び響いた。
「……俺の、なワケないよね」
ぽつりとつぶやいて、陽太は深く深く、帽子をかぶった。
顔を隠して、うつむいて、足早に環菜の前を通り抜ける。
未練がましい横眼で、陽太は、コール音の響き始めた携帯と、小脇に抱えられたチョコレートの子袋を見た。
きっとあの子袋は、環菜会長が忙しい合間を縫ってでも、チョコをあげたいと思っている誰かに渡るのだろう。あの携帯電話が呼び出している、幸せな誰かに……。
息をひそめて、陽太は環菜の前を歩み去ろうとした。その、瞬間だった。
ポケットで、いきなり何かが震えだした。
陽太は驚きのあまり、水をぶっかけられた猫みたいに垂直に飛び上がった。あわててポケットをひっくり返して、ぶるぶる震える物体を引きずり出す。携帯電話だった。
「えっ、わっ、あっ!?」
慌てて三度も失敗して、二つ折りの携帯をやっと開けた。ディスプレイを一瞥もせず、電話を取る。
「はっ、ひゃいっ!? もしもしっ!?」
「何を間抜けな声出してるの?」
冷ややかな声は、電話を当てた方の耳と、電話を当てていない方の耳、両方から聞こえた。
陽太の片耳に、通話が切れる「ぷつり」と言う音が響いた。
「丁度良かった。あなたを呼びつけようと思っていたのよ」
けれど、冷ややかなその声は、陽太に向かって響き続けていた。
陽太の目の前で、陽太に向かって、環菜が冷ややかな微笑を浮かべていた。
「かっ……環菜会長!? どうしてここひっ!?」
思いきり舌を噛みながら言った陽太の言葉に、環菜は呆れたように頬をゆるめた。
「別に、私がどこにいようと私の勝手でしょ? 強いて言うなら、ちょっと時間ができたから、あなたを探していたのよ」
「え……俺をですか……?」
「ええ」
頷いて、環菜は小脇に抱えていた子袋を持ち上げた。
びくん、と陽太の胸が高鳴った。うるさいほどの鼓動が耳の奥で響きだす。
……と。
不意に、鳴り響き始めた鋭い電子音が、陽太の心音をかき消した。
「あっ。ちょっと待って」
環菜は子袋を引っ込め、慣れた手つきで携帯を引っ張りだすと、耳にあてた。
「ちょっと仕事の話みたい。長引くだろうから、どっか暖かいところにでも入ってなさい」
ちっとも悪びれずにそう言って、環菜は携帯片手に陽太から離れていった。
ぽつん、と取り残された陽太の耳元で、心臓がうるさいほどに鳴っている。
あのチョコレート、もしかして、本当に俺宛てなんだろうか。
陽太の胸に、じわりと熱いものが宿った。けれど。
――また夢みたいな期待を……!
エリシアの声が、陽太の胸に氷水を注ぎ込む。
「そんなわけ、ないよね。きっと、もっと別の……がっかりするようなこと……」
たとえば、そう。「学園のみんなに義理チョコを配らなければいけないの。これとおんなじものを一万個買ってきなさい」とか。
あるいは、そう。「大好きな人がいるのだけど、どうしても告白する踏ん切りがつかなくて……。だから、あなたが代わりに、このチョコを渡してきなさい!」とか。
「ありうる、ありうる……」
ありうる。と一つ頷くたびに、陽太の胸が冷えていく。耳元でするどい風の音が響いて、お花の咲きかけた世界が、空と同じ薄灰色に戻っていく。
「待たせたわね」
ありうる、と何十度頷いた頃だろうか。環菜が携帯をしまいながら、陽太のところへ帰ってきた。陽太は、口元をひくつかせるように微笑んで、「いいえ」とかぶりを振った。
「えと……それで、俺はそれと同じチョコを一億個買ってくればいいんですね?」
「はァ?」
環菜はあからさまに眉をひそめた。
「何バカなこと言ってるのよ。……ほら」
環菜が、チョコレートの入った子袋を差し出してくる。
「あ……わかりました」
陽太は頷いて、子袋を丁寧に受け取る。
「えっと、これを誰に届けたらいいんですか?」
「……あのね、さっきからあなたが何を言ってるのか、さっぱり分かんないんだけど」
「ええと、ですから……俺が会長の代わりに、このチョコを誰かにですね」
「誰かにじゃなくって、私はあなたにこのチョコをあげたのよ」
「……え?」
冷たく麻痺した陽太の頭に、環菜の言葉はすぐには響かなかった。
じわじわと、じわじわと、氷が溶けていくように、環菜の言葉が陽太の頭に染みていく。
あなたにあげたのよ、と。
「あ……あなたにって、俺にですかぁっ!?」
「私の目の前に、他に誰がいるわけ? オバケでも見えてるの?」
「えっ、ええっ、でも……くしゅんっ」
くしゃみと一緒に、陽太の身体に震えが走った。
そういえば、どれくらいここに立ちつくしていたのだろう。
ぎゅっと自分で抱きしめた肩は、氷のように冷たかった。
「……あなた、まさかずっとここで待ってたの?」
目を見開く環菜に、陽太は努めて明るく笑ってみせた。
「あはは、ちょっとぼうっとしてたみたいで」
「呆れた。……見張ってなきゃ、私が逃げるとでも思ったの?」
「あっ、いえ、そんなことは……」
「ばかね」
環菜の手が素早く動いて、陽太の手から子袋をむしり取った。
陽太が「あっ」と言う暇もなく、環菜は袋を無造作に破いて、中からチョコレートの小箱を引きずり出す。
「あっ、あっ、あのっ、環菜会長!? 俺、なにか悪いこと言っちゃったんですか!? だったら謝りますからっ、そのチョコは、そのチョコだけは……んぐっ!?」
口の中にビー玉ほどもある塊を突っ込まれて、陽太の言葉が止まった。
「どう? これで分かった?」
薄くココアパウダーの付いた、白くて繊細な指先が、陽太の唇に触れていた。
口の中でほろ苦いパウダーが溶け消えて、甘いチョコレートがとろけだす。
「あなたにあげたチョコよ」
「んん……」
何か言おうとしたのだけれど、陽太の頭は真っ白で、ろくな言葉も浮かんでこない。やっと言葉が浮かんできても、口の中で「もごもご」と響くばかりだ。
「ウィスキーボンボン。暖まるわよ」
環菜は短く言いながら、自分の指先についたココアパウダーを舐めとった。
陽太の口の中に、ほろ苦い味が広がりだす。喉の奥に熱い液体がすべりおちて、胸の奥が、かあっと熱くなる。
「あ……あの、環菜かいひょう……」
「さて。それじゃ、私はこれから打ち合わせがあるから、そろそろ行くわね」
チョコレートの箱を陽太に手渡し、環菜はあっさりときびすを返した。
歩み去る憧れの背中。陽太は口の中のチョコレートを、もったいない気持ちと一緒に呑み込んで、
「環菜会長っ!」
声を張り上げた。
「あのっ……ホワイトデー、ぜひ、えっと、お返しさせてください!」
環菜が足を止めた。くるりと、首だけで振り向いた環菜の顔に、笑顔はなかった。
「はァ? 何言ってるの、あなた」
びくっ、と陽太の肩が跳ねる。ウィスキーボンボンで温まっていた胸の奥が、またすっと温度を失った。
「あっ……ええと、ごめんなさい。会長はお忙しいのに……。チョコもらえただけで身に余るほどの幸せなのに……この上、ホワイトデーに予定を開けてほしいだなんて……わがままを……」
陽太は、チョコレートの箱をきつく握って、努めて柔らかく微笑んで、環菜を見た。
「えっと、ごめんなさい、会長。その……もし、えっと、万が一、またいつか、暇な時間ができたら、その時にでも、お返しできたら……いいな、なんて、ははは」
「ばかね」
冷たい言葉が、陽太の耳に響いた。けれど、その声色は、むしろ柔らかい。
「ホワイトデーには、きっちりお返しを貰うに決まってるじゃない。この私からチョコを貰ったんだから、当然でしょ?」
「え……」
陽太の顔から、偽物の笑顔がかき消えた、数歩先で、環菜が呆れたように微笑んでいる。
「だからね、あなたは遠慮せずにこう言えばいいのよ。……またね」
「あっ……えっと……」
陽太の喉の奥に、胸の内に、じわじわと温かみが戻ってくる。
心臓の音が、耳元でうるさいほど高鳴っていく。
まだお酒を飲んだことはないけれど、強いお酒で酔っ払うのは、こんな感じなんだろうか。
「ま……また今度、です。環菜会長」
「よろしい」
満足げに頷いて、今度こそ、環菜の背中は遠ざかっていって、やがては街道の先へと消えた。
陽太はひとり、北風の吹く灰色の街道に取り残された。
けれど、もう寒くはない。ショーウインドーの向こうに並んだ、色とりどりのチョコレートも、ポップも、もう、チープな幻のようにしか思えない。
「また今度、かぁ……」
陽太の胸の奥には、ウィスキーボンボンの温もりが、まだじんわりと残っていた。