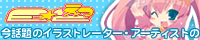今すぐゲームを確認する
- ホーム
- スペシャルコンテンツ
- バレンタインミニノベル2010
- どりーむ・ほしの様
ふくらめ! ガトーショコラ! / どりーむ・ほしの様

オーブンレンジの真っ赤な光に照らされて、丸型の中のショコラ生地が、むくむくと膨らんでいく。
どうか、どうかこのまま膨らんで。
ふぇいと・たかまちは、神さまにお祈りするみたいに、オーブンレンジの前で両手を組み合わせていた。
どうか、どうかしぼんでいかないで。
今度しぼんでしまったら、きっと私の心まで、くしゃりと潰れてしまうから。
ことの始まりは、二月十三日の朝だった。
今思い返せば、それは遅すぎる始まりだった。
その朝、ふぇいとが一人で気まぐれに町へ出てみると、街道に甘い香りが満ちていた。
暖かな照明に彩られた、たくさんのチョコレート。ころころした字体で描かれた、楽しげなポップ。ショーウィンドーの向こうに広がる夢のような世界に惹かれて、ふぇいとは一軒のお菓子屋さんに迷い込んだのだった。
少ないお小遣いを計算して、やっと選んだチョコレート菓子をレジに持っていくと、人の良さそうなおじさんが、ふぇいとの顔とチョコレートを見るなり、優しげな顔をほころばせた。
「おやおや、お嬢さん。プレゼント用かい? 明日はヴァレンタインだものね」
ヴァレンタイン。町中のポップに描かれていたけれど、イマイチ意味の分からなかったその横文字を、ふぇいとは思いきって、おじさんに尋ねてみることにした。
「あの、ヴァレンタインって、なんですか?」
ふぇいとの問いに、おじさんは一瞬、細い目をまん丸く見開いたけれど、すぐにまた優しそうな笑顔に戻って、
「ヴァレンタインって言うのはね、チョコレートに想いを込めて、愛の告白をする日のことだよ」
と、言った。
「あっ……あああ、愛の告白っ!? 明日!? 明日は愛の告白をしていい日なんですかっ!?」
「ああ、そうだよ」
柔らかく頷いて、おじさんはチョコレートをレジに通そうとした。
ふぇいとはあわてて、おじさんの手からチョコレートを奪い返す。
「やっ、やっぱりこのチョコやめますっ!」
「……そうなのかい?」
「はっ、はいっ! ええっと、おじさん! 調理用のチョコはどこに売ってますかっ!?」
おじさんが戸惑いがちに指さした売り場へと、ふぇいとは突撃した。
オーブンレンジの光の中で、ガトーショコラが膨らんでいく。
ぎゅっ、と、ふぇいとは組み合わせた両手に、きつくきつく力を込めた。
絆創膏だらけの小さな両手に、じわり、真っ赤な血がにじむ。
「――痛っ!?」
包丁を動かす手が、びくんっ、と止まった。
包丁の刃に引っかかった人差し指から、じわっ、と血がにじんでくる。
ふぇいとは、せっかく刻んだチョコレートに血が落ちないように、あわてて指を口にくわえた。
チョコレートの甘い味とは似ても似つかない、鉄の味が口いっぱいに広がる。
傷口にぐるぐると絆創膏を巻きつける。これで、十二枚目だ。
あまりにみっともない、絆創膏だらけの両手。ふぇいとの鼻の奥がつんとして、視界が滲んだ。
「ふぇいとちゃん? 何か作ってるの? あたし手伝おうか?」
リビングから聞こえてくる、どりーむ・ほしのの声に、すがりかけて、
「いっ……いいのっ! どりーむちゃんはこっち来ちゃだめだよっ!」
すんでのところで思いとどまる。
一人でやらなきゃ意味がない。
一人でやらなきゃ。
オーブンレンジの光の中で、濃いブラウンのショコラ生地が、型を飛び出すくらいに膨れ上がる。
あと少し。あと少し。
不意に込み上げてきたあくびをかみ殺して、ふぇいとは膨れきった生地を見つめ続けた。
キッチンに、まぶしい夕日が差し込んでいた。
「うー……なんで膨らまないのー……?」
ドロドロのまま型にこびりついたショコラ生地を見て、ふぇいとはため息を漏らした。
きちんと時間どおりに加熱したはずのショコラ生地は、ただの少しも膨らまず、とろけたチョコレートと大差ない状態のまま、型の底にこびりついていた。
「えっと……えっと……もう一回チョコレートから刻まなきゃ……痛っ!」
慌ててチョコレートを刻みだすと、みるみる、ふぇいとの指に絆創膏が増えていく。
「あっ! やっと膨らんできたっ!」
夜も更けたキッチンで、オーブンレンジの明かりだけが、ひときわ明るく輝いていた。
じわじわと、今度こそ膨らみ始めるショコラ生地。むくむくと膨らんだ濃いブラウンの生地は、しかしみるみる、ブラウンから黒へと変わっていって……、
「えっ!? えっ!?」
黒い煙をレンジの中に大量発生させながら、燃え始めた。
「かっ、かかかっ、火事ですっ!!」
ふぇいとはあわててレンジの電源をひっこ抜き、焦げたショコラ生地に水をぶっかける。
炎も煙もそれでおさまったが、あとにはびしょぬれのレンジが残された。
「あう……うう……。えっと、レンジ拭いて……ううん、その前に焦げ付いた生地をはがさなきゃ……。うう、何時間かかるかなあ……」
ふぇいとはちらっと時計に目をやった。
時刻は正午過ぎ。もう、二月十四日は始まってしまっている。
「うう……せめて、せめてあとひと月早く気付けていたらよかったのに……」
びしょぬれになった丸型を、レンジから取り出す。ぽたぽたとしたたる水滴が、ふぇいとの指に冷たく沁みた。
「あと何分加熱するんだっけ……?」
ふぇいとは、調理台の上に置いた携帯電話に目をやった。
ティスプレイには「二月十四日 五時五十五分」という表示が浮かび上がっている。
「あと五分……」
オーブンレンジの中で、膨らみきった生地がより濃いブラウンに色づいていく。
あとは、生地をはみ出て膨らんだ部分が、「くしゃっ」と潰れたら完成だ。
焼き上がった生地の中に、とろとろのチョコレートを閉じ込めた、ガトーショコラが出来上がる。
「お願い……。今失敗したら、もう……」
ふぇいとが絞り出すように呟いて、きつく両手を組み合わせた、その瞬間。
ばつんっ。
と音を立てて、オーブンレンジの光が消えた。
それだけではない。部屋中の蛍光灯がすべて消えているし、冷蔵庫のファンが回る音も消えている。薄暗くなった早朝のキッチンに、携帯電話のディスプレイだけがぼんやり輝いていた。
「えっ、ええっ!? 停電!?」
暗くなったレンジの中で、膨らみきったショコラ生地が、だんだんとしぼみだす。
「あうっ、あううっ。どうしよう。どうしようっ!?」
どりーむに助けを求めようとして、ふぇいとは思いとどまった。
一人で何とかしなくちゃいけない。
ひとりで……!!
「……そうだ!」
ふぇいとは、ショコラ生地が焦げた時のように、レンジのコンセントを引き抜いた。
コンセントのプラグを、絆創膏だらけの両手でぎゅっと握り込む。
「お願い……動いてっ!!」
叫ぶように言うと、ふぇいとは両手の中で、得意の雷術を発動させた。
ふぇいとの両手に電光が迸る。絆創膏の表面に、じわじわじわ、っと血がにじみだす。
それでも、ふぇいとはショコラ生地だけを見据えて、電気を放出し続けた。
――ぶう……ん。
震えるような音と共に、真っ赤な光が、再びショコラ生地を照らし始めた。
「はあっ……はあっ……」
血だらけの両手から、プラグがすべりおちる。
額にじっとりと浮いた汗を拭って、ふぇいとはオーブンレンジに手を伸ばした。
震える手で、三度も失敗して、やっと、レンジの扉を開ける。
「……ああ」
ふわっ、と甘い香りが、ふぇいとの鼻をくすぐった。
まだ余熱の残る、オーブンレンジの真ん中に、焼き上がったショコラ生地があった。
丸型をはみ出して膨れた生地が、てっぺんだけ「くしゃっ」と潰れた、濃いブラウンのガトーショコラが、薄く蒸気を纏いながら、そこにあった。
「やっ……」
ふぇいとは、血のにじむのも気にせずに、ぎゅっと両手を握りしめた。
「やった――――ッ!!」
ふぇいとの叫び声に応えるように、時計の鐘が、午前六時を告げた。
「はい、ふぇいとちゃん。ヴァレンタインのチョコだよ~」
どりーむから差し出されたチョコレートを、ふぇいとはきょとんと見つめた。
どりーむの顔とチョコレートの包みを交互に見つめ、それが自分へのプレゼントだと理解できると、ぱっと微笑む。
「え? ほんと? わ、私ももらっていいの?」
「? 当然じゃない」
ふぇいとはどりーむにもらったチョコレートを大事そうに胸に抱えこんだ。
「だってヴァレンタインって愛を告白するんでしょ! あ、あ、あ、あの、私もチョコ作ったのっ!」
包帯でぐるぐる巻きになった両手で、ふぇいとは小箱を差し出した。
ガトーショコラの微かなぬくもりが、まだ箱の中に残っている。
「あ、あ、……あいしてます……。あの、あの……ずっと、ずっと、そばにいていい?」
ぎゅっと目をつむって、ふぇいとは裏返った声を絞り出した。
この二日間、ずっと、ずっと、この瞬間だけを夢見ていた。
「ちょ、ちょ、ちょっと落ち着いてっ」
あわてたようなどりーむの声に、ふぇいとはゆっくり、目を開ける。
上目づかいに、どりーむを窺って、ふぇいとは小さく、首をかしげた。
「えと……だめ、かな……?」
「う~ん……どうしようかなぁ」
「……そっか」
ふっと、ふぇいとはうつむいた。
両手の傷跡が、急に痛み出した気がした。
瞳にじわっと、涙がたまる。ガトーショコラのぬくもりよりも、ずっと熱い涙が。
「どりーむちゃん……わたし……」
ふっと、顔をあげたふぇいとの額に、やわらかな何かが触れた。
中腰になったどりーむが、ふぇいとのすぐ目の前まで顔を寄せて、微笑んでいた。
「なーんて、冗談だよ。ありがとう、ふぇいとちゃん」
ふふ、と笑って、どりーむはもう一度、ふぇいとの額に口づけた。
「どりーむちゃん……うっ、ばか……どりーむちゃんのばかぁっ……大好きぃ……っ!」
小箱の中でガトーショコラがひっくり返るのも気にせず、ふぇいとは、どりーむにぎゅっとしがみついた。いじわるなどりーむの胸元を、思うさま涙で濡らしてやった。
ふぇいとは、どりーむの手をきつく握りしめながら、百合園の校舎を歩いていた。
どりーむが優しく握り返してくるふぇいとの右手には、もう、切り傷の痛みはない。
ただ、甘いしびれと、幸せな火照りがあるだけだった。
窓から午後の光が差している。空気がなんとなく暖かく感じられるのは、身体が熱いせいだろうか。
ふぁいとはさっきからじんじんと熱を帯びているひたいを、そっとさすった。
「どうしたの? さっきからおでこさわってるけど」
どりーむに言われるまで、ふぇいとは自分が無意識に何度もひたいをさわっていることに気が付かなかった。
びっくりしたふぇいとは、考えていたことを、思わずそのまま口に出す。
「えっ、あっ、なんかじんじんするの。たぶんいつものキスと違ったから……」
「ふうん? ……ふふ」
その言葉に目を細めたどりーむは、ゆっくりとふぇいとの顔に唇を近づけてきた。
触れそうになるぎりぎりのところで向きを変えた唇が、ふぇいとの耳に甘い言葉を囁く。
「いつものキスも、してほしい?」
「あ、あわ……」
耳に息を吹きかけられ言葉を失うふぇいとの手を、どりーむは優しくにぎった。
「部屋に帰ったらお茶をわかしましょ。ふぇいとちゃんのガトーショコラを二人で食べて――……」
どりーむはふぇいとの手を持ち上げて、包帯に覆われた人差し指にキスをした。
「それから、ふぇいとちゃんも食べてあげる」
指先から頭の中まで、どりーむの唇と言葉にしびれながら、ふぇいとは、何度も何度も頷いた。