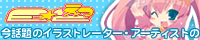今すぐゲームを確認する
- ホーム
- スペシャルコンテンツ
- バレンタインミニノベル2010
- エメ・シェンノート様
あの笑顔を追いかけて / エメ・シェンノート様

軽やかに鼻歌を口ずさみながら、エメ・シェンノートはボウルの中のケーキ生地を混ぜ合わせていた。
出来上がった生地をいくつかの小さな型に流し込み、焼きあげて、サテンのような光沢をもつチョコレートでコーティングしていく。
あっという間に、調理台の上には手のひらサイズのウサギを模ったチョコケーキが、ぴょこぴょこと並んだ。
完成したチョコレートケーキを眺めるエメの顔には、何かを慈しむような笑みが浮かんでいる。
ケーキを作り始めた時から、一点の汚れも付いていない純白のスーツと同じように、エメのその笑顔も、ケーキを作り始めた時から今まで一度も陰ってはいない。
ぴょこぴょこ並んだチョコレートケーキを、あるいは、その先にある何かを、エメは慈愛に満ちた笑顔で見つめていた。
※
チョコレートケーキを前にして笑顔を浮かべているエメを、物陰からじっと見つめる三つの視線があった。
「なんだかとっても嬉しそうだにゃう」
キャタピラつきのプレゼントボックスからひょこっと顔を覗かせて、アレクス・イクスが猫目をきらきら輝かせた。
「あれは恋をしている目ですよ。本当ですとも」
アレクスのプレゼントボックスの裏にひょっこり隠れて、ブーツを履いた白ネコの獣人、バスティアン・ブランシュが確信をこめた声で言った。
「ちょっと、やっぱり失礼ですよ。覗きじゃないですか、これ!」
片倉 蒼が線の細い端正な顔をしかめて言うと、アレクスがビシリと蒼の鼻先に肉球を突きつけた。
「キミ、それでもエメの執事なにょかい!?」
「どっ……どういう意味ですか?」
「恋愛に諦観していたあのエメが、あんなに優しげな顔で想い浮かべられる人物ができたのだとしたら、エメを想う者として、それを祝福し手助けするのが筋じゃないか。……そう言うことですね」
バスティアンがすらすらと言葉のあとをつぐ。
アレクスのプレゼントボックスから伸びた赤いリボンの端が手の形になって、バスティアンに向かってビシリと親指を立てた。
たじろいだように、蒼が呻く。
「そっ……それはそうかも知れませんけど、いや、でも仮にそうだとしても、ご主人様の色恋を不躾に詮索するなど執事にあるまじき行為……」
「おっと、動きだすみたいにゃう」
アレクスがエメを指さした。
エメはうさぎのチョコレートケーキをいくつかの小箱に分けて収め、それをまとめて大きな紙袋に入れると、嬉々として厨房を出て行った。
「追いかけるにゃう!」
きゅらきゅら、とキャタピラの音を響かせながら、アレクスがエメのあとを追い始める。
「ちょっとアレクスさん!? やめてくださいってこんなこと!」
「やめたければここにいるとよいですよ。お留守番、よろしく」
バスティアンは少しかがんで、ぽんと蒼の肩を叩くと、きびすを返してアレクスのあとを追った。
二人分の足音と、キャタピラの音が遠ざかっていく。
一人残された蒼は、
「まったくあの二人は……他人の恋をのぞき見するなど、執事として以前に倫理的にやってはいけない行為じゃないですか」
言いつつ、遠ざかっていくエメたちのほうをちら、ちらと見た。
「大体、恋と決まったわけでもないですし、もし恋だったとしても、ご主人様は必ずや、僕には真実を語ってくださるはずです。ええ、そうですとも。きっと……」
遠ざかっていくエメたちの背中を、蒼はじっと見つめて、
「……あの二人が余計なことをしないよう、見張っておく必要はあるかも知れませんね」
エメたちの背中を追って駆けだした。
※
ほのかに甘いバラの香りが、辺りに満ちていた。
手入れの行き届いた薔薇の学舎のバラ園を、エメは紙袋一つ提げて歩いてゆく。
その姿は、薔薇の学舎の生徒ではないというのに、絵になるほどに様になっていた。
「薔薇の学舎と言うことは、お相手は男性かにゃう」
きゅらきゅらとキャタピラの音を響かせながら、声をひそめてアレクスが言う。
アレクスの後ろにはバスティアンが、その後ろには蒼が、こそこそと続いていた。
彼らの姿は、忍んで歩いているというのに、驚くほど目立っていた。
「二人に余計なことをさせないため。僕はあくまでそのために……」
ぶつぶつ呟きながら歩いていた蒼は、ふと、バスティアンの背中にぶつかった。
「どうしました?」
「シッ! あれを」
身を潜めたバスティアンの後ろから、蒼はエメの様子をうかがった。
※
「俺に?」
早川 呼雪が、エメから小箱を受け取って、首をかしげた。
「ええ。チョコレートケーキです」
「どうして俺に?」
「だって、今日はバレンタインでしょう?」
呼雪はさらりとした黒髪をこぼして、小箱に視線を落とした。
それからまた、視線をエメに戻す。
「動機が分からんな」
「わからないですか? 一年に一度のこんなに面白い行事を、別に関係ないからと言ってスルーしたくはないじゃないですか。女の子たちは、たとえチョコを渡す恋人がいなくっても、友チョコを交換し合って楽しんでいるって言うのに」
呼雪は一瞬、何かを思案するように目を細めたが、すぐに、儚げな笑顔を浮かべた。
「……なるほど。実におまえらしいな」
「でしょう?」
エメの柔らかな笑顔に頷いて、呼雪は小箱を持ち上げて見せた。
「頂こう。親愛の証として」
「ええ、もらっておいてください。親愛の証として」
※
――信愛の証として。
エメの言葉を物陰で聞いて、アレクス達は小さく溜息をついた。
「……友達にあげるチョコだったじゃないですか」
ひときわ大きく溜息をついた蒼を、アレクスがリボンの端でビシリと指さした。
「甘い! そんなことでエメの執事が務まるにょか!」
「ちょっ!? 僕の何が甘いって言うんですか!」
「激アマにゃう! エメのあの笑顔を見れば一発にゃろう! さっきまでケーキを作っていた時と、今浮かべていた笑顔は質が違う!」
「……笑顔?」
ちら、と蒼はエメに視線を放った。
「……そう、言われてみれば」
呼雪と別れたエメは、柔らかな微笑を絶やさぬままに、薔薇咲き乱れる庭を優雅な足取りで歩きはじめていた。
※
「へえ、これはかわいいウサギだねぇ」
エメから受け取った小箱を開けて、佐々木 弥十郎はほんわかと微笑んだ。
「もらっていいのかい、これ」
「もちろんです」
「うれしいねぇ。……でも、困ったね、いまお返しできるようなものがないや」
「いいですよ、面白そうだから配って歩いているだけですから。喜んで受け取ってくれたら、それで」
「喜んでいるさ。いいものだねぇ、友チョコって。本命チョコとはまた違った嬉しさがあるよ。……まあ、本命チョコもそんなに貰い慣れてはいないんだけどねぇ」
弥十郎のいたずらっぽい微笑みに、エメははにかむような笑顔を返した。
※
「あの方は、ご主人様のご親友の弥十郎さん!?」
蒼は、声をひそめるのも忘れたように叫んだ。
「なるほどあるいは弥十郎さんほど親しい間柄ならば、友情を超えた愛に気づくと言う可能性も……」
「甘い! チョコレートよりもアマアマにゃ! それじゃあ百万年経ってもエメの執事は務まらんにゃう!」
「ええっ!? まだ甘いんですか僕は!?」
「あの笑顔を見てみるとよいですよ」
バスティアンにきっぱりと言われて、蒼はエメの方に視線をやった。
弥十郎と別れて歩きだしたエメの顔には、はにかむような笑みが浮かんでいる。
「……」
目を細めて、蒼はじいっとエメを見据えた。
「……わかりません」
「では修行と思ってついてくるにゃう」
リボンの端で蒼の肩をポンと叩いて、アレクスはエメのあとを追い始めた。
バスティアンもちょっと身をかがめて、ぽん、と蒼の肩を叩き、エレクスのあとを追う。
釈然としない顔で、蒼はしばしエメの横顔を見つめていたが、
「……ああっ、もう、待ってくださいよ!」
観念したように、バスティアンの背中を追い始めた。
※
「……」
エメは、天使を模った石像の前でふと足を止めた。
中天にある太陽に目を細めながら、エメは天使像を見上げて、何かを慈しむような笑顔を浮かべる。
※
「ストップにゃう!」
アレクスがキャタピラを止め、リボンの端でバスティアンを制した。
「ストップです」
バスティアンが足を止め、純白の短毛でもふもふと覆われた片手を上げて、蒼を止めた。
「……なんですか、今度は」
蒼は素直に足を止め、先を行く二人に倣って狭い茂みに身を隠しながら、胡散臭いものを見る目でアレクスとバスティアンを見た。
「あの笑顔にゃ! あの笑顔! あれこそ、ケーキを作っていた時の恋する笑顔にゃ!」
「ええ……? ちょっとよく見えないんですけど……」
蒼はバスティアンの肩にすがって、狭い茂みから身を乗り出した。
「おそらく、あの天使像の前で待ち合わせでもしているのでしょう。もうすぐ、あの笑顔を向けられるべき相手がやってくるはず……ちょっと、押さないでくださいよ」
「すみません……よく見えないんです」
蒼は、アレクスのプレゼントボックスにも手をかけて、さらに身を乗り出し、
「にゃにゃにゃ!? ちょっとタンマにゃ!」
アレクスのキャタピラが勝手に転がり、バスティアンのブーツが滑った。
「え……!?」
茂みに隠れていた三人はもつれ合うようにして、丁度エメの足元へと転がりでた。
「……あれ?」
天使像へ目を向けていたエメは、突然足元に転がってきたアレクス達に視線を落とす。
「君たち、どうしたの?」
「いいいい、いいえっ、あのこれには深い理由がありましてッ!」
アレクスとバスティアンを振りほどき、蒼は真っ先に立ち上がった。
きょとんとしたエメに向かって、蒼は何度も舌を噛みながら早口にまくしたてる。
「つまりですね、えっと……この二人! そうこの二人が! ご主人様が最愛の相手にチョコレートをあげに行くなどという根も葉もないことを言い出しまして!」
「にゃに! 一人で言い逃れとはずるいにゃう!」
「蒼もそれはそれは楽しそうについてきたでしょうに!」
「楽しそうになんてしてません! 僕はあなた達がご主人様や周りの方々に迷惑をかけないようにと……!」
言い合う三人を、しばしきょとんと眺めていたエメは、やがて白薔薇が花開くように、ぱっと笑った。
「あはは。そっか、みんな私を心配して、あとをつけてきてくれたんだね?」
三人は言い争いをひたと止めて、一斉にエメの笑顔を見た。
蒼とアレクスが、こそこそと言葉を交わす。
「……この笑顔ですか?」
「……似てるような、違うような、にゃう」
二人の言葉に気付いた様子もなく、エメは紙袋を持ちあげた。
「でも残念。私は別に、最愛の人にチョコレートを渡しに来たわけじゃないよ。大事な人たちに配って歩いていたことには変わりないけどね」
蒼が、ちらと冷ややかな視線をアレクスとバスティアンに放った。
「……」
「……」
アレクスとバスティアンは、申し合わせたように蒼から視線をそらした。
「本当は、君たちにも帰ったら渡そうと思ってたんだけれど……」
エメは、ちらと一瞬だけ天使像を振り返った。
エメの顔には、慈しむような微笑が浮かんでいて、けれどよそ見をしていた蒼たちは、誰ひとりとしてその視線には気付かない。
「でもよく考えてみれば、ここで渡すのが一番かも知れないな。うん」
「……ここで、ですか?」
蒼が問うと、エメは、若葉が朝露を垂らす時のように、こくん、と軽やかに頷いた。
紙袋から取り出した小箱を一つずつ、蒼達に配り、最後に自分の分も取ると、エメの提げていた紙袋は空になった。
「もともとね、最後に残った一個は、ここで私が食べるつもりだったんだ」
「ここで、ですか? ……でも、ここは野外ですし、埃っぽいのはお嫌なのでは?」
「今日は特別さ。……いいや、ここは特別……かな? だって、食べて見せてあげないと、おいしさが伝わらないだろう?」
「だれに……ですか?」
蒼の言葉には答えず、エメは微笑みながら、自分の分の小箱を開けた。
「ハッピー・バレンタイン」
晴れやかな声で言って、エメはうさぎを模ったチョコレートケーキをフォークで切り取り、口に運んだ。
蒼達もそれぞれ、釈然としない顔のままケーキを口に運び、
「……おいしい」
ぱっと、あっと言う間に顔を輝かせた。
「おいしいかい?」
「はい、とっても!」
笑顔を輝かせて、蒼がこくこく頷いた。
「もっと見せてあげてよ、おいしい顔」
「はい! ……えっと、どなたに?」
エメは答えず、ただ何かを慈しむような顔で微笑んだ。
暖かな昼の日差しが降る庭で、甘い薔薇の香りに包まれながら、エメたちは笑顔でケーキを口に運ぶ。
陽光を受けて輝く天使像が、エメたちの笑顔を見下ろしていた。
その瞳には人々を慈しむ、深い慈愛の色が浮かんでいた。