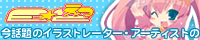今すぐゲームを確認する
- ホーム
- スペシャルコンテンツ
- バレンタインミニノベル2010
- 皆川 陽様
チョコレートが尽きるまで / 皆川 陽様
街道に並ぶ店々は、パステルカラーに飾り立てられ、漂うのは夢のように甘い香り。
行きかう人の声も軽やかに弾んでいて、青空から降る昼の陽光さえ、ポップなオレンジ色に染められているようだった。
「なんだなんだ? 今日は街がキラキラしてるぞ?」
テディ・アルタヴィスタが、街の光を映したように瞳をキラキラさせながら、きょときょとあたりを見回した。
『バレンタイン・キャンペーン』などとポップの掲げられた店々からは、行列が店先を飛び出して伸びている。
「なんだ? なんだ? お菓子屋さんのバーゲンか!?」
テディは鼻をひくひくさせて、甘い香りを溢れさせるスイーツショップを覗き込んだ。
「ちょっと、横入りしないでよ!」
店からはみ出た行列から、一人の少女が首を伸ばして眉根を寄せた。
テディはきょとんとした眼差しを少女の方へ向けて、首をかしげる。
「なあなあ、バレンタインってなんだ?」
「へ?」
今度は少女がきょとんとして、首をかしげた。
「バレンタインって、あれか? お菓子が超安い日か?」
「いや、うーん……どっちかと言えばお菓子は高くなる日だけど……」
少女はこめかみを?き、ふと、どこか夢見るような微笑みを浮かべた。
「バレンタインって言うのはね……――」
※
押しつけがましい極彩色が、街道をチカチカと飾り立てていた。
周囲に満ちているのは甘ったるい香り。
人々の甲高い笑い声は、誰かを笑い物にしているよう。
ぎらぎらした昼の光に、皆川 陽は目を細めた。
「なんだか、今日の街は居心地が悪いな……」
陽の吐いた小さなため息は、街道に満ちる華やかな熱気に押しつぶされて、消える。
街道を優く人々は、誰もが夢見るような表情で、ショーウインドーに並んだチョコレートや、やわらかく指をからめた隣の誰かを見ている。誰ひとりとして、陽がいることにすら気が付いていないかのようだった。
「……せっかくだから、ボクもチョコレートを」
ぽつりと言って、また陽はため息をついた。
「やめよう。一年で一番虚しい日を、これ以上虚しくすることないよね」
頭を振って、陽は足を速めた。甘い空気を振り切るように、周囲の景色から目を背けて、
「あっ! 向こうのチョコもうまそう!」
――ひたと、その足が止まった。
振り返った陽の視線の先で、テディが、ぱんぱんになった紙袋を両手に提げて、街道を駆け回っていた。
またひとつ、一抱えほどもあるギフト用チョコレートを買いこんで、すでに満杯の袋へ無理やり突っ込んだ。
「テディ!?」
叫ぶような陽の声に、テディがくるりと振り返った。戸惑ったような陽に向かって、テディはとがった八重歯をのぞかせ、いたずらっぽく笑う。
「陽!」
テディは街道の人ごみをするりと抜けて、陽の前まで駆けてきた。
両手に提げたやわらかなパステルカラーの紙袋を、まるで捕まえてきたカブトムシを見せびらかす小さな子供みたいに、陽の目の前で持ち上げて見せる。
「チョコ!」
「いや、チョコなのは大体わかるけどさ」
陽は、押しつけられた紙袋を両手で押し戻して、苦笑した。
「なんで、こんなにたくさんチョコなんて買ってるの? バレンタインだから?」
テディが、八重歯を引っ込ませて真顔に戻った。
「……陽、バレンタイン知ってるのか?」
「知ってるけど……?」
テディは、ぱっと花が咲くように笑った。
「僕はぜんぜん知らん!」
「ええ? でも、チョコこんなに買ってるじゃん」
「みんな買ってるからな! たぶんバレンタインはチョコをたくさん買う日だな!」
「いや……間違っちゃいないけどさ」
陽はぽりぽりとこめかみを掻いた。
「でも、別にチョコレートが安く買える日とかじゃないんだよ?」
「そんなこと、知ってるさ」
むっと、テディはちょっとむくれて見せた。
「今日はどっちかと言えば、お菓子は高い日なんだぞ!」
「……どうにも、テディの知識は中途半端だなあ……。誰かに吹き込まれたの?」
テディは問いには答えず、陽に紙袋を押し付けた。
「ちょっと持ってて!」
言うなり、テディはきびすを返して駆けだした。
陽が呼びとめる暇もなく、テディはギフト用のチョコレートを三箱も買い足して、満足げなほくほく顔と共に戻ってきた。
「ちょちょ、そんなに買ってきてどうするのさ!?」
「どうするって? 食べるに決まってんじゃん!」
陽の提げた紙袋に、追加でチョコレートを押し込んで、テディはまたいたずらっぽく笑う。
「一緒にくおーぜ!」
「一緒にって……二人で!?」
陽の叫ぶような声に、テディはこくこくと頷いた。
猫じゃらしを前にした子猫のような無邪気な笑みで、テディは陽を見上げる。
「あっ……もしかして」
ふと、テディの笑顔に影がさした。
街道の熱気を拭き散らすように、一陣の冷たい風が、ぴゅうと人々の合間を吹き抜ける。
「……陽、チョコ嫌いか?」
不安げな眼差しで見上げられて、陽はうっとたじろいだ。
「いや……チョコは、その、食べものとしては好きだよ?」
「じゃあ……この中に好きなチョコがないんだな!?」
くるりときびすを返して「買ってくる!」と駆けだしかけたテディの腕を、陽ががしっ掴んだ。
「いやいやいや! もう十分!」
「ええ!? そうなのか!?」
「そうそうそう! もう全部好きなチョコだから!」
「そうか!? じゃあ、全部ちゃんと食うか!?」
やけくそ気味に叫んでいた陽の言葉が、ぴたりと止まった。
すがるように見つめてくるテディの瞳を、陽は引きつった笑顔で見返した。
「えー……っと、ぜ、全部好きなチョコレートなんだけどさ……ほら、さすがに量が多いから……誰かにおすそわけしない? とっ、友達とか呼んでさ、皆でパーティしようよ!」
「だめだ。二人だけで食べよう!」
テディはきっぱりと言った。
「……へ?」
「二人じゃなきゃ駄目なんだ!」
「ええ……?」
陽は困ったように首を傾げたが、テディは頑として首を縦には振らなかった。
「ええっと……どうして?」
「どうしてもだ!」
「……もう一回聞くけど、テディ、バレンタインって何の日か知らないんだよね?」
「知らない!」
腕を組んで、つんと視線をそらしたテディを、陽はしばし、困惑した顔で見つめた。
道の真ん中で向かい合った二人の脇を、甘やかな笑顔を浮かべた人々が通り過ぎていく。
人々の柔らかな笑顔が沁み渡ったように、少しずつ、陽の困惑顔が笑顔に変わっていった。
「……ふう」
陽が小さく息を吐く。
どこか諦めたように、けれど、清々しいため息だった。
「……よし、わかった。食べられるだけ食べよう!」
「ほんとか!?」
ぱっと顔を輝かせて、テディは陽の顔を覗き込んだ。
陽の笑顔もテディに負けないくらい、少しやけくそ気味なほどに、輝いていた。
「うん! 今日はみんなこんなに楽しんでるのにさ、ボクだけ困った顔してるのも損だし! もうお腹壊すまで二人で食べまくろう!」
「おおっ! 陽、全部食べろよ! 絶対全部だぞ!」
「うん、全部だ!」
「全部だ!」
テディは、荷物を一杯に提げた陽の手を取って駆けだした。
華やかな笑顔を浮かべる人々の波をすり抜けて、テディが駆ける。テディいに手を引かれてこけつまろびつ、陽がその後を追う。
二人の顔には、街を飾るパステルカラーにも、街道を行きかう人々の夢見るような笑顔にも、空から降る眩しい昼の光にも負けない、眩しい笑顔が浮かんでいた。
「あっ、ところで陽!」
「うん?」
「バレンタインって何の日だ!?」
駆けるテディの背中に向かって、陽は少しだけ笑顔を収めて、答える。
「一年で一番……そうだな、一年で一番、無意味に楽しい日……かな?」
テディは、八重歯をちろりとのぞかせて、晴れやかに笑った。
「なるほどな! 僕も楽しい! 陽もか!?」
テディの笑顔に押されるように、陽もクスリと笑った。
「うん、ボクも楽しいよ。結構予想外にさ」
※
「――バレンタインって言うのはね」
少女は、首をかしげたテディを、あるいは、その向こうにある甘やかな何かを眺めるように微笑んだ。
「だーい好きな人にチョコを贈ってね、二人で一緒に、甘いひと時を過ごす日のことよ」