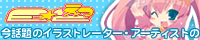今すぐゲームを確認する
- ホーム
- スペシャルコンテンツ
- バレンタインミニノベル2010
- 冬蔦 千百合様
おそろい / 冬蔦 千百合様

銀色の月光が、冬蔦 千百合の行く夜道を、白々と照らしていた。
千百合のすぐ目の前では、如月 日奈々のゆるくウエイブのかかった長髪が揺れている。
ピンク色の髪が月光を受けて、まるでもぎたてのみずみずしい桃のように輝いていた。
「――っと」
不意に、ピンクの髪が大きく揺れた。
足を絡ませて倒れかけた日奈々を、千百合は後ろから支える。
「大丈夫? 日奈々」
日奈々は、光を通さない銀色の瞳を細めて、照れたように笑った。
「えへへ……ちょっと、遊び疲れちゃった、みたい、ですぅ」
「そっか……。今日のデート、楽しかったもんね」
千百合は苦笑して、日奈々の腕を自分の肘に絡ませた。
日奈々も慣れたもので、すぐに千百合の意図を理解すると、肘にぎゅっとしがみついて、歩調を合わせてきた。
「千百合ちゃんに介助してもらうの……久しぶり、ですぅ」
「普段はなかなか頼ってくれないからねー。疲れた時くらい、白杖の代わりにあたしを頼ってよ」
千百合が声を立てて笑うと、日奈々は肘に頬を擦りつけるように、かぶりを振った。
「白杖だなんて……千百合ちゃんの方が、もっと頼れて、安心できる、ですぅ」
「……そっか」
千百合は、空いた右手で日奈々の髪を軽く撫でた。
月光に冴え冴えと照らされた夜道を、千百合は日奈々の歩調に合わせて、ゆっくりと歩いていく。
涼しい夜風が、時折頬を撫でていった。
そのせいだろうか、日奈々が千百合の腕に身を寄せるように、腕に力を込めてきた。
「どうしたの日奈々? 寒い?」
「……私も」
ぽつりと、かすれた声で日奈々が言う。
「私も……こうやって、誰かの白杖に……なれるのかなぁ……?」
「白杖?」
千百合は、振り返って日奈々を見た。
細い肩が、触れたら崩れそうなほど頼りなく揺れていた。
「私も……誰かのために、何か……できる人に、なれるのか、なぁ……?」
「……日奈々」
千百合は足を止めた。
腕をそっと引き抜き、日奈々に向きなおる。
日奈々のか細い両肩に、両手で柔らかく触れて、千百合は銀色の瞳を覗き込んだ。
「あのさ、千百合。あたしね、日奈々に好きって言ってもらえた時、すっごく嬉しかったの」
「……?」
さっきまでの不安げな表情が、ふとかき消えた。代わりにきょとんとした表情を浮かべて首をかしげた日奈々に構わず、千百合は言葉をつづける。
「その時初めて、あたしは自分の本当の気持ちに気づいたんだ。日奈々のことをとっても大切に思っている気持ちや、日奈々のこと、ずっと守っていきたいって思っている気持ちを」
「千百合、ちゃん……」
「その時、あたしはあたしの目の前が開けたような気がしたんだ。月が夜道を照らすみたいに、日奈々の言葉が、存在が、あたしの行く先を照らしてくれたんだよ」
空から降る硝子色の月光が、日奈々の身体を縁取るように照らしだしていた。
「日奈々はあたしにとって、もうとっくにかけがえのない人だよ。日奈々がいるから、あたしは日奈々を守って生きていこうと思えるんだもん。……――あの日、好きだと言ってくれた日奈々の言葉と」
千百合は、そっと自分の髪に触れた。
髪を結んだ青いリボンの、水を織ったように滑らかな感触が、指先に伝わる。
「日奈々に貰ったこのリボンが、あたしの行く先を照らしてくれる、あたしの白杖だよ」
日奈々に見えない笑顔の代わりに、千百合は日奈々の髪を撫でた。
「だから……自分がだれかの役に立てるかだなんて、そんなこと、言わないでよ。あたしにとって、日奈々はもうかけがえのない人なんだから」
ちょっと拗ねたように千百合が言うと、日奈々はきょとんとさせていた顔に、やわらかな微笑みを浮かべた。
千百合をまねるように、日奈々も千百合の髪に触れてくる。
「……ありが、とう」
日奈々の言葉に、千百合は「ふふ」と声を立てて笑った。
「こっちこそ。……あっ、そうだ」
千百合は日奈々の髪から手を離し、ポーチの中に隠していた小箱を取り出した。
リボンをかけた、ハート型の小箱だ。
「あのね、日奈々。これ、よかったら受け取って?」
千百合は、日奈々の白い両手を導いて、小箱を握らせた。
日奈々は、繊細な指先で小箱をなぞって、
「……ハート型、ですねぇ」
そう呟いて、微笑んだ。
「そうだよ? あたしの気持ちの形だもの」
「……嬉しい、ですぅ。……あっ」
ふと、日奈々の顔に不安げな影がさした。
「でも……私、お返し、何も、持ってきてない……」
「いいんだよ、お返しなんて」
千百合は、日奈々のこわばった頬にそっと触れた。
「このリボンと、告白してくれたあの日の言葉と、それと、日奈々がそばにいてくれること。それだけで、あたしにとっては一生分のプレゼントだからさ」
「……っ」
日奈々は銀色の瞳を、月光の落ちた泉のように潤ませて、小さく鼻をすすった。
「……ねえ、千百合ちゃん。この……小箱にかかってるリボンって……何色?」
「うん? 青色だけど?」
「小箱……開けて、いい、ですぅ?」
「うん、もちろん」
千百合の返事を待って、日奈々は小箱のリボンを解いた。
解いたリボンで、日奈々は自分の髪を結んで、微笑む。
「……おそろい、ですぅ」
包装用の安いリボンも、輝く桃色の髪の中にあっては、千百合のリボンに負けないくらい鮮やかなサファイアブルーに輝いて見えた。
「あっ、日奈々。リボンならもっといいのあげるよ!?」
「いいん、ですぅ。これで」
日奈々は、千百合の胸にぽんと頭を預けた。千百合の背中に手を回し、耳を胸に押し当てる。
柔らかく目を閉じた日奈々の顔に、まるで我が家に帰ってきたような安堵の表情が浮かんだ。
「……私もね、千百合ちゃんが、いてくれて……よかった、ですぅ」
深く吐息の混じる、落ちついた声で、日奈々は言う。
「今日だけじゃなくって……千百合ちゃんといると、いつも……手を、引いてもらってる気が……するん、ですぅ。千百合ちゃんが、隣を歩いてくれていると……見えないはずの、私の、目に……明るい道が、見える気が……するん、ですぅ」
日奈々は、へへ、と笑った。
「千百合ちゃんと、おそろい、です……ね?」
千百合は声を立てて笑い返して、日奈々の頭を優しく抱きしめた。
涼しい夜風に、日奈々の甘い髪の香りが混じって、千百合の鼻をくすぐる。
「……あれ? 千百合、ちゃん?」
千百合の腕の中で、日奈々がふと顔を上げた。
銀色の瞳が、いたずらっぽく笑う。
「鼓動が……速いよ? どうして、ですぅ?」
千百合は、甘い香りに緩んでいた頬を、きゅっと引きしめた。
「また……早くなった」
からかうように言う日奈々の顔を、千百合はむっとして覗き込んだ。
柔らかな日奈々の頬を、両手で挟むようにして抑える。
「……そうだよ?」
きょとんとした日奈々に、いじけた声で千百合は言って、
「……ん」
そのまま、柔らかくて微かに甘い香りのする唇に、口づけた。
一瞬の口づけ。すぐに顔を離して、きょとんとしたままの日奈々に「ふふ」と笑いかける。
「鼓動だって早くなるよ。……日奈々とおそろいでね」
ぱっと、頬を赤く染めて何か言いかけた日奈々の顔を、千百合はぎゅっと胸に押し付けた。
「むー……」
もぞもぞと暴れる日奈々を、千百合はきつく抱きしめて胸に押し付ける。
日奈々はやがて暴れるのをやめて、千百合の背中に腕を回してきた。
湿った吐息の音が、ふいに千百合の胸の中で響く。
「……日奈々、泣いてるの? 苦しかった?」
「……嬉しい、から、泣いてるん……ですぅ」
いじけたように、日奈々は言った。
「わかる、でしょ? ……千百合ちゃんと、おそろい、なんですからぁ……」
日奈々の言葉に、千百合ははっと目を見開いて、
「……そう、だね」
鼻をすすって、きつくきつく、日奈々の頭を胸に押し付けた。