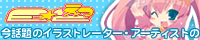今すぐゲームを確認する
- ホーム
- スペシャルコンテンツ
- バレンタインミニノベル2011
- ミーナ・リンドバーグ様

いつもよりおしゃれした、赤いチェックのワンピース。
ひまわり色の大きなリボン。
手にしているのは白い大きなお皿。
お皿の上にはチョコレートケーキ。何度も練習を重ねて作った、美味しいんだよと自慢できるケーキである。ケーキの上には『Happy Valentine's Day』と書かれたクッキーのプレートと、 鮮やかな赤が映える苺。ケーキだけでなく、お皿にもチョコソースやフルーツソースでデコレーションが施されており、見た目にも可愛い。
それを、ウエイトレスがトレイを持つ時のように華麗なバランスで持ち、
「真田先輩っ」
愛しの佐保に声をかけた。
「どうしたでござるか、ミーナ」
「ミーナがチョコケーキ作りました! 食べましょうっ♪」
「おお、かたじけない」
佐保が座るテーブルに、ケーキを置いて。
隣にちょこんと腰かける。
「これは美味そうだ。ミーナは料理上手でござるな」
「そんなことっ」
ないです、と両手をわたわた振る。
普段料理を作りはしても、ここまでのものは出来ない。
今日、この時のため、頑張ったから。
――できたんだよ? 先輩。
でもそんなこと、恥ずかしいから言えるはずがなく。
「えへ。……味に自信は、あります」
とだけ。
頬を赤くして、言うのだ。
「そうか、楽しみだ」
言われた言葉ひとつに浮かれながら、ミーナはケーキを取り分けた。
プレートの部分が乗るように切って皿に乗せ、佐保の前に置き。
「? ミーナ、フォークがないと食べられないでござるよ」
きょとんとする佐保に、
「あの、あの。ミーナが食べさせてあげます! あーんしてください!」
勇気を出して、言ってみた。
「あーん?」
「嫌、ですか?」
「ふむ。嫌とは思わなかったな……お願いするでござるよ」
あ、と開けられた口。手にしたフォークで一口分ケーキを取り、その中に入れた。
「ん! 見た目以上に美味でござる!」
「本当ですか!」
その言葉に嬉しくなる。笑顔で佐保が頷く。胸が、ほんわりあたたかい。
「先輩」
――ミーナにも、あーんって、してください。
その言葉は言いたいけど、断られるのが怖くて言えなくて。
口の中で言葉を転がす。転がすだけじゃ、佐保には届かないけれど。
「ミーナ、フォークを借りても良いか?」
その態度に気付いてか否か、佐保にそう言われた。
――やっぱりあーんは嫌、だったのかなぁ。
ちょっとしゅんとしながらも、素直にそれに応じると、
「あーん」
ケーキが乗ったフォークを向けられた。
「え、」
「お返しでござる」
へらっと笑う佐保は、きっとこの行為を深く捉えてはいないのだろうけど。
それでもやっぱり嬉しくて、
「あー、ん」
口を開いた。
ケーキの味は、よくわからなかった。