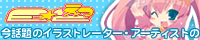今すぐゲームを確認する
- ホーム
- スペシャルコンテンツ
- バレンタインミニノベル2011
- フェイミィ・オルトリンデ 様
ユーフォリアへ渡す為のケーキ作りも無事終えて、いざ渡そうとするこの瞬間、無性に緊張してしまうもので。
「……やべえ。喜んでもらえなかったらどうしよう」
フェイミィはマイナスな思考に溺れてしまう。
そのたびに、大丈夫味は良いいっぱい練習したんだから、と自らを奮起させる言葉を紡ぐが、その甲斐もなく微妙に指先が震えていた。
――かっこわりー。
――でも、渡すからな。
それだけ決めて、ユーフォリアの許へと一歩踏み出した。
「ユーフォリア、様っ!」
気張ってしまって声が上ずる。それを恥ずかしく思ったけれど、振り返って「どうしましたか?」と微笑むユーフォリアを見たら吹き飛んだ。
温厚で優しい性格が、外見からあふれ出ている淑女。
とても綺麗で、理想で、憧れの人。
「あ、えぇと……そのっ、」
彼女を前にしたら、上手く言葉が出てこなくて。
必死で投げる言葉を探した。
「?」
――きょとんとした目も可愛いなあ。首傾げるなよー、あー首筋白いな綺麗だな。食べちゃいたいな。すべすべしてそう。
そんな煩悩も混じる頭をフル回転。
「これっ、受け取っていただけますか!」
なんとか出て来た言葉は、当たり障りの無いもので。
それだけかよオレそれだけじゃねーだろオレ、と叱責しながら続く言葉を口にする。
「カナンの事とか、ペガサスの件とか……世話になりまくりなもんで。せめてものお礼っつーか、なんつーか……」
だけど上手く続いてくれなくて、尻すぼみになっていく。
――あーかっこわりー、本当かっこわりー。
頬が熱いことを感じ、顔も真っ赤なんだろうなと余計に恥ずかしくなった。
それでも渡したいから、後退せずにケーキを入れた箱を差し出した姿勢で止まっている。
箱を持つフェイミィの手に、ひんやりとした、けれど確かに熱を持った指先が触れた。
「手作りですか?」
「え、なんでそれを」
「指先にチョコが付いていますし」
くすくす、笑われた。きちんと手は洗ったのに。恥ずかしくてそっぽを向いたら、
「ありがとう」
柔らかな声で、そう言われた。
お礼? いや、お礼を言いたいのはこっちの方で。だからケーキを作ったわけで。
「わたくしを想って、作ってくださったのでしょう? 美味しく頂きますね」
「っ、はい! そりゃもう、ユーフォリア様を想いまくりで作りました! 気持ちばっちりこもってます!」
「ふふ。嬉しいです」
本当に嬉しそうに笑ってくれるから、さっきとは違った意味で頬が熱い。
「こ……これからも宜しくお願いします!」
90度直角になるくらい、ぺこんと頭を下げて一礼。
「はい。こちらこそ」
そんな体勢だったから、そう答えたユーフォリアの顔は見えなかったけど。
声音からして、きっと微笑んでいてくれたに違いない。