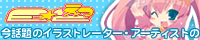今すぐゲームを確認する
- ホーム
- スペシャルコンテンツ
- バレンタインミニノベル2012
- 高峰 結和様

高峰 結和は硬い表情でチョコレートを見つめていた。
「さあ、ここからが大事なところだよ」
と、アンネ・アンネ 三号は結和に生クリーム入りの絞り袋を手渡す。
しかし結和の両手はかたかたと小刻みに震えるばかりだ。
それというのも、チョコレートがハート型である時点で、彼女はひどく恥ずかしい気持ちになっていたからだ。
「こ、これで文字を書くんですか?」
「そうに決まってるでしょ? ほら、真ん中のこのあたりに」
と、三号は優しく教えてくれるが、結和の緊張はちっとも解けない。
「う、上手く書けるでしょうか? ただでさえ料理は苦手だし、恥ずかしいし……」
と、結和は三号に訴えるが無駄だった。
「大丈夫だよ、大事なのは気持ちだって。それにバレンタインデーなんだよ?」
「そ、そうなんですけど、でも……やっぱり、いかにもな形のチョコレートは……」
結和は渡す時のことを想像して頬を赤らめた。
「うーん……だけど、本命チョコってこういうもんじゃないの?」
「そ、そ、そうですけど、そうなんですけど……ま、万が一、失敗したら嫌ですしっ」
結和はそう言って絞り袋を持ち直した。
途端に先端から生クリームが出てしまい、チョコレートめがけて落ちていく。
「うわわっ、ど、どうしましょう!?」
「お、いいチャンスじゃないか。ほら、この調子でL・O・V・Eって書いてみよう」
と、三号は前向きに言う。
後に引けなくなった結和は、ドキドキする心臓に我慢するよう心の中で言い聞かせた。
「え、える……おー……ぶい……いー……」
一つ一つ言葉にしながら、チョコレートの表面へ四つの文字を書き終える結和。若干いびつな形ではあるものの、読めない事はないため、結和にしたら上出来な方だった。
しかし、その完成した形を見た時、結和の恥ずかしさは限界を超えてしまう。
「こっ、こここ、こんなあからさまなメッセージ、む、無理です! はは、は、恥ずかしすぎて渡せませんっ!」
世の中の乙女たちはそうして気持ちを伝えるものだが、うぶな彼女には難しいものらしい。
「大丈夫だよ、結和。落ち着いて、次の作業に移ろう」
と、三号が声をかけた時だった。
軽くパニック状態に陥っていた結和は、つい両手に力を入れすぎてしまった。
直後に生クリームがぐにゃぐにゃと踊り出てきて、チョコレートの表面をつぶしていく。
「あああ! ここ、こんなつもりじゃ……ど、どうしましょう?」
せっかく書いた文字が読めなくなった。しかし、三号は優しい口調で言った。
「仕方がないね、作り直そう」
「っ……ご、ごめんなさい」
と、結和はがっくりと肩を落とす。
三号は気にする様子もなく笑い、彼女の肩をぽんぽんと叩いてやるのだった。