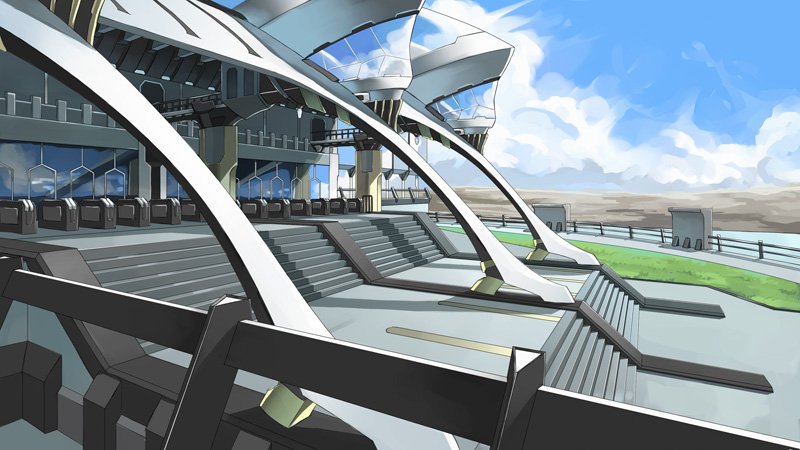リアクション
「……まったく、とんでもねーことになってやがんな」 * * * 「あっ! おにーちゃん、こっちこっちー!!」 倉庫の入り口で1人そわついていたノーン・クリスタリア(のーん・くりすたりあ)は、車を降りて走ってくる御神楽 陽太(みかぐら・ようた)に向けて手をぶんぶん振ったくった。 「遅くなってごめん」 「ううん。こっちこそごめんね、おにーちゃん。せっかくのお休みの日に呼び出したりしちゃって。環菜おねーちゃん、何か言ってた?」 「ばかだな。大事な妹からの緊急の呼び出しに、何も言うはずがないだろう?」 陽太は現在、パラミタ横断鉄道の実現をめざしている妻御神楽 環菜(みかぐら・かんな)の片腕として日夜奔走している。そのなかでの数少ない夫婦そろっての休日に陽太を呼び出してしまったことを申し訳なく思っているノーンを見て、陽太はくすりと笑って頭をなでた。 「早く行ってあげなさいって背中をたたかれたよ。 それより、占い師の術のせいで暴走している人がいるんだって? 現在の状況は?」 「えーとね、これがこうなって、ああでね……」 と、陽太はノーンからこれまでの経緯の説明をひととおり受ける。 「魔王軍を名乗る人たちが、ツァンダを火の海に変えようとしてる!?」 陽太はあらためてうす暗い倉庫の中を覗き込む。 あちこちで叫声や怒声が上がり、すっかりなかは混戦になっているようだ。 ふと、そのうちの1人がウェンディゴの脇をすり抜けて、入り口にいる陽太たちの方へよろめきながらも走ってくる。 だがそれもつかの間。 「チューガロン 轢き逃げ アターーーーーーーーーック!!」 軍用バイクが彼を跳ね飛ばして通り過ぎた。 それを目撃して、唖然となる。 「こ、これって……まさかなかの人たち、危険な薬を飲んでキメてたりはしない……よ、ね…?」 「ううん。みんな、外へ出さないようにしてるの。ちょっと強引になっちゃってるのは、人数差があるからなんだと思う……多分」 そのへんはノーンも分からないから憶測だ。 「おにーちゃん、どうしよう?」 「とりあえず、これを命じているレクイエムさんのところへ行こう」 陽太はできるだけ倉庫の壁際を通って、奥のスキップフロアへ向かった。 レクイエムはスポットライトとミラーボールの光のなか、幸せの歌を歌っていた。 目を閉じて歌うことに集中している姿は、周囲の喧騒から隔離した別次元にいるかのよう。 傍らにはいつしかペンギンアヴァターラのロイヤルちゃんがいて、両手(?)をばたつかせながらつま先立ちでリズムをとっていた。 「レクイエムさん、もうやめてください」 階段の途中から陽太は声をかけた。近付きすぎてレクイエムをヘタに刺激しないよう、探り探りゆっくりと残りの段を登る。 「こんなことをして何になるんです? 何が目的なんですか?」 レクイエムは歌うのをやめ、陽太を見た。 「アンタ、恋人はいる?」 「え? ……あ、はい。恋人というか、そのう……妻が、います、けど」 結婚して大分経つというのに、いまだ陽太は「妻」と口にするのがなんだか気恥ずかしい。 環菜を思い出してテレッテレになっている陽太の姿に、レクイエムはキーーーッとなった。 「幸せね! 幸せなのねっ! じゃあアンタなんかに恋に破れたアタシの気持ちが分かってたまるものですかあっ!!」 「恋に破れた?」 「そうよ! ふられちゃったのよ、こてんぱんにね。 アタシはプリマドンナだったの。彼は配属されてきたばかりの将校さん。連日あの人はアタシの舞台に通ってくれて、花を贈ってくれたり、食事に連れ出してくれたりしたの。でも、戦争が終わって……アタシに残ったのは、歌だけ。 アタシは貧しい村の出の娘でしかないから、あの人はアタシを捨てて去っていったの。国に残してきてた婚約者はお金も身分もあるきれいな女性で……アタシはしょせん、戦時の間の愛人。 ううん、もしかしたら最初から、お貴族サマのただの遊びの恋だったのかもしれない。でもアタシは本気だった。本当に愛していたのよ、ライナス…。 愛よりお金や身分がものを言う、こんな世界、大ッ嫌い! アタシはね、魔王サマの新しい世界で新しいアタシに生まれ変わって、新しい恋を見つけるの! それに、新しい世界になることがこの穢れた世界に生きる人たちの救いにもなるわ! つまりアタシは歌で世界を救ってやるのよ!」 「そ、それは極論です! この世界でだって、お金や身分の差があったって、ひとは愛し合って結ばれることはできます! 現に俺と妻だって――」 「なに? アンタ、じゃあライナスがアタシを捨てたのは、お金でも身分でもなく愛してなかったからだって言うの?」 「え? それ、さっき自分も口にしてたじゃあ――」 レクイエムが押し出す殺気に陽太はたじろぐ。 「キーーーーーーーッ!! なんて冷酷な人なの!! 傷ついてる乙女に対してその仕打ち、信じらんないッッ!!」 自分は口にしても他人はだめ。失恋した女のヒスに道理が通じるわけがない。 レクイエムは悲しみの歌に切り替え、さらに天のいかづちを導く。 「うわあっ!」 落ちてきた白光が陽太を打つも、陽太は直前に発動させていたインビンシブルでこれに耐えた。 よろめいた陽太に、レクイエムは追撃で天のいかづちを落とそうとする。 「おにーちゃん!! ――えーい!」 陽太が注意をひいている間に背後へ回っていたノーンが忘却の槍で不意打ちをかけた。うまく混乱している間の記憶を忘却して元の彼に戻ってくれたらという目論見があったのだが、しかし槍の穂先は服とわずかに脇の皮膚を裂いただけにとどまり、ねらいははずれてしまった。 ご主人さまを護ろうとロイヤルちゃんがとびかかり、ぺたっと顔に貼りつく。 「きゃあっ ♪ 」 ちょっとうれしそうな悲鳴を上げて、ノーンは階段を踏みはずしてスキップフロアから落ちた。 「くっ」 陽太はオイルヴォミッターを発射するも、華麗なステップで避けられてしまう。 「あー、あのポンコツ魔道書、女になってたのね。元からオネエ言葉だから全然分からなかったわ」 いつからそこにいたのか。反対側の袖口でセシリアが2人の戦いを見ながら呑気に言った。 「あの話ぶりからすると『ジゼル』でしょうか? 戦争恋愛映画の」 「多分ね。あの愛人うんぬんのセリフ、映画でまんま、歌姫が言っていたヤツだもの」 そのあとはカンペキ今のレクイエムの暴走だけど。 「しかしそれならそれでやりようもあります。「ジゼル」を説得して、ここを静めさせましょう」 「え? どうやるの? パパーイ」 セシリアは興味津々顔でアルテッツァの服のすそを引っ張った。 数分後。 「ジゼル!」 陽太目掛けて天のいかづちを落とそうとしていたレクイエムをセシリアが呼び、気を引いた。 レクイエムの手のなか、力が分散する。 「アンタは…?」 「フッ。みじめなモノね、ジゼル! たかが恋に破れたからって、ファンを煽って暴動を起こさせるとは…。 国一番の歌姫とたたえられた威光も地に落ちたものだわねっ! 同じオペラ座に在籍するドンナとして、とても見られた姿じゃなくってよ!」 なるべく居丈高な女性に見えるよう、セシリアは胸をそらし、口元に手をやってせせら笑いのポーズをつくる。 レクイエムはじーーーーーーっとセシリアを凝視し、そして言った。 「何やってんの? シシィ」 「あら、バレた? ってゆーか、そういうとこはちゃんと認識できてるのね。 やっぱ、駄目よ、パパーイ。ジャネットじゃないってバレちゃった」 「おやまあ」 ちょっと意外だったものの、すぐさま作戦の立て直しを図るアルテッツァを見た瞬間、レクイエムの顔がはっとなる。 「ライナス……まさか、あなた、ライナス? あなたもこの時代に生まれ変わっていたの?」 「――は?」 「ライナーーーース!」 抱き締めようと両手を広げて走ってくるレクイエムの姿に反射的、アルテッツァはその場から逃げ出しそうになったが、理性でぐっと踏みとどまった。 無理やり手を広げ、レクイエムを受け止める。彼と密接に抱き合ったとたん、背骨に沿って冷たいものが伝った。 「あなたがライナスだったなんて! 今生ではアタシたち、パートナーだったのね! これはやっぱり、2人の絆が運命である証!」 「……ジ、ジゼル、ここまでだ。もうやめなさい……でないと、ボクはキミに銃口を向けることになる」(棒) ほおをすりつけてくるレクイエムを振り払わないでいるのに精一杯で、セリフが棒読みになるのは仕方ないだろう。 「いやいやっ。そんなおそろしいこと、冗談でも口にしないでちょうだい。あなたの唇からそんな冷たい言葉、聞きたくないわ。この唇は、やさしくアタシの唇をおおうためにあるのよ。 ねえライナス。再会のキスしてちょうだい」 ……んーーーーっ。 「パパーイ! だめでしょ!」 セシリアの笑いを含んだ声で、初めてアルテッツァは自分がレクイエムを突き飛ばし、クロスファイアを放っていたことに気付いた。 「はっ! ……ああ……役を演じているだけだと分かってはいても、耐えられなかった…。オカマは駄目なんです。これは生理的なもので、自分でも何とも…」 鳥肌の立った両腕を服の上からさするアルテッツァの前で、ギリギリ砲火が当たらずにすんだレクイエムがむっくり体を起こした。 「お、オカマぁ? ……アンタ、言うにことかいてぇ! やっぱりアタシのこと、本当には愛してなかったのね! だまされた女の恨み、思い知りなさい!! くらえ! 天のいかづち!!」 しかしそれはセシリアが予測済みだった。ぷくくと笑いつつも、すでに対電フィールドが展開されている。 そしてファイアーウィップが飛んで、両腕ごと巻き込みレクイエムを無力化した。 「アツイッ! 熱いわああああっ」 「大変!」 魔道書本体も炎熱にさらされているのを見て、ノーンがあわてて出力を絞った氷術でレクイエムを凍らさない程度に適度に冷やす。 「ああっ! ライナスどうして? どうしてこんなことをするの? あなたを愛しただけなのに。こんなにも愛しているのよ」 「愛、愛とうるさいですね、本当に。ひとのこと見て連呼するのはやめてください、気持ち悪い」 ぷつぷつ寒イボが出始めたアルテッツァはレクイエムの姿を視界に入れまいと目を伏せる。 「こういうヴェルレクもこれはこれで面白いけどなあ。 えいっ」 セシリアが気絶するほど殴りつけて、レクイエムを正気に返した。 「……あら? アタシ一体何を」 元に戻ったレクイエムがあわてて呼びかけるも、ファンの集いで集められ、熱狂している人々は止まらない。 もうとっくにレクイエムの術を離れて彼らは暴走していたのだ。 「ど、どうしたらいいの?」 「あらら」 「ちょうどいいですね。このままただ帰っては夢見がさらに悪くなりそうだと思っていたんです。 やりますよ、シシィ」 マシンピストルを手に、騒乱のなかへ入って行こうとする。もちろん撃つためではない。鈍器として使用するだけだ。 「はぁ〜いはい、パパーイ。不当に受けた精神的損害の回復のため、おつきあいしますわ」 セシリアがひょこひょこついて行く。 「あ、待って2人とも! アタシも行く!」 「おにーちゃん、私たちも行こっ」 「うん、そうだね」 ノーンと陽太も混乱のなかへ身を投じたのだった。 激しい戦闘音が満ちたなか。 「……はっ」 ぱちっと音をたてて、ウーマ・ンボー(うーま・んぼー)が意識をとり戻した。 「お。やっと起きたか」 頭の方からアキュート・クリッパー(あきゅーと・くりっぱー)が覗き込む。 「それがし……一体…」 「おまえは用意してもらった海水の水槽で溺れたんだよ。覚えてないのか?」 フードマントの者に連れて来られたここで意気揚々海水の入った水槽に飛び込んだまではよかったが、ウーマは泳げないためぶくぶく沈んでアキュートに引っ張り出されていたのだった。 「失礼な。それがしはサカナなのに溺れるはずなかろう」 「サカナって、おまえまだ正気に返ってなかったのかよ!?」 「おお……あそこに波頭きらめく海があるぞ! アキュート!」 「って、ひとの話聞きやがれ! コラ!」 ふよふよ浮き上がったウーマは、そのまま吸い寄せられるように戦闘のど真ん中へ飛び込んだ。 「見よ、アキュート! 華麗に泳ぐこの姿を! それがし輝いてる…!」 「いや、どう見ても溺れてんだろーがよ」 人波にもまれ、ぶつかって、「アウッ、アウッ」となったあげくはじき飛ばされ、再び床に転がる結果になってしまったウーマを、アキュートはあきれて見下ろした。 「あの……大丈夫ですか?」 フードマントの者が寄ってきて、同じように心配そうに目を回しているウーマを見下ろしている。 「ああ。べつにあんたのせいじゃねーから気にすんな。水槽で溺れたのも、こうなったのも、変な術で暴走していたとはいえこいつの自業自得だ。 ま、ほかのやつらはともかく、うちのマンボウはどう見たって『清らかで罪のないサカナが生まれ変わった』くらいしか、説明がつかねえ姿だからな。本人がそう思い込んだってしゃーねえ」 「そうですか」 「……清らかで罪のないサカナ――って、俺は何を言ってるんだ?」 ほっとしているフードマントの者の前、アキュートはほおづえをついてひとりごちる。 「アキュートよ『漢は自分の言葉を疑ってはならない』。確信なき言葉を語るのは、漢のすることではない」 いつの間にかウーマが正気に返って目を覚ましていた。 「うるせえ! てめーは黙って目ぇ回してろ!」 ゴキン!! 「ギョッ!?」 せっかく正気を取り戻していたウーマだったが、アキュートの鉄拳制裁で再びぐるぐる渦巻き目になってしまう。 そんなウーマを見下ろして、アキュートは重いため息をついたのだった。 |
||