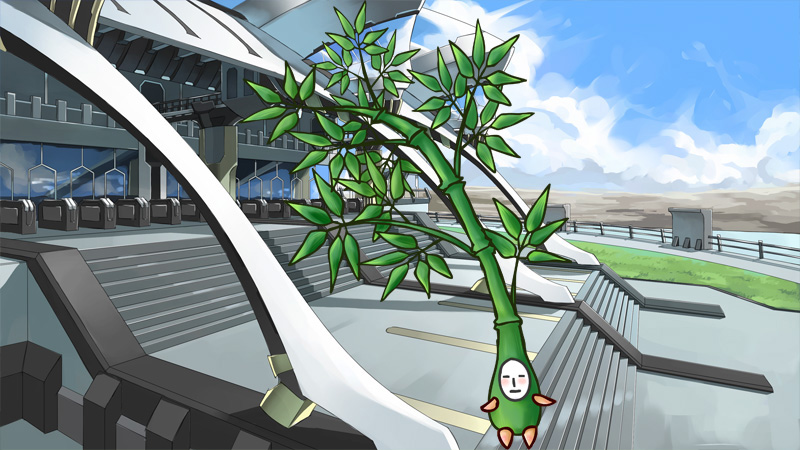リアクション
「さあ薬も無事手に入ったことだし。あとはこれをセルマに飲ませるだけねっ」 ☆ ☆ ☆ 「とりあえず、ひと通りの多い所へ行こう。その方が安全な気がする…」 わけが分からないながらも先のホワイトベールとのやりとりのような事態を懸念して、大通りへ向かったセルマ。 そこで彼を待ち受けていたのは富永 佐那(とみなが・さな)扮する海音シャナだった。 (ちょっとちょっと。どうしてセルマさん、まだ男の子のままなの?) 切れた息を整えながら歩いているセルマを見て、内心シャナはとまどう。 (失敗したわね、みんな) さてどうするべきか? 路上パフォーマンスをしつつ、必死に考えていると、腰に差してあった携帯がブルブル震えた。 すばやくオンを入れ、装着済みのイヤホンで受ける。それはホワイトベールだった。 「ごめんなさい、逃げられちゃった。でも今、そっちへ向かってるから、例の場所でセルマを引きとめておいて」 「……イエス」 プツ、とそこでオフにする。 「イエス、イエスイエスイエーースッ!! みんなーっ、今日は来てくれてほんっとーにありがとう!! 私も愛してるわーーっ!!」 「うわあああああああっ!! シャーナー!!」 「シャナっちゃーーーんっ!!」 ファンのどよめきが上がる中、シャナは仮設ステージを降りた。 そっと裏から出て、細路地を通ってセルマの背後に回り込む。 「ねぇねぇ、そこのあなた」 「え? 俺ですか?」 呼び止められ、振り返るセルマ。さっき見たステージに立っていた女性がそこにいるのを見て、少しまごついた。 シャナはセルマが自分に驚いているのを見て、にっこり笑う。 するっとその腕に自分の腕を巻きつけた。 「あなた、アイドルって興味ないですか?」 「ええっ?」 ――ナンパか? 「あれ? こういうの、言われたことないですか? 結構スカウトされてるように見えるんですけど」 あ、そっちですか。 「あの、俺、そういうの興味ないんで…」 あまり失礼にならないよう、そっと腕を抜き取ろうとしたのだが。 ガッチリ、ますます抱き込まれてしまった。 「みんな、最初はそう言うんです。かくいう私もそうでした。でも、一度体験したらもう病みつき。ふふっ。 そうだ、あなたも体験してみませんか?」 ぱちん。 いいこと思いついたとばかりにシャナが両手を打ち合わせる。 「ええっ?」 「いいこと思いつきました。さあ、行きましょう。私があなたを変身させてあげますわ!」 「ええええええーーーーーっ!?」 シャナに強引に連れ込まれたコスプレショップで、セルマはただただ呆然と目の前の衣装の山を見ていた。 「ふふふ。この私、コスプレネットアイドル・海音シャナが、セルマさんをすてきにプロデュースして差し上げますっ☆」 どんどんどんどん積み上げられていく衣装。 (これはアレだろうか? もしかして「ストップ」と言うまで止まらないんだろうか?) それだったらもう最初の1枚目でストップをかけていたんですが。 「あのー……これ、全部女の子の衣装に見えるんですけど、俺の気のせいでしょうか…」 そう言う間にも、シャナの手でハンガーからはずされたバルーンスカートがひらりと山の一番上に落ちる。 「あら? そのへんは気にしなくても大丈夫です。ちゃんと私に考えがありますから」 にこっと笑う彼女の方を、ぼんやりと見る。 と同時に、ショーウィンドーのガラス越しに、こちらへ走ってくるホワイトベールの姿がセルマの視界に入った。 まるで稲妻に打たれたように、セルマの脳裏をひらめきが走り抜ける。 「……あと俺、あなたに名乗りましたっけ?」 「えっ!?」 ぴょこっとシャナの肩が跳ねる。反射的なものだろうが、それで十分。 それを見た瞬間、セルマは脱兎のごとく店を飛び出した。 「あっ、セルマさん!!」 「待って、セルマーっ!!」 「これってほんとに何なわけ!?」 セルマはもう、パニックを起こしそうだった。 ☆ ☆ ☆ 「悠さん……悠さん…」 「うん?」 だれかに名前を呼ばれた気がして、篠宮 悠(しのみや・ゆう)はきょろきょろ辺りを見渡した。 が、それらしい姿はどこにもない。 「気のせいか」 再び歩き出した耳に、またも聞こえるか細い声。 「悠さん…」 「だれだ」 「俺です、セルマです」 人の幅ほどしかない、壁と壁の隙間からごそごそ這い出てきたのは、セルマ・アリスだった。 「一体どうしたんだ、あんな場所から出てくるなんて」 「ええ、まぁ。ちょっとありまして」 悠の家に落ち着くことができて、ようやく気分がほぐれてきたセルマは、なんとか笑みを浮かべてみせる。 「わけありなのは分かってる。でなかったらあんな所にひそんでたりはしないだろう。 一体何があった?」 「………」 何があったと言われても、返す言葉がなかった。何が起きているか、知りたいのはセルマの方だ。 だから口ごもってしまったのだが、それを見て、悠は「何かひとには言えないことが起きているらしい」と勝手に解釈したようだった。 「分かった。無理やり訊き出そうとは思わない。ただ、1つだけ教えてくれ。追われているのか?」 「――ええ。おそらくは」 「そうか」 何かに巻き込まれているとすれば、心身ともに支えとなるのはパートナーだろう。そう思った悠は携帯を取り出す。 「なら、シャオにでも連絡をとって――」 「待ってください!!」 短縮を押そうとした手を、あわてて掴み止めた。 「セルマ?」 「待って、ください…。いずれは、連絡をとろうとは思っています。でも、今はまだ…。 ちょっと、自分で考えを整理したくて」 「――そうか」 考えてみれば、彼だって携帯を持っているはず。連絡をつけたればそうしていただろう。 悠は思いあたり、黙って携帯をしまった。 「……すみません……せっかく心配してくださったのに…」 「いや。いいさ。今日1日くらいなら匿ってやれる。この屋敷なら安全だ。丸もいるしな。 オレはこれからちょっと出かける用事があるんだが、構わないか?」 「あ、はい。俺の方こそ、お忙しいときにお邪魔して申し訳ないです」 「なに、これぐらいなんともないさ。 ああ、部屋はどれでも好きに使ってくれていいぞ。無駄に広い家だ、部屋ならいくらもある。とにかく、これでも飲んで少し部屋で休め。顔色が悪いぞ」 「ありがとうございます。いただきます」 悠から手渡された飲み物を受け取り、さっそく口をつけた。 ずっと町を走っていたせいで、すっかりのどがカラカラだった。 「おいしい。でも、不思議な味ですね。こんなの初めてです。どうしたんですか? これ」 「ああ。さっき如月たちが持ってきてくれたんだ。そういえば、それ、セルマの好物なんだって?」 「よ。セルマ」 じゃあオレは行くから、と退室した悠と入れ替わりに、ひょこっと顔を出した如月 正悟(きさらぎ・しょうご)とホワイトベールを見て、セルマは盛大に口の中の飲み物を吹き出した。 「な……な、な…」 「あーあー、汚いなぁ。ひとんちでそんな粗相をしちゃダメだぞー」 「なぜここがっ」 「あら、簡単でしょ。電波を受信すればいいのよぉ」 まるで、だれにでもできる当たり前のことのように言う。 そんなはずない、どうせ正悟さんが何かしたんでしょう、と言い返したかったが、今はそれどころじゃなかった。 「うわああああっ!! か、体が痛っ!」 虹色の輝きを発し始めたセルマの体から、白い湯気が立ちのぼる。 「へー、こんなふうになるのか」 他人事のように――まぁ他人事だけど――つぶやいて、興味津々見下ろす正悟。 そうする間も、2人の前で、セルマはみるみるうちに女体化していく。 「……なんなんですかぁ、一体ーっ」 床にへたり込んだ格好で、セルマは言った。 何がなんだか全然分からない。 もう半泣きだった。 一方、正悟はそんなセルマもどこ吹く風。女体化が完了したセルマを見て手を叩いて喜んでいる。 「おお、巨乳美女!」 細身のセルマのことだから、きっとスレンダーで胸もこぶりになるに違いないと思っていた正悟は、思わぬ結果に口元をほころばせた。 「オルフェさんより大きいんじゃないの? ってゆーか、確実に大きいよな、その胸」 しげしげと、真上から服の中を覗き込む。 遅ればせ、ハッと気付いたホワイトベールが、正悟の背中を押した。 「なんだよ?」 「見ちゃだめ! 今、セルマさんは女性なんです!」 「そりゃそうだけど、元は男だからセルマも気にしないと思うぞ」 「気にします! 女性なんですからっ」 部屋の隅っこでぽしょぽしょ話している2人。 「うっうっ……こんなの、ひどいよ……おうちに帰れない…」 立ち上がる気力も沸かず、床にへたり込んだままのセルマ。 そのとき、シュルシュルと上から降りてきた何かが、セルマの胴に絡みついた。 「! ――あっっ」 否応ない力で、強引につり上げられる。 振り仰ぐと、天井の一部が開いて、巨大な目のようなものが暗闇に見えた。 「うわああああっ!!」 「セルマ!?」 「セルマさん!」 悲鳴を聞きつけた正悟とホワイトベールがそちらを向く。彼らに見えたのは、天井に引きずり込まれるセルマの足先だけだった。 「ワタシの役目は悠がいないときにこの家へ入り込もうとする間諜を片付けることである」 それが真実かどうかはともかく、天上天下唯我独尊 丸(てんじょうてんがゆいがどくそん・まる)はそう思い込んでいた。 この家に移って以来、天井裏にひそみ、侵入者がいないか見張る毎日。 そして今日もまた、見知らぬ侵入者が1人。 「……痛っ、痛いよ、丸っ! 俺だよ、セルマだってば」 奥へ引っ張り込まれる間中、セルマは必死に訴えたが、丸がそれを聞いている様子はなかった。 「間諜はうそをつくものである。そんなものに耳を貸すのは愚か者であり、わたくしは愚か者ではない」 「丸……信じられないかもしれないけど、俺はセルマなんだ…」 ようやく引きずりが止まって、ぐったりした様子でセルマが言う。 天井の梁でさんざん頭を強打し続けたせいで、意識が半ば朦朧としていた。 ウエストに巻きついていた触手がゆるむ。 やっと分かってもらえたのか……そう思った直後、さらに細くなった触手が今度は手や足、首、胸に絡みついた。 「ああっ! 丸!! セルマだってば!! 分かってくれたんじゃなかったの!?」 「間諜が真実を言うときはただひとつである。それは、拷問を受けて口をわるとき!」 「ええっ!? ご、拷問って、ちょっと丸!?」 「くのいちは体のあらゆる場所に武器を隠しておるもの。徹底的に調べさせてもらおうか」 セルマの言葉に重なって、体に巻きついていた触手が内側から服をビリビリに引き破った。 はたして正悟たちがたどりついたとき、そこには泣くセルマと、その前に直立不動している丸の姿があった。 「うっうっ……俺、違うって言ったのに、ちっとも聞いてくれなくて…」 シーツにくるまり、ホワイトベールに気遣われながら階下へ降りる。 「まったく、あの融通のきかなさはなんだ。一度悠に説教してもらわないと!」 ぶつぶつ言いながら階段を降りた正悟は、携帯を取り出して電話をかけた。 「今、着替えを持ってきてくれるように頼んだから、もうしばらく辛抱してくれ」 「……だれに?」 明るいリビングに戻ってこれたせいか、少し回復したセルマが用心深く訊く。 対し、正悟はあっけらかんと答えた。 「そりゃーもちろん、秋葉つかさ」 胸のサイズ的に。 |
||