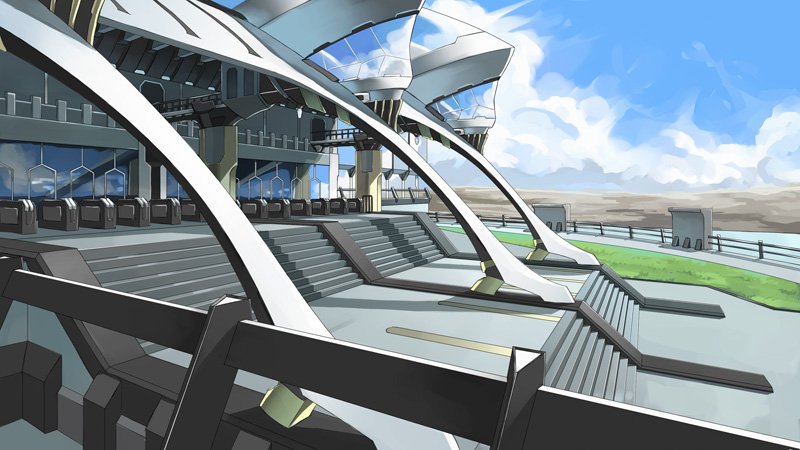リアクション
「さあ今度こそ全部終わりね」 * * * 長かった戦いも、ついに終幕を迎えたかに見えた。 しかしそうではなかった!! 「あーあー。どの魔王もみーんな口ばっかりでだらしがないったら」 ぞろぞろ帰り始めた全員の耳に、そんな言葉が届く。 それは、マイクを通して倉庫じゅうに響いていた。 「こうなったらいよいよこのあたしが出るしかないわね。 ライトスイッチオーーーン!」 軽快な少女の声とともにスポットライトが点灯する。スキップフロア上にいたのは、身長30センチのハーフフェアリー、ラブ・リトル(らぶ・りとる)だった。 「ハァーイ、みんなっ! あたしこそが全世界の女王、真の真の真のラスボス、みんなに愛されるラブちゃんよ〜〜〜〜〜〜」 まるでここがコンサート会場であるかのようにマイクを持って、空いた手で目の横にVサインを寝かせる、アイドルポーズをキメる。 「……まだいたのか」 ハァ、と重いため息が全員の口をついて出た。 「何よ何よー! みんなテンション低いわねーーー! もっと盛り上げていかなくちゃー! あたしはね、歌で世界を支配するの! その手始めにここであなたたちをやっつけて、あたしの子分にしてあげる! いでよ、わがしもべたち!!」 ぱちん、と指が鳴らされて、ぱたぱたと軽い足音が聞こえた。 ラブと同じライトの下に、テラー・ダイノサウラス(てらー・だいのさうらす)とエマーナ・クオウコル(えまーな・くおうこる)が現れる。 「ぎぁごろぅがげれぃぁ!」 「きゃおー!」 いつもどおり恐竜の着ぐるみで両手を振り上げ威嚇するテラーは分かりにくいが、実は自分のことを本物の恐竜ティラノサウルスと思っている。 エマーナはライオンだ。 いくら威嚇で牙をむいたところでどれもこれもちびっ子で迫力に欠けるているのは否めないが、当人たちにはまるでそのことに気付けている様子はない。 「しもべ?」 「ふふん。いいでしょ。毎日ケーキ5個あげるということで契約したのよ。もちろんあんたたちも逆らったりせずにおとなしくあたしの子分になるっていうなら、契約してあげてもいいわよ」 だがせっかくのその申し出を快諾する者はいなかった。 ――ケーキ毎日5個も食べてたら太るでしょ。 「あたしはアイドルだからいくら食べたって太ったりしないもーん。 さあ、テラー、エマーナ、やっておしまいなさい!!」 「ぅがぁ!」 「がおがおっ!」 ラブの命令を受けて、2人が襲いかかっていく。 その姿を見ながらラブもまた、マイクをかまえた。 「ふっふっふ。こうして最強(さいつよ)アイドルにして世界の真なる女王ラブ・リトルさまが本当の自分に目覚めた以上、もはやあんたたち下等なる地球とパラミタの人類どもは、あたしにひざまずいて毎日かかさず1人10種類のスイーツを貢ぎ続ける道しか残されてないのよ!」 そしておもむろに自らが(勝手に)名付けた歌『ミラクル・サッド・ドリーミング』を歌い始める。 四方に設置されたスピーカーを通して、悲しみの歌が倉庫じゅうに満ちた。 「くうっ…! こ、こんな…っ」 胸に迫る悲しみに意気消沈した彼らのなかで、テラーとエマーナが暴れる。 「ぐぎゃるぐるるるぅっ」 「がおがーーーっ」 それを見て。 「おのれ、悪の組織め! 正義のヒーロー、イングリットがぶったおすにゃ!!」 イングリット・ローゼンベルグ(いんぐりっと・ろーぜんべるぐ)は熱いハートを燃え立たせ、奮起した。 「グリちゃん!?」 驚く秋月 葵(あきづき・あおい)のとなりから、猛ダッシュで走り出す。 イングリットが向かった先にはエマーナがいた。 占い師の術で自分が実はライオンだったことを思い出し、噛みつき、引っ掻きでヒット・アンド・ウェイ攻撃をしているエマーナ。しかし彼女は未来人であって獣人ではないためその攻撃力はかなり低く、動きも早くないので簡単に避けることができる上、当たったとしてもせいぜいが猫並でしかない。 むしろ猫っぽい仕草がかわいくさえ見えてしまう、そんなエマーナの前に、イングリットが雄々しく立ちふさがった。 「そこのおまえ! よーく聞くんだにゃっ! これ以上ひとを傷つけるのは、この牙と爪にかけて許さないんだにゃっ! 猫の爪は悪事に使うものではないんだにゃ!」 「がうっ?」 「にゃーーーーーっ! まだやるというのにゃら、イングリットが相手になるにゃ! わいるど☆たいがーは決して悪を許さないんだにゃ!!」 「わいるど☆たいがーって、グリちゃん、それこの前貸してあげた漫画の主人公…。 え? グリちゃんも術にかかってたの??」 「行くんだにゃっ」 決めポーズをつけたイングリットによる、シャシャッと猫ひっかき攻撃! これをエマーナはひらりとかわし、距離を取ったあと、走り込んで死角からやはり爪をシャシャシャッとする。 「にゃっ☆」 「がおー!」 「にゃにゃにゃにゃにゃっ! にゃんっ」 「がおがおっ」 本人たちはいたって真面目なのだろうが、はたで見ているとどこかほほ笑ましい、猫ぱんちや猫ひっかきの応酬が始まる。 「やだ……なんかこう、ぎゅーって抱き締めたくなっちゃうんだけど…」 そんな声も漏れ聞こえてくるなか、葵1人はらはらしてしまう。 イングリットはここでの戦いに備えてパワードスーツを着用していた。今は同じネコ科同士のじゃれ合いを楽しんでいるようだが、ネコ科の気まぐれでいつ本気になるともしれない。 「本気で怒りの猫ぱんち出したりしたら、エマーナちゃん吹っ飛んじゃうよ…」 いや、それだけじゃすまないかもしれない。そうなったら目もあてられないことになるかも…。 そこで葵は一計を案じた。 ぷーんと漂ってきたおいしそうな香りに、イングリットはシャシャッとひっかこうとしていた手を止めた。 「にゃ!?」 ピタッと動きをとめて背を正し、鼻をヒクヒクさせて周囲のにおいを嗅ぐ。 「こ、これはまさしくイングリットの大好物! うな重のかおりなのにゃ!」 時刻はちょうどお夕飯時。ひととおり運動もこなしたあとなので、イングリットはすきっ腹だった。 においの出所を求めて振り返ったイングリットの視界に入ったのは、つっかえ棒とカゴで作られた罠の中央に置かれたうな重…。 コテッコテの罠なのはだれが見てもあきらかだ。多分、本物のネコでもこれが罠だということぐらい分かる。 「そ、そんな罠にはひっかからないにゃ……ああでもおいしそうなのにゃ…」 見えない糸で引っ張られるように、体がそちらへついふらふらと。 「ああ……駄目にゃ。体が言うことをきかないのにゃ…。せ、せめてひと口……ちょこっと食べて、パッと離れれば、きっと大丈夫なのにゃ…」 しかしひと口でも口にしてしまえば、それは至高の味。ハラペコが手放せるはずもなく。 イングリットは何もかも忘れて、うな重にかぶりついた。 「えいっ」 と、棒にくくりつけてあった紐が引かれて、イングリットはカゴの中に閉じ込められる。けれど、イングリットにはもううな重以外、何も見えていなかった。 「おいしい? グリちゃん」 「おいしいのにゃ! おいしいのにゃ! おいしい……のにゃ…」 ヒプノシスが効いて、イングリットは眠りにつく。カゴの網目から見える、カラッポのお重を抱えて幸せそうに眠るイングリットを、葵は笑顔で見守った。 そしてエマーナの方はというと。 イングリットがうな重に走ったのに合わせて、鼎が呼びかけていた。 「チッチッチ。ほらほら、こっちですよ。こちらへおいでなさい」 野良ネコを呼ぶように、しゃがみ込んで指を動かす。 それを見たエマーナは警戒を露わにしてうなったりもしていたが、ライオンになっても鼎のことは記憶に残っているのか、彼が気になって仕方がないようだった。どうするか逡巡するようにウロウロと周回したあと、ついに覚悟を決めたのか、まっすぐ走ってジャンプする。 「危ない!」 勢い、押し倒されて仰向けになった鼎を見て、あわてて和深が駆け寄ろうとしたが、鼎は手を振って平気だと伝えた。 「大丈夫です。襲われてるわけじゃありません。じゃれつかれてるだけです」 その言葉どおり、鼎を押し倒したエマーナは一心不乱にほおをこすりつけてマーキングすると、舐め始める。 「ちょっ…! あぁもう、いい子だから舐めるのはやめてください! くすぐったいじゃないですか」 「がおがおっ☆」 「はいはい。ライオンなんですね。 いいから少し離れて」 自分の上で箱座りしようとするエマーナを押しやって、鼎は立ち上がる。鶯の白衣についた汚れをぱんぱん払っていると、エマーナはおとなしく彼の足元にちょこんと座っていた。 足にすりすりと肩をこすりつけ、何かを期待する眼差しでまっすぐ見上げてくる。 (こんなに素直なエミーは初めてですね) ぼんやりそんなことを考えつつ、頭をなでてやると、もっとなでてと言わんばかりに自分の方から頭を押しつけてきた。 「にゃーっ」 抱き上げた彼女は想像していた以上に軽くて小さい。 「やれやれ。寒くなってきたことだし、服を新調してあげようと思ってたんですけどねえ…」 これは出直しかな、間違いなく。 赤子をあやすように背中をぽんぽん叩いていると、いつの間にかすうすうと小さな寝息が鼎の耳元でしていた。 はしゃいで騒いで、イングリットと遊び疲れたのだろう。 すっごく楽しかったと言わんばかりに笑顔でぐっすり眠り込んでいるエマーナを見下ろして、今日はこのまま抱いて帰ろうかと思う。 「本当に大丈夫か? すごい勢いで飛びつかれたみたいだけど」 「ええ。ちょっと頭をぶつけたぐらいです。もう痛みもありません」 気にして寄ってきた和深に、そう答えた。それでも和深はちょっと心配げだ。 「申し訳ありませんが、先に失礼させてもらいますよ。この子が起きてまた面倒をかけるかもしれませんから。 あ、謝罪はまた後日伺います」 「いや、それはいいよ。だれもけがしたわけじゃないから」 「そうですか?」 会釈をして、鼎はおもむろに入り口へ向かって歩き出した。 家への道すがら、ふとあることに思い至って言葉が口をつく。 「ああ、通販という手があったんだった」 と。 |
||