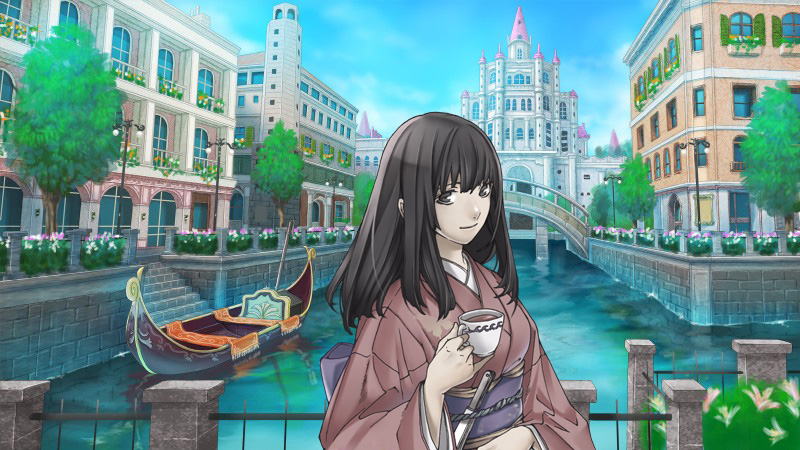リアクション
遥か昔、巫女王の治める人間の王国は長い平和と繁栄を享受していた。 ──我も情けない、な……願わくば来世こそは、姫、そなたと共に、平穏な世を歩み…たい…ものだ、な……── 「……そうだ、俺は、『我』は──“白夜の魔狼“と呼ばれた魔剣士・ツァン=ダーソック」 「やあっと思い出した?」 シャクタリアは嗤った。 「あの頃、帝国を裏切って人間なんぞと仲良くしていたアンタのことをたまたま知った。だからあたしがちょっと暗殺術の薬で暗示をかけたんだぜ? その秘宝を持って逃げ帰るように、ってさ。 ──馬鹿だよなぁ。ぼろぼろになってまで、一人で蒼角殿まで会いに行くなんて。 ついでにユーフォルビアに会いに来たあたしにまで逆らって、刃向うなんて。おかげで秘宝が結局手に入れられなかったよ!」 「シャクタリアああああっ!」 巽の、いや、ツァン=ダーソックの絶叫が響いた。 「だけどあたしが用があるのは、アンタじゃないんでね、後で相手してやるよ。そうさ──あたしを封印したのは戦巫女さん、アンタだよ」 シャクタリアはアルバを指差した。 「クハッ、アンタにゃ世話になったなぁ! あの時の続きと行こうぜ。 どっちが先に消し飛ぶかの短い付き合いだがよっ! オラァ、仏血滅(ぶっちめ)てやらぁ!!」 数奇な運命の交わりが、これから始まる復讐が、彼女には“愉快”だった。殺し屋にしておくには不適当な感情はユーフォルビアを放らせ、シャクタリアは薔薇の名の戦巫女へと突進した。 ヘリアンサスとアルバ・マキシマの脳裏に浮かび上がっては去るのは、苦い記憶。 ヘリアンサス──現世ではクリストファーという名の女子大の学生だ。百合園女学院の高等部に通っていた時分には、姫小百合団に所属していた。姫小百合団とは、ヴァイシャリーの白百合団に憧れた少女たちで構成されている、百合園女学院本校有志の自警団(実態は、サークルやファンクラブ)だ。 彼女は今までも、何度「前世」を思い出そうとしていた。高校生の頃、『深淵の暁闇』に立ち向かうことになったのも、記憶が戻らないもどかしさから故創出したペルソナ、だろう。 そう──これは「運命」だ。進学しながら、再び新百合ヶ丘を訪れた時に思い出すとは。 (それに、身長が前回から10cm以上も伸び「規格外」になったのも、魂が元の体躯に戻ろうと肉体の牢獄に抗っている結果なのさ、素晴らしい事じゃないか) アルバ・マキシマ──現世ではクリスティーと呼ばれる彼女も、『深淵の暁闇』事件までは、女性であることを受け入れられなかったが──前世の記憶を思い出すにつれ、違和感はなくなっていった。 ヘリアンサスは呟いた。 「そうだ……ユーフォルビアがツァン=ダーソックを信じた最初のきっかけは、俺の魔族の恋人と、知り合いだと、そう、俺が言ったから。だから」 ツァン=ダーソックがユーフォルビアを裏切ったと考えた彼は、後に恋人には問い質すことができた。だがその時というのは、戦火の蒼角殿で、敵としての再会だった。 ヘリアンサスは元婚約者──いや螺旋女王ドナと呼ばれる魔族の、気まぐれと姦計に引っかかったのだ。 過去の彼は、王国の戦士、身の丈8尺の偉丈夫。対応に輝く金髪が向日葵を連想させる、武骨な戦士だった。ドナにとっては扱い易い相手だったろう。 「俺はドナが魔王軍だなんて知らなかったんだ。それがユーフォルビアを逐電させる罠の一環だったなんて……。従者殿には悪い事をした。彼には殺されても文句は言えない。今生で女の体に閉じ込められたのもその罰、か」 だが、ホリダに殺されても、同じようにツァン=ダーソックを騙したシャクタリアに殺される訳にはいかなかった。 ヘリアンサスはアルバに並び、彼女を迎え撃った。 アルバもまた、手に魔力を集中させる。 「そうだ、ボクも生かされた。シャクタリアを封印し、ボロボロだったあの時。魔族に殺されそうになった時。螺旋女王に助けられたんだ。ただ巫女王の最期を見せつめられるためだけに」 残酷な魔族に、もう惑わされない。 「へぇ、やるじゃねぇか、じゃあ、こっちも手加減なしだぜ!!」 シャクタリアは一気に間合いを詰めるべく、跳んだ。同時に、首にかけていた数珠を引きちぎる。それは彼女の仏舎利で出来た数珠(ビーズ製の腕輪)の封印だった。 「<三神一体(トリムールティ)>」 そう、封印だった。喧嘩っ早く頭に血が上りやすい彼女が本気になって殴っては暗殺どころではないからと、付けられたものだ。それだけでなく、暗殺ではなくただの戦闘となって、反動でその身が塵となる可能性すらもあった。 ──が、それすらも忘れた。 封印を解くことで、彼女は創造神ブラフマー、繁栄神ビシュヌ、破壊神シヴァの三神をその身に宿せた。その状態のみ、暗黒属性の『黒い質(タマス)』、無属性の『激しい質(ラジャス)』、光輝属性の『純粋な質(サットヴァ)』を同時に使うことができる。 そして、 「全力解放、『大いなる黒(マハーカーラ)』っ!!」 にやりと笑い、彼女は手を掲げた。収束する黒、それは半径1km圏内を更地にすると言われる。 「<巫女王の加護>!」 アルバはヘリアンサスと共に、結界を張った。ただただ黒いその球状の何かはゆっくりと膨らむと、周囲の空気ごと結界を圧し潰そうとした。結界のうすぼんやりとした光が、所々で爆ぜる。 アルバはユーフォルビアを振り向いた。彼女の手を取ると、無理やり何かを握らせる。 「この結界が持つうちに、どうか逃げて欲しい。そしてこれを使って、現世に転生した巫女たちの記憶を取り戻して欲しい。巫女王の復活には巫女の力が必要なんだ。巫女たちの力を、キミが結界を解いた秘宝に集め、巫女王に捧げて欲しい」 「──では、こちらもいこうか」 ナイトが巽を見据えた。何かを守ろうとする者の覚悟は、だが、巽も同じだった。 「今度こそ姫は護る!」 巽の右腕が白く輝いた。今はここには実体として存在しない、だが懐かしい力──彼の前世での愛剣<白き闇(エクス・ノヴァ)>が宿っているのがはっきりと分かった。 (今度こそ共に彼女を護ろうと、力を貸してくれるのか……) 凡そ3メートル程の距離を挟み、二人はじりじりとタイミングを計る。 先に動いたのは、巽の方だった。右脚で地面を蹴って一気に距離を詰め、左脚を踏み込む。 その巽の視線と構え、呼吸と重心を、ナイトは読む。 重心を乗せた右拳の一撃を、円を描くように下がって回避。左脚に力を入れると、こちらも右足を一気に踏み込んで、下段から剣を振るった。 「っち!」 巽はわざと右脚を滑らせてアスファルトに転がって避け、立ち上がる。 だがその時、ナイトの剣には、死とでも呼ぶべきものが宿っていた。 「我に斬れぬ物無し、我に討てぬ物無し……我、刃を以て人を殺し、神を殺し、大地を殺し、空を殺し、太陽を殺し、月を殺し、星を殺し、理を殺し、混沌を殺す。我が振るう刃は万物普遍の死なり、それを以て森羅万象を殺さん」 <死刃>と呼ばれるその技は、詠唱し言霊によって生まれる概念的な『死』を刃に乗せて斬りつける事で、森羅万象を殺すというものだった。 「余力は残せない、という訳か」 構えなおした巽の右手が光る。 この光は、空間ごと相手の魂すらも残さず対消滅させる。対消滅時に発生する光は夜を昼にするほどで、完全覚醒ならば大陸一つを消滅可能、と言われていた。 「…… <夜ヲ蝕ラウ光ノ闇(アニヒレーション・ノヴァ)>!」 一瞬後、二人の影が交差した。 黒の剣と白い拳が交わり、発光し、周囲を白く黒く、黒く白く、染めていく──。 「わ、私、どうすれば……」 激化する戦闘と共に、託されたもの、庇われる自分という立場に、うろたえるユーフォルビア──もといアナスタシアだったが、その耳に、少女の声が届いた。 「ユーフォルビア。ボクだよ、ヨルだよ」 「ヨル……! ああ、いらして下さったのね!」 アナスタシアの顔が、ぱあっと輝いた。普段なら他人にそう簡単に見せない表情だが、それも当然だろう。 黒史病患者に追い回され囲まれて、散々頭が痛くなるような話を聞かされた中で、その名は救いの神に思えた。 ヨルという名前で一人称がボクの女の子といったら、百合園女学院生徒会副会長・鳥丘 ヨル(とりおか・よる)しかあり得ない。 ありえないはずだったのだが──、 「……あら? 貴方はどなたですの?」 電信柱の影から姿を現したのは、見覚えのない顔だった。ボーイッシュな小柄な少女という点ではヨル同様で(地球の)百合園の制服を着てもいたが、少なくともあの鳥丘ヨルでは、ない。 ヨルは怪訝そうなアナスタシアに向かって、もう一度、だからヨルだよ、と言ってから。 「……いいよ、忘れてても。ううん、元から覚えられてなかったかも、ね。ちょっと寂しいけどね」 (でもユーフォルビアの危機と同時に目覚めるなんて、やっぱり縁があるんだな) 彼女は、それを思って嬉しくなった。 前世での姿は、スラムの盗賊ヨル。しばしば権力者はアウトローを必要とするように、彼女もまた蒼角殿に雇われていた。 遺跡の調査といったものから、敵国やライバルの情報を探り、集め、必要とあらば工作を行うという危険な任務も行う。尤も、当時は男性だったけれど。 「ユーフォルビア、キミは魔王軍になんか渡さない。前世では身分が違いすぎて言えなかったけど、愛していたよ。今度は同性として仲良くしようね」 「……え、ええっ!?」 衝撃的な告白にアナスタシアが声をあげるが、ヨルは今はそんな場合じゃなかったね、とさらりと言った。 「たとえ記憶が戻らなくても、見捨てたりなんかしない。安全に、巫女王と仲間の魔術師のところへ連れて行くからね」 そして、閃光の中ゆらりと現れた真の、鬼気迫る姿にあっかんべーをする。 「残念、ボクに戦う気はないよ! <雲散霧消【砂塵】>っ♪」 瞬間、真が顔を庇ったように見えた。 地面から吹き上がった──舞い上がった砂埃が、真やその場にいた追っ手の視界を埋め尽くす。視覚だけでなく聴覚・嗅覚あるいはさえ奪われ、彼は1、2分の間は、動くことができないだろう。 さ、今のうちだよと、ヨルはアナスタシアの手を引いて駆けだしそうになってから、今黒ずくめの少女に気づいて、戸惑ったように問った。 「で、こっちの子は誰なの? 大事な人?」 「あ……」 アナスタシアはもう片方の手をつないでいる少女を見た。相変わらず自我に乏しい表情だ。 「い、いいえ。違いますわ。……この方は関係ありません」 「じゃあ行こう、急いで!」 「は、はい」 頷いて、このチャンスを無駄にしないように、とアナスタシアは黒ずくめの少女の目を見た。 「貴方は、この街からお逃げなさい」 「にげる……?」 「いいこと、黒史病とやらの原因が貴方にあるにしても、この劇の出演者には無関係ですわ。であれば、巻き込むわけにはいきませんわ。 今の貴方には、たとえただの地球人にだって、抵抗する力があるとは思えませんし──」 黒ずくめの少女は、目をしばたたかせた。多分理解できていないのだろう。でも、少しでも伝わる可能性があるなら、アナスタシアは言うべきだと思った。 「それに、百合園の図書室にいらしたのでしょう? でしたら貴方は今後百合園の生徒になる可能性もありますわよね? 生徒会長としては、生徒を守る責務がありますのよ」 アナスタシアは十字路で、彼女の背を、進行方向と逆に押し出した。 「また百合園でお会いしましょう」 それだけ言って、アナスタシアはユーフォルビアとして、ヨルと共に走り出す。 少女は茫然として、立ちすくんでいる──。 |
||