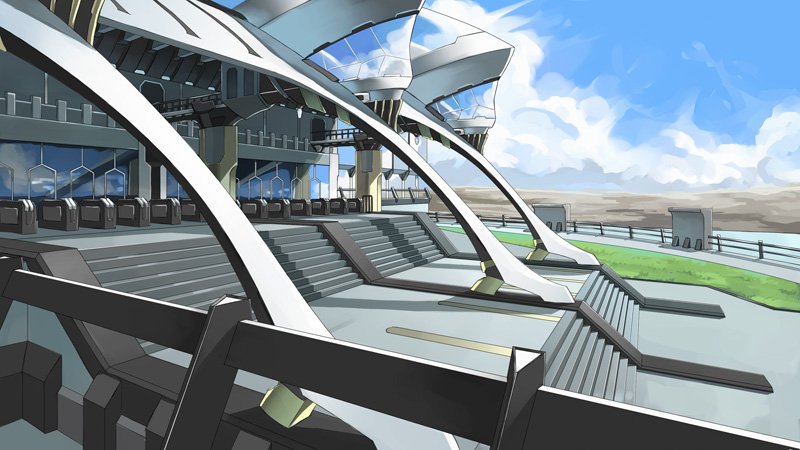|
 |
リアクション
「ぐぎぁらぎぁらぎぁ!」
恐竜が暴れていた。
着ぐるみで、身長は133センチしかなくて、手足も短くて、爪なんか綿を詰め込んだ布だったけど。
本人はいたって真面目だ。なにしろ自分をティラノサウルスと思い込んでいるのだから。
はるか恐竜が闊歩していた時代の地球では、ほんのひと握りの最強の生物の1つだったティラノサウルス。恐竜の王様。
同じ肉食恐竜が相手でも、1対1ならまず負けない。
おそらくテラーの脳内では、みんなに恐れられ、一目置かれるティラノサウルスと化した自分の姿が展開しているに違いなかった。
実際、彼の周囲の者たちは蒼白した顔で硬直しており、彼のシッポ攻撃も満足に避けられないでいる。
――現実はといえば、みんなラブの歌う悲しみの歌のせいで動きが鈍くなっていて、着ぐるみシッポがポスポス当たるくらいなんてことなし、わざわざ避ける気にならないだけなんですけどね。
「がるるぐぁぐるるぅ!」
みんな、自分を怖がってる!
よーし! おいしいケーキのためだ。ガンバってみんなをやっつけちゃうぞー!
ますます調子に乗って、テラーは手足をバタつかせ、体をねじってシッポを振り回す。
「……えーと…」
途中会った鼎から得た情報でこの倉庫へとたどり着いた直後、目に飛び込んできたその光景に高峰 結和(たかみね・ゆうわ)はとまどった。
もう事件は大体把握しているので、あの着ぐるみっ子が自分を恐竜と思い込んで暴れているのは分かる。
殴ってショックを与えれば、正気に返って暴れるのをやめてくれるだろうということも。
しかしどう見ても小さな子どものテラーを殴れるはずがなかった。
結和のやさしい心、大人としての良識が邪魔をする。
そこで次善の策として、結和は空飛ぶ魔法↑↑を使うことにした。浮かせて足場をなくせば踏ん張りも利かないし、これ以上暴れるのをやめさせることができるだろうという考えだった。
「ぐぎゃっ!? がぅがぉ! ぐれぅぎりぉろぅ! ぐぎぅりぇらがっ!」
突然宙に浮いた自分に驚くテラー。振り返って、すぐにそれが結和の仕業だということに気付いて手足をばたつかせ、文句を並べ始めるが、何を言っているか結和にはひと言も理解できない。
「あの……えっと。あんまり暴れないでね? 落ちちゃうから。今、安全な場所へ連れて行ってあげる」
術の解除についてはあとから考えるとして、ひとまずこのままここから運び出そう、そう思った矢先の出来事だった。
入り口までの距離を目算するためちょっと目を離した隙に近寄ったアヴドーチカ・ハイドランジア(あう゛どーちか・はいどらんじあ)が、頭の上にかかげた万能治療器具(自称)のバールを打ち下ろす。
それはもう、ナタで丸太を割るように。
「ぎゃうっ!」
「あ、アヴドーチカさんっ! あなた子どもにも一切容赦なしですかっ!?」
地面にたたきつけられ伸びているテラーをひざに抱き起こして、結和は叫ぶ。
「着ぐるみがクッションになって衝撃を殺すからな。少々強めにせねば治療にならん」
平然と答えたアヴドーチカは、今度はスキップフロアでスポットライトを浴びながら歌っているラブへと歩み寄る。
ラブは歌うことに夢中で、背後からの彼女の接近にまるで気付いていなかった。
「はうっ!?」
フルスイングしたアヴドーチカの一撃は無防備な小さな体を野球のボールのように吹っ飛ばす。
ラブはそのまま入り口を抜けて、あっという間に消えて見えなくなった。
「しまった。あれでは施術が成功したかどうか分からないか。……まあ、私が失敗するはずもないが」
治療を終えたバールを両肩に渡らせて、アヴドーチカは独り言をつぶやく。
「すみません、本当にすみません…。あの人、占い師の術にかかって正気を失ってるとかそういうわけじゃなくて、あれでいつもどおりなんです…」
穴があったら入りたい……というか、ここの床がコンクリートじゃなかったら今すぐ穴掘って入るのに。
唖然となっているみんなの前、結和は両手に顔を伏せた。
* * *
開きっぱなしの入り口から見える外は、もうすっかり夜だった。
「まったく、とんでもない1日だったな」
「なんだかどっと疲れたよ」
ラブの長時間ライブ、悲しみの歌の影響がまだ抜けきっていないのか、みんなすぐに動き出せないでいる。
なかにはその場にうずくまっている者もいた。
「でもまあ、これで全部終わった――」
「おい。ここにいるのが例の占い師とやらか?」
話をさえぎって、アヴドーチカが壁にもたれて倒れているフードマントの者を指し示す。
「あ。そういえばすっかり忘れてたわ〜」
「せっかくの休日をつぶされたわけだし。こうなったらひと目顔を拝ませてもらいましょ」
「だな!」
「甘い! 顔を見るだけですますもんですか! ……うう」
それぞれがそれぞれの思いで周りを取り囲んだ。
全員がそろったところでアヴドーチカはフードをとっぱらう。
そこにあったのは、
紫月 唯斗(しづき・ゆいと)の顔だった。
「唯斗!?」
「……ぅう……」
周囲に集まった人の気配を察知してか、むずむずと顔をゆがませて唯斗が目を覚ます。
「……あ、いたた…。なんでこんなとこにコブが…。
あ? あれ? みんな…」
最初、唯斗はわけが分からなかった。
どうして取り囲まれているんだろう? それになんでこんなに頭が痛いんだか…。
「なるほど。物事の元凶はおまえさんだったというわけだな?」
とアヴドーチカがうなずく横で
「おまえのせいで俺はあんな思いをしたのか…」
真司がポキポキと指の骨を鳴らす。
「えっ? ――え?」
自分を見下ろしている仲間たちが、必ずしも彼を心配したから囲んでいるわけではないことに遅ればせ気付いた。
冷たい視線にさらされているうち、徐々に記憶が戻り始める。
囚われのお姫さま役のアイシスをロープで縛って、それで………………だれかに後ろから殴られて…。
「ち、ちが…っ、自分は、協力を頼まれ……し、白さん!?」
大あわてで白の姿を捜したが、白はとうにこの場から姿を消していた。
唯斗を弁護する者は、だれもいない。
「違う……違うんです、じ、自分は……自分は……ああああああああああああっ!!」
倉庫の窓からピカピカと、青白い光や赤い光が夜空に向かって走り、何やら爆発音とか雷音とかが周囲に響き渡る。
それと合わせて絶叫も、長く、長く、続いたのだが、ここはかなりの街はずれで、モンスターが暴れても全然大丈夫な場所だったため、様子を見に来る者はだれもいなかった。
そして本物の占い師はといえば。
「〜〜〜 ♪ 」
とっくの昔に倉庫は抜け出していて、足取りも軽く隣街を目指して夜道を歩っていたのでした。