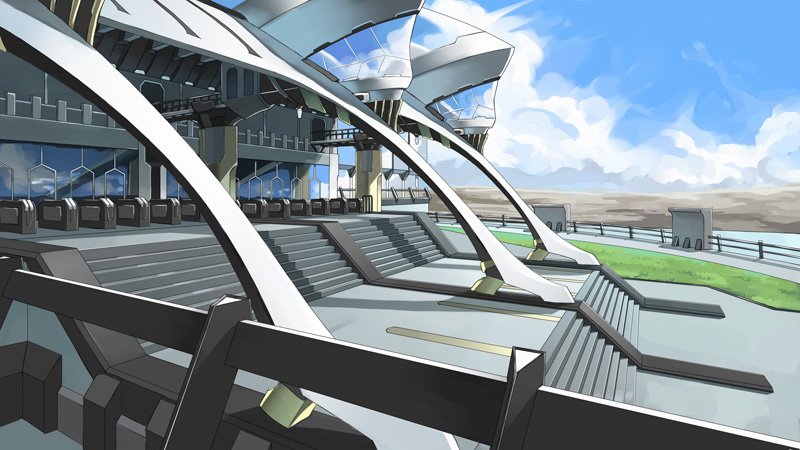リアクション
第2章 恋の話と戸惑う狼 1
外からは、ナイトパーティが順調に盛り上がりを見せているのか、活気付く若者たちの声が聞こえてきた。それを静かに耳にした九条風天は、同じくクオルヴェル夫妻とともに扉の向こうに一度視線を送った。やがて、どこか感慨深げに風天が口を開いた。
「それにしても……珍しいですね」
返事を返さないものの、若長のアールド・クオルヴェルの目は風天へと注がれた。背後で何かに羽筆を走らせていたアリア・セレスティも、背後からそれを見守る。
「普通父親というものは、娘が恋愛に興味が無いというのは逆に喜びそうなものだと思うのですけれど」
「地球の父親というものがそうであるかは分からぬが、少なくとも我々クオルヴェルの集落にとって子孫繁栄は重大な問題だ。喜んでなどおれんよ」
ステージのオープニングセレモニーのときとは打って変わって、謹言たる一族の長がそこにはいた。
「しかし……恋愛事というのは上手く行っている時の幸福感は心地良いものかもしれませんが、失恋した時の痛手はそれ以上です。それも含めて教えたいと言うのは分かりますが、本人が恋を望んでもいないのなら……それはただの親の願望の押し付けでしかないのでは?」
穏やかに述べるものの、風天の鳶色の瞳は突き刺すように鋭かった。はっきりと己の考えを主張する若き獅子に、アールドも半端な態度では挑めまい。
「リーズさんの事を考えられるなら、そんな軽率に動かれず、もう少し慎重になるべきであると思うのですが…………もしタチの悪い男にでもひっかかったら大変ですよ?」
風天の最後の言葉に、それまで冷厳に座っていた男の眉が動いた。さすがに、娘を愛する父親としては、軟弱な男に奪われるのはいかんともしがたいところだろう。そもそも、そういった理由もあって、アールドはあまりナイトパーティに賛同的ではなかった。
言葉を詰まらせた彼に代わって、風天に甘やかな女性の声がかかった。
「風天さんは……リーズを心配してくれているのですね」
そう言ってくすくすと笑うのは、アールドの妻であるリベル・クオルヴェルであった。つかみ所のない彼女の微笑に、風天は眉をひそめた。確かに心配しているのはもちろんなのだが、それを真っ向から言われては多少恥ずかしさが増すというものだ。
「こんな良いお友達を持って、あの娘は幸せだわ。あ、そうそう、風天さんがぜひうちの娘を
見守ってくれていたら、タチの悪い男にひっかかる心配もなくなりそうね。どうかしら?」
風天は呆気にとられた。
まさか、こんな切り返しをされるとは思っていなかった。そんな風に言われては、「いやです」と断るわけにもいくまい。なにせ――進言したのは自分なのだから。
心配は取り越し苦労か? それとも、何か他の目的でも?
いずれにせよ……と風天は決然と夫妻に目を向けた。
「もちろん、何かあれば、リーズさんを守るつもりではいますよ。しかし、子供はスグに大きくなって親元を離れていくのですから、今の一緒に過ごせる時間を楽しんでおくのが良いと思います」
整然と言い放って、風天は立ち上がった。
「さて、折角ですし、ボクも少し見て回ってきます。それではお邪魔しました」
言いたいことを言い残した風天は、身を翻して若長の部屋を出て行った。その背中を見送って、ようやくアールドは息をついた。
「ふむ……リーズの友人にあれほどの剣士がいたとはな……」
「風天さんは、『義剣連盟』という有志団体の隊長をされているんですよ。とても正義感の強い方で、義を重んじる素晴らしい方です」
興味深げに呟くアールドに、アリアがそっとお茶を差し出して補足した。
「なるほどな。あの堅物さはその正義感ゆえのものか……」
「あら、あなたととても良い勝負でしたわよ? 見ているこっちも、似てるなぁって思って少し面白かったわ。ねぇ?」
「そうですね」
コロコロと微笑むリベルがアリアに声をなげかけると、彼女も賛同してくすっと笑みをこぼした。
「うぅむ……」
所在なさげに、アールドは低く唸るばかりだった。
●
御凪 真人(みなぎ・まこと)は、ナイトパーティの詳細について書かれたチラシを見下ろした。そのプログラム欄に載っているのは、8割方恋愛系に偏ったイベントの数々である。続いて、彼は集落長に挨拶をしに行ったときのことを思い出した。思えば、あのときの長の妻――リベル・クオルヴェルはわざとらしく自分と
セルファ・オルドリン(せるふぁ・おるどりん)の関係を気にしていたような気がする。そして、今、パーティ会場を見回せばカップルの姿はいくつも容易に見つけることが出来る。
(やれやれ……)
真人は同情するようなため息をついた。
(ご両親の気持ちも分かりますし、彼女の立場上こう言う事を仕向けると言うのも分かるのですが、上手く行くものなのでしょうかね)
つまり彼は、このパーティの真意に気づいたのだろう。その上で、どちらの気持ちも理解できることから同情にも似た思いを抱かざる得ないのだ。とは言うものの、どちらに転ぶかは自分たちが気にしてどうこうなるものでもなかった。
となれば、素直にパーティを楽しむに限る。
「おっと、あんまり遅くなると怒られますね」
真人はチラシを懐にしまうと、目的の場所へ向けて歩き出した。やがて辿り着くのは、一つの立食会の場である。その一角にいる少女のもとに彼は足を向けた。
「も〜、真人遅い〜」
「すみません、ちょっと考え事をしてたので……」
彼を待っていたのは、パートナーのセルファ・オルドリン。そしてもう一人。
「わざわざありがとう。せっかくのパーティなのに買いに行かせたりなんかして、ごめんね?」
赤髪の中で狼の獣耳を生やした娘――リーズ・クオルヴェルが申し訳なさそうに言った。
「全然大丈夫ですよ。こういうのはセルファのでも慣れてますから」
「な、なによそれ……!? べ、べつにいっつもこんなことばかりさせてるわけないじゃない」
「冗談ですよ、冗談」
「も、もう……まぎらわしいのよ、いちいち」
楽しげに微笑む真人に、セルファはわざとらしくふてくされてみせた。そんな二人の様子を見ていると、リーズもどこか可笑しくてくすっと声を漏らしてしまう。
そんな三人のもとに、ひょこひょこと……小さな影が近づいてきたのはそんなときだった。
「うわっ……人形が動いてるっ!」
可愛らしい西洋ドレスに包み込まれた人形は、どうやらスタッフの一員のようだった。とことこと歩いてくると、人形のオレンジジュースの入った瓶をリーズの目の前に置いた。
「あれ、なんか挟まってる……?」
瓶のラベルに挟まってあったカードを手にとって裏返すと、そこに書かれていたのは『私もリーズっていうのよろしくね』というメッセージだった。
人形がウエイトレスをしてるわ、メッセージはあるわで、きょとんとして驚く三人。すると、そんな三人に少女の声がかかった。
「あ、あはは……すみません、脅かせてしまいましたか?」
「あなた……?」
見知らぬ少女は、テーブルの上でとことこと歩く人形を抱え、人懐っこそうな笑みで自己紹介をした。
「初めまして、私は
茅野瀬 衿栖(ちのせ・えりす)……しがない人形師です」