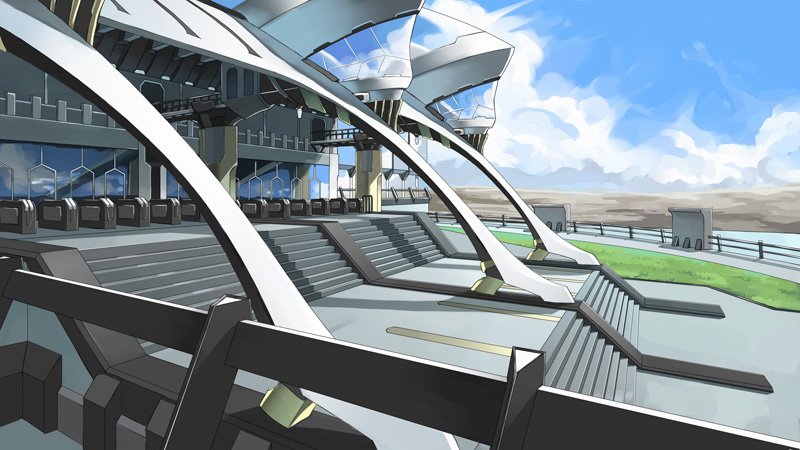リアクション
第4章 貴方の守りたかった場所
リーズは今日、色々な人に、たくさんのことを教えてもらった気がしていた。誰しもが悩み、誰しもが苦しみ、誰しもが切なく誰かを思って、誰しもがそれを乗り越えている。
恋に興味のある人、ない人……千差万別はあれど、彼らは少しずつ私に大切なことを教えてくれた。
しかし――リーズは一歩踏み出せないでいた。答えはもう目の前にある。踏み出しさえすれば、それはきっと彼女の中で芽を生やす。だが、それがどうしても出来なかった。不安? 恐怖? 戸惑い? いや、これは……彼女自身が、受け入れることを躊躇っているせいなのかもしれない。
リーズの足は、自然ととある場所に向かっていた。それは、集落の後方にある、村そのものを一望できるわずかに小高い丘だった。丘は同じく森林に囲まれているものの、そこには人が数名座れるほどの開けた場所がある。
そう時間もかからぬうちに辿りつくと、リーズは驚きに目を見開いた。
先客がいたからだ。
「陽太?」
「あ、リーズさん」
影野 陽太(かげの・ようた)がリーズに気づき、振り返った。彼は草原の上に座って、集落を眺めていたようだった。鳶色の穏やかな目が、彼女に向けられ、そして、それから更にその後ろへと視線を移した。
「あれ、リーズさんもいらしてたんですか?」
「音井……!」
振り返ったリーズは、紅茶を両手に持っている、太陽のような金髪を靡かせる音井 博季(おとい・ひろき)を見た。博季は、柔和に微笑んだ。
そこに、がさがさと音を立てて、更に二つの影が現れた。
「ん……まさかとは思ったが、お前たちか」
「あなたは……」
リーズは、登場したその人影にはっとなった。
――レン・オズワルド(れん・おずわるど)。サングラスの奥から僅かに漏れる紅柘榴の光が、じっとリーズを見据えた。彼は、リーズにとって印象的とも言える人物だった。あの、黄金色の獣を目の前にして、唯一それを守ろうとした人。
彼の隣には、リーズの見知らぬ少女がいた。
「あ、あなたがリーズさんですかっ」
「そ、そうだけど……」
「初めまして、冒険屋ギルドのマスター、ノア・セイブレム(のあ・せいぶれむ)と申します」
子供らしい仕草でぺこりと頭を下げたノアに応えるよう、リーズも頭を下げた。
「皆さん、ここで何をなさってたんですか?」
ノアの言葉に、リーズたちは目を見合わせた。
自然と丘に集まった彼らは、誰ともなく、それぞれについて話し始めた。
リーズは、丘の上の静かで穏やかな不思議な雰囲気もあったせいだろう……今回のナイトパーティでの一連の事を皆に話した。
誰も、彼女の声を遮ろうとは思わなかった。それは失礼に値するという礼儀でもあったことはもちろんだが、何より、彼女の一言一言をじっくりと噛み締めようと思っていたからだ。
リーズが何かを考え込んで踏み出せないでいるのは、自然と誰もが理解できた。だが、彼女が何をそこまで心の奥に抱えているのか、彼女自身にしか分からぬことでもあった。いや、それどころか、彼女はそれを言葉にするのさえ躊躇っているようでもある。
だから、彼らは彼女の手助けになることを願って話すしかなかった。無論――そこには、リーズが自分の気持ちを話したように、自分たちの心を誰かに聞いてもらいたいという気持ちもあった。
リーズに紅茶を差し出した博季は、そっと話し出した。
「僕は……人の気持ちは、儚くて物凄く壊れ易くて、たまに辛いけど、でも凄く暖かいものだと、思ってるんです。それは、恋だって同じで、本当に良いものだと……」
彼は、誰かを想っているのだろうか。遠くを見る眼差しで、話を続けた。
「……だからこそ、慌てるものでもないし、リーズさんは、リーズさんのペースでいいと思います。たとえ、今それが恋だと気づかなくても、恋じゃなくても、リーズさんなりに、生きていければ……。だってほら、貴女の周りにはこんなに素敵な人がいるんだもの。一歩ずつ、いろんな人を好きになって、恋愛に発展していけばいいんじゃないかな、って思いますよ」
リーズに語るようにしつつも、彼は自分自身に言い聞かせるような口調でもあった。きっと、リーズの知らない何かが、彼の心にあるのだろう。
博季に続くようにして、そっと口を開いたのは陽太だった。
「俺には、世界で一番愛している女性がいます。臆病者で無能者な俺ですが、その人に認められたい、支えたい、守りたい……隣に立てるようになりたいと思って無我夢中で走るうちに、少しはマシになれた気がします。月並みですが、誰かを愛することで人は強くなれるのかもしれません……彼女が俺のことをどう想ってくれているかは、残念ながら全然わかりませんけど」
自嘲する笑みを浮かべていた陽太だったが、その瞳が切なげ、哀しみを帯びてきたのは、次の台詞を口にしたからだった。
「その人が……殺害されました」
ポツリとこぼした言葉にリーズたちはどうしていいか分から、彼を対して哀れむような目を向けるだけしかできなかった。
「俺は彼女を守ることも、死の場面に立ち会うこともできませんでした。正直、自分が死んだほうがましだと思えるくらい、絶望まみれの日々を今送っています」
これまで、リーズはたくさんの人の話を聞いてきた。その中には、過去に恋人をなくしたであろう人の話を聞く機会もあった。だが、これほどまでに、悲しみに満ちた声で語りかける者はいなかった。……陽太にとって、それはあまりにも近すぎる過去だっだ。
「ですが、少しだけ希望があるんです。ナラカへ行く列車に乗って、彼女を地上に連れ戻せるかもしれないんです」
陽太は微笑んだ。悲しみを見せないように、必死にそれ隠して決意を秘める彼は、皆の目にとても眩しく映った。
「何かの縁ですし……もしも、その人を復活させることができたら、彼女を紹介させてもらって良いでしょうか? 遠目にあの人です、って指摘するだけになるかもしれませんが」
仮にその人を復活させることが出来たとしても、彼は彼女と愛し合えるとは限らない。それでも、その人を愛しているからこそ、彼は強く生きようとしている。
リーズは、陽太の提案に頷いた。いつか、その人と陽太が隣り合って自分と会えるときを、切に願う。
「リーズ……ちょっといいか?」
それまで、博季や陽太の話をわずかに離れて聞いていたレンが、リーズに声をかけた。彼は、ノアとともに丘からの出口でリーズを待ち、彼女を視線で招いた。
「…………」
どこか深い面持ちの彼らの様子に、リーズは不思議と胸のうずく予感がした。
●
道すがら、レンはリーズに。あの魔獣との戦いから数ヶ月の間に起こった様々な出来事を話した。冒険屋の仕事として舞い込んだ巨大豆の木の暴走事件や、とある少女の依頼で両親の思い出の花を取りに行ったことなど、レンはリーズの知らない場所でたくさんの冒険を巡っていたようだった。
やがて、三人はひっそりとした夜空の瞬きもわずかに届かぬ場所に出た。
「これが……」
その場所にそっと置かれるようにして建てられている石碑を見つめて、レンが呟いた。
ゼノ・クオルヴェル――リーズの祖父であり、クオルヴェルの集落にとって最大の危機を救った、英雄と称えられる男の墓が、そこにはあった。
定期的にリーズか誰かが花を替えているのだろう。鮮やかな花の数々が置かれた石碑の前に、そっとレンは一輪の白い花を捧げる。
「それが……」
「クラウズ……少女の両親にとって、思い出の花だったものだ」
道すがらの話に聞いていた花は、まるで澄み渡った雲のように美しい白だった。少女と獣人の間の、絆を結ぶ可憐な花。レンはそっと目を閉じて、黄金色の瞳をした獣人と、彼の封じてこの世を去ったゼノに、思いを馳せた。
かつて、お互いは共に強き英雄を目指す親友であった。好敵手として切磋琢磨しながらも、時に笑い合い、ときに悲しみ合った、かけがえのない親友。
だが、いつからだろうか。彼らは分かれ道を歩んでしまう。英雄たる力、何者にも優る力を求めた獣人は、闇にとり込まれ、そして魔獣として変貌した。親友には、それを止める術はなかった。強く、気高い戦士として成長したゼノは、親友を前にして対峙した。
どれだけの痛みだっただろう。どれだけの、悲しみだっただろう。彼は魔獣を封じることしか出来ず、救うことは叶わなかった。
(……信じていたはずだ)
レンは思った。きっと、ゼノは彼が戻ってくることを信じていたはずだと。だからこそ、彼は魔獣をこの世から滅しようとは思わなかった。今ではなくとも、いつか、彼を救えるときが来る。そのとき、彼を支えてくれる人が、仲間と呼べる者が、必ず現れるであろうと。
シアード――魔獣という罪深き英雄となった男はいま、自分自身と戦っている。
(貴方はもう、この世にいない。だからこれは……俺の一方的な約束に過ぎない。でも、聞いてくれ)
レンは心の中で、決意を秘めた声で墓石に言った。
(……シアードのことは、任せろ)
そっと、レンは瞼を持ち上げた。そして、リーズに向かって振り返る。
リーズは、レンの顔が決然としているように感じた。そして、それは……間違いではなかった。
「リーズ、俺は、お前に伝えたいことがあって、今日、此処に来た」
「伝えたい……こと」
「シアード……いや、ガオルヴは、生きている」
レンの言葉を聞いたリーズの瞳は、これ以上ないほどにはっと見開かれた。
生きている……彼が、生きている。レンの声が、リーズの中で巡る。
「ガオルヴはいま、自分自身と向き合う為の旅を続けている。そして、この花……クラウズの花の少女を助けた獣人というのも、彼だ」
リーズはレンの声がはっきりと聞こえながらも、どこか遠くから声をかけられているような気分だった。これまで、彼女の中ではっきりと息づいていたものが、愕然として崩れる。驚きなのか、喜びなのか、感情が入り混じって、自分でもよく分からなくなる。
だが、なぜだろう。
リーズは、不思議と心が躍っているような気分でもあった。探していたものを見つけたような、森の中で一筋の光を見つけたような、そんな、自然と震えてしまう気持ちが、彼女の口からゆっくりと声をこぼした。
「生きてる……ガオルヴが……彼が……」
ずっと、心の影はあの黄金色の瞳を捜していたのかもしれない。
あの哀しい目を思い出すたびに、リーズの心は締め付けられいた。救えなかったという後悔の念が彼女の中に巣くっていた。
「変わり続ける彼に、会いに行かないか……?」
レンの提案に、リーズは打ち震えそうになった。生きているのなら、もし、また一度会えるのなら、私は……。
「答えを、見せに行きましょう」
ノアが、リーズに向かって微笑んだ。
きっと彼女にとって、ガオルヴの存在は大きすぎたのだろう。それを一人で抱え込んで、納得しようとした結果、心の中にどうしようもない、答えの見つからない思いを抱えてしまった。
「答えを……」
リーズは、ゼノの墓を見つめながら呟いた。