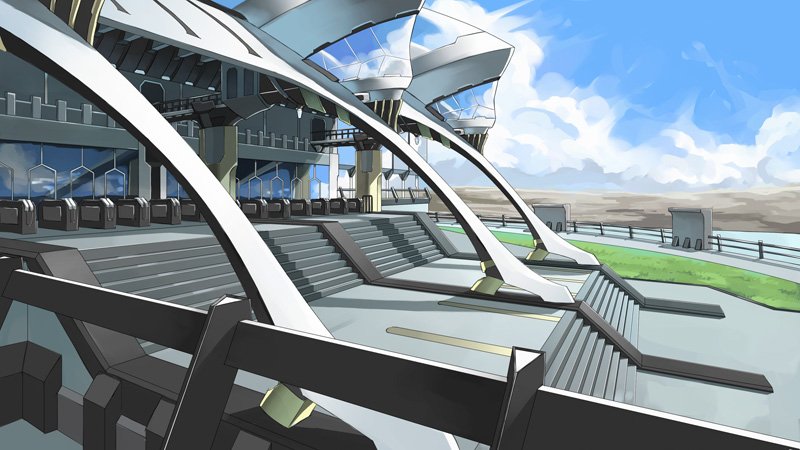First Previous |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Next Last
リアクション
第2章 そんなこんなでも肝試し 3
「んで……どういうことなんだ?」
茂みの奥でビール缶を片手に林田 樹(はやしだ・いつき)が聞くと、緒方 章(おがた・あきら)は脳天気な笑みを浮かべつつ振り向いた。
「『肝試しって、男らしさを見せる良い機会なんじゃない?』……ってアホ魔鎧にけしかけたんだ。そうしたら、速攻で申し込んでいたってワケさ、樹ちゃん」
「はぁ、それは何ともまぁ、殊勝なことだな」
樹は興味なさげにつぶやき、ビール缶をぐいっと口にあおった。
だが、すでにビールはほんのわずかしか残っていなかったらしく、彼女は中身のなくなってしまった缶をしかめ面で見つめた。
そんな彼女に、章がきょとんとした表情で聞く。
「殊勝? ……それって、あのアホ魔鎧が恐がりだってコト?」
樹はうなずいた。
「ああ、そうだ。あの魔鎧は、正真正銘のヘタレだ。前にどこぞの幽霊騒ぎがあったときは、防弾ベスト姿のまま固まってしまったくらいだからなぁ。……ジーナの恐がりに、巻き込まれないと良いが……」
「えーっと、ちょっと待って。あのバカラクリの恐がりって、え?」
「ああ、ジーナは極度の幽霊恐怖症だ。前に教導団の女子お泊まり会で、ホラー映画を見ていたときは、恐怖のあまり、枕を木っ端微塵にしてしまったなぁ、ははは」
樹は大したこともなさそうに軽く笑い飛ばす。楽天的な彼女と違って、二人をたきつけてしまった章は、しまったといった表情をしていた。
だが、彼も考え方を切りかえることのできる男だ。
「えっと…………僕、しーらないっと」
あまり深くは考えこまないようにして、とりあえず成り行きを見守ることにした。
と、そんな彼らの前に、その問題の二人組がやってくる。
先に立ってスタスタと歩くのはジーナ・フロイライン(じいな・ふろいらいん)だ。その一歩後ろで、、新谷 衛(しんたに・まもる)が気まずそうな表情を浮かべている。
「……じなぽん、そろそろ返事聞かせてくんねぇ?」
無言に耐えかねて、衛が聞いた。
「返事?……返事って、何でございやがるでますですか」
しかし、ジーナはふてくされたような顔ですっとぼけるばかりだった。
「んなっ! ……このオレ様の告白だっ! すっとぼけやがるとは良い根性してやがるぜっ!」
「告白?! アレのどこが告白だってゆーんですかこのバカッパがぁ! ただ単にワタシの口っ……えっと、キス……えっとぉ……」
振り返ったジーナは声を張りあげたが、次第に尻すぼみになっていった。頬は紅潮して、恥ずかしそうにもじもじと指をからめている。
たたみかけるように衛が言った。
「ああ、キスしたぞ。激しくヤったぞ、そうして告ったことを忘れたのかよ」
その時のことを思い出したのか、ジーナの顔が真っ赤になった。
「……とっ、とにかくあんなのノーカンです! あんなキスして告白だなんて、ば、馬鹿げてますアホですもっかい死にさらせなのです!!」
「だーっ!! こーなりゃヤケだ、もっかいその体に聞いてやるから覚悟しろっ!」
「えーえー言っときますけど、あん時は不意打ちでしたが今度は心の準備があるから大丈夫なんですよーっと!」
「くぉんの、調子に乗りやがって……。今度はそれ以上のコトしてやんよ」
「それ以上ってなんなんですか? チキンのクセに! スタートの時に膝ガクガクしてたクセに!」
二人の言い争いは徐々にエスカレートしていく。
「……えっとー、この流れだと止めに入った方が……」
茂みのなかにいる章が樹に提案した。だが、彼女はにやりとして返した。
「いや、よく見ていろ。……いい『酒の肴』が出来るぞ」
「うわー、樹ちゃん、えげつないなぁ」
新しいビール缶をあおりながら言う樹に、章は苦笑した。
その間に、ビビリであることを見透かされた衛は、顔を真っ赤にして誤魔化すようにまくし立てていた。
「テメーだってブルってトイレ行きたがって――」
そのとき。
とんとんと、誰かが衛の肩をたたく。
「うっせーな、いま取り込み中なんだよ!」
衛は振り返って確認することもせず、邪魔者に牙をむいた。しかし、恫喝に負けることなく、再び邪魔者は彼女の肩をたたく。
「だから、取り込み中だから静かにし――」
さすがに業を煮やして、衛は振り返った。その顔がピタッと止まる。
目の前にいる邪魔者の正体を見て、彼女は信じられないものでも見ているかのように目をパチクリさせた。
そこにいたのは白布を被った、いかにも幽霊らしき人物だった。
「やあ、お化けだよー」
「でっ、でっ……でたあああぁぁぁ!!」
「きゃあああああああああああああ!!」
本当に幽霊であれば、そんなに陽気に自己紹介をすることはない。しかし、気が動転した二人はそのことに気づく暇もなく、とにかく目の前の脅威を追い払おうと反撃に打って出た。
六連ミサイルポッドとバニッシュがお化けに炸裂する。
「え、ちょ……ぎゃああああぁぁぁ!」
ミサイルと光の魔力の爆発にやられて、お化けは悲鳴をあげた。それでもなお、二人の攻撃は続く。
お化けの絶叫を聞きながら、茂みのなかの二人は苦笑を隠しきれなかった。
●
比賀 一(ひが・はじめ)と
比賀 亘(ひが・めぐる)は順調に肝試しコースを進んでいた。
順調とは言っても、あくまでも道を間違っていないという程度に収まる。歩を進めるスピードに関して言えばさほどではない。
一だけならまだしも、亘がいるからだ。
「く、暗いぃ……」
彼女は森の暗闇に怯えながら、ひしっと一に抱きついていた。彼の身長では、腕が巻きつくのはちょうど一の腰下ぐらいだ。
「あー、確かに暗いな。明かりが懐中電灯だけってのも、雰囲気が出る」
一は懐中電灯の明かりを前方にさしながら言った。
道中、白布のお化けや人魂風の青い炎が出てくるものの、それは彼を恐怖に陥れるまでには至らない。むしろ、一はお化けそのものよりも、メイクがよく凝られているなぁと、金の注ぎ具合のほうに感心していた。
(そもそも、さすがにこのトシでは驚かないっつーか、お化けなんぞよりももっと怖いのがあるっつーか……なぁ)
そんなことを心のなかでつぶやく。
だが、亘はそうは限らないようだった。
「ふにゃー、こわいよおにーちゃーんっ」
「……あんまりひっつくな、亘」
「だって……だってぇ……」
ぎゅっと抱きついて離れない亘は、涙目になって一を見上げた。お化けが出てくるたびにこの調子だ。
呆れたように、一はため息をつく。
「あのなぁ……少しはお化けぐらい怖くないって気概を持たないとだめだぞ?」
「きがいってなーに?」
「…………いや、いい。俺が間違ってた」
亘に難しい説明は無理だ。一は大人しく諦めた。
「こわいー……でも、おにーちゃんの体あったかぁい……」
亘はそう言って、ぎゅーっと力強く一の体を抱きしめた。
照れ臭そうに、一はポリポリと頬をかいた。心なしか、その頬はわずかに紅潮している。
亘に抱きしめられると、そのぷにぷになほっぺたが太ももに当たって、どこかくすぐったい。『おにーちゃん』と自分を慕ってついて回る彼に、最初のうちは戸惑ったが、今となってはそれも慣れたものだった。もしかしたら逆に、こうして抱きしめられていないと寂しいのかもしれない。
(まさか……な)
自分の考えに笑い飛ばすように、一は苦笑した。
と、再びお化けが二人の前に現れる。それも、今度はよりクオリティの高い、白骨お化けだった。
「にゃあああぁぁっ!? おにーちゃん、おにーちゃん、おにーちゃあああぁんっ!」
泣き喚いた亘は猫のような絶叫をあげる。
「わ、亘、怖いのはわかるけど! ちょっと抱きしめる力が強すぎるんじゃねーの……っ。ほ、骨がミシミシ言っておがあああぁぁぁ」
抱きしめるどころかホールド状態にもっていかれた一は、亘の腕に抱かれながら死の淵をさまよう。
彼が泡を吹いて倒れそうになるのは、そう間もない後のことだった。
●
First Previous |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Next Last