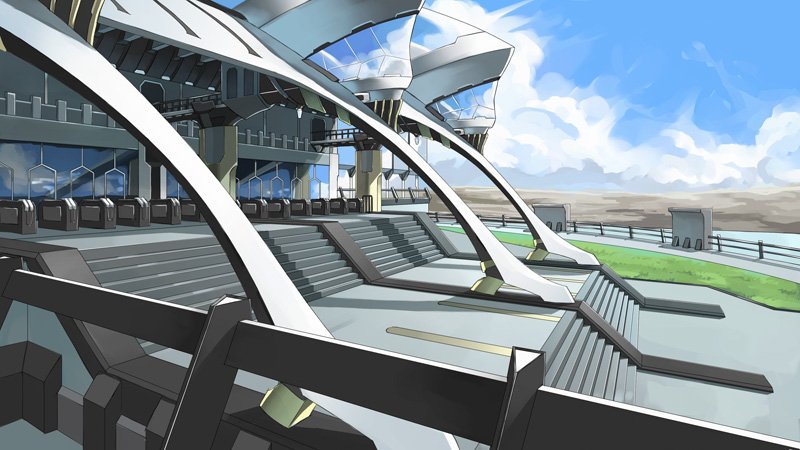リアクション
第1章 キノコ狩りツアーは各所開催中? 3
巨大な巣の中はとても静かであった。ときどき、どこか遠くから地響きのような音が聞こえてくることもあるが、それは恐らくサンドワームが移動している際の音であろう。それ以外は、さほど問題が起こるわけでもなく、意外と無難に事が運んでいた。
だから、だろう。
「しかし……アレだよな」
「ん?」
アキラ・セイルーン(あきら・せいるーん)は、ふと口を開いた。それに、先行していたパートナーたち二人――ルシェイメア・フローズン(るしぇいめあ・ふろーずん)とセレスティア・レイン(せれすてぃあ・れいん)が振り向いた。
「伝説のキノコならここにもあるっつーのになぁ」
伝説の『太陽のキノコ』を探すルシェイメアたちにとって、その言葉は不可解きわまりないものである。怪訝そうな表情を浮かべて、ルシェイメアが言った。
「どこにそんなものがあると言うのじゃ?」
「あるじゃねーか。ホラここに」
一点を指さすアキラ。
ルシェイメアたちの視線は、そちらに集中する。つまり、彼の股間に。
「…………」
「…………ニコ」
瞬間、アキラの股間にすさまじい衝撃が走った。
「ぐほぉ!?」
ルシェイメアの足が、無言で彼の大事なところを蹴りあげたのである。無論、アキラは悶絶して、倒れ伏す。
「ぬおおぉぉぉ……」
「さ、セレスよ。そんなドアホゥはほっといて先にいくぞ」
「ええ? で、でも……ルーシェさぁぁん」
あまりにも自業自得なアキラを心配する、心優しいセレスティアを連れて、ルシェイメアは先へとすたすた歩いて行った。残されたアキラは、股間の痛みが収まるまで涙ぐむしかなかった。
「あー、いたいよぉ。まだズキズキするよぉー」
「自業自得もいいとこじゃな」
「だ、大丈夫ですか、アキラさん」
股をかばうようにして歩くアキラに、セレスティアが近づいて心配そうな声をかけた。まあ、事実、かなりの致命傷ではあるわけだが。
「あー、大丈夫大丈夫。俺の息子は元気だよ。なんなら触って確認しても……」
「アホかぁっ!?」
「あぶっ!」
ノリルシェイメアが素早く取り出した光条兵器――という名のハリセンが、アキラの脳天を見事なまでの音を発して叩いた。光条兵器としての使い方を間違っている気がしないではないが、アキラにはむしろ効果的なようだ。
「ル、ルーシェ、なんか最近威力が増してきてないか……?」
「気のせいじゃろ」
そんな二人のやり取りを苦笑して見つめるセレスティア。そんな、いつも通りの探索の途中で、はたとアキラたちは足を止めた。
その理由は、彼らの歩む先。その一点にあった。
「あれって……」
「ふむ……」
「どうかんがえても……サンドワームだよな?」
ずるずると這いずってやってくるのは、アキラのうん十倍はありそうな体躯の巨大生物。地球で言うところのミミズをでっかくしたようなサンドワームは、まだアキラたちには気づいていないようだった。
と、そんなミミズもどきを見てアキラが一言。
「このミミズって……食ったらウマイのかなぁ」
「「……え”?」」
さすがにその発想はなかったのか、二人は度肝を抜かれた顔でアキラを見つめた。お前、正気か? といったように、ルシェイメアが慌てて声を挟んだ。
「貴様……! まさかアレを食べるつもりなのか!?」
「えー、だって、ゲテモノはウマイっつーのが世間の相場じゃないのさ〜」
「ええぇ……ア、アキラさん、本当にアレ食べるんですかぁ……や、やめた方がいいと思うのですが」
二人はもちろん、反対の声をあげるが、どうやらこの男、触るなと言われたものは触りたがる性分なようで。なにやら格好よさげに顔の角度を決めてイケメン面になった。
「ふっ……いいか、セレス。この世には、いや、男には、避けては通れぬ道があるのだよ。そう、人はそれをチャレンジ精神と呼ぶ!」
「顔は決めてても言ってることは無茶苦茶じゃぞ」
イケメン面も数秒ともたないようで、ルシェイメアに突っ込まれると同時に、アキラはぷしゅーと眠気顔に戻った。
「まあ、冗談はともかく……もしかしたら美味しいかもしれないじゃん」
「……いやまぁ、本人が食べたいというのであれば、ワシがとやかく言う事もないのやもしれんのじゃが」
「んじゃ、早速……えーと、コホン。『一狩り行こうぜ!』」
「なぜ言ったし」
「……いや、お約束かと」
と、どうやらやり取りが許されたのはそこまでのようだった。
こちらに気づいたサンドワームが襲いかかってきたと同時に、三人はそれぞれ飛びのく。普段はボケているアキラも、さすがに敵に襲われた時までは馬鹿なことはしなかった。
「スナジゴク!」
アキラの声を聞いて、控えていたスナジゴクがサンドワームの動きを封じた。それによって生み出された隙に、お化けキノコが睡眠効果を持つ胞子を撒き散らす。そこからは、たたみかけるようにアキラたちの攻撃がサンドワームを襲った。
ときどき、パラミタペンジンがぴょこぴょこと攻撃を加えるのが、よいアクセントである。
そうこうしているうちに、サンドワームは尾を切り裂かれたところでずるずると逃げ出して行った。意外にも素早いその背中を見送って、ようやくひと段落する。
「さて、じゃあ持ち帰るか」
「あ、やっぱりですか」
有言実行。
巨大ミミズの尾を小分けするアキラを、ある意味凄いと思うルシェイメアとセレスティアなのであった。
●
巣の中を慎重を期して歩むのは、いかにも日本人らしい精悍な顔立ちをした男であった。鋭く研ぎ澄まされた双眸は、まるで何かを警戒するように視野全体を把握している。
「小次郎さん」
そんな彼に、柔らかな声色の声がかかった。が、どうやら男の神経は別のことに集中し過ぎているらしく、応じる声はない。
これまで何度も声をかけているのか。しびれを切らして、柔らかな声はいくぶんか声を張って男を呼んだ。
「小次郎さんっ」
「ん……あ、ああ、リース。どうしたんですか?」
「どうしたんですか、じゃありませんわ。探索に集中するのは良いですけど、私の声ぐらいは聞こえるようにしておいてくださいませんと、困ります」
ぷりぷりと頬を少しばかり膨らませて、目の前の娘が言った。ばつが悪そうに、
戦部 小次郎(いくさべ・こじろう)はぽりぽりと頭をかく。
「……そんなにひどかったですか?」
「それはもう」
あからさまなため息をついて、小次郎のパートナーである
リース・バーロット(りーす・ばーろっと)は呆れていた。普段は温和でやさしい彼女がここまで言うとは、よほどだったのだろう。小次郎自身も、自分を反省した。
「5度目でようやく振りむいていただけました。何をそんなに考えていたのですか?」
「いえ、ちょっと……本当に太陽のキノコがあるのかどうか、考えていただけですよ」
「……でも、それを見つけに、ここまで来たんのですよね?」
言ってる意味がちょっとよく分からないといったようなリースに、小次郎は返答した。
「正確には、真偽を確かめに、というところですか」
「真偽?」
「本当にここに太陽のキノコがあるかどうか……噂が本当なのか、という。もちろん、キノコを見つけてひと稼ぎしよう、というのも、あるのですけどね」
いたずらっぽく微笑を浮かべた小次郎に、なるほどとリースが納得のいった頷きを返した。確かに、噂そのものの真偽というのも気になるところである。噂というものに限らず、人の話はやはり元となるものがなければ育たぬものだ。地球的に言えば、火のないところに煙はたたぬ、ということか。
「だから、サンドワームは避けて通るのですね」
「騒動を大きくしてもしょうがないですからね。それに、こちらからお邪魔させてもらってるわけですし」
もっともらしい意見に、さすが小次郎だと感心するリース。であったが、すぐにそれは勘違いだと知れた。
「……まあ、他の方がサンドワームを引き寄せてくれればこちらが楽……というのもあったりなかったりなんですが」
ここのところ、どうやら彼の腹黒さは増してきているようだ。
根は変わらないのだろうが、どうにも昔に比べるとこなれてきてしまっているというか、なんというか……ある意味では、良いようにも悪いようにもとれるところである。
「あ、そういえばリース」
「はい?」
「例のもの、用意していますか?」
「ええ、もちろんですわ」
そう言って、リースは自分の懐からとある小ビンを取りだした。それは、特殊な配合によって作り出されている悪劣な匂いを発生させる香水であった。もともと、サンドワームは地中で生きる生物であるため、人間の各器官に当たるものが相当進化していると思われた。となれば、恐らくは嗅覚に関してもそれ相応の反応を見せるはずである。
そこで、この強烈な臭気を漂わせる香水だ。
「小次郎さん?」
「ほら、あれを見てみてください」
「あ……」
小次郎が指を指した先には、ちょうどいいところにサンドワームがいた。寝ているのかぼーっとしているのか、その場から動かないサンドワーム。小次郎たちは、自分たちの進行方向から逆側に向けて、香水を投げ飛ばした。
パリン! という甲高い音に反応して、サンドワームがむくりと動き出す。そして、徐々に近づくにつれて、サンドワームは臭いにつられるように動き始めた。
「いまです、リース」
「は、はい」
サンドワームが臭いにつられている隙に、小次郎たちは恐る恐る歩き出した。
こうして、なんとかサンドワームから逃れた小次郎たちは、その後もワームの気をそらせるために香水を利用していくのだった。
●