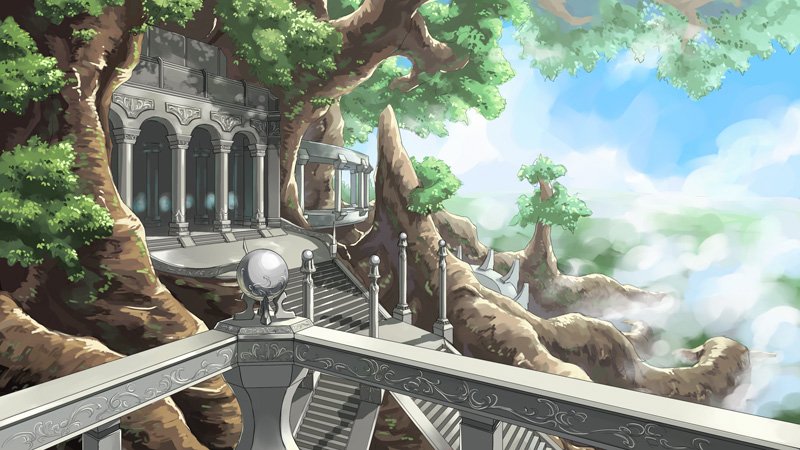リアクション
◇ ――静かな、とても静かな部屋の中。 琥珀色の紅茶で満たされたカップを手に、一人の女性が椅子に深く腰掛けている。 「突然の無礼を、まずお詫びさせて下さい」 ソーサーにカップを置く女性を前に、赤羽 美央(あかばね・みお)が胸に手を当てて、頭を下げた。 美央がゆっくりと頭を下げると、身に纏った魔鎧 『サイレントスノー』(まがい・さいれんとすのー)から、金属音が鳴る。 少女が、ちいさなバスケットを受け取り託された、始まりの場所。 赤ずきんの家。 その家に、突然押し掛けた美央と天音を前に、その女性は驚くこともせず、それどころか柔和な笑顔を見せた。 「お止め下さい……そんな事より、お茶でも如何?」 そう言って椅子から立ち上がろうとする女性を、美央が手で制した。 「すみませんが、遠慮させていただきます」 「代わりと言っては何だけど……いくつか、聞きたい事があるんだよね」 「まぁ、何でしょう? あ、どうぞお座りになって」 天音が勧められるまま、女性の前に置かれた椅子に腰掛けてから脚を組んだ。 「不躾な質問だけど……貴女は、誰?」 「私は、『母』と申します。と言っても、貴方達には聞こえないでしょうけれど」 微笑を崩すことなく口を開いた『母』の声は、名前を口にした所で、何者かに吹き替えられたかのように耳に届く。 「……『お母さん』でいいのかな?」 「えぇ、そのようにお呼び下さい」 天音が冷静に、母に向かいあう。 (……今のは?) (解らない……ですが、この世界での『役割』が、存在を表す『名』に干渉しているのかもしれないですね) 天音の傍らで、美央が自らの鎧に囁くと、サイレントスノーが興味深そうな口調で答えた。 (もし何かを偽るような事があったら、嘘感知ですぐに解りますから、問題は無いでしょう) その言葉に、美央が鎧の一部を指で撫で、『母』に向かって口を開いた。 「いつも『赤ずきん』ちゃんに護衛を付けているみたいですが、近くの森なのに護衛というのも変な話です……なにか理由があるのでしょうか?」 「えぇ、あの子が、狼が出ると言うものですから、母親としては心配で」 淀みなく答える『母』の言葉に、肌がピリピリと反応する。 理由も、何が偽りなのかもわからないが、この母親は真実を口にしていない。 美央が、槍を握る手に力を込める。 「……嘘は通用しませんよ?」 「そうですか……変わった方ですね。ふふ」 不意に、天音が前に乗り出して、顎の下で手を組んだ。 「この『物語』って……何なの?」 鋭い目つきで問いかける天音に、『母』はカップを手にして自らの口元に運んだ。 瞼を伏せながら紅茶を含み、ゆったりとした動作でそれをまたソーサーに戻す。 「いいでしょう。お話します。ここに客人が来るのは珍しいですし、ね」 「この『物語』がいつ始まったのかは、私にも解りません。気が付いたら、ここに居ましたから」 「……続けて下さい」 自分の言葉に偽りが無いかを確かめるように、視線を送る『母』を見て、美央が話の続きを促す。 「あの子、『赤ずきん』は、人と狼の間に生まれた子……人狼です。そして、私は人間です」 そう言って、窓の外に広がる森を懐かしむように目を向ける。 「森の中で、狼に出会いませんでしか?」 『母』の問いかけに、天音は首を横に振った。 「この『物語』は、貴方達のように迷い込んできた方々が命を落とすと、狼として生かし続けてきました。 そして、増殖した狼はやがて群れとなって、統べる者を求めました」 「それが、あの赤ずきん?」 「はい。あの子は、迷い込んだ人々を狼達の元へと導き、食事を与えることで彼らのリーダーとして、今まで生きてきました」 「……例えば、それが出来なくなったとしたら?」 天音の疑問に『母』が、口元を押さえて微笑んだ。 「統率を失えば、群れは暴走し、食事を求めて人を襲い続けるでしょう。この物語の理では、狼は狼を食べられませんから――人を食べるのは当然ですよね?」 その言葉を聞いて、美央がこめかみに指を当てた。左右に視線を流してしばらく思案した後に、口を開く。 「……それならば、赤ずきんが統率者である必要は、どこにあるんですか?」 統率者が存在しても、統率者を失っても、最終的に狼が人を襲う事に変わりは無い。 「私、とってもとっても、狼の肉が好きなんです。煮ても、焼いても、好きで好きでたまらないんです。 ふふ……あの子がいると、簡単に狼を捕まえられるんですよ?」 『母』の唇が、卑しく曲がる。 狼は、狼を食べられない。世界の決め事として。それでも――人は狼を食べることが出来るのだ。 まるで、童話の中に出る魔女の様に唇を曲げる『母』が、天音の頬に手を伸ばす。 「人間のお肉は……おいしいのかしら?」 ◇ ――森の中では、未だに狼の集団に追われて、赤ずきんを抱えながらソーマが走っていた。 少し遅れる形で、終焉を見届けようとする者達も付いて来ている。 「どうなってるんでしょう?」 巨大な影となって走る狼達を追いかけながら、ユイ・マルグリット(ゆい・まるぐりっと)は考えをめぐらせる。 赤ずきんは、人を食べない。狼も食べない。人ではなく、狼でもないから。 そして、狼は狼を食べずに、人を食べる。それなら、狼でもあり、人でもある赤ずきんは? 「この世界では、赤ずきんが狼に食べてもらえない?」 「だけじゃ、なくて……猟師の人も、いないみたいだねぇ……まだ、走るのかなぁ」 ユイの独り言に、隣を走っていた風人・七海(ふうと・ななみ)が語りかけた。 あくまで傍観者として、この世界を散策して回っていた七海は、この本の登場人物が狼と赤ずきん、それに母親以外は存在しないことを知っていた。 「それじゃあ、この話は終わらない……?」 横で併走していた火村 加夜(ひむら・かや)が、ユイと七海の会話を聞いて、顔色を変える。 赤ずきんを食べる狼のいない『赤ずきん』。 おばあさんのいない『赤ずきん』。 猟師のいない『赤ずきん』。 足りないキャスト。 完成しない童話。 走りながら、物語を見続けていた一行に暗い影が落ちる。 「とりあえず、どうするんだ?」 「……順当に行けば、婆さんの所に届けるしかないか?」 「十ニ本先の大きな木を右に曲がって。獣道が見えたら、その道に沿ってそのまま真っ直ぐ」 侘助の問いかけに、ソーマが眉間に皺を寄せていると、不意に腕の中の赤ずきんが声を上げた。 「……今、何本目だ?」 「多分、八本」 二人が半信半疑の中、赤ずきんの言葉通りに走ると、木々の合間から古びた建物が見えた。 都合よく、ドアが半分開いている。 「とりあえず、行くしかねえか!」 勢い任せに飛び込んだソーマの手から離れた赤ずきんの目の前には、狼の顔。 唐突に飛び込んできた赤ずきんに、ヘルがたじろいでいると、赤ずきんは笑顔で歩み寄った。 「ねぇねぇ、おばあちゃん。どうしてそんなに茶色いお肌をしているの?」 「は、畑仕事で日焼けしちまっ……してしまってねぇ」 突然の質問に、ヘルが上ずった声で答える。 「どうしてそんなにお声が枯れているの?」 「風邪をひいてしまってねえ」 赤ずきんは、何かを確かめるように指折り数えて質問を繰り返した。 赤ずきんが目を閉じて、小さな声でヘルに尋ねる。 「……どうして、そんなに大きいお口をしているの?」 「お前を食べる為だ……ぜ?」 バッと両腕を広げて、襲い掛かろうとするヘルの動きが、不意に止まった。 何故か、自分の身体に赤ずきんが抱きついていたからだ。 「……食べて?」 幼い少女の懇願に、ヘルは手を上下左右にウロウロとさせていたが、やがて戸惑いながらも赤ずきんの背中に手を回した。 部屋に身を潜めていたザカコが、何か文字が書いてある紙をヘルに向ける。 「あ、あぁ美味い。ははは、どうだ食べてやったぞー……?」 ザカコが持っている紙に書かれていた文章を、たどたどしく読むと、赤ずきんはヘルに身を任せて動かなくなった。 「こ、この後はべぶ!?」 慌てふためくヘルの顔を、外から入ってきたリナリエッタが突然蹴り飛ばした。 「な、何しやが――」 「私、猟師だし。早く、離れてくれるぅ? 石つめるわよ?」 鼻筋を押さえながら起き上がるヘルに、リナリエッタがケラケラと笑う。 訳も分からずに、とりあえずヘルが赤ずきんから離れる。 「そーれーで、と」 リナリエッタが赤ずきんの頬に触れようと手を伸ばすと突然、少女の目が開かれた。 むくっと起き上がり、リナリエッタの顔を見て笑ったかと思うと、その胸元に飛び込む。 「おばあちゃん、こんなところにいたんだ……これでようやく眠れるよ」 そう言って、赤ずきんは少女らしい笑顔のまま目を閉じた。 ◇ 「誰がババァだ!? この小娘!」 ――図書室内に、リナリエッタの声が響き渡る。 ふ、と気が付けば、森は本棚に。枝は本に変わっていた。 森を駆けていた者達も、全員が揃っている。 静かな図書室に、最後の『赤ずきん』のページが捲れる音が鳴る。 そこには、幸せそうにベッドで寝る赤ずきんの挿絵が、描かれていた。 |
||