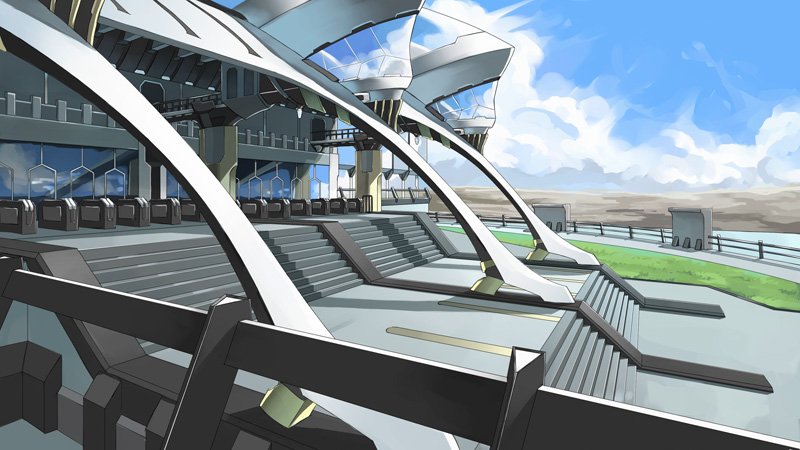リアクション
■
倒れた博士が縛り上げられ、転がされる。遺跡に残っていた作業員達も、次々と遺跡を離れ始めた。
暴走していた機晶ロボも――菫に足蹴にされながら――その動きを止めている。
流れ弾や爆発で植木声を上げる人々の合間を、影野 陽太(かげの・ようた)のパートナー、ノーン・クリスタリア(のーん・くりすたりあ)が走り回っていた。
「おにーちゃんも頑張ってるんだ……わたしも頑張る!」
遺跡を見渡して、いつに無く真面目な顔をしながら傷付いた人を見れば、敵味方問わず治療を始める。
気を失っている作業員を安全な場所で寝かせながら、ノーンが動きを止めないイロンVを見上げた。
(……あの大きいのが止まらなかったら、もっとたくさんの人が傷付いちゃう)
彼女にとって、それがどんな人間であれ、傷を負う事は辛い事でしかないらしい。
「ははは、はははは。心配ないでござるよ、これ以上……あの異論Vの横暴はミーが許さないでござる」
悲痛な表情を浮かべるノーンの横で、不可思議な言葉で高笑いが上がった。
目を向ければ、そこにはイコン――いや、『イコンにも見える』機晶姫、クリムゾン・ゼロ(くりむぞん・ぜろ)が腕を組んで立っていた。ノーンの表情から心情を汲み取ったのかは定かではないが、その声は自信に満ち溢れている。
「異論じゃなくてイロンだよ。まあ、どっちでもいいけどさ」
微妙なイントネーションを放つクリムゾンの言葉に、葉月 エリィ(はづき・えりぃ)がツッコミを入れるが、当の本人は気にせずにイロンVを見上げていた。
エリィの背後――黒い闇から溶け出すように、金の瞳が光る。
「異論でも遺恨でもいいから、早く始めましょう?」
肩に掛かる黒髪を後ろに流しながら、エレナ・フェンリル(えれな・ふぇんりる)が現れた。
エリィ達がクリムゾンを先頭に、のらりくらりと前進を続けるイロンVの前に躍り出る。
「零システム・マジックモード起動……」
クリムゾンが、おもむろに右腕を上げると、機晶石から溢れるエネルギーが、その形を変えた。
集約された魔力が、広げられた掌に集う。
それに合わせて、エレナも自身の魔力を眼前に構えた腕に集中させる。
「クリムゾンフレア発動」
無機質に告げられたその言葉が詠唱となり、クリムゾンの右腕に終結した魔力が炎となってイロンVに放たれた。
周囲の酸素を燃やしながら飛翔する炎が、景色を歪めながらイロンVの装甲を直撃。間髪入れずにエレナの放った炎が、クリムゾンの撃った装甲と同じ場所を焼き払う。
熱せられた鉄板が赤々と色を変える様子を見て、クリムゾンが腰を落とし、両腕に構えた銃――機晶キャノンでイロンVに狙いを付ける。
「ぬ……邪魔をするな!」
イロンV内部――機晶ロボのコクピットに備え付けられたモニタを見ながら、エヴァルトが叫ぶ。
鉄塊の身体を傾けながら強引に方向を変え、足元でこちらに狙いをつけるクリムゾンに向かってイロンVを発進させた。
「えぇい! 何か武器は無いのか!」
操縦桿を足で踏みつけながら、何時の間にか手に入れた資料――『イロンV完全設計書』のページをめくっていく。
全30ページのその資料を半ば破り捨てるように目を通していくと、22ページ目、『兵装一覧』と書かれたページに目的の文字を見つけた。
「ミサイル射出装置――赤のコードに繋がれている黒の箱から伸びている緑の線に繋がれた箱に付いている青いボタンの3つ隣の星型のボタン……わかりにくい!」
丁寧に書かれているようで、まったく不親切な資料を投げ捨てて、エヴァルトが星型のスイッチを力任せに押す。
短い電子音の後、イロンVの肩に備え付けられたミサイルポッドから、無数のミサイルが飛び出した。
「ちゃちな花火だね! クリムゾン、気にせず狙いな!」
飛来するミサイルに向けて、エリィが腕を交差してその両手に握った銃を構えた。
1発、2発、3発と空中でミサイルを打ち落としていく。と、爆発の合間から、更に追加のミサイルが迫る。
身を翻しながら、残ったミサイルを打ち抜くエリィのすぐ横を、弾痕が真っ直ぐに走った。
エリィが軌道を修正して迫り来る弾丸を踊るように避けて、弾の撃ち出されている先を見上げる。
視線の先――イロンVの腕に備え付けられた機銃から、笑い声が上がった。
「ハハハ! よーし! このまま突っ切れー!」
「止めないか、ニサト! と云うよりな……このままだと落ちるぞ!」
腕の先で機銃を撃ちながら嬉しそうに声を上げるニサトに、クリスティーヌが「もう勘弁してくれ」と言わんばかりに声を上げる。
事実、クリスティーヌが言う通りイロンVの装甲は、早くも限界を迎えようとしていた。
「チャンス、みたいですね」
ローブの隙間から出した手に、杖を握りしめ――御凪 真人(みなぎ・まこと)がイロンVを見る。
その横では、乳白金のツインテールを夜風に揺らしながら、名も無き 白き詩篇(なもなき・しろきしへん)が冷たい視線をイロンVに向けていた。
「資源ゴミにしては、馬鹿な大きさじゃな……バラしてリサイクル業者に売りつけるのにも、骨が折れそうじゃ」
「白、どうやら想像していたほど、機械的な部分は多くないようです」
「そうじゃな……真人、遅れるでないぞ」
短いやり取りの後、白き詩篇が手にしていた杖の先に手を掛け、先端部分を勢いよく回した。
淡い光を放ちながら回転するルーンを見てから、白き詩篇が杖をイロンVに向ける。
「傲岸不遜の鉄塊よ、次はまともな用途に使われる事を祈るんじゃな」
呟きと共に、杖の先から無数の氷塊が放たれ、闇夜の中を白い軌跡が走る。
やがてそれは不愉快な音を立てながらイロンVの装甲を凍りつかせた。が、間髪入れず、真人が凍結部分に炎の嵐を呼び出す。
凍り付き、青黒く変色していた装甲が、再び赤く色付いた。
数発こちらに向けてミサイルが放たれたが、それすらも巻き込んで、白き詩篇と真人は氷塊と炎を交互に放ち続ける。
加熱と冷却を繰り返されたイロンVの装甲が、無残な色に変わり果てた。
「まだ形を留めるか……クズ鉄の分際で。だが、これでトドメじゃ」
白き詩篇が一際大きく杖を回転させ、地面にその柄を付き立てた。酸の霧がイロンVの装甲を溶かし、瓦解させる――はずだった。
しかし、それは突如向けられた一振りの剣によって阻まれた。
「何の真似じゃ……理由如何によっては、その身の保障はしかねるぞ」
「ロボットは悪くない。悪いのは、操る人間の心だ! ロボットを妙なことに使おうとする気持ちがダメなんだ!」
白き詩篇の言葉に、剣を握り締める手に力を込めながら、鬼院 尋人(きいん・ひろと)が叫ぶ。
(そうだ……ロボットは、悪くない。いつだって悪いのは――)
――尋人の脳裏に、幼い頃の記憶が蘇る。
施設に預けられている生活の中で、少年だった尋人が楽しみにしていた縁日の日。
差し出した手に渡されたのは、僅かばかりの小銭だった。
小さな手でも握り締められる、その『全財産』を手に、出店を見て回る。
沢山のお菓子や玩具など、どれもこれも欲しい物ばかりだったが、自分の手の中にある資金では、とても全てを買う事は出来ない。
慎重に、何度も店を見て回って――最後に選んだのは、輪投げだった。
明らかに輪よりも大きなぬいぐるみや、およそ届かない距離に置かれた高価な玩具が並んでいる中で、一体のブリキの人形が目に映った。
下半身がキャタピラで上半身にミサイルを搭載したブリキのロボット。
花火の光に照らされるその人形が、幼かった尋人には無敵のヒーローに見えた。
「欲しい……」
思わず、呟く。周囲の笑い声に飲み込まれそうなその声を、輪投げ屋の親父は聞き逃さなかった。
「おう! 兄ちゃん、遊んでいきな! 今ならオマケしてやるよ!」
威勢のいい声と笑顔――何より『オマケ』の一言に惹かれた尋人が、手の中で暖かくなるほどに握り締めた小銭を、店の親父に渡す。
「毎度あり! これが欲しいんだろ? じゃあ、これはオマケな」
そう言って、店の親父がブリキ人形を少しだけ手前に寄せた後、三つの輪を尋人に渡した。
1投目、2投目と投げた輪が、人形を掠めて転がっていく。
最後に残された輪を握り締め、目を閉じて祈った。
(神様、お願いします……)
必死に最後の輪に願いを込める尋人に、店の親父が「もうちょっとだ、頑張れよ兄ちゃん」と煙草を咥えながら適当に声援を送る。
それすらも耳に届かない程に集中した尋人は、出来るだけ身を乗り出して――最後の輪を投げた。
飛んでいく輪が、スローモーションに見えた。
1投目、2投目の飛び方を見て、方向の修正を掛けられた輪が、確実に人形へ向かって飛んでいく。
輪が頭を潜り、腕を通った瞬間、尋人の目が大きく見開かれた。
(やった! 取れた!)
喜びの表情を浮かべた瞬間――輪が、キャタピラに引っかかって斜めに止まった。
「っかー! 惜しいな兄ちゃん! 下までちゃんと通ってないとあげられねぇんだわ!」
「ぇ…………え?」
今にも泣き出しそうな表情を浮かべる尋人の目の前で、無常にも人形から輪が外される。
口を開いたまま自分を見上げる尋人に、店の親父は笑顔を見せた。
「仕方ねぇ! 大サービスだ! もう一回やるってんならここに置いてやるよ!」
そう言って、店の親父は尋人の正面。手を伸ばせば届く距離に人形を置いた。
「どうする、兄ちゃん」
煙草をもみ消しながら店の親父が聞いてきた、が――幼い尋人には、もう一度遊ぶ資金は残されていなかった。
――濃く、深く記憶に根を張る思い出を引き出した尋人が、手に持つ剣に力を込めた。
視界の隅にそびえるイロンVが、苦い記憶のブリキ人形と被る。
(イコンに乗って、あの大きいロボットにワイヤーロープで作った輪を投げて……あの時の、決着をつけるんだ!)
尋人は強い決意に満ちた瞳で、白き詩篇に向けて剣を振っていく。
「輪投げ、輪投げ、輪投げ……絶対に、取る!」
「訳が解らん! 真人! この者、何らかの洗脳を受けておるかもしれんぞ!」
「みたいですね……ちょっと目の焦点が合っていませんから」
一心不乱に剣を振るう尋人を、真人達が二人がかりで抑えに掛かった。
◇
「ルイ、クド! 敵のロボはもう殆ど壊れかけてる……今がチャンスだ」
人間兵器と化したクドを振るいながら残った残党を蹴散らすルイに、出来るだけ致命傷を避けながら、作業員達の足などを撃ち抜きつつレンが叫ぶ。
その声を聞いて、チャリオットタンクのスピードが上がり、ルイ達はイロンVに急接近した。
「さぁ、行きますよ! クドさん!」
「お、おうイェア……」
散々武器として振るわれ、流血が止まらないクドが力なく返事を返す。
どことなく曲がってはいけない方向に腕が曲がっている気もするクドを見て、セラエノ断章はローブの裾から『生まれた時の姿の写真』をチラチラと出していた――が、不意に風が吹き、写真がハラリと落ちた。
グロッキーな表情を浮かべていたクドの目が見開かれ、地に落ちた写真を凝視する。
「…………何、だと?」
――写真に写っていた物は『セラエノ断章が魔導書だった時の表紙』だった。
バレちゃった、と言わんばかりに舌を出すセラエノ断章を見て、クドの脳内に展開されていた妄想――ある種の楽園が崩壊しかけた時、冒険ロボGRKCの前に、一人の男が立ち塞がった。和服の上から黒革のロングコートを羽織って、その手に銃を構える男――平賀 源内が、イロンVの破壊をしようとするルイ達に銃を向ける。
「おぬしら! 漢の浪漫を何だと思っとるんじゃ! たいがいにせにゃあ……」
「ハハ……男のロマン? そんな物、たった今しがたブチ壊れた所でさァ。生まれたままの姿、と来たらそれはもう俺の……いや、全国の男の夢、裸体。そう、裸体だと思うさ、そうだろ? ハハハハ!」
壊れたように笑い声を上げるクドを見て、源内の頬が引き攣った。
――何だか解らないが、多分色んな意味でヤバイ。
理解できない恐怖に源内が身を引こうとした瞬間、クドの身体に満ちていた魔力が全て開放される。そのタイミングに合わせて、ルイがクドを力任せに振り抜いた。
「クド・バァァァァット!!」
「ぐおぉおッ!?」
ルイの叫び声と共に、全ての魔力を解き放ちながらクドが源内を吹き飛ばした。――正確には、なすがままに武器として扱われただけだが。
「……馬鹿だねぇ」
放物線を描きながら砂漠の闇に向かって飛んでいった源内を見て、パートナーのノアは溜息混じりに呟いた。いつのまにか顔を覆っていた布は外されている。
いざとなれば半ば暴走気味の源内を、無理矢理にでも止めようと思っていたが、間に合わなかったようだ。
「……知り合いか?」
煙管から煙を漂わせながら、源内が消えていった闇を見つめるノアに向かって、レンが問いかける。が、ノアは肩を竦めてキセルの中に残る火種を落としながら、
「さぁ? 髪の毛先ほども思い当たらないさね」
と、短く答えた。
「くふっ……俺の……パラダイ、ス……」
「クド。ほれ、しっかりせい。だらしのない」
既に虫の息で何事かを呟いているクドを見て、チャリオットから降りた麻羅が身体を支える。
薄く開いた唇から、淡い光が漏れ出す。と、その光がクドの身体を包み込み、傷を癒していく。
「おぉ……天使様、いや……神様」
「何を寝ぼけておるのじゃ。起きろ、呆気者」
自分に向かって唇を尖らせるクドの頬を、麻羅が平手で打つ。
1発で正気に戻っている様に見えたが、何故か麻羅は2発、3発と往復で平手打ちを重ねる。
「痛ッ、痛ッ、いや、悪くない? かも……あ、やっぱり痛ッ。も、もう大丈夫でさァ」
リズミカルに頬を打ち続ける麻羅の手を、クドがやんわりと制止した。
「ぬ……そうか。しかし、身体の傷は癒えても、まだ精神的に疲弊している様にも見えるな……緋雨」
「え? ……あ、うん。あの……こ、これは麻羅から頼まれたから、仕方なく渡してるんだからね! べ、別にあなたの事、何とも思ってないんだから勘違いしないで!!」
そう言って緋雨が取り出したのは、可愛くラッピングをされたチョコレートだった。明らかに、何処かで買ってきた適当な物とは違う『本気感』が溢れるそのチョコレートに、クドの瞳に輝きが戻る。
「あぁ、俺ァ毎日がバレンタインだから、日付が違うとか小さな事ァ気にしやせんぜ。この気持ち、確ッかに受け取」
「いや、本ッ当にたまたま! これしかなくて! 仕方なく渡すの!」
クドの言葉を遮り、緋雨がクドの手からチョコレートを奪い取るとラッピングをはがして、中身のチョコレートだけをクドの口に押し込んだ。
モゴモゴと呻きながらチョコレートを食べ終えるクドに、セラエノ断章が駆け寄り、耳元で囁いた。
「実はね……もう一枚、違う写真があるんだ♪」
「違う、写真……?」
「うん♪ そうそう。あんまり人には見せないんだけど……クドっちが頑張ってくれるなら、見せてもいい……かな?」
頬を染めながら、上目遣いでそう言うセラエノ断章の言葉を聞いて、クドは自らの足を上げ、ルイに向けた。
「ルイさん……まだ、まだ悪は滅びちゃいねぇんだ。俺達が休息するのは……この世界に平和が戻った後!」
「おぉ! 素晴らしい! その精神! その想い! いいでしょう! 一緒に奴等を叩きのめしましょう!」
ルイが、ガシっとクドの足を掴んで持ち上げる。
この上なくやる気になったクドを見て、緋雨が何となく――本当に、何気なくセラエノ断章に問い掛けた。
「……さっきと違う写真って、『表表紙の次は裏表紙でした♪』とかじゃ、ないですよね?」
「ハハハ……冗談が過ぎます、よ?」
緋雨の言葉に、クドは笑いながらセラエノ断章を見た。
冗談だと――『そんなわけないじゃん!』と、そう言ってくれるだろうと思っていた。が、予想に反して、セラエノ断章の表情は硬かった。そして、セラエノ断章は悪戯がバレた子供のような笑みを浮かべた。
「……テヘッ☆」
「テヘッ☆ って……マジですかぃ」
あらぬ想像を巡らせ、『それ』だけを心の支えに武器として復帰したクドの精神力が、ガクッと削げる。
力無く垂れ下がったクドの腕が、ルイの足元を叩いた。
「ぬ……? これは、必殺技のタイミングですね!?」
それは、特に何の意味も無い――強いて言えば脱力した腕が当たっただけの事だったが、ルイはそれを何らかの合図だと受け取ったらしく、今までよりも大きく、強くクドを振り回し始めた。
回転数を上げるルイの身体は、次第に大きくなり、その額には角が現れた。巨大化しきったルイの足元から、チャリオットが軋む音が響く。
身体の大きさを倍程に変貌させ、額から大きな角を生やしたルイは――既に鬼そのものだった。身に纏っていたダンボールも千切れ飛び、今やただのゴミとなっている。
「行きますよ、必殺! クドバット・ホームランッ!!」
「ぁー……もう、どうにでもなればいいさ、ハハハ☆」
――全力のフルスイング。再びクドの脳内で生み出された楽園が崩壊し、それと共に体に残されていた魔力が開放される。
チャリオットを『蹴って』生み出した力を、正確に腰の回転、腕の振りによって、再び人間バットと化したクドに伝え、振りぬく。
解き放たれた魔力にルイの力が加わり、生み出された攻撃がイロンVの脚部――機晶ロボを抉り取った。