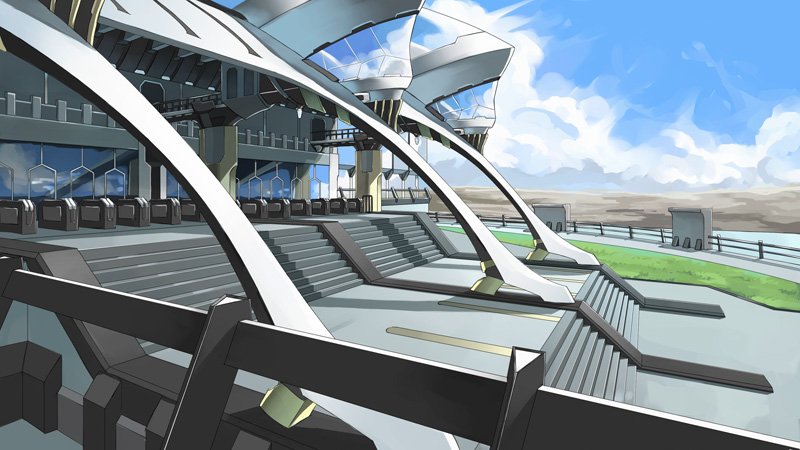リアクション
◇ ――イロンVの足元。 狸の面で顔を覆った男は、鉄の塊――イロンVを満足そうに見上げて、声を上げた。 「おー! ついに完成したかイロンV! ようやくコイツが動くところが見れるわけだなッ!」 周囲を飛び交う弾丸をものともせずに、爛々と赤い瞳を輝かせる獣 ニサト(けもの・にさと)の背後で、狐の面を付けたパートナー、田中 クリスティーヌ(たなか・くりすてぃーぬ)が小さな溜息をついた。 理解しがたい趣味、というものがあるのは構わないが、今回については特に度を越えている。 「……そういや、誰が乗るんだコレ?」 「特に決まってはいないな」 ニサトの言葉に、何処からともなく現れた白衣の男――博士が答えた。 それを聞いて、ニサトが自らの掌に、拳を打ち付けてニンマリと笑う。 「決まってないなら俺が乗っても問題ないな!」 「あぁ、構わんよ。丁度、現状を打破するのにパイロットを探していた所だ」 「……いや、待てニサト。コレに乗るとは正気の沙汰じゃないだろ。云ってはなんだが、まともに動くとは思えん」 (などと云って考え直すようなヤツではない、か) 博士とニサトのやり取りを見て制止するクリスティーヌの声は、予想通り届く事はなかった。 (用意していた医療キットで事足りればいいがなぁ……) 「君、少しいいかね?」 喜々としてイロンVに乗り込もうとするニサトを追って歩き出そうとしたクリスティーヌを、博士が呼び止めた。 振り向いたクリスティーヌに、博士が近寄る。 「何……男が乗り込んで、どうなろうと別に構わんと思ってはいたが、君のような女性が乗るなら話は別だ」 「と、云うと……?」 いぶかしむクリスティーヌに、博士が耳打ちをする。 それを聞いたクリスティーヌの表情が、さらに困惑したそれに変わった。 「おーい! 早く来いよ!」 呼び声に目を向ければ、イロンVの搭乗部に足を掛けながらニサトが『えくすかりばー』と書かれた木刀を振るっている。 不敵な笑みを浮かべる博士を横目に、クリスティーヌは足早にニサトの元へと向かった。 「何話してたんだ?」 小首を傾げながら近づいてきたクリスティーヌにニサトが問うが、聞かれた本人もどう説明していいのか解らないのか、複雑な表情を浮かべる。 「コクピットの赤いランプが点灯した場合は、速やかに脱出せよ、だったか。よくは解らんが、そう云っていたな」 「ふーん……ま、とりあえず乗ろうぜ!」 鼻歌を交えながら、ニサトが脚部――機晶ロボに備え付けられた梯子を上っていく。 程無くして、コクピットの搭乗口を開こうと手を掛けた瞬間、大きな音と共にイロンVが動き出した。 「ぬぅぉおぁ!?」 衝撃に、振り落とされそうになるニサトが、イロンVに必死でしがみつく。 クリスティーヌも何が起きたのかわからずに、梯子に腕を絡ませ、落とされないように耐えていた。 ふいに、無人のはずのコクピットから、笑い声が上がった。 「ククク……フハハハハハ! これは夢想家の手には余る物……さりとて腹筋校長にみすみす破壊させるわけにもいかん! この鉄塊、俺のイコンの強化に使わせてもらうぞ!」 それは、覆面で顔を隠しながらイロンVの強奪を虎視眈々と狙っていた男、エヴァルト・マルトリッツ(えう゛ぁると・まるとりっつ)の物だった。 「これだけの鉄屑と重火器類、売るだけでもどれほどの戦功点になるだろうか!? 考えるだけでも笑いが止まらん! それでは、さらばだ! ハァッハッハッハッハァ〜ッ!!」 高らかな声と共に、イロンVが動き出した。 ――以外にも順調に発進し始めたイロンVの装甲を、ニサトがよじ登る。 腹部から背面にぐるりと備え付けられた足場を通って、機銃が備え付けられた腕まで移動すると、身体をベルトで固定した。 「若干予定とは違ぇが……ふはははは!! ゆけぇ! イロンV!! お前の力を見せつけろッ!」 動き出したイロンVにテンションを上げながら、ニサトは機銃を撃ち回す。 「クソ……ッ! このままだと、マズイな」 涼司がイロンVを見上げて、歯噛みした。重量と高さが災いしたのか、さしてスピードが早くないながらも、イロンVはゆっくりとその身を進める。 ――その時、涼司の肩に手が置かれた。 振り向けば、既に夜を迎えているにも関わらず、サングラスを掛けたままのレン・オズワルド(れん・おずわるど)が笑っていた。 「……任せろよ。俺たちは、プロだ」 「何か、策が有るのか?」 涼司の言葉に、レンが笑みを深くする。そしてそのまま何も答えずに腕を上げると、腕の動きに合わせるかのように、暗闇からチャリオットが現れた。 本来、四頭のオナガーが引くはずのチャリオットは、しかし何故かその倍の数――八頭のオナガーによって動かされている。 よく見れば、後部の馬車が二台横並びで連結してあった。 「よ……っこいしょ、と」 馬車の部分から、水心子 緋雨(すいしんし・ひさめ)が掛け声と共に降りると、鮮やかな色の和服の袖が揺れ、綺麗に伸ばされた黒髪が後を追うようにその身に掛かる。――その手には、何故かダンボールが持たれていた。 緋雨が、「何事か」と視線を送り続ける涼司を気にも留めずに、ダンボールを広げ、連結されたチャリオットに向かって手を振った。 「何じゃ、緋雨。準備は任せたはずじゃが……?」 馬車の部分から、細かなフリルやレースがあしらわれた衣服に身を包んだ天津 麻羅(あまつ・まら)が降りてくると、緋雨は嬉しそうに笑った。 「こういうの、麻羅の方がセンスあるじゃない? それに『チャリオットを連結してカッコいいタンクに見立てるのじゃ!』って楽しそうに言ってたから、任せた方がいいのかな、と思って」 「ばっ……馬鹿を言うな! ギルドの代表がやるとゆうておるのじゃ、長を立てるのも年長者の役目じゃろう……わ、わしはそういう子供っぽい事は好んでおらんからな、仕方なく手伝う事にしたまでじゃ!」 緋雨の指摘に顔を赤くする麻羅だったが、言葉と違い行動は早かった。次々とダンボールを切り出し、緋雨に指示を出す。 涼司が目の前の光景にツッコミを入れる隙すらも与えずに、チャリオットが――見た目だけはそれっぽい――タンクに早変わりした。 「これはまた、すごいですね! このままでも十分戦えそうです!」 即席タンクの後ろから、ルイ・フリード(るい・ふりーど)が白い歯を剥き出しにして笑いながら現れた。 二メートルを超える巨体を誇るルイが、自分よりもはるかに大きな鉄塊、イロンVを見上げて更にその笑みを大きくする。 「アレと戦うんですね……ふふ、腕が鳴りますね!」 「そうです! 話に聞く所によれば、あのロボットはイコン並みの強さとの事……それならば! 私たち冒険屋もロボを用意して、戦うのです!」 言葉通り腕に力をこめてギチギチと腕を鳴らしているルイの足元で、ノア・セイブレム(のあ・せいぶれむ)が高らかに宣言した。 「なるほど、ロボにはロボをぶつけるのですね! ……ちなみにこちらのロボはどちらに?」 肝心のロボットを探して視線を泳がせるルイに向かって、ノアが指を指した。 ◇ 「何かですね、グレート・ルイの武器になれとか言われたんですが……そもそもグレート・ルイってなんすか」 眠そうな眼を擦りながらぼやくクド・ストレイフ(くど・すとれいふ)が目にしたのは――ダンボールに身を包み、まさに今、ダンボールロボにならんとしているルイの姿だった。 次いで、視線をタンクと化したチャリオットに向ける。ルイを見る。チャリオットを見る。 「グレートじゃなくて、ジャイアント、ですよ」 半眼のクドに向かって、ノアが親指をグッ、と見せる。 意味が解らずに何度か視線を往復させているクドに、ルイが駆け寄った。 「ルイさん一人じゃ危ないからルイさんの剣となり盾となって頑張る、とは……私、感無量の極みです!!」 「……いやいやいや、まだ何も言ってないし。承諾した覚えもないし。って言うか、また?」 肩を掴んで前後に激しく振るわれながら、クドは過去に武器として扱われた記憶を掘り返していた。 身体を激しく揺らされた衝撃なのか、武具として扱われそうになっている自分の労を省みてなのか、へにゃへにゃとその場に座り込んだクドに、ルイのパートナー、シュリュズベリィ著・セラエノ断章(しゅりゅずべりぃちょ・せらえのだんしょう)が近寄って、笑顔を見せた。 「クドっちが身体を張ってルイと一緒に頑張ってくれたら、セラの生まれた時の姿の写真をあげるよ☆」 最高の笑顔で口にされたその言葉に、クドは常人には見えない速度で立ち上がる。 その顔に、眠たげな表情は既に無い――どころか、何故か活気に満ち溢れていた。 「男、クド・ストレイフ……諸悪を滅する為ならば、武器でも盾でも何にでも!」 その言葉を待っていたかのように、ルイがクドの足首を掴んで持ち上げ、肩に担ぐと、チャリオットに乗り込んだ。 セラエノ断章がその横に立ち、腰に手を当てて胸いっぱいに息を吸い込む。と、握り締めた拳を高らかに上げて歌い出した。 「主題歌、『それ行け! 僕らの冒険ロボGRKC(ジャイアント・ルイ・クド・カスタム)!!』 ぱぱぱっ〜ぱん! (せいっせいっ) ぱぱぱっ〜ぱん! (せいっせいっ) ぱぱぱっぱっぱっぱっぱぱ〜♪ 行け! 行け! 僕らの〜冒険ロッボォー♪ 蜜柑箱アーマーを巨人に被せた傑作機〜♪ 武器は人畜無害の人間バットォ〜♪ 盾にもなる便利な人ッ材さぁ〜♪ 今日も何処かで悲鳴を察知 チャリオットタンクに運ばれ颯爽と〜♪ 『冒険ロボ! GRKC参上! (キラッ)』 どうせ被害はこちらの人材一人♪ 『戦いに犠牲は付物なの』 強大な敵が現ればこいつの出番『クドバァーット!』 最後の決め手だ!! 『クドバット・ホォームラン!!』 今日もやってくる平和な時間♪ それ行け! 僕らの♪ 僕らの冒険〜ロボォ〜♪(わーわー♪)」 ご丁寧に、合いの手やSEを存分に自分で付けながら歌い切ったセラエノ断章は、満足そうに胸を張った。 (気持ちいいー! ふふ……リアが居たら絶対に「真面目にやれ!」とか怒られるだろうなぁ) 頭の中で、頬を膨らませながら怒るリア・リム(りあ・りむ)を想像して、苦笑する。 ――パチパチパチ、と手を打ち合わせる音が響く。 「ふむ。中々どうして、素晴らしいじゃないか。テーマソング、か。これは終夏君の話も真面目に検討しなければいけないな」 「てめぇは……?」 散漫な拍手の音に涼司が振り向くと、そこには白衣の男、博士が居た。 線の細い身体をフラフラと揺らしながら近づく博士に、何故か奇妙な重圧を感じて涼司が後ずさる。 「見た所、この襲撃……中核は君のようだが」 「襲撃? 馬鹿言うな……おまえがあのデカブツの生みの親か?」 涼司と博士の視線が交差する。周囲の音をそこだけ切り取ったような緊迫感が流れる中、先に動いたのは涼司だった。 距離を詰める博士の視界から外れるように横に走り、飛ぶ。 「一撃で決めさせてもらう!」 叫び声と共に振るわれた剣が、音速を超えた斬撃となって博士に襲い掛かる。が、その攻撃は白衣をほんの少し切り取るだけに留まった。 着地と同時に振り上げられた剣も、僅かに身を反らせて避けてみせる。次の瞬間、涼司の胴にレンチを握りこんだ博士の拳がめり込んだ。 くの字に曲がる身体を無理矢理動かして、博士の手を取って力任せに背負い、投げる。鈍い音と共に、肩から千切れた博士の腕が飛ぶ。 転がる腕を見て涼司が目を見開き、慌てて振り返ると、そこには両腕を仰々しく広げた博士が笑っていた。 距離を取る為に後退した涼司の足に、先ほど投げ飛ばした腕――義手が当たった。 「何のマネだよ……笑えねぇ」 「身代わりの術の変型だよ。何、大昔の漫画で読んでね。使ってみたくなっただけだ」 「手品師にでもなった方が、お似合いじゃねぇか?」 微笑を浮かべる事を止めない博士を見て、涼司が嘲るように笑った。 そして、博士の背後に一瞬、視線を向ける。 「そっちがその気なら、こっちも一つ、面白ぇ物見せてやるぜ」 短く息を吐き出し、駆け出す。 視界から外れようともせずに、真っ直ぐに向かい来る涼司を見て、博士は眉根を寄せた。 涼司が何の工夫も無く、横薙ぎに剣を振るう。休む事無く次々に繰り出される斬撃を、博士は下がってかわしていく。 「特に学習もせずに無駄な攻撃を続ける人間……か、言うほど面白くもないな」 心底つまらない、といった表情を浮かべる博士に、涼司が口の端を持ち上げた。 「今だ! ブチかませ!」 その叫び声に博士が異様な気配を感じて振り向くと、眼前に迫っていたのは――クドの頭部だった。 これが単純な攻撃であったなら、避けるのは難しくなかったかもしれない。 だが、迫り来るその攻撃は、人の――青年の顔面。しかも、直立不動のその青年を振るっているのは、ダンボールに身を包んだ巨漢だった。 戦闘パターンに無い現実が視界に入り込み、僅かに反応が遅れる。 「唸れ! クド・バァーット!」 チャリオットで水増しされた高さのルイが振るうクドは、野球のバット、というよりもゴルフのスイングに近い軌道で博士の額をしたたかに打ち据えた。 衝撃に吹き飛ぶ博士の額と、クドの鼻から鮮血が溢れる。 「……どうだ! ビックリ人間ショーならこっちの方が上だろ?」 「いや、実際に身体張ってるの俺なんすけどね……」 勝ち誇る涼司を見て、振り回され続けるクドが鼻血を撒き散らしながら呟くが、その声は誰にも届かなかった。 |
||