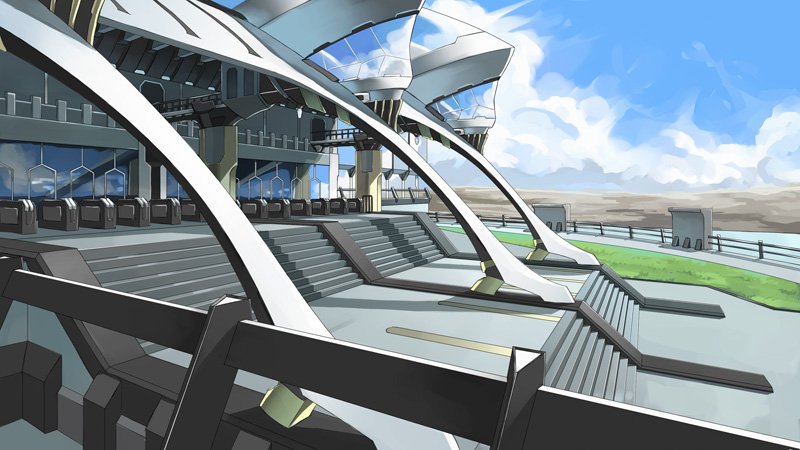リアクション
よみがえっちゃった過去や前世の記憶とやらのせいでツァンダの街なかで暴走者が続発しているころ。 * * * 彼の必死の祈りが通じたか。 「白! みんな、お待たせ!!」 ガラッと勢いよく引き戸が開いて、レンタル勇者コスプレに身を包んだセルファ・オルドリン(せるふぁ・おるどりん)が現れた。 「遅いぞセルファ! 何をしておったのじゃ!」 差し込んできた外の光にまぶしげに目を細めつつ怒る白に、セルファは顔の前で拝むように両手を合わせた。 「ごめんごめん! なんかさあ、予想外に事が大きくなっていっぱい集まったって携帯で教えてくれたじゃない? これは私1人じゃ大変だーと思って、こっちもかき集めてきたのよ。ホラ!」 セルファが横にどいて場所を譲る。 後ろには、名前をいちいち羅列すると何行に渡るか分からないのでここでは割愛するけど、正義を愛する心の持ち主が結構な人数で集まっていた。 「あ、集めすぎじゃないかの?」 魔王真人を勇者セルファがこてんぱんにして、反省させてオワリ、の筋書きだったのに、えらく話がふくれ上がってしまったことにあらためて気付いて、さすがにちょっと白もビビる。 「そんなことナイナイ。それにちょっとぐらい多すぎたって、正義側なんだからなんくるないって」 あははと笑って白の不安を軽く一蹴して、セルファはあらためて最奥の椅子に腰かけた真人に向き直った。 こほ、と空咳をひとつしてのどを整えると、勇ましく見えるよう一歩踏み出した体勢で指を突きつける。 「魔王真人!! ここで会ったが100年目! 神妙に観念して私の剣に倒れなさい!」 「セルファ、そのセリフはちょっといろいろ混じり過ぎておかしいぞ。ちゃんと練習してきたのか?」 推薦してやったじゃろう、ほら、その手の漫画とかアニメのDVDとか。 「う、うるっさいわね! 忙しくてそこまで手が回んなかったのよ!」 赤面しつつセルファはこれがその証拠だと背後の者たちを指す。 「と、とにかーーーく!! 私、勇者はあなた、魔王を倒す!!」 「それだとシンプルすぎじゃ」 やはりセルファに勇者役は無謀だったか。 (といっても、あとはもう1人しかおらぬしのう…) ああ、頭が痛い。 思わずこめかみに指を添えてしまった白の脇をすり抜けて、セレンフィリティがロングコートをなびかせつつポールダンサーのごとくリズミカルな足取りで前へ進み出た。 「ふふっ。さっそく私の出番のようね。 まずは私が相手よ、子猫ちゃんたち」 「私が、なんですって!」 「子猫ちゃんって言ったのよ。私が歩んできた艱難辛苦、修羅の道に比べたら、あなたなんか子供用ビニールプールに張られた温水につかってたまぬけ面のアヒル隊員も同然!」 くわっ! とセレンフィリティの目が見開かれ、まさに悪鬼のごとき気迫が噴き上がる。 「アヒルごときがこの私に勝てるわけないのよッ!!」 なぜこれほどまでに彼女は力説し、断言するのか? ここで説明しよう! 実はセレンフィリティにはかつて、セレアナという美貌の恋人がいた。 恋人と腕を組み、仲睦まじくデートをしていた途中、ふと目についた宝くじ売り場で1枚ずつ宝くじを購入。寄り添い合う2人のように、それは連番だった。 が。当選したのはセレンフィリティのみ。しかも大金の5億ゴルダだ。 あっという間に億万長者になってしまったセレンフィリティと一般人のセレアナ。それでも2人は愛し合う恋人同士だった。 「こんなあぶく銭、パーっと使って終わりにしちゃいましょ」 地球のラスベガスへ貸切ジェットで飛び、最高級ホテルの最上階スイートルームでイチャイチャしつつ、カジノへ。けれどそこでも大当たり。5億ゴルダは5000億ゴルダに膨れ上がってしまった。 しかもそこで彼女のツキは止まらない。 さらに調子に乗って株やらFXやらバイナリーオプションに手を出したら、そこでもドッカンドッカン大当たり。ついには地球が丸ごと買えるほどの大富豪になって、ついに夢のセレブ生活へ! それでも2人の愛は消えなかった。 「私たちの愛は永遠よ、セレアナ」 「私もよ。愛してるわ、セレン」 その愛に最初のかげりが見え始めたのは、その直後からだった。 やがて彼女の身の周りにはその巨万の富と美貌を目当てに雲霞のごとく怪しげな連中が群がり始めた。どこへ行くにも、それこそトイレにまでパパラッチがついてきて、プライバシーなどないも同然。2人のあることないこと、ないことないことが連日紙面を飾り、平穏だった生活が一転、どこまでも有象無象のやからにつきまとわれる、うっとうしい人生に。 当然のことながら、彼女たちの財産をねらって命をおびやかす者も現れた。 遠い親戚を名乗るあやしげな人物が続々と彼女たちを訪ねてきた。偽造された手紙、遺書、はては書いた覚えのないラブレターや婚姻届けまで! それらを偽物と立証し、無効にする裁判漬けの日々が何年も続いた。 「もう疲れたの……追わないでちょうだい…」 その言葉を置手紙に、セレアナは消えた。陰謀で消されたのか、去って行ったのかはあれから何年も経った今でも不明のままだ。 「――だからってお金をうらんだりはしないわ。お金は物よ。使い勝手が良くて、便利な道具。変わるのは人。信じられないのは人の心…。 愛なんか信じない。人なんか信じない。決して裏切らないのはマネーだけよ」 持ち上がったセレンフィリティの手には、いつしか機関銃が。 「!」 それが、驚きに目を瞠るセルファを蜂の巣にした。 「みんな、みんな!! 人なんかこの世から消えてしまえ!!」 セルファの後ろに並んでいた人影に向かって機関銃を連射する。弾切れになれば、即肩にかけてあった対物ライフルを引き下ろし、これも撃った。それを撃ち尽くしたら、対戦車バズーカも。 「うおおおおおおおおおおおおおおおおっ!!」 爆風と黒煙が上がるなか、足元に転がしてあった日本刀を抜いて、シュヴァルツを片手に敵群へと突貫する。 目につく者はかたっぱしから全て一刀の下斬り伏せ、遠くの者は眉間を撃ち抜く。それは、動く者がいなくなるまで止まらなかった。 いや、だれも動かなくなっても彼女の攻撃は止まらない。特別改造したブルドーサー、通称キルドーザーに乗って何度も何度も、何度も何度も、執拗なくらい往復して、元が何であったかも分からないくらいぺちゃんこにして、ようやく彼女は止まった。 キルドーザーの溶接された内側で、セレンフィリティは勝利のおたけびを上げる。 「アヒャヒャヒャヒャヒャヒャヒャヒャヒャヒャヒャ!!!! どいつもこいつも! 金、金、金、金! マネー、マネー、マネー!!! 金が欲しけりゃこのあたしを倒してからにしな!!!」 「……な、何? この人?」 アヒルがどうのと叫んだきり焦点の定まらないうつろな目をしてへらへら笑っているなと思ったら、突然口角泡吹いて高笑いしだしたセレンフィリティに、セルファは思わずあとずさった。 説明を求めるセルファの視線に、白は深々とため息をつく。 「だから言うたじゃろ。外に放置しておくとアブナイやつらを集めたと」 「そう説明を受けたからここにいたわけだけれど、これはちょっとひどすぎるわね」 闇色の強い壁を離れて光のなかへ進み出たのはセレアナ・ミアキス(せれあな・みあきす)である。 「術で創作された脳内設定とはいえ、彼女のなかで私が行方不明にされてるってどういうことかしら――っていうか、今のってこの前借りてきたDVDのコメディ映画のあらすじまんまじゃないの」 あれだと私、いくつよ? 少なくとも10歳は歳とってるわよね、と眉をしかめつつ、高笑いして今にも両手の銃をぶっ放し始めそうなセレンフィリティへと近付く。 そして、背中越し、ふわっと両腕で包み込むように抱き締めた。 「ねえセレン。あの映画のように、あなたにお金よりも大切なものがあるって少しずつ教えてあげるには、今はちょっと時間が足りないわね」 「……う…?」 「だから、短期間で・集中的に・効率良く学習させてあげる」 どこぞの通信教育ばりの宣言をして、セレアナは強気の笑みを見せるや人目もはばからず、いきなりセレンフィリティの唇を奪った。 「!!」 セレンフィリティは驚き、引き離そうとするが、すでに両手首はセレアナにとられている。 そのまま両手を後ろ手に回されて、為す術なくセレンフィリティはセレアナと唇と、それ以外の露出している肌部分を親密に密着させた。 触れ合った肌が互いのぬくもりを伝え合い、まじり合って、同じぬくもりで調和する。 まるで1つのもののように。 そしてセレアナは容赦なく、セレンフィリティの息を奪い続けた。 「まったく。しようのないおばかさんね」 紅潮したほおのまま、くたっと気絶したセレンフィリティの体を両手に抱き上げ、ふふっと笑う。 お姫さまのように運ばれていくセレンフィリティの面には、満足そうな笑みが浮かんでいた。 |
||