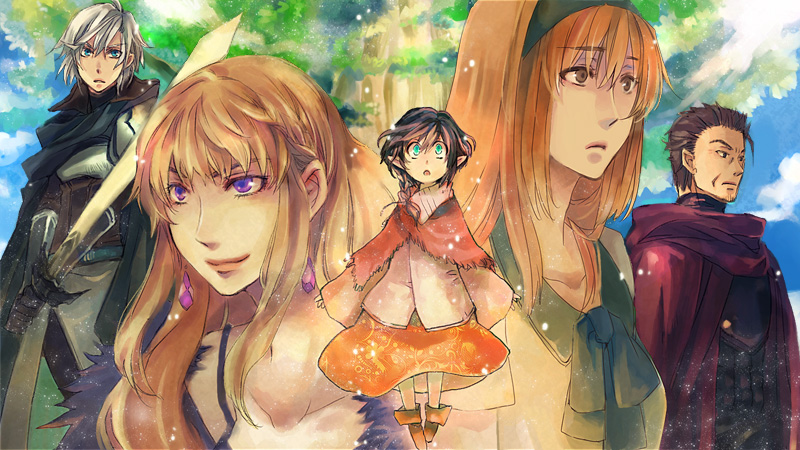リアクション
◇ ◇ ◇ 今は治まったと言うが、あの後も何度か起きていた地震によってか、エレメンタルドラゴンの棲処に至る入口は塞がってしまっていた。 消沈して、とりあえずルーナサズに戻った清泉 北都(いずみ・ほくと)達を、イルダーナが目覚めた翌日にはすっかり元に戻ったトゥレンが見かけて、どしたの、と声を掛ける。 「ふうん」 話を聞いて、トゥレンは何事か考えた。 「……あんたら、魔力どんなもん?」 「え?」 「俺も自慢できる程でもないしな。 こういうの、アヌが得意だったんだけど……」 ブツブツ言いながら、ちょっと待ってて、と歩いて行き、暫くして、彼は杖を手に戻って来た。 「それは?」 クナイ・アヤシ(くない・あやし)が訊ねる。 「龍の杖。選帝神様に借りて来た。じゃあ行こうか」 「何処へ?」 「エレメンタルドラゴンのところだよ」 龍を駆り、確かこの辺だなあと彼が向かった場所は、龍の背山脈の山中、特に特出したものは無い場所だった。 此処は? と訊ねると、「“震源地”だよ」とトゥレンが答える。 それで理解した。 此処は、エレメンタルドラゴンの居る場所の、真上だ。 「ちょっと記憶に自信が無いから、暫く話しかけないでね」 不安なことを言って、とん、と地面に杖を立てると、トゥレンは呪文を唱え始める。 杖から現れた光の線が、踊るように紋を描きながら広がって行き、やがて魔法陣を描き上げた。 す、とそこから杖を抜いて、トゥレンは陣を出る。 指先で北都達に、中に入るように指示し、最後の一言を呟いた。 一瞬後、北都達は見覚えのある地の底にいた。 以前見た龍の形をした光の塊は、今もそこにあって、けれど、以前のような苦しそうな雰囲気は感じられない。 「もう大丈夫、ですか?」 返答は無い。 けれどそこにある穏やかな気配に、北都とクナイは安堵した。 「……よかった」 呟いた北都の口から、歌が零れる。 ウラノスドラゴンの前でしたように、巨人族の歌、大地を称える、故郷を想う歌だ。 気がつけば、目の前にトゥレンがいて、北斗は慌てて歌をやめた。 「時間切れ」 トゥレンは笑う。 あともう少し居たかったけれど、仕方がないのだろう。 礼を言おうとした北斗は、自分が両手に何かを持っているのに気付いた。 光、だ。 「え、っと……?」 両手の上に乗っている光に戸惑う北都に、トゥレンが言う。 「両手を合わせるように握って、固めて」 言われた通りにすると、合わせた手の中で、光が収まる。 開いて見ると、そこには透明な宝石があった。 「ドラゴンドロップだよ。凄いね」 超稀少品だよ、とトゥレンは笑う。 クナイは足元を見つめ、心の中で、エレメンタルドラゴンに礼を言った。 そしてどうかこれからも、パラミタを、大切な人のいるこの世界を護って行って欲しい、と願った。 |
||