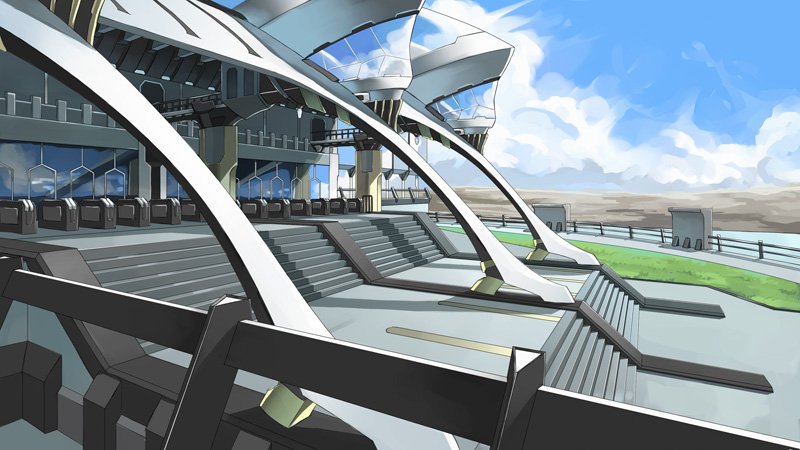リアクション
「だれにも俺の毛は刈らせねええぇぇぇぇぇぇぇえええ!!」
ドップラー効果を伴って追い抜いて行った松原 タケシ(まつばら・たけし)の姿に、メルキアデス・ベルティ(めるきあです・べるてぃ)は目を丸くした。
「なんだ? ありゃ」
しばーらく後ろ姿を見送って、ああと思い当たる。
「タケシか、あれ」
メルキアデスとタケシの間に面識はなかったが、とある事件により、彼の方はタケシを見知っていた。
それどころか体をのっとられていたタケシを元の彼に戻すためにひと役買った者でもある。
「あの様子だと、まーたあいつ何かに巻き込まれてんのか」
あきれると同時にピンときた。
ここはまたもや俺様の出番じゃね?
タケシが巻き込まれた事態を収拾する → 感謝される俺様 → ツァンダの偉い人から表彰される → 昇格のチャンス!
いつものすがすがしいほどみごとな論法である。
「なあ、タケシを追ってみようぜ、フレ――」
振り返ってみて、そこにいつものパートナーの姿がないことに気付いた。
そうだ、今日は別行動してたんだった(汗)
いるのは外見がポンコツなら中身もポンコツのロボプロトタイプ・アクト ツー(ぷろとたいぷあくと・つー)である。
「タケシ?」
とつぶやいて、ぼーっと突っ立っている。
駄目だ、パパはあてにならない。
メルキアデスは携帯を取り出した。
「ああ、隊長。……はぁ? 今すぐですか?」
通話の相手は同じ教導団のマルティナ・エイスハンマー(まるてぃな・えいすはんまー)だった。
せっかくの休日、新しい秋服を揃えようとショッピングを楽しんでいたというのに、いきなり何を言ってくるんだろう? この人は。
マルティナは眉をしかめつつ、まるでそこにメルキアデスがいるかのようにまじまじ携帯を見つめる。
『何か用事でもしてた?』
「え? ……まあ、それはそうでも…」
ないと言えばない、あると言えばある、の微妙な状況だ。
1人だし。ひと通り買い物は終わって、お茶でもしようかと思ってたとこだったし。しかも場所はツァンダだ。
これがヒラニプラだったら「残念ですね、お力になりたいのはやまやまですが、距離が離れすぎですわー」とか適当なこと言えたのに。
「何があったんです?」
『説明はあとあと! 超緊急事態発生だから! 一刻も早くタケシのやつを捕まえないと! とにかく、すぐ来てくれ!!』
(タケシって、先日教導団でゴタゴタを起こした人よね?)
これは本当に緊急事態なのかも。
「そこ、どこですか?」
あきらめ半分、通話口をおおってため息をそっとついて、マルティナは詳しい場所を聞こうとする。
そのときだった。
『――うわっ!! ちょ! 何やってん――』
――ガシャンッ!! ブツッッ! …………ツー…………
地面に落ちたような音がして、いきなり携帯が切れた。
「た、隊長!?」
ええっ!? これってもしかしなくてもかなり非常事態!?
デパートの袋をガサガサ揺らしながらマルティナがたどり着いた先。
そこでは、だれかを羽交い絞めにしているメルキアデスの背中があった。
「タケシ」
「だーかーらー! 違うってーの!!」
「タケシさん? 確保できたんですか?」
回り込んでみると、それはメルキアデスのパートナーのアクト ツーだった。
「おおマルティナちゃん、いいところに!」
マルティナに気付いたメルキアデスが助かったと笑顔になる。
「もう落としたケータイ拾う暇もなくてさー。きっとマルティナちゃんだったら機転利かせて来てくれると信じてたっ」
「何されてるんです?」
「いや、パパが――」
そのとき、マルティナに気をとられたメルキアデスの拘束がわずかに緩んだ。するりと抜け出たアクト ツーは、ひょっこり側路から現れた男性に後ろから近付くと、ぽんと肩を叩いた。
「タケシ」
「え? 違いますけど…?」
「タケシ、どう、どう」
「はあ!? ――って、うわ!」
いきなり変なロボに抱きつかれた男性は、びっくりして買い物袋を落としてしまった。
ガシャッと何かが潰れた音が…。
「わーーーっ!! 卵が!!」
あちゃーっ、とメルキアデスは思わず顔に手をあててしまう。
アクト ツーは不思議そうに小首を傾げてあせる男性を見つめると、違うと言わんばかりに首を振って、またひょこひょこ歩き出し、今度は女性へ…。
「タケシ」
「え?」
「パパ、彼女は女性だから。ほら、スカート履いてるだろ?」
言っても無駄だ。オンボロロボのアクト ツーには男女の区別がつかない。
彼にとって自分以外の者はほぼ全て「息子」なのだ。パートナーのメルキアデスですらそうなのだから、他人の区別がつくわけもなかった。
メルキアデスに言われて、アクト ツーは不思議そうにスカートを引っ張って持ち上げる。
「キャーーーっ!! 痴漢っ!!」
ハンドバッグでぶん殴られたアクト ツーは吹っ飛んで、別の男性にぶつかって一緒に転がった。
「――ぶっ。な、なんだぁ? こいつ」
「た、タケシ、どう、どう」
「ああああ……すみません、どうも、すみません!」
あせりまくったメルキアデスがぺこぺこ女性や男性に頭を下げている間にも、アクト ツーはひょこひょこ歩いて行く。
そこに横から自転車がチリリリン。
「パパ、危ないっ!! って……え?」
「わっ! バカ! どけよ!!」
アクト ツーを助けようと駆け寄ったメルキアデスとアクト ツーを避けようとした自転車がぶつかった。
「うっひゃーーー!」
ドカッと跳ね飛ばされたメルキアデスはそこにあった喫茶店の立看板を巻き込みつつ倒れる。
もう何がなにやら。
それからさらにそんなことが数回繰り返され、ようやく通りの端っこでアクト ツーを再び羽交い絞めにしたとき、どちらがより多くの傷を負っているか、マルティナには甲乙つけられなかった。
「タケシ」
「をいパパ! パパってば! よく聞け! ここにいるのはみんなタケシじゃねーし!
そもそもタケシ、おまえの息子じゃねーだろっ!」
「タケシ」「タケシ、どうどう」を繰り返し、もがいて抜け出そうとするアクト ツーを必死に押さえ込む。
「……それで、タケシさんはどちらですか…?」
マルティナの忍耐は、危険水域をかなり下回るところまですり減っていた。
「あ? ……えーと。あっちへ向かって走って行ったなぁ」
「それ、いつのことです?」
「マルティナちゃんの来る、10分くらい前」
「……私がここへ来て、もう大分経つんですけど…」
ああ、言っても仕方ないかも。隊長はこういう人なんだから。知ってるはずでしょ? マルティナ。
深々とため息をついて、なんとかイライラを押し戻そうとする。
「それで、彼が何をして、どこへ向かっていたか分かってるんですか…?」
「え? 全然。走ってったのを見ただけ。ただあいつのことだからきっと何かに巻き込まれてるんだと思って追跡しようとしてたんだけど、パパがこんなになっちゃったから」
メルキアデスが一句一音発するごとに、マルティナの背後でゴゴゴゴゴ…という効果音が聞こえそうな勢いでドス黒い暗黒のオーラが膨れ上がる。
「つまり、ただここを走って行っただけの人を追いかけるのに、休日の私を呼び出したというわけですね? しかもあんな、まぎらわしい電話の切り方をして…!」
「ま、待って、マルティナちゃんっ!! 電話は不可抗力! パパがいきなりあんなこと始めたからあせって落っことしたわけで、決してわざとじゃ――」
「……隊長。私ね、ここへ来る道すがら情報収集してきたんです。なんだか今ここでは、催眠術みたいなものにかかって暴れて迷惑かけている人たちがたくさんいるんですって」
「へ、へえ〜…。すごいね、マルティナちゃん…」
早くもいやな予感がしてきて、メルキアデスのほおが引きつる。
「私、優秀ですから。その場合の対処方法もちゃんと教わりました。すごく簡単なんです。衝撃を与えればいいんだそうですよ――気絶するほどの」
マルティナの手がスナイパーライフルを持ち上げる。
「待って! 待って! それ、しゃれになんないからっっ!!」
「暴れているってことは、きっとアクト ツーさんもそうなんですね。今から彼を正気に返してあげます。ちゃんと押さえててくださいね、隊長。
あ、そうそう。この角度からだと隊長にも当たっちゃうかもしれませんけど、べつにいいですよねえ」
にっこり天使のごとき無垢なほほ笑みを浮かべて。
マルティナは容赦など微塵も見せず、自分にはない、男性の弱点へ向けてゴム弾を発射した。
近距離から。
しかも連射で。
「アーーーッヒャヒャヒャヒャヒャヒャヒャ〜〜〜〜ッ!!」
「まったく。私のせっかくの休暇を邪魔するなんて、そんな隊長はお仕置きをされて当然です」
長い桃色の髪を肩向こうへ払い込み、マルティナは背を向けて立ち去る。
あとに残ったものは――――……
……合掌。
* * *
さて。
まあメルキアデスの勘が大ハズレていたのかといえばそうでもなく。
タケシは今、占い師の術によって自分をヒツジと思い込み、自分以外の者は全て自分の毛を刈ろうとしているシープ・シェアラーに見えていた。
「刈られてたまるか……刈られてたまるか……」
呪文のようにぶつぶつつぶやいては油断なくきょろきょろ辺りをうかがっている彼の近くでは、
「お館さま、お任せください。私が必ずあなたをお守りします! この刀に賭けて誓いましょう!」
同じく術にかかって自分は戦国武士だと思い込んだ
リーレン・リーン(りーれん・りーん)が、無駄に無意味に抜き身の剣をぶんぶん振り回している。
はっきり言って、傍目にはかなりアブナイ2人組だ。
そんなだから目撃情報もたくさん出てくる。
「いた、タケシだ」
周臣 健流(すおみ たける)が通り1つへだてた向こう側にタケシとリーレンの姿を見つけて駆け出した。
「あ! 待て、健流!」
それに気付いた
コア・ハーティオン(こあ・はーてぃおん)が制止の手を伸ばすが健流は止まらない。
「タケシ!」
「く、来るなあああっ!! 来たら容赦しないぞ!!」
「お館さま! ここは私が!!」
逃げ出したタケシと健流の間にリーレンが立ちはだかる。
ことわっておくが、これは2人が互いを認識できて連携を取っているからではない。ひたすら逃げようとするタケシとお館さまを護ろうとするリーレンの行動が合致しただけのことである。
「リーレ――うっ」
「たああああっ!!」
リーレンが大上段から剣を振り下ろす。
それを受け止めたのはコアだった。
数太刀かわしたあと、リーレンは小さく舌打ちをして走り去って行く。
あとを追おうとする健流の肩を掴み、今度こそコアは止めた。
「あまり無茶をするな、きみはまだ病み上がりの身だ」
コアは彼の身が心配だった。
遺跡から連れ出した直後、彼はすぐさま病院へ搬送された。コアたちが運んでくれた薬は彼の持病の発作をある程度緩和させていたが、強度の発作を長時間引き起こしていた結果、健流は長らく面会謝絶で入院することになったのだ。
そしてようやく解除され、見舞いに来たコアたちからタケシたちの現状を聞いて、強引に退院してきたのだった。
「……もうなんともない」
その手を放せ、と言わんばかりに振り払った健流は再び走り出そうとする。
それを、壁に腕を組んでもたれた
高天原 鈿女(たかまがはら・うずめ)が冷静に制した。
「コアの言うとおりよ。あなたが本調子でないのはあきらか。でもそれは、あなた自身分かっていることでしょう。
ここで無茶をして、また病院のベッドへ逆戻りしたいの?」
「…………」
「大丈夫! そんなことにはならないさ! なあ!」
ばん! と背中を叩いて、笑顔でコアが請け負う。
「友というのは大切な存在だからな。きみの気が逸るのもよく分かる。なぁに、今度は私がついている。何かあってもあのときほど深刻にはならない」
また安請け合いをして、とその姿に鈿女はふうと息を吐く。
「ただ、だからといって無茶はしてくれるなよ? きみが彼らを心配しているように、きみを心配する者だって少なからずいるんだ。
さあ、さっさとタケシたちを追おう」
「――あの」
タケシやリーレンの消えた側路へ走り出したコアを、今度は健流が呼び止めた。
ん? と振り返った先、呼び止めたのは自分のくせに、健流は彼が振り返るとは思わなかったという表情でうっと詰まる。目をそらし、逡巡するような間を開けたのち。
「…………
すまない……」
健流はのどにつかえたものを押し出すように、いかにも言葉にしづらそうに小さくつぶやいた。
「なんでもないことだ。私たちは友だからな!」
コアは一点の曇りもない、輝く笑顔で応える。
「どうしたの? ハーティオン」
健流との距離が開くのを待ってから、鈿女が訊いた。
「……いや。なんかこう、だれにもなつかない野良ネコが少しだけ体に触れさせてくれたときのような、妙に感慨深いものがこみあげてきて」
健流を野良ネコに例えたことに、ぐるりと目を回して鈿女は少しあきれた様子を見せる。
「それ、彼には言わない方がいいわよ」
「もちろんだ」
鈿女の忠告を本当の意味では理解していない顔つきで、コアは真面目に応じた。
「にしても、ラブのやつがいてくれたら空から居場所を探索してもらえるんだが……何をしているんだ? あいつは」
なんとはなし、空を見上げつつぼやいたときだった。
「あたしの時代がキター!!」
耳をつんざく奇声が響き渡る。
「やーーーっと思い出したわ! なんてすがすがしいの! あたしは世界の女王、みんなに愛されるラブちゃんだったのよ〜〜〜」
喜々として飛ぶ
ラブ・リトル(らぶ・りとる)が、コアの視界を右から左へ横切って行った。
「ラブ!?」
「やれやれ。あの様子だと、あの子も例の占い師とやらに遭遇したようね。
まあいいわ。30センチのハーフフェアリーにできる事なんてたかが知れているでしょう。あの子のことは後回しにして、先にほかの事から片付けていきましょう」
まったくもう、よけいな手間を増やしてくれて、というふうに首をふりふり鈿女は側路へ走り出す。
その後ろを健流が。
「……ラブ」
コアはラブの消えた方角に少し長く目を止めていたが、結局は彼もまた2人に続いて追跡へと入った。
これがとんだ判断ミス、大失態だったことに彼らが気付くのは、そう遠くない未来のことだった。