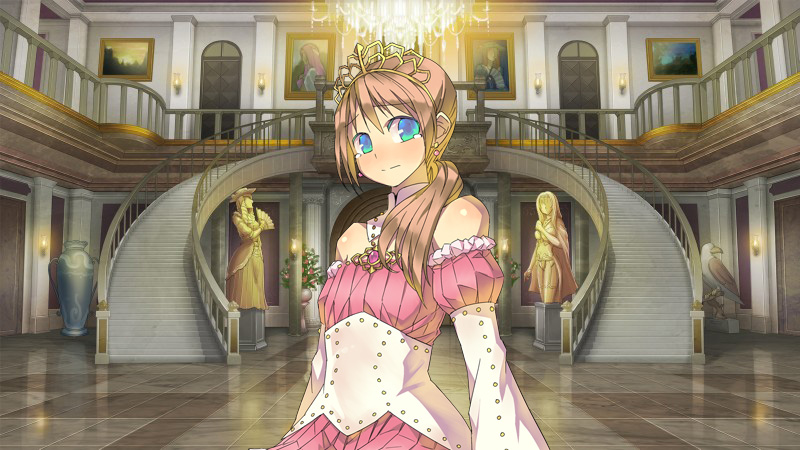リアクション
第4章 塔でのできごと
「……何度目でしたかしら?」
「確か、これで五度目だね」
「……流石に疲れてきましたわね」
アナスタシア・ヤグディン(あなすたしあ・やぐでぃん)は息を整えると、塔を見上げて腕を組んだ。
三階建て――に見える、つまり細長い窓と居館や城壁との高さの比較などから――の塔に挑戦すること五回、その五回とも何らかのトラップに引っかかって外に放り出されている。
円形の塔は残っている品々から見て、魔術の研究用に建てられたもののようだった。魔術の成果だの高価な書物や器具は魔法使いにとっては命にも等しいもので、ということは当然他の場所より警戒がなされることになる。
「だからこそ、それだけ重要なものが眠っているということですわ!」
アナスタシアは力強く言ったものの……、
「どーですか、うまくいってますか?」
のほほんとした顔の守護天使がやって来ると、アナスタシアはあからさまに苦々しい顔をした。
「……うまくいっているように見えますの?」
「えーと、うまくいってないんですか? じゃ、うまくやるまで何度でも挑戦すればいいですよ!」
何かに影響されたのか、ぴかーとかぺかーとか擬音が付きそうな、何も考えていない朗らかな笑みを浮かべる守護天使。再びアナスタシアが「それは少し楽観的過ぎるのではなくて?」とか言っていると、目ざとく見付けた「天敵」がやってきた。
「殺雪だるまの次は、お花畑を蹂躙して血と破壊をほしいままにする堕天使ってところかしら?」
目をきらーんと光らせて(勿論、からかう意味で)やってきたのは、マリエッタ・シュヴァール(まりえった・しゅばーる)だった。
「……またですか」
「またって何よ、失礼ね。さすがに堕天使なことはあるわね、潰されて死んでいった数百の命を一顧だにしない」
ちょっと意地の悪い笑顔で、からかう気満々で――いや、マリエッタがそれ以外で守護天使に用があるとは思えないのだが。
「そんな堕天使にもチャンスを上げるわ。これから塔に入るの、先頭に立ちなさいよ。どうせ格好イイ所見せたいんでしょ?」
「はあ!?」
「……もう、からかうのは止めなさい」
後ろからマリエッタのパートナーである水原 ゆかり(みずはら・ゆかり)が軽く制止するものの、マリエッタは譲らなかった。余計なことになる前に帰ろうとする守護天使の首根っこを掴むと、前に立てる。侵入者が人質を取ったような扱い。
「いざという時には盾になってよね」
「……いや流石にそれは人道的な観点からどうなんでしょう?」
「大丈夫よ、死なないから。ちょっと痛い目に遭うかもしれないけど」
慌てて自分に“禁猟区”をかける守護天使を、ゆかりはちょっとかわいそうに思った。が、危ない罠もなかったし問題ないだろうと納得し、マリエッタに続いて塔に続く短い階段を登り、一枚の扉を開けた。
アナスタシアや他の契約者も彼女たちに続く。
「財宝の場所ですが、私はこの塔に隠されているんじゃないか? と推測しているんです」
アナスタシアらにゆかりは話しかける。
「秘宝というのは必ずしも金銀財宝そのものを意味するものではなく、それを手にすることにより無限の富を生み出したり、あるいは強大な魔力を得ることができたり……といったものじゃないかしら。
ましてやその城に魔女が住んでいて、研究を行っていたとすれば、当然、その研究こそがカギを握るのであって……」
「そうですわね」
「探検家が秘宝を持ちだせなかったのは、それが塔や城の敷地内部から持ち出せないよう、魔法的なプロテクトをかけていたのではないか? と」
「ええ、その可能性は十分ありますわね」
塔の中は狭かった。外観と同じ円形をしており、側面にはガラス窓があって、四方から採光と換気ができるようになっている。
一方には大きなかまど、窓の下には机とイスや低い棚、壺などが並べられ、窓がない壁は天井まである本棚で埋まっていた。いかにも研究室といった感じだ。
かまどの反対側には階段があり、二階、三階と続いているが、中央に魔法陣や大きな窯があったり、実験器具の違いがあったりするけれど、基本的には似たようなものだ。
「魔女って言えば私も魔女だし、何か分ることがあるかもね」
マリエッタが頷く。
ゆかりとマリエッタはそれぞれ本棚の背表紙の字を辿り、適当な本を幾つか引き抜いて読み始めた。
中身は基本的なものから本格的なものまで、各種の魔術の本や資料が揃っていた。中には本人の手書きらしい本やノート類も多く混じっている。古風で上品だが、やや殴り書き気味の筆跡が多い。
中身の多くはパラミタ内海、特にこの島周辺を中心とした自然だった。
手書きのものは博物誌のようになっており、動植物についての細かい記述が豊富にあった。
「薄暗くて読みにくくありませんか?」
冬山 小夜子(ふゆやま・さよこ)は窓を開けると、蝋燭に火術で火を灯した。LEDランタンも持っては来たけれど、やはり調子が悪いのか光量が低かった。
「私たちも調べましょうか。その前に少し掃除をした方がよさそうですけど……」
周囲にうっすらと埃が積もっているのを見て、小夜子は指先の埃を外に払った。
彼女は普段の露出度の高い崑崙旗袍ではなくラバースーツに身を包んでいる。尤も、どちらも身体の線が露わであることには違いがない。
「掃除かぁ……罠とか発動しない? 直接触るのは危ないかも? これならたとえ爆発してもましかな?」
綺麗好きな小夜子に、鳥丘 ヨル(とりおか・よる)が林で拾ってきた木の棒を見せながら注意を促す。
ヨルの横で、同じく木の棒というか木の根というか、要するにゴボウを同じように握ったレオーナ・ニムラヴス(れおーな・にむらゔす)が、
「ええ、このゴボウさえあれば契約者の能力も装備も何もいらないわ! そう、全裸だっていいの!
……あ、確か『石橋は叩いて叩き壊す』と言うからね。アグレッシヴに行かなきゃね」
「……そうですわね、ご一緒に探索致しましょう。その、方法はお任せしますわ。全裸は困りますけれど」
小夜子はアナスタシアと一緒に、二人を見比べて、くすくすと笑った。同じ棒を同じように握ってても、全く正反対なことを言うものだから。
小夜子はいつも通りの力が出ず、窓を開けるにもひと苦労だったことに不安を感じていたが、それですっかり気分が晴れてしまった。
「しかし……、アナスタシアさんは大丈夫です? 契約者じゃ無いですけど……」
「あら、ご心配ありがとうございますわ。私、身体はどうともありませんわよ。
確かにこの島には何かの力が満ちていて、干渉されて、魔法が封じ込められているような感じはしますけど」
アナスタシアは、掌からぽんぽん、と光の球を出すと、天井に放った。それはゆらゆらと揺れて天井で留まり、蛍光灯のように部屋を明るくする。
「攻撃的な魔法は表に出せないようですけれど、こういったものは問題なさそうですわ」
「そうですか。ところで、さっきの罠は大丈夫でしたか?」
アナスタシアの長い髪や、濃紺の服――探検なので今日は白いブラウスにジャケットとハーフパンツで、イギリスの寄宿舎の少年風だった――にも埃が目立っていた。
「これが終わったらお風呂に入った方が良いですわ。船医の方が用意している筈ですし……」
小夜子が言うと、レオーナが顔を輝かせる。
「ええお姉様、あたしもお風呂ご一緒します!」
「……レオーナさんったら。じゃあ、始めましょうか」
小夜子は苦笑する。そうして一斉に探検を始めた。
ヨルはツンツンと木の棒であちこちを突き、第六感で危なそうなものはさらに慎重に、“サイコキネシス”でふよふよ浮かせている。
「どんなトラップでも、お姉様と一緒なら恐くないの!」
レオーナはぴたっと壁や床に張り付き、犬のように上半身を下げて、鼻をひくひく、匂いをくんかくんかしながら四つん這いで突き進んでいく。
小夜子は二人が触って問題なかった場所の埃を払いつつ、本棚を眺め、実験道具を見て回った。
「薬学、薬草学、生物学……植物学、動物学」
「こちらは、天候、地形、四大元素……ですかしら?」
蓋つきの机を上げると、中に乾燥した種々のハーブが入っていた。その中に、切られてなお瑞々しい花が混じっている。
「まるで博物館ですわ」
「キャー、お姉様、こわ〜い!!」
小夜子の横で覗き込むアナスタシアの隙を突いて、レオーナがしがみついて、Gカップを惜しげも無く押し付けた。
(ふふふ、お姉様との仲を深めたり、既成事実を作って「GL的な関係」として周囲に認知させてやるわ!)
「きゃっ!」
その勢いでアナスタシアはよろめき、机の中に手を突いた。すると……、もわもわっと白い煙が顔を直撃し、彼女は不意に強い眠気に襲われて、ごちんと机の中に突っ伏した。勢いで、蓋がバタンと閉まり、机にサンドイッチされる。
(きっと謎を解いて、この城を、あたしとお姉様のマイホーム=愛の巣に……)
妄想を続けるレオーナだったが、さすがに、小夜子が助け起こそうとするのを見て、ゴボウを差し込んで手伝った。
アナスタシアはクラクラする頭を押さえ、
「さっき、全裸でもいいと仰いましたわね……それならゴボウを剥いて皮で服を作って差し上げますわ。それから進路相談の続きですけれど、ここで魔術を学んでゴボウ農家になってはどうかしら?」
「ちょっと大丈夫アナスタシア? 休んだ方がいいよ」
ヨルは秤やすり鉢を見て回っていたが、ふらふらのアナスタシアを見て、椅子を勧めた。
「みんな、休憩にしようよ。ほらお茶。おいでよアナスタシア、シール入りチョコもあるよ」
「ええ。少し休ませていただきますわ……、……きゃあああ!?」
アナスタシアが アナスタシアが沈痛な表情で頭に手をやりながら、椅子に座る。と、その時……。座った途端、その姿がかき消えていた。
「うおっとぉ!!」
と、同時に、上階から別の、男性の大きな声が響いてきた。
*
少し前の事である。
千返 かつみ(ちがえ・かつみ)と三人のパートナーは、百合園の生徒たちを一階に残して、塔の上階を見て回っていた。
慎重に歩みを進めるかつみの横を
千返 ナオ(ちがえ・なお)は
ノーン・ノート(のーん・のーと)を肩に乗せ、通り過ぎて行ってしまう。更に
エドゥアルト・ヒルデブラント(えどぅあると・ひるでぶらんと)も続く。
「気を付けろよ、初心者になったつもりで注意して進まないとな」
言いつつ、かつみは急いで歩調を合わせる。
彼の手には、輪ゴムがあった。これを指をピストルにして発射すれば、何かの役に立つかもしれない、と思ってのことだ。
「ま、確かに冒険ってきくとわくわくするよな。秘宝そのものというより、秘宝を『見つける』っていうのがさ」
だから、先に行きたくなる気持ちも、分かる。
「だからって、どんどん進むな」
「一応私たちも気をつけてるから大丈夫だって。むしろかつみの方が危ないよ」
エドゥアルトが振り返って言うが、心配してばかりのかつみの耳に入っていないようだ。
「だから振り返るなって、おいノーン」
ノーンはナオの背中から身を乗り出して、本棚を食い入るように見つめている。
「おっ、これは……」
「危ないって、何かあったら取ってやるから。で、どれにするんだ?」
「どれということもないが……魔女がどんな魔法を研究していたのかがわかれば、秘宝の内容にも予測がつくかもしれないな」
早速本を一冊手に取り、うむうむ、と頷いているノーンに、エドゥアルトとナオがわくわくした顔で話に加わる。
「やっぱり魔法関係かな?」
「魔法のオーブとかかもしれないですね、エドゥさん」
「……ふむふむ。これは空間の干渉と保存に関する魔法のようだな。私にとっては、これがお宝だな。
私はここでちょっと本読んでるから、みんなは先へ……」
ナオの肩からひょいとテーブルに飛び降りた彼を、かつみは見過ごさなかった。
「ノーンも一人でうろうろするな」
「いやだー私はここで本読むー、おたからー!」
かつみはひょいと、ノーンを取り上げたようとしたが、ノーンは机の上に落ちた本にしがみついたまま、手足をジタバタさせた。かつみは眉をひそめて力を入れノーンを持ち上げると、屋上への階段を上った、が……。
「ほら、行ってみるぞ――うおっとぉ!!」
ノーンが、かつみの手からぽーんと放り投げられて、宙を舞う。かつみの片足は、太ももの付け根まで階段の一部に沈み込んでいた。
階段の数段は本物で、その先一段が幻覚だったのだ。ナオはノーンを見事キャッチすると、ツンツン、と階段をつつく。かつみの嵌った一段以外は本物のようだ。かつみの横をすり抜けて上まで上がるも、
「これ、絵で書いてるだけですよー」
屋上に続く天井扉に触れてから、ナオが振り返って報告する。
エドゥアルトは苦笑いしながら深いスリットに嵌ったまま動けないかつみを引っ張り上げ、三階の部屋まで連れて行く。
「はい、ハーブティいれてきたから少し落ち着いて」
「……俺は、落ち着いてるぞ」
「はいはい」
むすっとするかつみにエドゥアルトは優しく微笑みかけると、そっとしておいて、今度はナオに話しかけた。
「そういえばナオは冒険の話とか好きだよね?」
「ええ、これでも俺、冒険にはちょっと詳しいんです。部屋の真ん中の台座に宝物があってもだいたい罠が用意されてるから、すぐに入っちゃダメですよ!」
指を立てて得意げに言うナオ。どこかで読んだ本、冒険小説や冒険記か何かの知識であろうが、とても嬉しそうだった。
「今回の冒険が終わったら、冒険記書きますね。きっと面白いものになりますよ」
これは後日最終的に日記になったようだが――、
「私達は嵐や多くのの困難を乗越え……えーと、たくさんの仕掛けとかあっておもしろかったです」
日記だって、後で誰かの役に立つだろう。
*
「ア、アナスタシアー!?」
「ここですわー!」
ヨルが声を上げれば、屋外から返事が聞こえる。
窓枠に手を突いて下を覗くと、地面に置かれた椅子の上に座っているアナスタシア――という不自然な光景が広がっていた。彼女は窓の方へ向けて手を振っている。
ヨルの横から顔を出した
藤崎 凛(ふじさき・りん)は事態を把握すると、早速二階から階段を駆け降りていき、側に近寄った。
「お姉様ご無事ですかっ?」
アナスタシアが椅子から降りると、椅子はまるで存在しなかったかのように二人の目の前からかき消えて、再び、振り返ったヨルの背後の定位置に出現する。
二人が戻って来ると、ヨルは腕組みして唸った。
「椅子叩いたんだけどなぁ。……これ重量感知式?」
「……うう、これで六回目ですわ」
ヨルから手渡されたお茶を、今度は安全な椅子に座って飲みながら、情けない息をつく。
凛は椅子に二度引っかからないように目印を付けると、自分もお茶を頂きながら話題を変えた。
「持ち帰れなかった秘宝………単純に持ち運べなかったのかもしれませんが、ここにないと意味がないものなのかもしれませんわね」
「物理的に無理だったのか、感情的に無理だったのか気になるなぁ」
ヨルが凛の言葉に答えると、
「秘宝か……魔女の大切なものなんじゃないかな? こうして近づく者の力を奪ってでも守りたいような」
凛のパートナー、
シェリル・アルメスト(しぇりる・あるめすと)が彼女の背後に立ったまま、答えた。
「どんな秘宝なのかしら……」
「拝めるものなら拝んでみたいね。記念として」
凛は夢見がちな少女らしく、うっとりと思いを巡らせる。
「魔女のお住まいということは、秘宝にも魔法が掛かっていたり、魔法に纏わる何かがあるのかも……」
「普段の力が使えないっていうのは、結構不便なものだね……と思ったけど、リンはあまり変わっていな……いというか、楽しそうだね……」
晴れる前から目をキラキラさせていたくらいだった。小さな体に重量だけは気を付けて、ふわふわしたお嬢様の外見には似合わない無骨なバッグパックに装備を選んで詰め込んでいたのだ。
手袋も絹ではなく丈夫な冒険用のものだ。小さいすり鉢・すりこぎも持ってきている。
その凛は、辺りを見回してふと思い出したように、
「そういえば、お庭やここにある植物ですけど、薬効があるものが多いですわね」
勿論薬は毒でもあるわけで、有名なハーブだって使い方次第だ。だから怪しい研究をしていないとは言い切れないのだが、概ねいわゆる「白魔女」的な植物だった。
「そうか、魔女が住んでいた場所なら薬効のある植物が生えていても不思議じゃないね」
「そういえば、先ほど頂いたメモによりますと、守護天使のアル何とかさんが、屋上で庭園らしきものを見たとか……」
アナスタシアは言って考え込むと、今度は二階に行きましょう、と誘った。
二階の奥にはダミーの扉があって、押し開けると中は狭い滑り台状になっており、うっかり足を出すとそのまま滑っていってしまう。さっきアナスタシアがひっかかったのは、それだった。凛は二度と落ちないよう、ロープを組んで網を張る。
また皆で道具を手分けして調べる。
「……この中央の魔方陣とか怪しいよね?」
ヨルはぐるり、と周囲を見回すものの、“女王の加護”はどこからも特別な反応を示さなかった。
「何となくだけど、深刻な状態になる仕掛けはないような気がするんだ。この仕掛け自体が侵入者を楽しんで迎えているような」
小石をポイ、と魔法陣に投げ入れて反応しないことを確かめる。
「アナスタシア、どんな研究がしてたと思う?」
そう話しながら、慎重にコンコンと壁を木の棒で叩いていく。アナスタシアは資料をめくりながら、
「保存に関する魔術のようですわね。それから植物の栽培……要するに、無人でも永遠に続く温室のようなものを研究していたようですわ」
「そうか……。……あっ、ねぇみんな、これ見てよ」
壁の音が変わった部分。そこには一枚の鏡がかかっている。鏡の枠は寄木細工のようになっていた。皆がそれを解くと、鏡が外れ、裏側の壁部分からへこみ……小さな穴が現れた。
そして中には、一つのレバーが収まっている……。