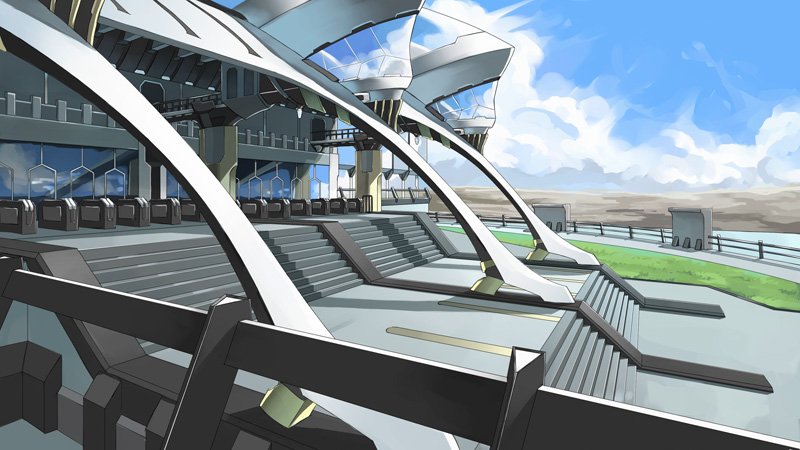リアクション
◇ ――太陽が傾きはじめ、荒野を緋色に染めていく。 少しずつ夜へ近づく空を見上げながら、山葉 涼司(やまは・りょうじ)は舌打ちをした。 「日が落ちる前に、見つけねぇとな」 涼司は手紙の内容で大体の位置まで把握できていたが、問題の遺跡を未だ発見できずにいた。 「この辺りなのは間違いないわ。それに、それだけ大きな物を作っているのなら、きっとすぐに見つかるわよ」 「……まぁ、確かにな」 リカイン・フェルマータ(りかいん・ふぇるまーた)が声をかけると、眉間に皺を寄せていた涼司が表情を和らげた。 その様子を見て、リカインは笑顔で考えをめぐらせる。 (環菜君の時みたいなこともあったし……これが罠じゃない、とも言い切れないのよね。さすがに、涼司君を誘い出して襲おう、ってわけじゃないとは思うけど) 「警戒するのは、悪い事じゃないわよね」 「ん? 何だ?」 「何でもないわ。それにしても、涼司君って……最近、色々と人気よね」 「い、イキナリ何を言い出すんだ」 突然の言葉に、涼司が慌てふためく。心当たりが有るのか無いのか、やや頬を染める涼司を見てリカインは微笑んだ。 リカインの顔を見て、涼司はからかわれた、と判断したのか額に小さな青筋を浮かべる。彼女としては、校長としての任を背負いながらも、こういった面倒事の処理もしなければいけない涼司を労っての歓談のつもりだったのだが、上手く伝わらなかったようだ。 「あ、またハリセンで叩くのは無しよ? って言うか、ただのハリセンで人を気絶させるとか、普通じゃないわよね……何かコツとかあるの?」 「ふっ……機密事項だ」 後頭部を手で隠すリカインに、涼司が得意げにハリセンを振るそぶりを見せて、胸を張る。 ――その時、リカインの視界に小さな光が入り込んだ。よく見れば、それは砂漠を疾走するニ機の機晶ロボだった。 併走する機晶ロボの上には、仮面や覆面で顔を隠した人影が見える。 「涼司君、アレって……」 リカインの視線の先を、涼司が追う。 「怪しい、ってレベルじゃねぇな。丁度いい……あいつらにご案内願おう」 真っ直ぐに走る機晶ロボを追って、涼司達は駆け出した。 ◇ ――涼司達が機晶ロボを頼りに遺跡へと向かっている頃。 遺跡から程なく離れた距離に、一人の少女が佇んでいた。漆黒のドレスに身を包み、博士達――謎の集団がいる遺跡を見つめている。いや、見つめている、というよりも『顔を向けている』といった方が正確だろう。 その少女――中願寺 綾瀬(ちゅうがんじ・あやせ)の目元は、身に纏うドレスと同じ、黒い布で覆われていた。 「イロンV計画……山葉校長はこの計画を危険視し、強制的に取り止めさせようとされていらっしゃるようですが、イーグリットアサルトを所持する蒼空学園との違いはあるのでしょうか?」 目元を覆う布と、乳白金の髪の合間から開かれる唇が、誰ともなしに開かれる。 「私達が生まれるよりも遥か昔より人間は『自分の行いを善とし、他者を悪とする』傾向が強いですが、今回の山葉校長も完全にソレですわね。他の世界、他の種族……私達は、この地をシャンバラの民から奪った訳ではなく借りて居るにすぎないはず。そこへ『イコン』と言う兵器を我が物顔で配置している……他の種族からみたら武力による圧力と受け取られても仕方ありませんわね」 回答を求める事も、自分の言葉に確証を得る事も望まないような口ぶりで、綾瀬は口を開き続けた。 「まぁ、そんな事は私には関係ありませんわ……今回のこの騒動、楽しませて頂ければ結果はどちらがどうなろうが関係ありませんので」 「ま、人間に限らず生き物なんて、結局は自分の気持ちを最優先に行動する存在なのよね」 独白の後。綾瀬に向けて語られたその言葉は、その身に纏うドレス――漆黒の ドレス(しっこくの・どれす)のものだった。 「自分と他人が同じような事をやっているならば、自分を正当化し他人を否定する」 自らを纏う者と同じく、誰に聞かせるでもない口ぶりでドレスが語る。 「その2者だけで済めば簡単だけど、今回は更に色々な思惑が動いてそうだからねぇ……綾瀬、今回は結構『楽しく観れる』と思うわよ」 そこで始めて、ドレスは綾瀬に向けて言葉を投げかけた。ドレスの言葉に綾瀬は口を開く事をせず、小さく微笑んで応える。 「イロンV計画側、山葉側。そしてその間で動こうとしている者の行動……その全ての『外側から』今回の出来事を観て楽しませてもらいましょう」 笑みが含まれた声音が、夕日に染められた荒野に吸い込まれる。 その時――遺跡から、けたたましい音が鳴り響いた。 ◇ ――涼司達が遺跡に立ち入るや否や、入り口付近に置かれた箱から甲高い音が鳴り渡った。 「何だ!? 何なんだこりゃぁあ!!」 そこかしこで赤色灯が回り、鼓膜を震わせる警報音が遺跡に響き渡る中、その音よりもはるかに大きな声で叫ぶ男が一人。 身を包むライダースーツには、銀色のプロテクターが。握り締め、震わせる拳には、グローブが。そして、顔にはフルフェイスのヘルメットが。 上から下まで総合的に見れば、何となく日曜日の朝に悪の組織と戦いそうな雰囲気を醸し出している。 そんな――ある意味では遺跡に集う集団に負けず劣らず怪しい井出達の男、風森 巽(かぜもり・たつみ)はイロンVを見て、未だ拳を震わせていた。ヘルメットを被る頭は、何かに失望したかのように、うなだれている。 (武器満載、巨大、ロボット……そこまではいいさ。あぁ、問題ない……だが!) 巽が突然、顔を上げて、周囲を見渡す。そして博士を視界に捕らえると、猛然と駆け出した。 緊急事態とも取れる喧騒の中で何故か慌てる事も無く、テーブルに五線譜を広げながら終夏と和やかに話し込む博士の側まで駆け寄ると、テーブルに拳を打ちつけた。 大きな音と共に、テーブルに乗っていたカップが揺れる。 「お前か……このオレの気持ちを、全国の男の子の夢を、希望を――あんな鉄屑にしやがったのは!」 巽が赤色灯の光を反射して赤く輝くヘルメットの奥から、鋭い視線を博士へ向けた。 突然の来訪者に、博士はスッと立ち上がって、眼鏡のフレームに指を添える。 「何だね君は……いきなり現れて至高の傑作に対して、随分な物言いではないかね?」 「至高? 傑作? ハッ! いいぜ、教えてやる……いや、刻んでやるよ。いいか、よく聞け」 何故か巽は、テーブルの上に立ち、直立して遺跡全体に手を広げると、大きく息を吸い込んだ。 空気を読んだのか、たまたまなのか。鳴り響いていた警報音が静まる。 「お前らに足りない物、それは! 資金、ドリル、技術力、推敲力、客観視、デザイン、計画性! そして何よりもォー! 浪漫! が足りないっッ!」 ビシィ! っとイロンVを指差して言い放つ巽に、博士が冷笑を浮かべた。 「若いな……このロマンに溢れるイロンVに『ロマンが足りない』とは……改めて見たまえよ、この完璧な構造、何者にも負けぬ兵力。そして頭部に輝く『V』の文字を!」 「ふざけんな! 機能美を追求するなら、御飾りの頭だの腕だのつけるな! 武装もゴテゴテつけりゃいいってもんじゃねぇ! 敵味方構わず一斉掃射かっ!?」 巽はテーブルを飛び降りて博士の胸倉を掴んだ。 何が起こっているのかいまいち理解が出来ない――というよりも単純についていけない、と周囲の空気は語っているが、巽の熱い想いは止まらない。 「情熱も! 浪漫も! あるんなら死に物狂いで作り上げろよ! お前らの理想のロボットって奴を! これか! これがお前らの理想か! こんなもんで満足か!? 壊す価値すらねぇよ! 自動車工場の作業ロボットにも劣るわっ!」 「……って、言ってるけど、そこの辺りはどうなんですか?」 誰も入り込めないと思われた語り合いに、迷彩色の防護服に身を包んだルカルカ・ルー(るかるか・るー)が加わった。その手にはビデオカメラが握られており、博士と巽に向けられている。 「非常に、理解に苦しむな。加えて……言わせて貰えば、そのスーツ。君のロマンの片鱗は見えるが、修繕の後が目立つな。君の言葉を借りるなら『死に物狂いで作り上げた』わりには壊れやすいようだが? ……君のロマンも底が浅いなァ」 「なッ……これは、その、アレ……だ」 博士の言葉に、巽が大きく後ずさる。 「そう言われると、セロテープっぽいのも見えるね、そのヘルメット」 「ぐぅッ!」 ルカルカが、巽にカメラを向けながら呟く。カメラを操作して、ヘルメットの修繕部分をアップで撮影する事も忘れない。 博士だけでなく、ルカルカからも心理的なダメージを負った巽が、その場に膝を付く。 「……以上、イロンについて異論を許さない主張でした♪」 身体を震わせる巽をそのままに、ビデオカメラを自らに向けてレポーターよろしく撮影を続けるルカルカに、博士が興味深そうに目を向けた。 「なかなか、他者の心を折る事に長けているな……ところで、君は?」 「あ、っと。ただのカメラマン? です」 ルカルカが、疑問符を交えながらも博士にカメラを向ける。映りこんだ博士の背後では、ワイヤーに繋がれたイロンVが今まさに持ち上げられようとしていた。 「おい……何してるんだ」 博士にカメラを向けながら取材を行おうとするルカルカに、涼司が声を掛けた。 ルカルカは、頬を痙攣させながら額に青筋を浮かべている涼司にカメラを向ける。 「……戦場カメラマン?」 ファインダーを覗き込みながらそう答えるルカルカに涼司が何か言おうと口を開きかけた瞬間、大きな音が遺跡に響いた。 |
||