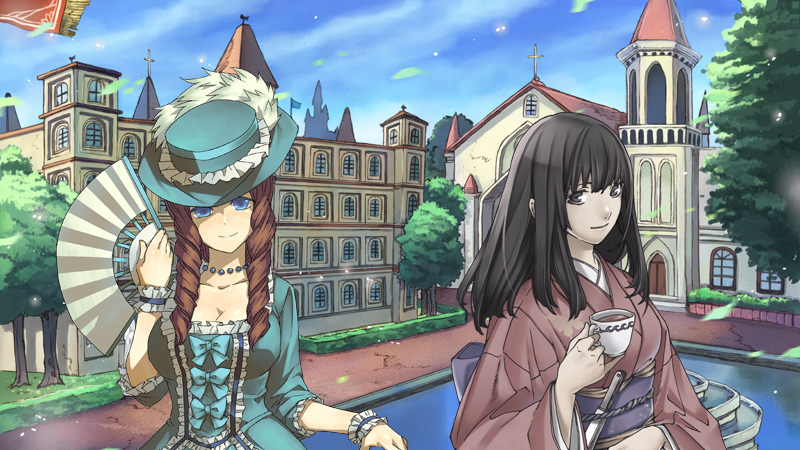リアクション
桟橋からほど近い海面に、一匹のイルカが鼻先を突き出してぷかぷか浮いていた。 * その頃、イルミンスールから訪れた薔薇十字社探偵局の面々は、桟橋にいた。 百合を守るのは黒薔薇の魔導師リリ・スノーウォーカー(りり・すのーうぉーかー)と気高き白薔薇の騎士ララ・サーズデイ(らら・さーずでい)、そして黄薔薇の花妖精ユノ・フェティダ(ゆの・ふぇてぃだ)だった。 その日の朝三人(主にユノが他二人を紹介するかたち)でラズィーヤに挨拶をした後からずっと、船に続くタラップ周辺を警備していた。それぞれ腕章を付けている。 探偵局が暇なので、アルバイトに来たのだ。 「あ〜っ! ララちゃん、この荷物サインしちゃったの?」 ユノが、どこかの商店から運ばれてきた木箱を前に、声をあげる。 「ああ、したよ」 「バカバカ、船に運ばせてからサインしなきゃダメじゃない。しょうがないなあ、この荷物はララちゃんが運んでね」 ユノに言われ、ララは面食らったような顔をした。 「え、私がか?」 「そうよ。この荷物が無くなったら、疑われるのはサインしたララちゃんなんだから」 「ちぇっ……」 ララはその重い荷物を何とか持ち上げると、船の中へと運んで行った。中身はお茶会の後に配られる、スタッフ用のお土産が入っているはずだ。 その時、ララと入れ違いにヤーナと百合園の生徒たち、それにフェルナンがタラップを降りてきた。 リリは顔ぶれに違和感を抱きつつ見送るが、その背中にユノがひっついた。 「事件よ!」 「事件? ただの散歩だと思うのだよ」 「お客さんが、お茶会中なのにわざわざ船を降りたのよ! 絶対何かあるわ!」 言うや否や、ユノはこっそりと彼女たちの後を追跡し始める。どうすべきか一瞬迷ってから、周囲には海軍が数人見張っているのを確認し、リリはユノを抑える役に回ることに決めた。 「一人で持ち場を離れてはいけないのだよ……うん?」 後を追っていくと、ヤーナの向かう先、リリとユノの視線の先に、百合園の生徒二人が見慣れぬ男性と共に現れた。 「あれは、船に入り込もうとして追い出されたとかいう獣人ではないか?」 * 「円ちゃーん!」 顔がよく見えるようになった距離で、歩が手を振ると、円も手を振り返した。 「来たね。彼女がヤーナさんか……な、って」 円の言葉が終わる前に、カイハ彼女の横から消えて、ヤーナの前に息を切らせて立っていた。 「ヤーナ!」 「……カイさん、ごめんなさい。父が失礼をして……」 「いいんだ、解ってる。それよりも──ああ、皆さん、ヤーナを連れてきてくれてありがとう」 「ありがとうございます」 二人視線を交わしあってから、並んで、生徒達に頭を下げる。 「じゃあ、詳しい事情を話してもらおうかな。……最後は族長の裁定が必要だろうけど、ね」 円に促され、カイは追いかけてきた事情を語り始めた。とはいっても、それはごくごく端的で。一言さえあれば十分だった。 「俺の親父が、本島に残ったみんなも説得しようとしてる。数日中には話をまとめて、移住の話を“原色の海”に持って行くつもりだ」 「そんな……!」 「どういうことなの?」 問う歩に、ヤーナは青くなって説明した。 「“原色の海”には三つの部族が住んでいます。戦争は起こらないけれど、互いに多少牽制し合っている、そんな関係が続いています。そのうち、青の旗を掲げる部族と、私たちは古くからの取引がありました。海底に棲む、私たちに近い種族です。そこに保護を求めたんだと……」 保護を求めた、それ自体は問題ではない。だが住むところを追われ、部族がばらばらのままでものごとが進むのは好ましくなかった。 「万一でも人間に支配されるくらいなら、海を移動してでも移るって言い張ってるんだ。族長が帰ってから話すのが筋だろうって言ったんだが、親父も頑固だから、俺の話なんか聞いてない」 「もしそうなったら……もう、会えなく……?」 ヤーナは顔を手で覆った。カイは安心させるように、ヤーナの頭をなでるが、その表情は僅かに暗かった。 「大丈夫だ、急に決まるわけじゃない」 これからどうすべきか。一同が考え込んでいると──その耳に、かすかに歌声が届いた。 聴覚の鋭敏なイルカであるヤーナとカイが、共にお茶会の会場である商船を見上げた。つられて、生徒達もその先を見る。 ──メインマストの上に、数人の人影があった。 その先端に立った少女牛皮消 アルコリア(いけま・あるこりあ)は、海風に長い黒髪を靡かせている。 髪を邪魔そうにかきあげ、眩しそうに目を細めた。 (んぅ、良い天気。日差しは少し強いですが、夏故に致し方なし、ですね) そして一度、視線を下方に向ける。パートナー達もそれぞれマストに腰掛け、木で休む小鳥のようだった。シーマ・スプレイグ(しーま・すぷれいぐ)だけは白百合団員の警備員として、ローブと暗器で周囲への警戒を続けている。 (……ふふ、皆さんきっと、皆それぞれの思惑、願い、望み、目的があってこの場に居るんでしょうね。 自らの願いで、人を否定しない事を選んだ人はどうすればいいのでしょう? 人が人を傷つけるのは、望みが、目的が、理由があるからです。 一つは、誰かを否定したくないという望み自体を愚かとし、人を否定して生きていく道。一つは、自らの望みを消し去り望みを持たぬことで、自らの望みで人を否定しない道) 手で作った陰の下で、視線を水平線の彼方へ向けた。 (誰も間違ってなど居ないんですから) 「刃を振るう時も、誰かを殺めた時も、大切な人を抱きしめたときも、ただ一つ変わらなかったその気持ちで……歌いましょうか」 (【幸せの歌】を、私の持てる技量で、ナコちゃんとラズンちゃんと。水平線の彼方まで、蒼空の向うまで、届かせる積りで歌いましょう。 きっと私は気にしすぎて、雁字搦めになって動けなくなってしまったから、踏み潰した蟻の事など知らぬとはき捨てれば進めるだろうけど。できないから、今日は皆の為に歌いますね) アルコリアは、息を吸い込むと、歌を風に乗せた。 同時に、彼女より下方で、ナコト・オールドワン(なこと・おーるどわん)が竪琴の旋律を奏で始めた。 (マイロード・アルコリア様が仰るなら、演奏は喜んでいたしますわ。わたくしにとって、マイロードこそ善、マイロードこそ神、マイロードこそ正しさ。 故に、マイロードの判断であれば、それに従いますわ。例えそれが闘争でなくとも) ラズン・カプリッチオ(らずん・かぷりっちお)のメロディーが後を追いかける。 三人の奏でる音楽が、商船の甲板の上へ、桟橋へ、波間へと漂っていった。 少女は 永遠の幸せの中で嘆き続けている 自分を包む世界は 優しくて 暖かいのに 幸せでない世界を 夢見て 涙している 救われない者がいるから 自分も救われてはいけない 望み叶わぬ者がいるから 自分も望んではいけない 望む力は 前へ進む力 前へ進む事は 地を踏みしめる力 ラズンは歌いながら、考える。 一歩二歩と歩いて、踏み潰してしまった相手を、小さな虫と言った者は 悪人なのに、小さくて気付かなかった人は 多くの物語で主人公と呼ばれている。 進むということは、何かを踏みつけること。それは正しいことかどうか、それが見たい。それを知りたい。 ここにいる理由があるなら……きっと、そういうこと。 |
||