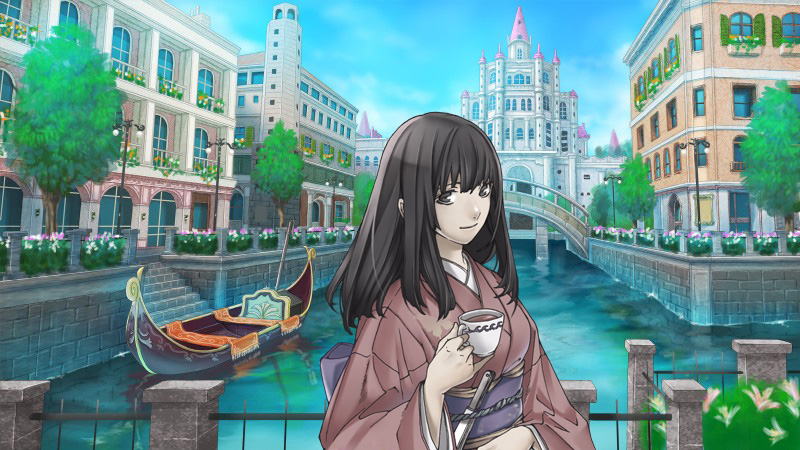リアクション
──ざり。
どこからか(広場の地面や砂場から)舞ってきた砂を踏む音がした。
スーツ姿に鞄を片手に。その男は、城壁(傾斜に埋め込まれた飛び石)を器用に登っていた。
彼の名は高木 賢治(たかぎ けんじ)(エッツェル・アザトース(えっつぇる・あざとーす))。近くを通りすがったサラリーマン。真面目そうな眼鏡の似合う黒髪の30歳。年齢=恋人いない歴。
だがそれは仮の姿だ。
真なる名、魂の名(ソウルネーム)はエルヴァート・ガタナソア!!
(何よりも愛する巫女王……我が手にするまでは、止まれぬ!!)
彼は巫女王の兄にして、神術を扱わぬ故に王位継承権から外れた証として姓を変えた、廃王子でもある。
同時に呪術や魔術を極め、その秘術の数々で数多の魔神を滅ぼし、魔王の帝国に最も出血を強いた大魔術師でもあった。独自に編み出した術式は、空間や時間にすら干渉できるほどだった。
その彼は、幼少のころより妹である巫女王に恋心を持っていた。その気持ちは成長とともに強くなるばかり。
転生のきっかけとなった戦争半ばに、遂に魔王の甘言に乗り祖国を裏切った。『王国を滅ぼしたら、巫女王はお前にやろう』と言われたのだ。
彼は一転して王国にとって最悪の敵となった。今まで禁じていた様々な外法に手を出し、暗黒の魔術は、倒した魔族よりもより多くの人間を葬ったという。
最期には魔王とともに蒼角殿に彼女を求めて乗り込み、巫女王の封印術で封じられることとなってしまった。
──だが、妹を憎んでなどいない。
転生した今も彼女を愛するその気持ちには変わりがない。
やっとこの結界に辿り着き(余りに他の病気の学生たちより年齢が違うので、情報があまり入らなかった)遠くから、復活した巫女王の姿を見た時は歓喜に胸を躍らせた。
たとえその経歴故に(その年齢故に)、王国どころか魔族の民に冷たい仕打ちをされようと(公園を利用する親子の白い目や、露骨に避けられたり)や、幼い時世話になった長老に説得されようと(日向ぼっこ中のおじいさんの「何があったか知らんが、人生いつかもっと楽しいことがある」という説教を受けても)、この狂おしい想いは変えられようがなかった。
彼は呟く。
「闇の邪法で強化したこの肉体は、既に痛みもない。私はこの叶えられない愛の痛みを感じているだけで精一杯なのだから……」
こんな時に来るなんてタイミングが悪すぎる、まとめてさっき浄化されておけばよかったのに。と、セレンは心の中で悪態をついた。
「……久方ぶりだな。愛しの妹よ……」
物見台に現れたエルヴァートは、過去の記憶と全く違わなかった。魔王のような威厳はなく、魔王のような威圧感はなく、魔王のように闇に覆われ、魔王とは違って、絡みつくようなある種の迫力があった。
「二度と会いたくなかったわね。それに、愛しの妹に久しぶりに会い来るにしては、随分と悪趣味で物々しいじゃない」
セレンは、エルヴァートの左右に立つ生ける鎧──亡者の魂を宿らせた錆びついた鎧・リビングアーマーを見て忌々しげに吐き捨てる。
「邪魔をするゴミどもを露払いするためには仕方あるまい」
これも、前世と同じだ。いや、余計執着が深まっているような感さえある声音だった。彼にとって、巫女王こそが絶対的に価値あるもので、それ以外は下種なのだ。
(話し合う余地はないですね……)
「たああっ!」
セレナはたっと地面を走り出すと、気合と共に槍を突き出した。それをエルヴァートは受ける。
「やった!?」
腹を突き刺す確かな手ごたえに、セレナは喜ぶ。が、その槍の一撃は確かに傷をつけたのに──切り口はぶくぶくと泡立ったかと思うと、瞬時に再生していった。
「魔術を極めし我が肉体は、もはや人のそれと同等ではない」
魔術師は概ね、接近戦・肉弾戦に弱い。セレナが槍を振るえば、避けるのも難しいだろう。ただ彼は強力な再生魔術を自らにかけ、近接戦闘が苦手というハンデを克服していた。
セレナの眼前に、腹に槍を突きたてたまま手を伸ばし、指先を広げると、ぴたりと額を掴み取った。掌に紅い魔法陣が閃く。
「うっ!?」
頬が青ざめ、一気に血の気が引いた。一瞬にして激しい倦怠感と虚脱感が襲う。その横顔を、二体のリビングアーマーがさびた剣を振り回して両側から振り下ろそうとし、その時、脇から雷を纏った弾丸が発射され、手首の部分を打ち抜いた。
「セレナから離れなっ!」
がらんがらんと音を立てて、握った剣ごと、リビングアーマーのガントレットが転がる。
セレナは首を振って遠くなりかける意識を取り戻すと、左手でエルヴァートの手を払い、一歩背後に飛び、槍の射程に距離を取ると、彼女は問いかけた。
闇の瘴気を纏った体躯。先程まで目の前にあった、凶器に満ちた瞳。そこからもたらされる彼への恐れを振り切るように。
「巫女王をどうするつもりです!?」
「あえて聞くまでもないだろう。永遠に我が物となるのだ! 我が魔術は時を超越し老いを回避する。この魔術が続くまでだ。やがて死を迎えるとも、死しても躯として。肉体朽ちるとも魂を共にして。遥か輪廻の果ての果てまでな!」
「……時は満ち、世界に落日が迫り……そして、私たちの終焉の時も間もなくやってくる。万物全てが逃れようとして決して逃れ得ぬ、終焉という魔物……いずれ終焉を避けられないなら、せめて……あなたから先に滅ぼして見せましょう……」
彼の返答に、セレナの一角獣の角を削りだした槍の穂先に、雷光が宿った。
「<雷光の閃き(ライトニング・ストライク)>っ!」
跳躍。そのスピードに体重を乗せられ、上空から穂先が繰り出される。槍は雷となってエルヴァートの体を貫く──光よりも早く、光よりも強く。
セレナの電撃に貫かれ──だが、彼は槍を握りしめた。
彼女は危険を察知し、引き抜こうとするが、深く刺さったそれは再生していく筋肉にがっちりと掴まれ、
「抜けない……!?」
「ゴミめ、跡形もなく消え去るがいい! ──<クルーエル・アルティメイタム>!!」
それは、魔術の究極到達点の一つであると言える空間や時間の流れに干渉し、あらゆる力や存在を根本から消滅させる破滅の真理だ。
片手で槍を掴み、ずぶずぶと腹に埋めながら、右手で術式を展開させていく。眼にも見える魔力、魔法陣の緻密な術式な何重にも彼の指を掌を手首を取り巻き、構成されていった。
床から半身を起しながら、巫女王は、その術式が何であるかに気付いた。
「お兄様、セレナを消さないで! それに、その術は──!」
「そうだ、代償として使用すればするほどに魂はすり減っていき、それは二度と戻らない。そのまま魂が完全に失われれば、自身の存在自体が消滅し輪廻の輪にもどることも無い」
「やめてお兄様!!」
巫女王の頬を伝う涙に、セレンは複雑な感情を抱きながらも、リビングアーマーを鉄くずにした銃を納めた。ただそれは、巫女王のために攻撃の手を休めるのではなかった。
「……あたしはかつて自ら立てた誓いを果たせず、それが故に巫女王を護れなかったその真実……あの恐るべき事実を前に、何もかもが色褪せ、世界はただ無意味な何かに成り果てた」
いまさら何を、と、呪文を呟くエルヴァートの口元に嘲笑がひらめいた。
セレンはそれを見ながら、手を高く頭上に挙げた。相手の術式の展開までおそらくあと数秒の、猶予がある。その数秒、彼は術式を手放さない、その自信がある。
「……しかし、あたしは必ず誓いを果たす。もはや何者にもあたしから巫女王を奪えないように、奪う事が永遠にできないその極地へ、あたしが今いる場所を変容させて見せる。
そしてあなたは……永遠にあたしたちに届かない場所へと叩き落としてやるわ。そこで永遠の喪失感に包まれたままに……残りの生涯で償わせる」
両手の間の景色──空間が、歪んだ。屈折率の高い球を通して見た時のような景色としての歪みと、時の制止した、時空の歪みが生まれる。
「<重力半径(シュヴァルツシルト)>!」
その歪みは、彼女の言葉と同時に瞬時に消え去ったかと思うと、突如肥大化し、エルヴァートを中心に出現した。
エルヴァートはその歪んだ空間の中に閉じ込められ、そして、細くも夥しい量の電撃で全身を焼かれながら切り刻まれていく。
そう、たとえば彼女の術は、本来ならエルヴァートには大した効果を及ぼさなかっただろう。その魔術によって或いは纏う闇によって。
それでも、このセレンの言葉は言霊となって呪いとなって、予言となって、宣告となって、ゆっくりとではあるが彼の闇を引きはがしていった。
「あたしたちから永遠に“奪えない”ただ惨めなあなた……それが真実の全て」
ばらばらに、散り散りに、その想いも過去も全て閉じ込めて、切り裂いて。
「さよなら……アデュー……愛するあなたへ。君も、いつか、あたしのようにしてごらん?」
エルヴァートの最期を見届けた巫女王、セレンとセレナは、続いた戦いに力尽きて、ゆっくりと目を閉じた。
色々な感情が渦巻いてはいたけれど、戦いがすべて終わった今は、ただただ眠りたかった。
彼女たちを労わるように風が優しく吹き、先程までエルヴァートであった灰の塊は、舞い散り、どこかへと運ばれていった。
*
アナスタシアは今、城の中にいた。
巫女王復活の混乱の中、巫女王たちが上階へ上っていくのを見届けた彼女は、周囲で倒れている人々の怪我の有無を確認し終えると、彼らにかすり傷以外の外傷がないこと、それにすっかり眠ってしまっているのに気付き、床にへたり込んでいた。
(そういえばここはどこなのでしょう。公園の名前や……番地とかいうものが分かればいいのですけれど……)
ぼんやりと見上げた空には、のんきに虹がかかっている。
「虹ですわ。雨上がりでもありませんのに、不思議ですわね……」
しばらく眺めていたアナスタシアだが、違和感に気付いた。虹が、長く長く尾を引いて、伸びていく。現在進行形で作られているのだ。それに半円でもなくて、まるでそれは飛行機雲のようだった。
おかしいと思ってよくよく目を凝らすと、その虹はある一点から描かれているのだった。
自然現象ではなく、“虹を架ける箒”の仕業であると彼女が気付いた時、何時間か前に、メールを貰っていたことを思い出した。
慌てて携帯を開くと、メールに返信する。
予想を裏付けるように、すぐにその虹は空中で途切れたかとと思うと、高度を下げて旋回し始めた。
「ここですわ!」
アナスタシアは窓の一つからバルコニーに出て、虹に向かって手を振った。
間もなく箒は──箒に乗った
宇都宮 祥子(うつのみや・さちこ)は、空から舞い降りてきた。
飛び降りるようにすたんと箒から降り立った祥子は、ほっとしたように肩をなで下ろした。
「ようやく見つかったわね。さあ、もう大丈夫よ」
「ご心配をおかけいたしましたわ」
二人はアナスタシアにとっていささか不安であった物見台に上がって、吹きさらしの一月の空気を避けるべく彼らを室内に運ぶと、校長に応援の電話をかける。これで一安心だ。
城をぐるりと見て回って、祥子は倒れている人数の多さにちょっとびっくりしたが、病気の人を見てみたかったな、などと終わってみればのんきなことを思っていた。
その思いを感じ取ったのかどうか、倒れていたうちの一人がゆらりと立ち上がった。
「ユーフォルビアをどうするつもり……!?」
まだ正気に戻っていない彼女に向けて、祥子は、髪をかきあげて挑発する。
「私は
“虹の”グランシャリオ。残念ね。この女はこの世界でも私のモノなの」
ユーフォルビアをたぶらかした魔族で虹の七色+無色の魔術を操る女魔導師。ほうき星の膨大な魔力を蓄えた箒を魔術の杖として魔導を行使する──という設定だ。
彼女はさらに挑発するべく、アナスタシアに甘い声をかける。
「ほら、あの時みたいにお姉さまって言ってご覧なさいな」
「……な、何を突然仰いますの!?」
(ほらアナスタシア、適当に口裏あわせて!)
目を丸くする彼女に、祥子は小声の早口で言った。
アナスタシアは、これは乗り切るしかないのかと思い(彼女以外が到着するまでは助けてもらうしかないのは判り切っていて)、渋々口にした。
「……お……お……お姉、さ、ま……」
微妙な恥辱? から、顔から火が吹き出すように、上目遣いで彼女を睨む姿を、祥子は堪能する。
(ふふふ、結構楽しいかも……)
ノリノリの祥子は箒をくるくる回した。虹色が円を描き、ちょっとした奇術や魔術のように見える。
「ふふ、七色に輝く竜の鱗が弾幕となりて敵を討つ──
<竜鱗虹弾(レインボー・ドラゴンバレッタ)>」
勿論架空の必殺技だ。相手のために丁寧に解説を入れる。
「きゃああっ!」
思った通り、少女はダメージを受けたつもりになって仰け反った。
「更に、これはどう!? 七色の光を歪曲させ紡ぎ出すは総てを無に帰す虚空の色!
<白く黒い虚空の孔(オール・イン・ワン)>!」
「きゃああああああーっ!」
攻撃を受け?ばったり倒れてしまった少女と祥子を見比べて、アナスタシアはゆっくりと首を振ると、呆れたように言った。
「こんなことをして恥ずかしくありませんの?」
「いやねえ、恥ずかしがってる場合じゃないなーと。アナタを助けるためにもね」
祥子は楽しそうに微笑んで、片目をつぶってみせた。
「一応魔法少女だし?」
*
「転生者」たちの戦いは、魔王の封印が行われ、巫女王は生き延びるという形で終結した。
倒れた患者は契約者の百合園の生徒達が向かって簡単な手当を行い、手配した百合園女学院本校のバスで回収及び病気の治療をすることになった。
バスが走り去るった頃には、祥子もアナスタシアも、すっかり安心していた。新百合ヶ丘をよく知っておくために、ホテルまでは歩いて帰ろうという話になっていた。
──しかし。物語は続いていた。
「新設定」が原作に追加されたから。世界を終焉させる獣が目覚めていたからだ。