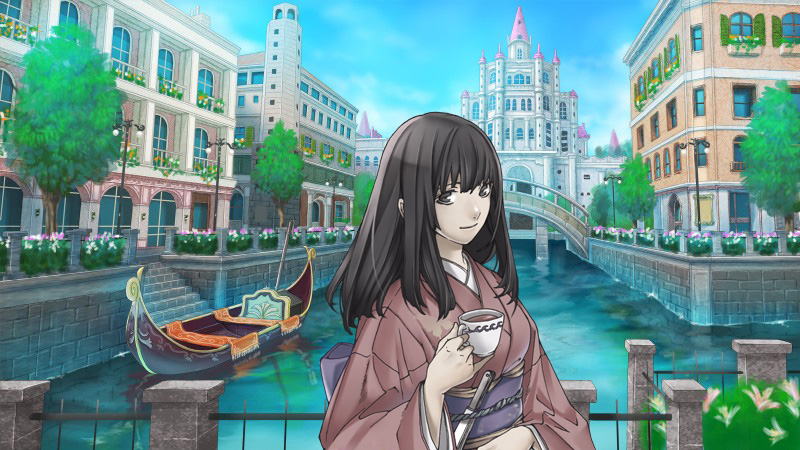リアクション
――獣の慟哭が響いていた。 見たこともない風景が、会ったこともない人々が眼前を通り過ぎていく。 恐怖に顔を歪ませ、呪いの言葉を吐く者達。獣は静かに引き金を引いた。 あたたかな光に目を細めると、小さな食卓を囲む子ども達の笑顔が見えた。 その場所で、獣はどうやら安らぎを感じているようだった。 しかし…… 『さぁ、これでお前を縛るものはなくなった。再び魔王様に尽くせ』 炎が天を焦がす。黒煙が立ち昇ってゆく。 瓦礫の下、庇いあうように抱き合い、動かなくなったあの子たちの姿。 ……そうか。獣よ、お前は…… いつの間にか頬を伝っていた雫に気づく。 その時俺は初めて、その叫びが己の喉から出ていたものなのだと理解した。 鉄心。魔族の青年。魔族には珍しく銃を扱い、先代魔王の指南役でもあった程の実力者であった。 帝国──現魔王が開戦を決定したのは、彼の存在に勝利を確信したのが理由の一つであった、とも言われている。 事実彼が指揮し育て上げた軍勢は、十数に及ぶ戦場を経験してなお無敗。その名は王国にまで轟き恐怖されていた。 だが彼の心の裡を知る者は少ない。彼が戦を始めた理由が、更なる戦を無くすためであったことを知る者はなお少ない。彼が魔王と交わした約束──講和の提案──を反故にされたことを知る者も。 ある日目の当たりにした『戦の結果』は、彼の心をすり減らすに十分だった。 彼は軍を退き銃を置き、穏やかな生活を手に入れることにした。身寄りをなくした子等と過ごす、貧しくとも満ち足りた……。 だが、彼は逃れられなかった。彼自身がもたらしてきた勝利は新たな勝利を呼び、巫女の王国の子供たちに絶望的な経験をさせたという事実から。 だから、最終的には再び銃を取り、巫女王に協力し、魔王を背後から撃つことになったが──。 「これは、魔王軍からの『依頼』だ。転生者を『狩れ』と」 ニケが倒れ、鉄心に殺到するエクスセブンと妹たちは、その声に死臭を嗅いだ。 「<黙祷(silent prayer)>──」 瞬間。彼の背後に無数の怨霊を見た。 死が、迫ってくる。彼女たちの指先は震え、脚が立たなくなり、地面を噛めず地面に手を突いた。顔をあげようとする気持ちが折れた。 ──これこそが彼の能力。「勝てない」「倒せない」「間合いに入れば確実に殺られる」 等の恐怖を抱き、この恐怖をぬぐわない限り、勝ち目はない。 そんな怯えた子羊たちを刈り取るなど、児戯に等しい。 鉄心が引き抜いた銃の引き金が、リズミカルに引かれていく。一人、また一人と肩や足を撃ち抜かれ、倒れていった。 「みんなしっかり!」 仲間たちの後方で、秋子のバイオリンが、幸せのメロディで心を鼓舞しようとする。 このままでは全滅だと、エクスセブンと秋子は覚悟した。 だが、何故だろう。彼は「止め」をささなかった。 左腕を撃たれた妹の一人が気力を振り絞り、鉄心の前に辿り着くと、スティレットを彼の心臓に突き立てようとする。 だが、その隙は余りにもとってつけたようで。目を開いたまま、妹は刃先を胸から一センチ余りのところで止めてしまい、そのまま突き立てることはできなかった。 「……どうした。好機だろう?」 躊躇う彼女に、鉄心は寂しそうに笑うと、 「奴は……俺の教えを良く守っているよ。見事に俺の弱点を突いて来た」 「奴……?」 「魔王だ」 彼は話し始める。 かつて巫女王の血に連なる全ての者を『狩って』いた事。そして見つけ出した一人の少女は身寄りをなくした子ども──魔族も分け隔てなく──を救おうと、自らがやせ衰え既に死の床にあったこと。 その姿に、この戦に疑問を抱く自分は永遠に勝てない事を悟り、彼女の意思を継いだこと。だが転生した子供らが呪いに苦しみ、再び命を失いかけていること。 「分かるだろう? お前と俺、両方が無事で……と言う訳にはいかんのだ」 子供達と暮らし既に命を奪えなくなっていた鉄心は、もう銃を持つ手をあげることはなかった。 それはまるで死を受け入れようとしているように見えた。 妹はどう決断すべきか、迷い──、 ──その時、声が響いた。 「あなたに神の恵みによる魂の救済を……、<神の秘蹟(エクス・オペレ・オペラート)>」 声が響き、彼の力を、記憶を、洗い流していく。 「全てが終わった時、あなたは何も覚えていないでしょう」 どさりと倒れた鉄心を見下ろす一人の少女──涼風 淡雪(すずかぜ・あわゆき)。 過日の『深淵の暁闇』事件の時点では、ただの黒史病患者だった地球人だった。フリーの能力者で神と人間とを仲介し、神の恵みを人間に与える秘跡の執行者という設定の。 しかしその後、彼女は本当に契約者になった。勿論契約をしたというだけであって、その契約に至るまでのストーリーは彼女の頭の中で作られたものだったけれど。 「これでいいかしら?」 振り返る淡雪に、立ち尽くしていた黒ずくめの少女が頷く。 「いい。けがは、こまるのよね?」 「ええ。あの自作の短剣は凶器になるから。全てやりすぎれば、怪我するわ」 「じゃあ、それでいい」 一時間程前、二人が会った時。 「──本当に、いたのね。都市伝説なんかじゃ、なかったんだわ」 アナスタシアと別れたばかりで行くあてもない黒ずくめの少女に、淡雪は手を差し伸べた。 「貴方をずっと探していたの」 無表情の少女に、彼女は一歩踏み出した。 「私があなたの影を踏み、月が天に極まり私が“死の舞踏会(ダンス・マカブル)”に招待され、姿を消したあの日。幻想が人々の前より隠れし日より300と65日が過ぎたわ。 幾多の世界と運命を超えて今、都市の影たるあなたが姿を現した。影の娘よ、今度は共に踊りましょう、この世界を」 今読んでいる本(の、運命とか世界とか転生とか)に毒されていた少女は、同類であろうと、淡雪の手を取った。 「共に世界の行く末を見るのよ、空の果てまで」 理解者──そう、少女には思えた。 今度は本の中ではない。自分の周囲で起こっている出来事の結末を見届けるのだ。 本に夢中になっていないで、自分で見るのだと彼女は思い立った。 ……だから行こう、空の果てまで。風の吹く場所を。 彼女たちは、門の奥へと姿を消した。 「ま、待って──」 呼び止めようとした秋子の背後には、だが新たな敵が迫っていた。 |
||