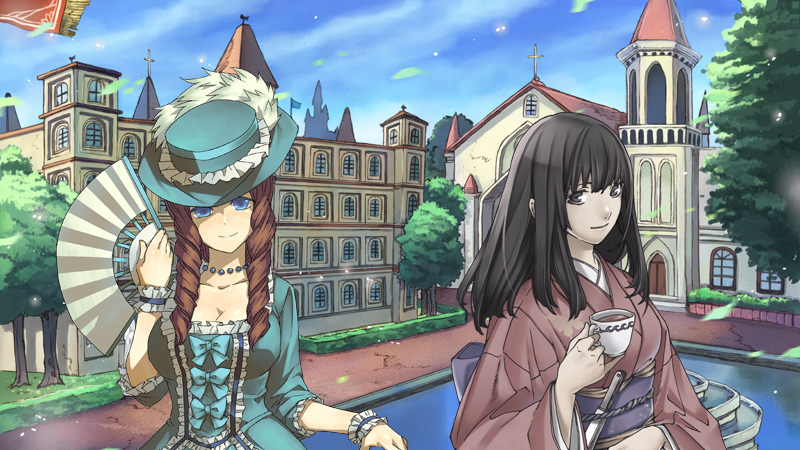リアクション
第6章 アダモフ、倒れる
アダモフが咳き込む──その、少し前。
ラズィーヤに代わって彼の席に着いたのは、藤崎 凛(ふじさき・りん)と冬山 小夜子(ふゆやま・さよこ)、シェリル・アルメスト(しぇりる・あるめすと)だった。
三人とも役員に立候補はしていないが、それぞれの考えで今回のお茶会にスタッフとして参加している。
こちらに来てから、凛と小夜子の二人は、アダモフの咳が気にかかり、彼の側にいた。
「ヴァイシャリーの景色と言えば、大運河ですわ。水上バスやゴンドラが行き交い、どの時間も、日の光がとても美しく反射して──」
小夜子が先ほどから語っているのは、ヴァイシャリーのことだ。
「湖上の街ですから、海運がとっても発達していますの。店や倉庫街には運河に面した裏口があって、船からすぐに積み下ろしができるようになっておりますのよ」
けほん。咳き込んだアダモフに、小夜子はすかさずお茶を勧める。
(持病があるのに遠路はるばるいらして、辛いでしょうね……。でも……慣れているのでしょうか)
それとも、秘書の仕事には含まれておらず、医者などを近くに同行でもさせているのだろうか? 彼を診るべきアダモフの秘書バレは、今は近くの別のテーブルに移って、商人たちと談笑している。
(少しでも楽に過ごせるように、私たちが気を付けて差し上げなければ)
お茶をすするアダモフの負担にならないよう、気を配りながら、小夜子は会話を続ける。
「ヴァイシャリーは交易の街でもありますの。特産と言えば……服や宝飾品のデザイナーが腕を競っていますが……」
交易品など他にあったかどうか。小夜子は今までの生活で培ったヴァイシャリー知識を動員した。
「材木、種々の海産物、ワインやオリーブオイルにチーズ、ハム、ハーブ、紅茶なども産出しておりますの」
「ほう」
「……技術的な面ですと、古くから伝わる建築、彫刻・絵画などの美術品、香水、美しいガラス細工に料理……、大きいものですと造船がありますわ。ゴンドラのような小さな船から、機晶石を用いたものまで。変わったところですと、オペラなどの無形文化などですわね」
「実際のところだね」
アダモフは咳き込みながら。
「エリュシオンにも古くから蓄積されてきた様々な技術と産物がある。勿論ヴァイシャリーにも興味は尽きないが、ヴァイシャリーには地球から取り入れた技術がある。それらが融合したものは、何かないのかな?」
両者の結晶であるはずの百合園女学院は、どちらかというと、地域との調和を大事にしている様子である。蒼空学園のような校舎からして先進的な技術を取り入れたり、教導団のように積極的に軍事に転用したり、ということもない。
「ヴァイシャリーに限りませんけれど、携帯基地局や上下水道施設やエアコン、そういった技術でしたらありますわね……ただヴァイシャリーには、交易の中継地点としての立地の利点があると思いますわ」
「そうだろうな」
アダモフは深く頷いた。再び、咳き込む。
「──暑くありませんか? こちらをどうぞ」
凛が、ジンジャー入りのハーブ・コーディアルをアダモフに差し出した。氷はなし。今は暑いけれど、胃に冷たいものが続くと負担をかけると思ったのだ。彼女は夜、冷えるころに備えてブランケットも用意する念の入れようだ。
「これは美味しいの」
「アダモフ様のお口にあったようで嬉しいですわ」
ハーブを抽出したシロップを水で割ったものだが、度を越した辛党の凛からすれば、かなり甘ったるく感じるものである。実は、パートナーのシェリルが、あらかじめ秘書に味の好みを聞いておいた。
それからシェリルが聞き出したのはもう一つ、アダモフの病状についてである。
(パラミタ気管支炎の一種、とか仰っていましたわね……)
若い頃から見習いとして大きな商会に入り、やがて独立・支店の拡大・交易と、商人としての道を邁進してきたアダモフは、自分の体の不調を顧みなかったらしい。病院に行く時間もなかなか作らず、最初は軽かった咳を慢性化させてしまったのだという。今は時折起きる発作を、薬で抑えているそうだ。
(こんな大事なお客様を、私がお相手できるかしら……いえ、練習だって沢山したし、今日はシェリルだって側にいてくれるんだもの……)
「何かありましたら、お申し付けくださいね」
笑顔を絶やさない凛を見て、側にいるアナスタシアは不思議そうな顔をしていた。
アナスタシアはやる気になればずっと笑顔でいることもできるだろうが、それは淑女の嗜みという、彼女にとっての作法の一環に過ぎず──心が必ずしも伴っているとは言い難いものだったからだ。
彼女がここにいるのは、先日百合園で開かれたティーパーティで同じ席になった縁と、シェリルが呼び止めたからだった。
「──どうだい? こういう細やかな気配りなんかは、百合園お嬢様の伝統みたいなものだろう。新しい事を取り入れるにしても、良いものは良いと認めて調和を図っていくのが大切なんじゃないかな」
シェリルはこっそりと、アナスタシアに微笑んだ。
「気配りが……百合園の伝統だと仰いますの?」
お茶会でいまいちいいところを見せられないアナスタシアは、少々戸惑っているようだ。
「これが百合園の伝統だと……? そんな作法など習っておりませんわ……」
「作法じゃない……だったら何だと思う?」
シェリルの謎かけは、選挙や形のことで頭がいっぱいになっているアナスタシアには、なかなかの難題のようだった。
ラズィーヤが席を立っておよそ三十分ほどたった頃、アダモフは、失礼すると言い、懐の中を探った。そろそろ薬の時間だったのだ。
そして咳き込み、咳き込み、手がかき回され、空を切り──、
「発作……!」
凛は小さく叫ぶと、慌てて立ち上がり、アダモフを抱えるように抱きとめた。
咳が続く。咳の合間にかろうじてできる呼吸は激しく、荒々しく、吹きすさぶ風のような音がした。
(ラズィーヤ様がいらっしゃらないとこにこんな! でも、とにかく何とかしませんと!)
凛は背中をさすりながら、失礼しますとアダモフの上着に手を入れた。ポケットを確かめるが、そこには何も入っていない。
誰かが携帯に向かって、軍医をはじめとした医療スタッフの要請をしているのが聞こえる。
凛はアダモフを椅子から床に腰を下ろさせると、上着を脱がせた。念のため上着を広げるが、どこのポケットにも手帳など文具が少し入っているばかりで、薬らしきものは見当たらなかった。
「むむ……今助けますぞ」
お茶を運んでもこぼしそうだから。そんな理由で、今まで隅っこでパートナーのレキや他の参加者の様子を見ていたミア・マハ(みあ・まは)が、飛び出した。
──スタッフの仕事の第一義は『お客様をおもてなし』すること。雰囲気を乱さず、交渉しやすい『場』をつくること。手柄を争うような輩はわらわがお仕置きしてやろう。
そんな風に考えていたミアだったが、これはちょっと想定外の事態だ。いや、想定内、か。
ミアが、うずくまるアダモフの背に手をかざす。“清浄化”の光が激しい呼吸を抑えていく。唇の間から、ひゅーひゅーという音が徐々に小さくなっていった。
「一旦落ち着いたようじゃが、休ませた方がいい。本来の薬がないことにはまた繰り返すじゃろうしな……」
「個室へ運びましょう」
「それがいいの」
警備の海軍スタッフの力を借り、二人はアダモフを、彼に用意された個室へと運んで行った。
その間に個室に軍医が駆け付ける手筈が整えられた。
残ったスタッフたちは騒ぎを大きくしないようにと、ハーララや商人たちに説明をしている。
「ご気分の悪いお客様がいらっしゃいましたが、落ち着かれたようです。皆様はそのままお茶をお楽しみくださいませ」
ただの持病か……と思われたが、それを見逃さない目があった。
『アダモフが倒れた。原因は持病で、薬は未所持。だが──不審な動きをする男を1名発見』
松平 岩造(まつだいら・がんぞう)が会場に素早く目を走らせながら、会場の警備担当者に“テレパシー”を送った。
*
アダモフが倒れ、不審者が見つかった。
その情報は、直ちに警備責任者
フランセットにも伝えられた。
「
ミルディア・ディスティン(みるでぃあ・でぃすてぃん)、悪いが君のパートナーを従妹殿へ報告にやってくれ。君は生徒の指揮と万一の連絡のため、ここに残れ。携帯が通じるからな」
「は、はいっ」「かしこまりましたわ」
和泉 真奈(いずみ・まな)が、ミルディアの返事と同時に、指令室を小走りに飛び出した。
「両者に関連性があるかは分からん。アダモフ氏には持病があると聞いている。が、不手際は不手際だ」
フランセットはそこまで厳しい口調で言ってから、ふっと表情を緩めた。
「うちの軍医は、バカだが腕はいい。心配するな、このような事態にも備えてある。──後は、従妹殿の領分だな」
*
『あの男……アダモフの秘書バレだ。甲板から船内へ移動中。追跡頼む』
『──了解。私が行くわ。丁度良い恰好してるしね』
岩造に応えたのは、一人の船員──に扮した、
ルカルカ・ルー(るかるか・るー)だった。手に持つデッキブラシは、実は薙刀を偽装したものだ。
横目で船内に降りていく彼を見送りつつ、ベルフラマントを羽織って気配を消すよう努める。パートナーの
夏侯 淵(かこう・えん)も彼女に続く。
百合園の友人たちのお茶会が、安心できるものであるように──そのために来たルカルカだったが、役立つ時が来たようだ。とはいえ、役立つのは純粋に嬉しいが、そんなことなどない方がいいに決まっていた。警備の任に就くにあたって、ラズィーヤに言った「軍が動く事は無いに越した事ないんです。戦争で食べてるくせに変ですかね」の言葉が蘇る。
(今回のお茶会、騒動を仕組み「治安維持に不安ありの口実で不平等協約を結ぼうとする可能性」もあるわ。国益を守らなきゃ!)
二人は“空飛ぶ魔法↑↑”で飛行しながら追跡していく。
といっても、追跡は程なく終わった。彼は廊下を歩いたかと思うとすぐに、用意された個室に入ったからだ。
「不審ってだけじゃ捕まえられないわね。窓の外は?」
「行ってくる」
淵は近くの丸窓にダッシュすると、双眼鏡を目に当てた。個室に備えられたデッキに秘書の姿が見える。
彼は懐から何かを取り出すと、手を振った。きらりと光るものが宙を舞う──。
「ルカ、窓、何か投げた! 取ってくる!」
言うや否や、淵は腕時計型加速装置“アクセルギア”を全開にした。超高速の超人的瞬発力が彼の体に宿り、取り巻く時の流れを緩慢にさせる。
「てええいっ!!」
窓を開け、窓枠を蹴り、空を疾る。小さな体を一生懸命伸ばし、放物線を描いて海面へと落下するそれを、淵は掴み取った。
船が停泊しているのを幸いに、そのまま淵は窓枠に手をかける。同時に“アクセルギア”の効力が切れ、彼の体は疲労に絡め取られた。
「大丈夫?」
ルカルカが淵を廊下に引っ張り上げると、彼はにやりと笑って、握った右手を突き出した。その手を開くと、ケースが零れ落ちた。
それはプラスチックのような素材でできた仕切り付きケースで、錠剤や粉薬が納められている。
「お疲れ様。これはラズィーヤさんに届けに行くわ。淵はそこで休んでていいわよ」
「冗談だろ。これしきで……」
立ち上がろうとした淵の膝ががくりと折れた。
「……三十秒。三十秒だけ休んだら後を追う」
「はいはい。でも、それより追うより、秘書が逃げないよう、見張っててね。誰かとグルだってこともあるかも」
「了解した」
淵が頷いてから、ルカルカはラズィーヤの元へと急いだ。
こうしてケースは、「軍人が出すと事が大袈裟に成るから、ラズィーヤさん達が使うのが良いと思うのよ」の言葉と共にラズィーヤから──そして、アダモフへと渡されることになる。