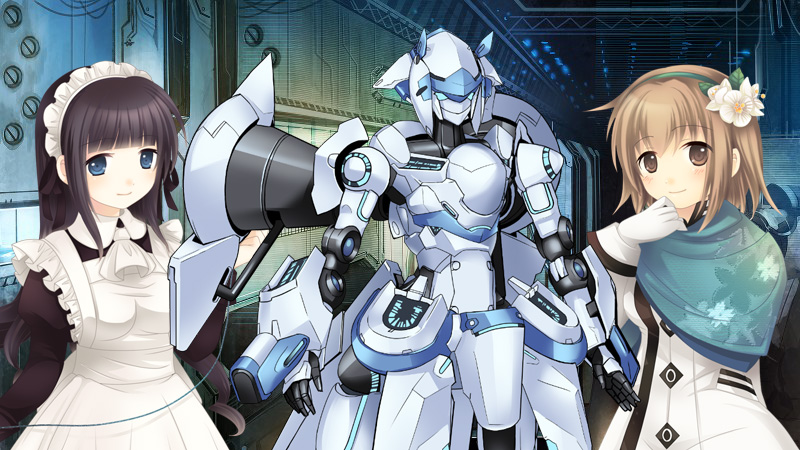リアクション
* * * アルテッツァ・ゾディアック(あるてっつぁ・ぞでぃあっく)は、新年度に入ってからも、表面上は変わりなく教員としての仕事に明け暮れていた。 しかし、仕事が終わると青い錠剤をかじっては酒を流し込み、そのまま寝落ちるという生活を続けていた。 それが、かえって彼の心と身体を蝕んでいた。 「あああああっ!!」 悪夢を見ることも多くなった。 (……生き残るんだ、何をしてでも、生き残ってやるんだ……) 生への異常なまでの執着。彼を彼たらしめているのは、もはやそれだけだった。 「ゾディ!」 ヴェルディー作曲 レクイエム(う゛ぇるでぃさっきょく・れくいえむ)が彼の元へやってくる。彼と一緒に、すばるも入ってきた。 シミュレーター訓練以後、アルテッツァを治すための手立てを探していた彼ではあったが、その原因が彼の心の内側にある以上、簡単には見つからなかったようである。 だから、こうやって直接話しかけに来たのだろう。 「……ヴェル、ボクは生きていますよね。ボクは、生き残れていますよね……あはは、ははぁっ!!」 「ええ、ちゃんと生きてるわよ!」 壊れかけているアルテッツァに、目を合わせてくる。 「ねえ、アンタの生への執着、元となったのは何なの? アタシに血をくれる前に何が起こったの?」 言い方を変えてくる。 「……いいえ、『アンタにとって一番嬉しかった記憶』はなぁに?」 「一番、嬉しかった、記憶……?」 過去の風景が彼の脳裏を過ぎる。 「アルト、お前のフィドル、綺麗な音だな」 それは、彼が旅芸人だった頃。 自分のフィドル――ヴァイオリンを褒めてくれた人がいた。自分が生きるのは、自らの存在意義を認めてくれた「彼女」のため。 「そう、ボクは『彼女』のために、生きていくと……決めたんだ」 じっとすばるの顔を見つける。「彼女」の代用品として契約したその少女を。 (大丈夫、『キミ』のために、ボクは生きていこう) そのとき、彼に緊急連絡が入る。F.R.A.G.による宣戦布告の知らせだ。 「……行きましょう」 彼は教員であると同時にパイロットだ。そのため、招集に応じてイコンベースへと向かう。 そんな二人を見送り、レクイエムは憐憫の視線を送り、呟いた。 「……ヒトって悲しいわね。自分を認めて貰えた記憶が『のりしろ』になるなんて」 * * * 天沼矛内、ミーティングルーム。 宣戦布告を知ったパイロット科の生徒達がここに集まっていた。 「F.R.A.G.第一部隊は南アメリカの上空にいる。シャンバラ側に与しているアジア圏を通らないよう、迂回しているようだ」 ゾディアックを巡る戦いで、学校勢力のバックについている先進諸国の軍隊も出動している。未だに厳戒態勢が敷かれているため、アジアを抜けようとすれば中国、ロシアの軍隊との衝突は避けられない。いくらF.R.A.G.が一国の軍隊を凌ぐとはいえ、余計な戦闘はしたくないということだろう。 「幸い、と言っていいのかまだF.R.A.G.が来るまでに時間がある。部隊を整えて迎え撃つ準備は、十分に可能だ」 パイロット科長の言葉を受け、小隊編成が行われる。 「翔くん」 桐生 理知(きりゅう・りち)は辻永 翔(つじなが・しょう)に声を掛けた。 「小隊、一緒に組ませてもらえないかな?」 「ああ、構わない。ただ、俺達は今回例の次世代機で出ることになった」 「私もだよ。まだ試作段階だっていうけど、それでも未知の可能性を秘めてるってことだから、志願したんだ」 F.R.A.G.は強い。だが、理知にはそれ以上に気掛かりな存在があった。 「それに戦いが起こったら、またあの青いイコンが出てくるかもしれない。もし、あれが出てきたら、止めなきゃいけないよ」 「確かにな。F.R.A.G.以上に、厄介な相手だ」 もちろん、それだけではない。その青いイコンのパイロットについても、普段の学校生活の中で、ヴェロニカから聞いていたのである。 加えて、あの機体の力は底が知れない。おそらくF.R.A.G.のクルキアータが束になって挑んで、辛勝出来るかどうかだろう。だからこそ、あの機体の出現も視野に入れれば、F.R.A.G.の機体を超えるスペックを誇る新型機の力が必要となる。 「もうじき整備が終わるはずだ。一度機体を確認しに行った方がいい」 確定した翔達の小隊は、全員が第二世代機に搭乗することになっていた。実機の確認をすべく、ハンガーへと向かう。 「ええと、操縦系統はシミュレーターに先行導入されていたものから変更はありませんよね?」 リンドセイ・ニーバー(りんどせい・にーばー)が第二世代機の整備を担っていた真琴に尋ねた。 「はい。トリニティ・システムのエネルギー連動、及びエナジーウィングの展開はシミュレーターに導入されたデータと同じです」 彼女と桐生 景勝(きりゅう・かげかつ)は、一週間前にイコンシミュレーターにイーグリット・ネクストのデータが導入されてからというもの、時間の許す限りシミュレーターにこもって訓練を続けていた。 「近いうちに実機でも試運転が出来るようになるみたいなことは聞いていたが……それが実戦になるとはなぁ」 おそらく、実機そのものはシミュレーターにデータが反映された時点で完成していたのだろう。ただ、調整が済んでいなかったために、パイロット科には伏せられていたらしい。 「シミュレーターで動かした感じではどうだったんだ?」 同じ小隊のデビット・オブライエン(でびっと・おぶらいえん)が聞いてくる。 「最初は機体に振り回されっぱなしだったなー。とにかく出力と瞬発力がヤバい。乗りこなすのは難しいかもしれねぇが、確かにこれならあのクルキアータってヤツとタメ張れるぜ」 とはいえ、景勝はあくまで対白のクルキアータ――ミス・アンブレラことメアリー・フリージアとまだ見ぬそのパートナーが駆る【アスモデウス】を想定してシミュレーションを行っていた。しかし、そのデータは学院にないため、ただでさえ手強い指揮官機の設定を格闘特化、速度をその機体の上限にしてもらい、一対一で戦い続けた。 「シミュレーターでは、まともに動かせるようになりましたね。仮に武器が使えない状態でも、補助スラスターを上手く使えば空中で格闘も出来ることが分かりましたし」 装甲にダメージは負うが、回し蹴りで相手の武器を破壊することは、シミュレーターでは可能だった。 「しいて言えば、従来の機体よりも『人間らしい動き』が出来るってとこだ。覚醒を使わなくてもな」 さすがに覚醒抜きで勝つのは厳しいが、互角の戦いが出来るまでにはなった。 「機体での性能差はなくなった。あとは、パイロット次第ということか……」 笹井 昇(ささい・のぼる)が呟く。 クルキアータの中に覚醒のような切り札がない限り、機体性能面では劣勢ではなくなった。しかし、パイロットの習熟度は未知数だ。 イコンシミュレーター上で勝てる技量を身に付けている、それが彼らに対抗するための最低ラインである。 * * * 「力を貸して欲しい」 星渡 智宏(ほしわたり・ともひろ)はヴェロニカ・シュルツ(べろにか・しゅるつ)に同じ小隊に組み込んでもらうよう、依頼する。 F.R.A.G.での事情聴取から学院へと帰還した彼は、相手のことを学院の誰よりも知っている。その正体も。 「何か、考えがあるみたいね」 ニュクス・ナイチンゲール(にゅくす・ないちんげーる)が彼を見上げ、口元を緩めた。 「出撃後、詳しいことは話す」 改めてヴェロニカに視線を移す。 「『今のF.R.A.G.を確かめる』その力になりたい」 ヴェロニカはまだ今のF.R.A.G.を知らない。同じ一個人としてF.R.A.G.の指揮官と対話した智宏は、組織ではなく人として見た彼女達の志を知っている。 学院のみんなを守りつつ、かつF.R.A.G.への被害も抑える。それを「戦場」で成せるのは、双方の内情を知っている自分達だけだろう。 「うん、分かった」 その目には強い意志の光がある。ヴェロニカと「F.R.A.G.」という名称には浅からぬ因縁があるらしいことは耳にしているが、それはどうやら本当らしい。 「智宏さん、今のうちに機体を確認しておきましょう」 時禰 凜(ときね・りん)に呼ばれ、二人はハンガーへと移動する。イーグリット・ネクストでも二挺拳銃が可能かを改めて確認するために。 智宏達が離れた直後、ヴェロニカに声を掛けに来たのはミルトだ。 「ヴェロニカ、前に渡そうかどうしようか迷ってたんだけど、もしヴェロニカが生身のソースイの昔のこと、少しでも知りたいって思うことがあったら開けてみて。そのまま開けなくてもいいよ」 「……ありがとう」 渡すなり、すぐに彼はヴェロニカから離れて周囲をきょろきょろと見渡した。山葉 聡(やまは・さとし)とサクラ・アーヴィング(さくら・あーう゛ぃんぐ)の姿を見つけ駆け寄ろうとするものの、二人が教官に呼び寄せられたためにタイミングを見失う。 ふと、ちょうどニュクスも離れ一人になっていたヴェロニカの方に視線を戻すと、一人の少年が彼女の前にいるのが見て取れた。 霧羽 沙霧(きりゅう・さぎり)である。 会話は聞こえないものの、どこかよそよそしい感じだ。 「あの……」 沙霧の視線は斜め下を見ている。ヴェロニカとはどうも真っ直ぐ顔を合わせられない。 「僕も兄がいて……三人なんだけど」 ヴェロニカの兄のことは、彼も知っている。 「みんな僕と違って優秀で、前を向いていて、両親も僕のことなんて見向きもしなくて……。でも、一番下の兄さんだけは僕のこと気に掛けてくれてたんだ。海京に移動する前までは、時々手紙もくれたし」 ヴェロニカに対しては変わらず複雑な心境ではあるが、兄という存在に対しての思いから、他人事には思えないものがあった。 「こ、こんな話どうでもいいよね、その……」 「ううん、そんなことないよ。いい、お兄さんだね」 ヴェロニカは優しく微笑みかけてきた。きつく当たってしまうことが多いために、それがかえって辛い。 「僕も、お兄さんを助けられるように手伝うから……で、でもそれは鈴蘭ちゃんが一生懸命だからであって、君のためってわけじゃないから!」 そこまで口にしたところでいたたまれなくなり、逃げるように駆け出していった。 「はあ、はあ……」 ハンガーへ向かう通路の途中で立ち止まる。 「そんなに慌ててどうしたのかなー?」 声のした方を振り返ると、一人の少年――ミルトがいた。 「はーん。もしかして、ヴェロニカのことが気になるの〜? うんうん、分かるよ。気になる子の前だと素直になれなくて、ついきつく当たっちゃうんだよね? 甘酸っぱ〜い、このこの〜」 「ち、違う。そんなんじゃない!!」 ニヤニヤとしているミルトを振り払い、急ぎ足でハンガーへと向かった。 * * * 「ニュクスちゃん、ちょっといいかしら?」 館下 鈴蘭(たてした・すずらん)は、ヴェロニカと合流しようとしていたニュクスを呼び止めた。 「この間、ニュクスちゃんが悲しそうな目をしていたのが気になってたの。この戦いから戻ったら、その訳を聞かせてね」 前に一瞬だけ見せた彼女の表情が、鈴蘭の中で引っかかっていたのだ。 「ええ。けれど、それは受け止めたがたいものかもしれない。それでも聞きたい?」 「それでも、よ」 ニュクスは【ナイチンゲール】を制御するためのプログラムだというが、自分達とは違う存在のようには思えない。 「人間の感情ってね、一説によるとただの電気信号に過ぎないんですって。0と1の配列の違いだけで、笑ったり怒ったり悲しんだり……私達の心も、そんな風に出来てるのかしら」 そっとニュクスの両手を包み込むように握って、まっすぐ彼女の瞳を見た。ニュクスの手からは温かさも感じられる。 「私達、仲間よ」 「仲間……?」 珍しく、ニュクスが驚いたように目を見開いた。 「私もあなたも、ここにいるの。みんなと一緒に、今ここにいるの。だから、もし苦しいことや悲しいことを抱えているのなら、頼って貰えない方が辛いの」 ニュクスがどんな存在だろうと、何を背負っていたとして、それは変わらない。自分達が肩を貸すことでその重荷が減るのなら、どんなものだって、幾らだって担げる。それが「仲間」というものだ。 「わがままかもしれないけど、あなたのことを信じさせて。そして、私を、私達のことを信じて欲しい」 すると、ニュクスはいつもの微笑を浮かべた。 「信じるわ。戻ってきたらわたしのこと、わたしが『見てきた』ことを話すわね」 絶対に伝えると約束して、ニュクスと別れた。 (『今ここにいる』か) ニュクスは一人佇み、通路の奥を見つめた。 (これが最後の『今』になってくれれば――) * * * 「各小隊、出撃準備に入れ」 イコン部隊の指揮を執る五月田 真治教官長からの指示を受け、各自搭乗する機体の最終調整に入る。 彼を含め、出撃する教官は第二世代機プラヴァーに乗る。海京の最終防衛ラインを彼らが構築するのだ。 「五月田教官長」 オリガ・カラーシュニコフ(おりが・からーしゅにこふ)は自機に向かう前に、五月田に声を掛けた。 「どうした? お前も早く準備をしろ」 あくまで冷静に振る舞っているが、時折その顔に陰りが見える。それがオリガには気になっていた。 力強く頷き、決心したように五月田と目を合わせる。 「F.R.A.G.との戦いが終わったら、お時間を頂けませんか? お伝えしたいことが、あるんです」 それに対し、教官長はただ一言。 「……絶対に死ぬなよ」 「はい!」 だから、教官長も。 約束を交わし、彼女は自機へと歩みを進める。 「だから、オリガも死亡フラグばっかり立ててるんじゃないわよ?」 呆れ半分な様子でエカチェリーナ・アレクセーエヴナ(えかちぇりーな・あれくせーえうな)がオリガの顔を覗き込んできた。 「無理はしませんわ。それに、ブルースロートは守るための機体。誰も傷付けさせたりはしませんわよ」 そのために、この機体の力を最大限に引き出せるよう訓練を積んできたのだから。 「それならいいんだけど……」 それでも、エカチェリーナには嫌な予感が拭えないようだった。 |
||