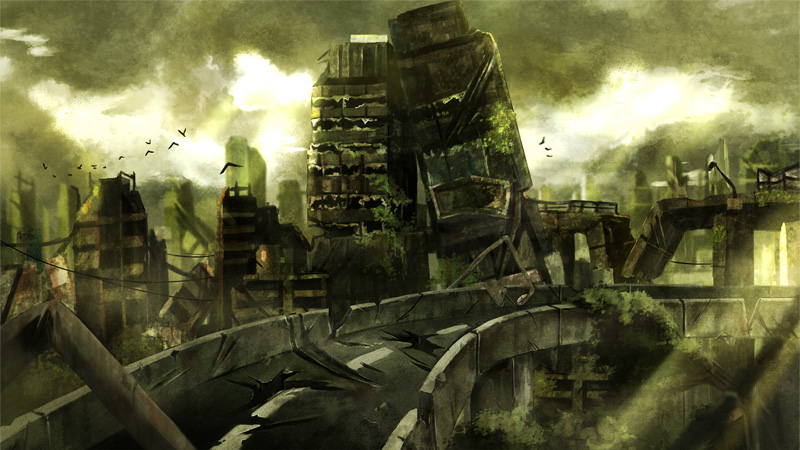リアクション
*********************** よう、と軽く挙げた彼の右腕がひどく細くなっていることに気がついて、小鳥遊 美羽(たかなし・みわ)は思わず涙ぐんでしまった。 「どうした? カンドーの再会、ってやつか?」 彼は照れ隠しのように笑った。かつて、制服を着ていてもわかるほどパンパンに張っていた胸板もすっかり薄くなり、顔には頬骨が浮いていた。顔も土色だ。せっかく矯正した視力もふたたび衰えたのだろう。以前のように眼鏡をかけている。 それでも、彼は山葉 涼司(やまは・りょうじ)だった。 「俺の胸に飛び込んで来てもいいぜ……と、言いてぇところだが、ごらんの通り弱っていてな、それはやめておくわ」 「もう! 死んだと思ってたんだからね! 何年も……」 「俺はしぶといんだよ」 ぐるりと周囲を見回して涼司は言った。 「皆と同じでな」 数は多くない。決して、多くない。 だがそこには、蒼空学園の制服姿が揃っていた。いずれも誇りのように、それを脱ぐことを認めなかった者たちだ。両手があれば十分数えきれるほどの人数、いずれも制服はボロボロで、汚れてもはや原形をとどめていないものも珍しくない。 裸電球ひとつしかない薄暗い地下倉庫、ここに彼らは集っている。照明の暗さは、彼らの服装の惨憺たるありさまを覆い隠すどころかむしろ助長しているようにも見えた。 だがそんななか一人だけ、まるで現役学生のように綺麗な制服姿の青年があった。 美羽のパートナー、コハク・ソーロッド(こはく・そーろっど)だ。花も恥じらうような美青年、いや、戦士ゆえ美丈夫というべきか。白い右の翼、光が実体化した左の翼、いずれもクランジ戦争前から変化なく、時の経過が彼だけ避けていったかのように見える。 コハクは右の拳を心臓の上に当て、すっくと直立して述べる。 「ご帰還を祝します、山葉校長。僕らはツァンダ解放戦線、元蒼空学園生による抵抗組織です。リーダーは美羽、これまでずっと各地で、ツァンダをクランジから取り戻すために戦ってきました」 「ルカルカ・ルーたちからおおよそのことは聞いてる。……帰還、か。嬉しい言葉じゃないか。大げさじゃなく、古巣に戻ってきた気がするぜ」 エデンから解放された涼司はこの日、レジスタンス本流と協力関係にある組織『ツァンダ解放戦線』と合流を果たしたのだった。ここまでの道のりにおいて、レジスタンス本隊の護衛を受けてきたのはいうまでもない。 解放戦線のメンバーはここに見えているだけ。かつてはもっとずっと大人数だったが、転戦を繰り返しながら大きく人員を減らし、たったこれだけになっている。戦死者、脱落者はもとより、途中で心が挫けた者との別れもあったという。現在も独立は保ち名前も存続しているとはいえ、もはや解放戦線はレジスタンスにおける一部隊のような立場で、遊軍的な存在となっている。 なお彼らは一週間前のエデン攻略戦には加わらなかったが、その周辺の戦闘で本隊を支えていた。 戦果はあった。活動は前進した。 されど、このとき周辺戦でやはり犠牲者があり、ますます解放戦線のメンバーは減少している。士気の低下は否めないものがあった。 だがそれも今日限りだ。 蒼空学園の旗頭だった涼司は、今でも元蒼空学園生たちにとって心のよりどころなのである。いわば、消えかけていた焚き火に、強い固形燃料が投入されたようなものだ。炎は一気に燃え上がっていた。 「校長」 と進み出たのはベアトリーチェ・アイブリンガー(べあとりーちぇ・あいぶりんがー)。美羽のもう一人のパートナーである。 「みんな、『校長』と呼んでくれるのは嬉しいが、あいにくと蒼学がもうねぇんでな。……『元校長』だよ」 しかしベアトリーチェは首を振った。 「いいえ。私たちが再興を諦めない限り、それでもあなたは私たちの校長です!」 「私だってそうだよ、涼司」美羽は目を拭って涼司を見上げた。「私だって『元』じゃなくて現役で、『蒼空学園のアイドル』なんだからね!」 「ではアイドルにしてリーダーの美羽に問いたい」 涼司は笑っていたが、眼差しは真剣だった。 「レジスタンスはいよいよ、空京陥落を狙うという話だったな。これに応じたツァンダ解放戦線の……いや、俺たちの動きを教えてくれ」 「もちろん計画済みよ」 美羽は腰に手を当て、にっこりと微笑んだ。 美羽の制服は痛みが激しく、片側の袖はなくなっていた。 されどそれでも、こうして笑顔になれば、それはまさにアイドルの笑みであった。 「ただ、涼司、その前に聞きたいことがあるんだけど、いい?」 「おうよ」 「私たち、今でも親友よね?」 「そういう質問には……言葉で答えるべきじゃねぇよな?」 すると涼司は、開いた右手をぐっと差しだしたのである。 「これが答だ」 「うん! わかった!」 パンと音を立て、美羽は彼の手をしっかりと握った。 涼司の手はずいぶんと肉が落ち、骨張ってすらいたが、そこに込められた力には美羽の身が震えるほどの生命力が感じられた。 |
||