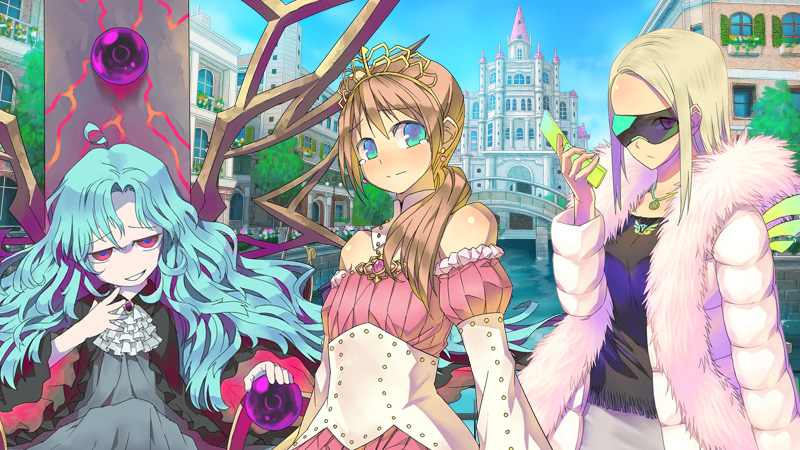リアクション
○ ○ ○ 花火大会当日。 百合園女学院の屋上では、静香主催の花火とヴァイシャリーの夜景観賞会が行われる。 静香が初めて観賞会を企画したのは、2019年のこと。 3回から5回目はささやかな会であったが継続して行われており、観賞会は今年で6回目となる。 「百合園女学院へ、ようこそいらっしゃいました」 百合園女学院の校門側にて、生徒会役員のレキ・フォートアウフ(れき・ふぉーとあうふ)が訪れた人々に微笑みを向け、美しくお辞儀をする。 彼女は、水色の地に紺や藍色の流線が描かれている浴衣姿。 「ようこそお越しくださいました」 「ごきげんよう」 共に受け付けを担っている生徒達も皆、可愛らしい浴衣姿だった。 「花火が始まるまで、まだしばらく時間がありますが、催しもございますので、ゆっくりと楽しんでいってくださいませ」 レキはプログラムを手渡し、地図の部分を手で指し示す。 「緊急の際や、迷われているお子さまを発見された時には、こちらまでお願いいたします。 こちらにはステージが設けられており、花火開始までの時間、歌や演奏を観賞していただくことができます。 その他何かお困りのことがありましたら、腕章をしているスタッフをお申し出ください」 「ありがとう〜。今ならいい場所とれるかな?」 「はい、花火は何所からでも楽しめますが、夜景を見るのでしたら、こちら側がお勧めです」 レキは一人一人に丁寧に説明をしていく。 「あ、なにこれ、なにこれー」 小さな男の子が受付けに飾ってある西瓜模様の紙風船に気付いてつっついている。 「お土産用の風船だよー。もっていく?」 「うん、ちょうだい!」 レキはお土産用に用意してきた紙風船を男の子に渡して、ふくらまし方を教えてあげる。 「紙で出来てるから、空気入れすぎないようにね。お外で投げたり叩いたりもしちゃだめだよ」 「うん!」 男の子は嬉しそうに受け取って、手を振ってお母さんと校舎の方に向かって行った。 続いて、要人たちが受付けに近づいてきた。 「お疲れ様。開始までまだ時間あるけど、お客様随分と集まってるみたいだね」 「こんにちは、桜井校長」 「ごきげんよう、静香様」 静香とヴァイシャリー家の人々だ。 「……お疲れさまです」 他の生徒達と同じようにレキは頭を下げて静香を見守る。 「うん、熱中症にならないように、ちゃんと休憩をとりながら頑張ってね」 「はい、校長も無理はしないでくださいね」 レキがそう言うと、静香はありがとうと微笑んで、ヴァイシャリー家の人達を屋上へと案内していく。 「校長……校長だなぁ」 静香の後ろ姿を見ながらレキが漏らしたその言葉に、後輩達が首をかしげる。 「昔はホント、静香ちゃんという感じで、飾りっぽくて……。ラズィーヤさんに言われるままに行動していたけれど、今は自分の意志で校長をやっているのが分かるから」 貫録というものがなく、気弱そうな外見に変わりはなくて、自分に自信がない部分も変わってないのかもしれないけれど。 「他から見て、ちゃんと強くなってることが分かるから、もう少し自信を持つといいと思うんだ。男らしくなった……と言うとちょっと変かもしれないけど」 「ふふ、可愛いままですしね。大人の女性になったといった方が自然な気もします」 「そうかも」 後輩の言葉にレキは笑みを浮かべた。 (やっぱり好きな人が出来ると違うんだなぁ) そしてそうも思っていた。 「お疲れさま! みんなちゃんと、水分摂ってる?」 お菓子や飲み物を配っている祥子・リーブラ(さちこ・りーぶら)が、台車を押して近づいてきた。 「リーブラ先生、お疲れ様です。はい、気を付けています。街や屋上はどうですか? もめごととかないといいけど……」 「今のところ、問題は起きてないわ。素敵な花火大会になるといいわね。スポーツドリンクおいていくわね」 「ありがとうございます」 レキと生徒達は、祥子からスポーツドリンクを1本ずつ受け取った。 そして。 「ようこそお越しくださいました」 「ゆっくりと楽しんでいってくださいませ」 優雅な笑顔で、客を百合園女学院に迎え入れていくのだった。 祥子はエレベーターを利用して、台車に乗せたお菓子を屋上に運んだ。 夏の熱い陽射しで、屋上はとても暑かった。 場所をとるために、早めに訪れた人々は、パラソルを立てて、団扇で仰ぎながら過ごしている。 「今夜は星も観れそうね」 汗をぬぐいながら、祥子はテントの下にお菓子を運んでいく。 「……なんだか、ビヤガーデンにしたくなっちゃう」 専攻科に所属する生徒が、運び込まれたお菓子をテーブルに並べる。 ポップコーンやベビーカステラ、スティック系の菓子などなど、摘まんで食べやすいものが多い。 「未成年が多いから、お酒は出せないけれど……百合園の屋上じゃなければ、そういうのも面白そうよね」 祥子は生徒と顔を合わせて微笑み、配布の準備を進めていく。 「静香さんこんにちは!」 大量の荷物を抱えたルカルカ・ルー(るかるか・るー)が下見をしている静香に駆け寄った。 後ろから、ダリル・ガイザック(だりる・がいざっく)もゆっくりと近づいてくる。 「こんにちは、ルカルカさん」 静香は優しい笑みを見せた。 ……だけれど静香が今、精神的にとても辛い状態であることはわかっている。 (ラズィーヤさんが……留守にしてて……頑張ってる静香さんを手伝いたい) そんな思いから、ルカルカはダリルに頼みこんで、こういう場に合ったお菓子を大量に作ってもらい、2人で抱えてきたのだ。 「ダリルが作ってくれたお菓子、皆さんにお配りしてもいいかな?」 「うん、ありがとう。とっても喜んでもらえると思う……でも芸術品みたいなのじゃないよね?」 ダリルのお菓子作りの技術については、静香も知っている。 「配布用に小さいものにしてもらったから、大丈夫」 ルカルカが静香に担いできた箱の中身を見せる。 溶けにくい素材を使った、チョコレートやキャンディー、クッキーなどが沢山入っていた。 「今年は沢山人が集まりそうだから、助かるよ」 「それじゃ、配らせてもらうね。あ、静香さんもどうぞ。皆様もよろしければ」 ルカルカは数種類のチョコレートと飴を小さな袋に入れると、静香、それから静香と一緒にいた人達に渡した。 「ありがとう。小分けするのに場所が必要なら、あっちのテントでどうぞ」 「うん、場所お借りします! あとで食べながら花火観ようね」 ルカルカがそう言うと、静香は笑顔で首を縦に振った。 日が沈みかけた頃には、百合園女学院に続く道や運河には列ができていた。 その少し前に。百合園警備団、生徒部に所属するイングリット・ネルソン(いんぐりっと・ねるそん)は休憩をとることにした。 彼女は、警備団員として、百合園に続く道の交通整理や警備を担当している。 「ちゃんと休んでね。これから花火が始まるまで、忙しくなるだろうし」 イングリットに休憩を促したのは、マリカ・ヘーシンク(まりか・へーしんく)。白百合団で、イングリットと共に活動していたOGだ。 「そろそろ日が沈みますし、気温も下がると思いますから、大丈夫ですわ。ただ、辺りが暗くなる分、犯罪には気を付けなければなりませんけれど」 「そうね。あたしもこの辺りの警備、手伝わせてもらうね」 「警備団の仕事ですから、任せていただいて大丈夫ですわ。マリカさんも屋上から花火を楽しんでくださいませ」 「花火も楽しむけれど、まだ時間あるしね。こういった仕事もなんだか懐かしくって! だから気にしないで。指揮してくれるのなら、勿論従うよー」 卒業してからまだ数か月しか経っていないのに、マリカは百合園の校舎も、こういったイベントも、とても懐かしく感じていた。 「ふふ、ありがとうございます。それでは花火が始まってからの休憩時間では、ご一緒しませんか?」 「うん、是非! ……息抜きに、捕縛術の組手や型でもしようか?」 「そうですわね。お願いしますわ」 2人は目を強く輝かせて、微笑み合う。 「そういえば、生徒会の補欠選挙、新学期にやるんだってね?」 「はい」 マリカの言葉に、イングリットは少し緊張した面持ちで頷いた。 「あたしはもう投票できないけど、イングリットが当選すると信じてるよ。当選したら、任務を頑張ってね」 「はい! 皆と一緒に、百合園と、わたくしたち自身のために、頑張っていきますわ」 「うん、期待してる。それじゃ、代わりに交通整理してくるね。また後で」 マリカは手を振って、休憩をしているイングリットの代わりに交通整理に向かっていった。 「イングリット、そろそろ人も増えてきたし、最終確認いいかな」 休憩を終えて仕事に戻ろうとしたイングリットの下に、百合園警備団、生徒部で活動している漆髪 月夜(うるしがみ・つくよ)が駆け寄ってきた。 「この辺りは、ヴァイシャリー警察が担当してくれるんだよね」 「そうですわね」 月夜は地図を広げて、イングリットと共に確認をしていく。 「校門付近はティリアが直接指揮してるし、受付けにはレキがいるから大丈夫で……。 人手が足りないのは、運河のあたりかな。ゴンドラで来る人も多いしね」 「ええ、河原の見回りにもう少し人員を割いた方が良さそうですわね」 「人があまり通らないところも、危険が潜んでいるかもしれないし……屋台とか多い場所は混み合って、迷子とか沢山でそうだよね。屋上の運営本部の他、受付けでも迷子の保護できないかな? 簡単な応急手当も出来るよう救急箱も置いておくと良いかも。屋上のテントと同じように、冷たい飲み物とか、簡単なお菓子もあったらいいかな」 「そうですね、レキさんに伝えておきましょう」 月夜とイングリットは警備ポイントや迷子対策について話し合いながら、河原へと歩いていく。 事前に月夜は警備団の皆と打ち合わせた内容を地図にまとめて、メンバー達に配布してあった。 月夜の提案により、百合園内部を警備している生徒達は通信機を持っており、イングリットや月夜のような外部をも担当するメンバーについては、携帯電話の番号を地図にのせてあった。 「イングリットは、警備団生徒部の代表に立候補するんだよね?」 「はい、そのつもりですわ」 「それで、警備団で何を目指すの?」 「何といいますと?」 「んーと、例えば私は、自分の力で誰かを守ったり助けることが出来るようになりたい。 刀真と一緒にいなくても、私だけの力で何かが出来るようになりたいの」 月夜は、パートナーの樹月 刀真(きづき・とうま)の剣だ。 だけれど、剣としてだけではなく、1人の女として自立することの必要性に、気づいていた。 その為に、警備団で学んでいきたいと月夜はイングリットに話した。 「わたくしは、強さを求め続けたいと思っています。個人の強さは、日々の鍛練で培うことができるでしょう。だけれど、個人の戦闘能力が高ければ、人を守る強さも高いとはいえないということに、白百合団の活動で気付きました。 ですから、この警備団でわたくしも皆様と共に、学んでいきたいのです。 それぞれの強さを持った百合園の皆様と、切磋琢磨し、成長していきたいと思います」 「うん……あの」 「はい」 「私も一緒に頑張る。だから……えっと、ご指導ご鞭撻のほどお願いします」 そう言って、月夜はイングリットに頭を下げた。 「こちらこそ、よろしくお願いいたします。……もし、わたくしが独りで暴走しそうになったのなら、張り飛ばしてでも止めてくださいませ」 「……ふふ、イングリットを張り飛ばすのは大変そうだけれど、イングリットやイングリットについていく皆を守るために必要なら、遠慮しないからね」 「ええ」 月夜とイングリットは強い目で微笑み合った。 |
||